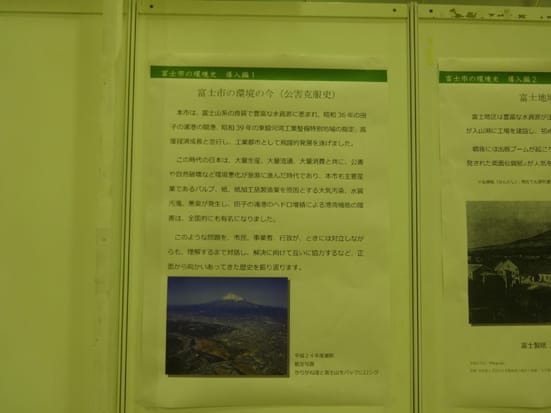平成27年11月25日
「地方創生」に取り組む地方自治体の動きが活発化しています。私は地方創生は地方間の競争という考え方で取り組んでいますが、当然のことながら行政だけでなく議会も両輪のごとく責任を果たさねばなりません。
県民の皆様から時々聞かれるのが「今は議会中?」という問です。例えばその方が私に対して相談事があったとすると、「閉会中」ならば時間がとりやすいとの配慮があるのかもしれません。また、閉会中には時間がとりやすいことは事実ですが、極論を言うと議員活動が「議会開会中」に集中していると捉えているようにも思います。
普段の議員活動はまだまだ県民の皆様にうまく伝わっていないようです。私は二期目を迎えほぼ毎日、私の議員活動をブログに記して公開しています。最近は、その様子を見ていただく方も増え、普段の議員生活を理解していただいているようにも思えます。
ただ、ブログを見る人は全体から見れば極一部で、年4回発行する広報誌を通じて県政・議会報告をさせていただいていますが、誌面の限りがありますので、全てを伝えることは不可能です。自ら主催する議会報告会や、人が集まる会などで少し時間をいただいてお伝えしたりしています。
県民代表といわれながらも、県民の皆様からもっと身近に感じていただけるよう、まだまだ努力が足らないことを反省しています。
さて、地方創生に戻りますが、先ほど行政と議会の一体化について触れました。地方創生は行政が主体で取り組むものでなく、そこに住む市民や企業が実践して効果を生み出すもので、行政はその支援をしていくことです。
例えば、「人口減少対策」では、出生に関わる「自然減対策」と、雇用に関わる「社会減対策」があります。子どもを産み育てやすい環境や雇用の拡大を支援することはできますが、仕組みがあっても市民が実践できなければ効果は上がりません。
要はその仕組みが当事者である市民にとって使いやすいものかどうかです。市民の意見や気持ちを十分に取り入れているか、現場の立場で仕組みができているかです。その検証をしていくのは議会の役目であり、それ故に県民代表となるわけです。私たち議員が県民と身近にいないとすれば、仕組みが形骸化し、効果を上げることはできません。
地方の競争である地方創生は、行政、議会、市民、企業等地域が一体で取り組んでこそ、勝ち抜くことができます。
さて、地方創生における議会のあり方について少し触れたいと思います。
議員は一人で活動することはできますが、議会という組織の一員であり、物事を決める時には最終的に採決という手続きで規定以上の議員の同意が必要となります。
自分と同じ考え方を共有できる議員をできるだけ多く見つけなければなりません。特に、議員自ら仕組みを作る場合、例えば「議員発議条例」がいい例ですが、多くの議員の賛同を得なければ目的が達成できません。普段から議員同士の交流を深め、様々な議論を重ねていくことが重要です。
市町の場合は、基礎自治体と言われるように行政単位では基本となる規模であることから行政全体での取り組みとしてまとめやすい様に思えます。静岡県の場合はこの基礎自治体が35あり、自治体単位で、あるいは周辺自治体と一体で、東部・中部・西部の区分けのように、県全体で取り組む課題の他、地域ごとに取り組む課題も多く存在します。
県議会議員は、県全体と地元自治体だけを見ているのでなく、基礎自治体の枠を超えたものは何らかの関わりが持てる立場と理解しています。
県内では、三島田方地域や浜松市域など、広域での課題についてそれぞれの地域選出の県議会議員が集まり勉強会を開いています。また、富士市で本年度から取り組み始めた域内選出県議会議員と市議会議員による合同勉強会などがあり、より地域性の強い政策提言に向け議員活動が活発化しています。
さらに「議員連盟」という組織を立ち上げ、政策課題となり得る分野を掘り下げるための勉強会を開いています。私の所属する自民改革会議では、農林水産業振興やスポーツ振興、防災、物流、国際交流、医療・介護、教育、中小企業支援等、31もの議員連盟を立ち上げ、関係する業界関係者との意見交換や現地視察などを通じて、政策提言に務めています。11月19日には、私も発起人となって「リハビリ支援議員連盟」を立ち上げたところです、これは、地域包括ケアシステムが機能する上で重要なリハビリ分野の充実を図るために設置しました。
このような活動を実現するために議会閉会中も時間を費やしており、最近では「通年議会」として「常に議会を開いている状態」にという意見もあります。
1999年に「地方分権一括法」が制定されて以来、地方の自主自立を目指し議会自ら政策提言できる仕組み「議員発議による条例制定」が進行しています。私が県議になって以来、静岡県議会では年平均1本以上の議員発議条例が制定されてきました。
地方創生を本格的に進めるための今後の課題は、広域な取り組みを活発化することが重要で、市町や議会の枠を超えた連携をもっと進めなければならず、その取り組み次第によっては、地方間競争に負けてしまうこともあり得ます。フンドシを締め直して頑張らねば。