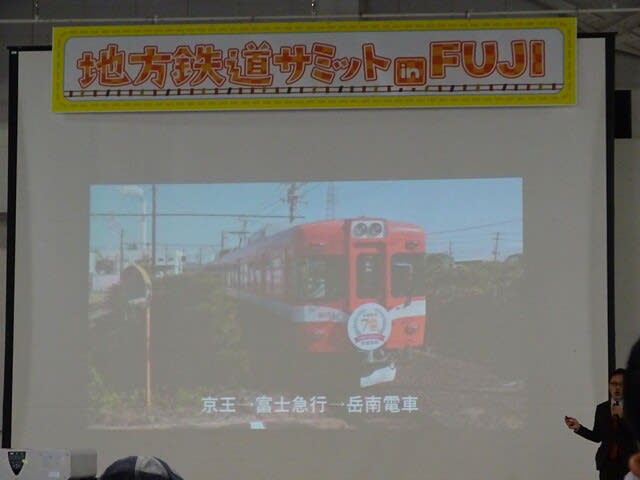令和4年11月30日(水)
富士商工会議所商工振興委員の10月に行われたアンケート結果が届きました。商工振興委員は市内の商工業者70名ほどがいて、分野は様々です。
その時々の経済状況や地域の情報などを提供してくださり、現場の意見として大変貴重な内容です。その中から気になる情報を抽出してみました。
やはり一番気になるのは、新型コロナウイルス感染症の影響や、原油高・物価高騰による課題が多く16名が述べていました。
住宅建築業者からは、物価高の影響で材料費の値上がりは非常に厳しい状況が続いている。木材については一部国産に変更していく予定である。住宅設備も価格上昇のほか、入荷も遅れ気味で、住宅価格の上昇を招いている。お客様からの問い合わせや受注も月ごとにその差が大きく、先が読めない。
その他、卸売業や小売業、製造業、建設業などの分野でも、同じように材料費の高騰による製品価格への転嫁を強いられているものの、消費者の買い控えに直結するものであり、経営的に大変厳しいといった意見が多く見られました。
製造業からは、仕事を受注するにあたり1か月前に見積書を作成したが、原材料費の値上がりが短期間で発生しており、受注が決まる直前と比べて、その差が大きく、受注にあたり大変苦労しているという意見もありました。
燃料小売業者は、燃料高に対応して、ガソリン等に次いでガス料金も国が支援策を検討している。しかし、地方で利用の多いプロパンガスは対象外となるようで、制度設計を見直してほしい。
税理士からは、資源高が中小企業を直撃する中、物価高で従業員からの賃上げ要望が高まっているため、連合は来年の春闘ではベースアップ分を含め5%程度の賃上げを要求する方針と報じられている。賃上げに関しては優遇制度もあるが、中小企業は厳しい経営環境におかれ、要望に応えるのに苦慮している。
行政による支援策について触れているものもありました。
小売業からは、県の物価高騰補助金は、パソコンのような汎用品も対象になるため、非常に活用しやすい制度だと感じている。省エネ設備などへの更新を検討していきたい。
物価高騰が地域経済に与えている影響はかなり大きいと感じています。これに対する行政支援も実施されていますが、利用者にとって使いやすいものなのか、現場の声に真摯に耳を傾け、きめ細やかな支援ができるよう声を上げていきたいと思います。