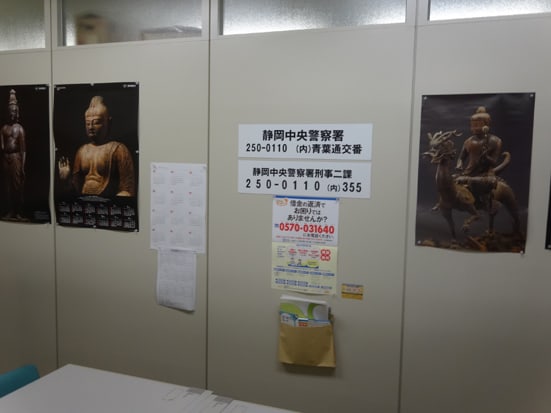平成28年7月27日(水)
県内視察二日目は、静岡市内にある「静岡地方税滞納整理機構」と、「ふるさと納税で沸く焼津市」、富士山静岡空港西側に設置された「原子力防災センター」、「広域防災拠点」の4箇所を回りました。
「静岡地方税滞納整理機構」は、本来であれば、市町が徴収義務のある地方税の徴収困難事案の滞納整理を主として行う、静岡県と県内全市町で構成する組織です。簡単に言えば、市町で徴収できない地方税を、市町に代わり徴収する組織です。

(機構入り口に掲げられた看板)

(担当者から取り組み状況を聞く)
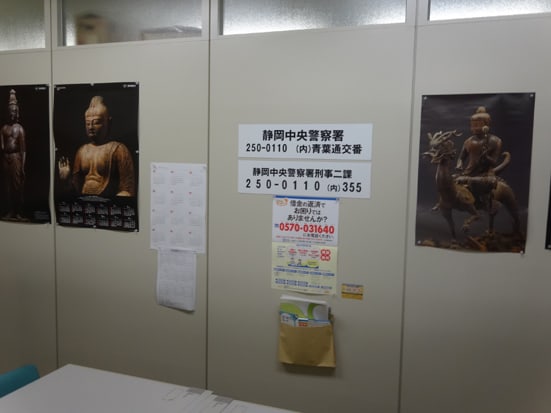
(相談室の壁には、もしもの連絡先が掲示されている)
全国では、都道府県とそこに所在する全市町村が一体となって組織するところは、本県と長野県のみです。
滞納整理の他には、市町職員の徴収業務及び課税業務の研修、軽自動車関係税の申告書処理業務を行います。
税の徴収は、その市町運営の原資であり、それが徴収できないとなれば、行政運営に大きく影響が出ます。平成27年度の本機構が関わって徴収された税額は、22億4千万円であり、多額な税金の確保につながりました。
滞納整理の特徴は、差し押さえ・公売など、法律に基づく強制徴収の方法を中心とした滞納整理で、市町の場合、対象者と職員の存在そのものが身近なケースもあり、強制的な手続きはしにくいとされます。それを、離れた組織であれば淡々と事務的に対応できるということです。
どのような税が滞納対象かというと、固定資産税、個人住民税、国民健康保険税が9割を占めるということでした。
法的な処置を間違いなく進めるために、時には反社会的勢力を対象とすることもあり、事務局には、弁護士、国税OB、警察OB、銀行員などが顧問職で配置され、週1回4時間の勤務が行われています。
次に視察したのは、焼津市役所で「ふるさと納税」の寄付額で、平成27年度全国第2位(38億2,500万円余)となった、焼津市の戦略を伺いました。

(冒頭で挨拶する、中野焼津市長)

(提供された焼津市のふるさと納税に取り組む説明資料)
最近は、ふるさと納税に関心が高まり、同時に「お礼の品」について、何かと話題になっています。品物は高額化・多様化し、納税という感覚からずれてきているのではと言われています。
ふるさと納税の仕組みを簡単に説明すると、地方自治体がふるさと納税者を募り、納税してくれる人に対して、納税額に応じたお礼の品を送るというものです。
焼津市では、ふるさと納税者が市に寄付(納税)すると、その寄付額に応じ、焼津市特産の海産物を中心とした、約900品目のお礼の品から希望されるものを納税者に送ります。このお礼の品は、市内業者の協力を得て、希望する品物代金を市が協力業者に払い、業者から納税者にお礼の品を送るという流れです。
ふるさと納税者は、全国から魅力的なお礼を用意しているまちを選択します。焼津市は、この魅力的な品揃えを整えることで多くの納税者が集まります。市が取り組む「ふるさと納税」への考え方は、お礼の品を市内業者が取り扱うことで、「産業の活性化」と本来の目的である「税収の増加」のほかに、「市の知名度の向上」(シティセールス)も図られます。
市内業者にとっての「産業の活性化」とは、商品の宣伝、販売機会の増加、売り上げの増加が見込めます。
ふるさと納税者は、納める税金の総額は変わらないということで、この制度に注目しています。
寄付者の地域は、東京都が26.4%、神奈川・千葉・埼玉県が26.5%で、合計半数を超えています。また、寄付金額の内訳では、1万円から3万円未満が56%と最も多くなっています。
38億円の寄付金を原資としての内訳は、お礼品送付他事務機費が約18億円、管理費に4億円、寄付金を活用した「子育て支援」、「流入・交流人口の増加」、「健康寿命の延伸」を目的とした基金に16億円です。「ふるさと納税」を活かしたまちづくりに大きく貢献しています。
これらの施策を思い切って実現した、中野市長のリーダーシップに感銘しました。
最後に、富士山静岡空港西側に設置された「原子力防災センター」は、浜岡原発から2kmほどの距離に設置されている原子力災害対策施設の「オフサイトセンター」と「環境放射線監視センター」を、国が原発から5~30km離れた場所に立地することを見直したことにより、浜岡原発から19.6km離れた静岡空港隣接しに、一体の施設として建設したものです。

(原子力防災センターの外観)

(こんな車両も止まっていた)

(原子力防災センターと広域防災拠点について説明いただいた担当者)

(放射性物質を取り除く大きなフィルター)


(免震装置)

(これも免震装置)

(放射性物資分析室)

(災害が発生した時の前線基地となるオフサイトセンター内)

(ここに原子力の専門家が座って、事故対応を行う)

(関係機関との直通電話)
福島第一原発事故は、様々な教訓を残しました。巨大地震や津波などでこれらの施設が使えなくなると、原発のコントロールができなくなり、また適切な情報が得られなくなることにより、被害は甚大なものになります。
大きな地震から施設を守り津波の被害を受けることなく、また放射性物質の拡散による影響を極力避けるための、「最後の砦」というべき施設です。
建物は免震構造で、原発からの距離を保つことで、先に述べた被害から守られています。
環境放射線監視センターは、各地に設置された放射線監視モニターからここに情報が集まり、自動集積され全体を常時監視することになります。
また、原発周辺で捕獲した魚類や野菜などへの放射性物質の監視を、現在ある浜岡のセンターで行っており、11月を目途にそれらの監視機能が全てこちらの施設に移転されます。まだ、検査環境は整っておらず、視察では空の部屋を見て回りました。
オフサイトセンターは、発災時に「原子力災害現地対策本部」が設置されます。その機能を果たすための数々の施設を視察しました。この施設は、7月1日に国から正式運用が指定され、もしもに備えています。
最後に「広域防災拠点」では、国は平成27年3月30日付けで、「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画」において、救助活動、医療活動、物資の受け入れ等を総合的にかつ広域的に行う、「大規模な広域防災拠点」として富士山静岡空港が位置付けられました。

(空港に隣接する広域防災拠点)
県が所有する原子力防災センターと富士山静岡空港に隣接した土地を活用し、7月上旬には陸上自衛隊による兵站施設開設訓練も行われています。
また、災害時に多くの航空機が飛来することを予想して、航空機用燃料タンクの増設も行われました。
災害対策に完璧はないのかもしれませんが、極力それに向けた取り組みを実感します。