子供を叱るのも、常に真剣勝負です。甘く見てはいけません。
子供の叱り方などについては、ノウハウ本のようなものも出ていますが、個人的には、あまりそういうテクニックに頼りすぎるのもどうかと思います。要は子供の人格を認め、きちんと尊重しつつ、また自分の言葉にも重みと責任を持って、語りかけることが大切だということでしょう。テクニックは、その結果論と見ることができます。
子供を叱っていると、屁理屈をこねられるということもあると思います。
-こういう風にされたら嫌でしょう?-
-ううん、僕(私)は平気だもん・・・-
こんなやり取りになってしまうと、多くの親は、そうした屁理屈に対して、「言い訳するな!」とコミュニケーションを切ってしまうようです。しかし、それでは親の負けです。
念のため、はっきりさせておきますが、親が全体の状況を把握できていなかったり、子供の側にも言い分があるにも関わらず、それを十分に聞かないまま叱るのは論外です。ここでは、そうした全体把握を十分にした上で、子供が悪いことがはっきりしている状況下における叱り方を論じています。
子供がしたことが、本当にやってはいけないことであれば、子供は子供なりに、悪いと思っているはずです。子供が悪いことをしたのが明白であるにも関わらず、屁理屈をこねるのは、子供がそれを素直に認めたくないからだと見るべきでしょう。つまり、子供には子供なりのプライドがあって、親に対してささやかな抵抗をしているわけです。
そういう意味で、子供の人格を尊重しながら叱らなければならない親としては、ここからが勝負です。私の場合、このようなケースにおいて、子供のプライドを守りつつ、彼らを諭すために、今後に向けた約束をすることにしています。
-分かった。でも他の人は嫌なんだから、今後、同じことをするなら○○にしよう-
屁理屈に対して、グダグダ話しても仕方ありません。ただ本当に間違っていることをしているのならば、親は、それが他の人に迷惑にならないように対処しなければなりませんし、そのことをきちんと子供に対して宣言しておく必要があります。他人が嫌がったり、迷惑になる言動を繰り返すというのであれば、子供に対して、今までと違う待遇にしなければならないことを伝えるのです。
これに対して、子供は「うん」と答えるしかありません(「嫌だ」と答えたら、「じゃあ、これからは止めようね」ということで話は終わります)。これが親と子供の約束になります。その約束は、叱られている子供にとってネガティブな条件(行かれない、食べられない、遊べない等々)になりますが、子供が自分で間違っていると思っていれば、口答えできないので、その条件は飲まざるを得ません(子供が間違っていると思っていなければ、何かしら他の言い訳をするでしょうから、その場合には、真摯に耳を傾けなければならないでしょう)。
ここまでの約束ができたら、あとは見守ることです。親は、それ以降、同じような場面で、子供がどのように振る舞うかをきっちり観察しておくのです。そして、そこでもし、子供が前回と違って、正しい振る舞いができたら、きちんと褒めてあげることが大切です。
-見てたぞ、良くできたな-
ここまでで、ひとつの教育完了です。この時点で、子供に対してネガティブな条件を飲まされるという約束は、実行されなくて済むことになります。つまり、すべてが円満に片付くわけです。
私の経験上、子供がどんな屁理屈をこねたとしても、上記のような約束させれば、なんだかんだ言いながら、それ以降は、きちんと言ったとおりの言動をしてくれるようになってくれます。つまり、子供に対して、行かせない、食べさせない、遊ばせないなどの条件を飲ますことはなく、きちんと親の言うことを聞いてくれるわけです。そして、それを褒めてあげると、なかなか照れくさそうにしたりします。
ここから私が感じることは、どんなに屁理屈をこねようが、言い訳をしようが、子供たちは子供たちなりに何が良くて、何が悪いかを感じ取ることができているということです。親が間違いを指摘した瞬間、一時的に屁理屈をこねて抵抗しようとも、本当に悪くないと思っているわけではないのです。そういう意味で、親としては、そうした一時的な子供の抵抗にカリカリするのではなく、冷静に子供の良心を呼び起こしてあげるような叱り方をしなければいけないのだろうと思います。
大人の方が弁が立つし、腕力もあるのは当然のことです。そういう意味で、親が子供を力でねじ伏せるのは、とても容易なことだろうと思います。しかし、それは親の慢心であり、大人の驕りです。子供を叱る際には、そのような力技でなく、子供を一人の人格ある人間として尊重しつつ、彼らがいかに間違っているかを諭し、二度と同じ過ちを繰り返さないように導いていかなければなりません。子供たち自身の良心を呼び起こしてこそ、叱る意味もあるというものです。















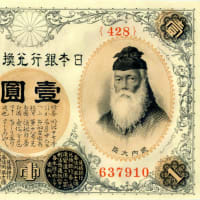
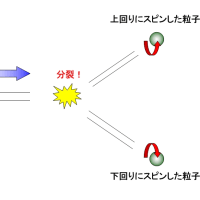
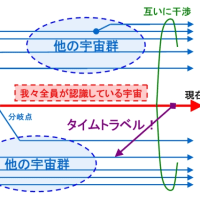
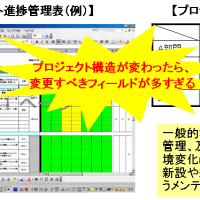
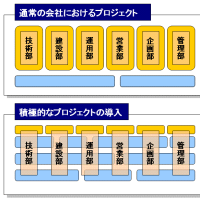





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます