-触らぬ神に祟りなし-
特段、説明する必要はないと思います。「下手に手出しをせず、知らん顔をしていた方が良い」という意味の諺です。これとは別に、私としてはこの諺に含まれる言葉が、「神とは何か」を考える上で、とても深い意味を含んでいるように思えてなりません。
つまり、「神は祟る」ということです。
一神教的な考え方からすれば、人に祟るのは悪魔であり、神が人間に祟るというのは、少々、滑稽に聞こえるかもしれません。しかし、多神教的な世界観からすれば、何も不思議なことではありません。つまり、神にもいろいろいるのであり、人々を救ってくれる神もいれば、人々を苦しめる神もいるというのは、特段、おかしなことではないということです。
一例を挙げれば、学問の神として名高い菅原道真は、「祟る神」としても有名です。神田明神が平将門を祀ったのも、彼を「祟る神」と畏れるが故でした。もしかすると、国を譲った(奪われた)大国主大神が祀られた出雲大社も、国を譲られた(奪った)当時の権力者から「祟る神」として畏れられ建てられたのかもしれません。いずれにしても、多神教的な日本の神社には、単にそこに祀った神様を敬うだけでなく、畏れるという側面も強くあるわけです。
このような「神にもいろいろいる(あるいは、いろいろある)」という考え方は、人間の神に対する接し方にも、大きな影響を及ぼすものと考えられます。つまり、同じ神であっても、その神に接する人がどのような人であるかによって、それが「救う神」にも、「祟る神」にもなり得るということです。神というのは偉大な存在であり、人智を越えた力を持つ存在として敬われながらも、人間が間違ったことをしたときには、その力が大いに人々を祟るとして、とても畏れられるわけです。
このことは、神に接する人間に対して、緊張感をもたらします。そして、そうした人間と神との間にある緊張感が、人間自身の自律を促し、冒頭の「触らぬ神に祟りなし」という諺を生む背景にも影響したのではないかと思うのです。
翻って、一神教を考えたとき、神はただ「救う神」としての顔しか持たず、人間の側の自問自答を促せない危険性を孕んでいると思われます。「救う神」としての顔しか持たない神は、人間との間にあるべき緊張感を失います。つまり、神は救ってくれる存在であり、人間が背負う罪を許してくれるという側面だけで語られると、それが人間の自律する力を殺いでしまうわけです。自らを律する力を失った人間に対して、これを苦しめる日本的な「祟る神」は、一神教的には悪魔になってしまうため、もはや人間は聞く耳を持たなくなります。こうして、人間は暴走を始めるわけです。
私なりには、神との間に緊張感を持たず、自らを律する力を失って、ただ許されると信じる人間が奉る神こそ、人間の心の隙に蔓延る悪魔ではないかと思います。
そういう意味で、一神教的な神は、とても悪魔に近いところにいることに注意が必要です。また逆に、災いを振りまく「祟る神」こそが、人間を自律させてくれる有難い神である可能性についても、きちんと認識しておく必要があるでしょう。
別に宗教を否定するわけではありません。ただ、神や悪魔という概念の狭間で、「祟る神」は、とても面白い位置にいると思うのでした。
《おまけ》
一神教の信者と思しき方々が、とても自らを律しているとは思えない状況下において、さも全てが許される呪文のように神の名を唱える場面を目にすることがあります。このあたりには、非常に大きな違和感を覚えます。それは神ではなく、貴方の心を手玉に取っている悪魔なのでは?ちゃんと自分を律しています?神様って本当は怖いの知ってます?と突っ込みたくなるのです。















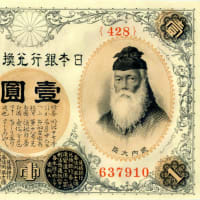
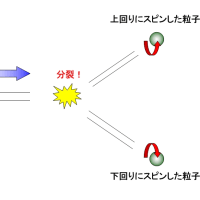
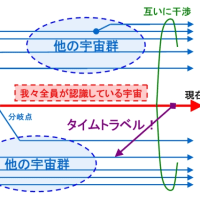
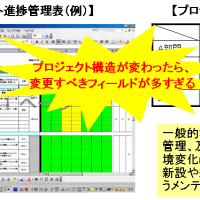
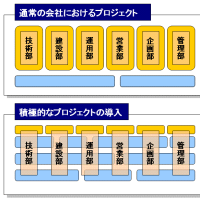





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます