
Thelonious Monk Quartet with John Coltrane 『complete live at the five spot 1958』
‘歌’を作れる数少ないジャズピアニスト、いや、唯一のジャズミュージシャンと言わせてもらう。セロニアスモンクとは正しくコンポーザーではなく、ソングライターである。曲ではない。歌なのだ。モンクのポップな楽曲とは全てに歌詞をつけて歌える種類のものだ。そのソングの至高性はジャズで計る事はできず、再評価の基軸はポップスのフィールドにおいてこそ成立する。それこそレノンーマッカートニーと並び評されても違和感はない。100年後に評価されるソングの領域にエリントンと並んでかろうじて顔を出すジャズアーティストとしてセロニアスモンクは登場するのではないか。
世紀の大発見と言われた『at Carnegie hall』(05)以来となるモンクカルテット ウイズ コルトレーンの音源リリース。驚くほどクリアーな音質だった『at Carnegie hall』と違い、こちらは適度にノイジーな音質で逆に味がある。しかも客の話し声、グラスのガチャガチャした音などが演奏と一緒に飛び込んでくる。これが逆にいい。コルトレーンは‘ソロの時にレジをチャーンっと鳴らす無神経さ’をジャズへの芸術的無理解に覆われたクラブという商業空間の問題として批判した事がある。しかしこのクソ生真面目なコルトレーンによる真摯なソロがモンクの超越ポップな世界の中では、こじんまりハマッてしまうのは何故か。モンク楽曲の突き抜けたポップ性による環境支配性があらゆる雑音や喧噪をその音楽世界に取り込む広さを有しているからだ。静寂に立ち上げるべく究極のソング、「round about midnight」さえ、ノイズを許容する事を我々はモンクの過去のライブアルバムで知っている。酔客の喋り声が楽曲の間に絡む「round about midnight」がスタジオテイクの緊張感に増して味があるのは、やはり、楽曲の持つ力であると想起する。
マイルスグループをクビになったコルトレーンが助けを求めるように参加したモンクカルテット。人生の転換期だったと後に回想するコルトレーンがモンクから学んだものは果たして何だったのか。モンク楽曲の素っ頓狂でプリティなテーマに続くコルトレーンの無骨で長大なソロ。マイルスのところでもモンクとでも「結局、同じ事、やってるやん」と突っ込みたくなるようなその‘生真面目、真っ直ぐ’スタイルだが、そのフレーズ、音階がより圧縮されたものに感じられるのは、モンクメロディの雄弁さのせいか。つまり、コルトレーンを加えたモンクカルテットは歌と音響の相互性を実現していると思われるのである。明確な意志を持った歌、誰もが口ずさみたくなるような明快なメロディを持つモンク‘歌曲’だからこそ、ソロ演奏の音階的圧縮性や音響的な堅固さとのコントラストが鮮明になる。交互に現れるテーマとソロは旋律的振幅性やもはや演奏の根拠さえ、別の場所から発せられるような対比を生み、それは意外性へとつながってゆく。しかも大衆的ですらあるだろう。
モンクの元を離れたコルトレーンが60年代以降、すさまじいばかりの音楽創造を遂行してゆく一連の演奏作品の中に、テーマの強化、即ち、歌う強さを押し進め、ソロの無軌道なフリー性との対比、融合を計った事はやはり、モンクの中にあるコンセプトに通底する部分を認めないわけにはいかないだろう。
ジャズの批評では、しばしば、コードワークの斬新的手法やモード奏法に関する研鑽という点がコルトレーンのモンクカルテットでの収穫であると指摘される。それもあるだろう。しかし、私には、モンクの作る歌に感銘を受けたコルトレーンが、自らの創造において、自分の歌を歌う必然性を感じる事によって、音響探求との両立と作品の普遍性、娯楽性を勝ち得たという成果の方が、より大きいモンクからの影響だったと感じるのである。
2009.2.23



















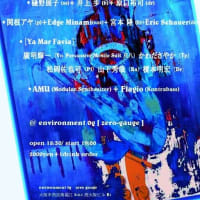






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます