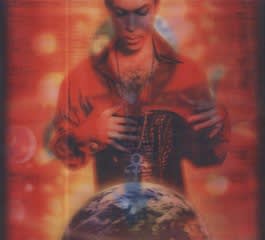
福井県小浜市が米民主党の大統領候補オバマを応援する会などを作り、勝手に物を送ったりして、日本の恥をさらしている。同じ名前という事だけで面白くもない親父ギャグを外国に発する無神経さ。案の定、当のオバマには相手にもされていない。平和ボケを通り越したもはや幼稚なお遊び如きを公的にやってしまう、この日本独特の脳天気さが許せない。町興しなら別のやり方でやればいい。こんなものシャレでもユーモアでもない。阿呆だ。「その政策にも共感している」などと厚顔無恥な言い訳けまでしている。じゃあ訊くがお前達は何故、ヒラリーじゃなくオバマなのだ?そもそも何故、民主党なのだ?小浜市と言えば拉致被害者もいるだろう。拉致問題の早期解決の為には比較的、親日的な共和党、マケインを応援するのが本筋じゃあないのか。そんな単純な話じゃないって?もっと深い読みと分析があるって?ああそうかい。勝手にやってろ。
と、どうでもいい事でムキになってしまったが、私はオバマには興味を持っている。
「リベラルのアメリカも保守のアメリカもなく、ただ“アメリカ合衆国”があるだけだ。ブラックのアメリカもホワイトのアメリカもラティーノのアメリカもアジア人のアメリカもなく、ただ“アメリカ合衆国”があるだけだ。イラク戦争に反対した愛国者も、支持した愛国者も、みな同じアメリカに忠誠を誓う“アメリカ人”なのだ」
きれい事でもあり、戦略的言説でもあるが、彼のエネルギーの源泉に一種の‘アイデンティティークライシス’がある事は感じられる。黒人と白人のハーフ。父はイスラム。自らはプロテスタント。ルーツが単純に規定できない多様性を背負ってしまった苦悩。それが思考の包容感覚、多義性に直結しているのか。人権派でありながら国家主義者。格差や貧困を社会と個人の双方に対する責任と因果関係に求める真のニュートラル精神。自らの立場をワンサイドに置く‘解りやすさ’を放棄し、総体を意識する困難に向かう気構えを感じる。それとも単なる二枚舌なのか。ただ、パウエルでさえ自制した黒人初の大統領という座を目指してしまった自分の拠り所をもはや相対的な思想には見出せなくなっているのは確かだろう。多様性を貫いて自爆するか、それとも大ブレイクするか。
「父親が黒人で母親が白人」と昔、嘘をついたのはプリンスだった。子供じみたジョークにしては内面の屈折度が推し測れるというものだ。こんなまるで朝日新聞のような捏造をばらまく彼もまた、遙かなる多様性を希求する‘アイデンティティークライシス’の持ち主だろうか。もっとも、その変幻自在な才能、広角な音楽性を顧みれば、彼を単なるブラックミュージックの旗手と規定しなかった世間にも許容されるジョークではあるだろう。80年代のプリンスの驚異的な作品群は黒人音楽をリードし、超越し、無効化していた。プリンスはあの時代、確かに<プリンス>というたった一つのジャンルだった。JBもスライもスティービーもマービンもアイザックも彼の中にはいたが、私達はプリンスにブラックミュージック的後継ではなく、突然変異的アーティストの戦慄性を見ていた筈だ。
ブラコン化した瀕死のソウルミュージックの灰の中からプリンスは現れた。初期のソウルモードから徐々に戦略的変身に至りポップスターとなる。それは白人迎合的な結果ではなく、内部の屈折感覚、特異な感性からくる必然的発展であっただろう。彼の内部には、あらゆるセクトの解消に向かうラジカリズムがあったと思う。黒人アーティストとして当然持つソウルアイデンティティーすら既成概念を差異と認め、溶解させた。ヒップホップ台頭期にもそれらとリンクする強力なリズムを有しながらプリンスは結果的にメジャーな音楽性を誇示した。白人ハードロックもどきのエレキギターを偏愛する姿にはもはや、‘超越ポップ’としての天才性が見えたものだ。
人種やナショナリティ、性差までもイメージ的に解消した小柄な黒人。気持ち悪いエロさ、悪趣味。そのマッチョと程遠い‘異人’キャラクターは新たなブラックミュージックの創造を思わせたが、そのフォロワーは生み出さず、孤高の天才となる。作曲、編曲、演奏、制作、ビジュアルイメージ、全てを一人でやってしまう孤独。バンドを組んでもそれはライブ用で、レコーディングでは全ての楽器を自分で多重録音するオタク性。寂しい奴だ。
『Purple Rain』(84)から『Around The World In A Day』(85)、『Parade』(86 )、『Sign "☮" The Time』(87)、『Lovesexy』(88)、そして最強の海賊版『black album』(87)とその神憑り的才能は永遠のものに思えたものだが、しかし意外にも翳りはやってきた。『Batman』(89)あたりからおかしくなり、何とも微妙な『Graffiti Bridge』(90)に至る。良いのだがプリンスにしては驚きのないアルバムだった。そして『Diamonds And Pearls』(91)を聴いたときのショックは忘れまい。こんな面白くないレコードが本当にプリンスなのか。続く『Love Symbol』(92)も同様の凡庸さであった。ヒップホップ隆盛期に聴くにこれらは正直、苦しかった。
90年代を境に失速していったプリンス。
無尽蔵の才能と思われたアーティストがゆっくりと普通のタレントに定着していった。その天才の最たるものはコンポーザーとしての力量だったが、それはやはり有限であったか。ポールマッカートニーやスティービーワンダーでさえ授からなかった‘永続する才能’を神はプリンスに対しても例外を認めず与えなかったようだ。
パーラメント的ブラックモードを実現した『black album』(87)がワーナーによってリリース不可になった時、プリンスの中に創造に対する抑圧や葛藤が生じたのかもしれない。『Diamonds And Pearls』(91)の<悪趣味>は嘗ての<悪趣味>とは訳が違った。それは白人資本に迎合した産物に映った。プリンスがプリンスをコピーした。ヒットはしたが、その音楽クオリティーの低下は隠せなかっただろう。ワーナーとの対立は深刻だったか。彼は資本主義に絡め取られ、妥協した。その抑圧を突き破る楽天性をプリンスは持ち合わせていなかったという事か。ジョージクリントンのような在り方、奔放性とは無縁なプリンスはやはり内向的な感受性のアーティストだろう。あらゆる‘疎外’こそがパワーの泉であり、強い‘アイデンティティークライシス’こそがその表現の豊饒性を実現していたのだから。彼の内面の屈折度が音楽創造以外のところでマイナスに作用したのかもしれない。もはやヒットチャートを回復する事が命題になったプリンスは同時期のヒップホップの隆盛も尻目に見ながら存在性を失っていく。随分、勝手な推測をしているが、それ位、その凋落ぶりの印象は強かった。
ワーナーが『black album』をボツにした時、何かが壊れ始めたのだ。あのハードコアな音楽を資本は許容せず、プリンスはその反発で高濃度ポップアルバム『Lovesexy』を作り上げた。私は『black album』と『Lovesexy』を二枚組にしてリリースするべきだったと思う。彼の音楽性の両輪を具現化した大作になった筈で、それは結果的にプリンスの認識のされ方がより広汎になる可能性があったのではないか。
90年代、プリンスの音楽的試行錯誤はそのまま、迷走の記録となった。
*****************************
その復活は意外と言えば失礼か。本来のソングライティングが光る『3121』(06)
同時代に適合したように言われヒットしたが、私はむしろ同時代ブラックミュージックの退行のベクトルとプリンスの復活がリンクしているように感じている。90年代のプリンス失速と同時に隆盛したハードコアラップや創造的ヒップホップ。それらは若きブラックメンのスタンダードとなり、時代の絶対的メディアとなる。しかしメジャーシーンでの変質は90年代後半から始まっていた。嘗て80年代にブラコン化したソウルの軟弱志向と同様、2000年前後、ヒップホップはマッチョ路線のゴテゴテ感覚を伴い、軟化に至る。プリンス再登場の契機があらわれた。
プリンスはやはり黒人音楽の衰勢と共に在るようだ。シーンが沈滞化するとその存在が浮上する。ヒップホップの後退現象を私はそのサンプリング至上主義が招いたものと思っている。古典を掘り、サンプリングする加工作業が限界にきた時、黒人達は速やかに‘演奏’に還るべきだった。それをしなかった。サンプルのネタが尽きた今、作曲と演奏が再び、問われ出した。従ってその才能の権化たるプリンスが復活したのだ。
『PLANET EARTH』は復活第2弾。
クールファンク、ゴージャスメロウバラッド、ミニマムポップ。ギターロック。
プリンスの全方位的ソングライティングが発揮される。10曲のみという短めの構成もいい。
彼の多面世界とはそれが自然発生的に抽出される時、表現の極みとなる。逆にある特定のコンセプトや一つの方向を向く時、表現力の遅緩状態が現れる。プリンスにとってアイデンティティーとは果たして玉石混淆であろうか。ただそれは方法論の多様性であって、プリンスは明らかにいつも物語を紡ぎ出そうとしている。‘一つの物語’、‘真理なるもの’へのアプローチが彼のテーマであり、苦悩の源泉でもあった。多面世界とはアイデアの宝庫たりえど、内面の深部に於ける‘アイデンティティークライシス’は常に実際問題として立ちはだかる。彼はいつも‘一つの道筋’こそを求めていたのだ。私が思うにそのアプローチを純粋に音から立ち上げる時、雑多なものが一つのまとまりを示し、普遍的作品へと昇華していたのではないか。逆にコンセプトが先行する時、無惨な形として現れる。
『PLANET EARTH』はプリンスの素直な作曲が光り、多数のメンバーによるバンドサウンドの開放性を実現した。メシオパーカーまでいる。今回の作品の意図は地球の未来に対する想いを散りばめたコンセプトアルバムらしいが、もはや、そのメッセージの重きが楽曲の構築感の前で霧散する印象がある。つまり音から立ち上がった結果としてのコンセプト、メッセージがその背後性としてバランスよく収まっていると感じられる。
ストーリーテラーたる資質、或いはビジュアルメージの音象化というプリンス独特の感性は‘視ている場所’の相違をしばしば私達、凡人に突きつけただろう。しかし作品としての客観性はいつも楽曲先行主義に従った制作の時、発揮された。『PLANET EARTH』はそんなアルバムの一つだろう。曲がいい。それだけだ。ただ、それこそが全てだ。
「guitar」というそのまんまのタイトル曲で得意のメタルギターを弾きまくるプリンスの開放的音響。初心に還った?いや、千曲あるというストックの一部を出しただけ。そんな答えがさり気なく返ってきそうな感じがする。無自覚なほど自然体な天才の最良部分がここに現れたようだ。
2008.4.5



















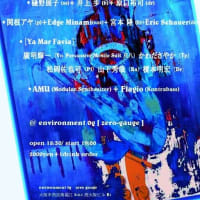






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます