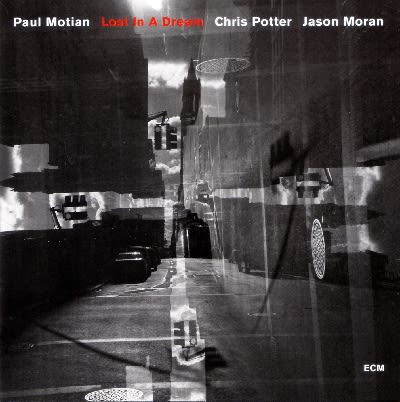休日も忙しく、せめてもの刺激剤として、スティーヴ・リーマンを3枚お供に日がなデスクワーク。
■ 『On Meaning』(Pi Recordings、2007年)

Steve Lehman (as)
Jonathan Finlayson (tp)
Chris Dingman (vib)
Drew Gress (b)
Tyshawn Sorey (ds)
■ 『Travail, Transformation, and Flow』(Pi Recordings、2008年)

Steve Lehman (as)
Mark Shim (ts)
Jonathan Finlayson (tp)
Tim Albright (tb)
Chris Dingman (vib)
Jose Davila (tuba)
Drew Gress (b)
Tyshawn Sorey (ds)
■ 『Mise en Abime』(Pi Recordings、2014年)

Same as above
どの瞬間も不穏なるものが充満している。緊密ではあるが、ヘンリー・スレッギルのグループのようにすべての時空間に筋線維がみっしりと張り詰めているわけではなく、しかし(デイヴィッド・マレイのオクテットのように)ルーズでもない。テンションの多寡が価値ではないから、もうひとりのサックスやチューバが加わって厚みを増したオクテットが、クインテットよりも単純に進化したというわけでもない。
充満したアウラは、徹底的に人工的で、覚醒した何か。ひとつひとつが眼や脳を持った無数の意識的な粒子の中で、抑制されて、いびつに自覚的なリーマンのアルトソロが繰り広げられる。この音楽をIT空間に浮遊させるヴァイブの効果もある。ひたすらに多数の情報を収集し、ときに知的、ときに乱暴に吐き出したようなタイショーン・ソーリーのドラムスにも耳が吸い寄せられる。
この3枚はそれぞれ素晴らしいのだが、中でも、最近作の『Mise en Abime』は異常に完成度が高い。リーマンが発する電子楽器の音も抑制的でクール、またエロチックな感もある。
●参照
スティーヴ・リーマンのデュオとトリオ
ジョン・エスクリート『Sound, Space and Structures』(タイショーン・ソーリー参加)