さて、計算の仕方は身についた。うちは完璧と思われている方も油断は禁物です。
文章題の式作りと、答えの書き方という山があります。
「ずつ分ける」は『割り算』が刷り込まれていれば、立式は比較的容易だと思います。
あと、テストの一番上に『あまりある割り算』というタイトルが書いてあれば、まず間違いなく割り算でしょう。
のんびりちゃん達は、そういう事を頼りに案外簡単に立式までは持っていけます。
(まとめの問題になって、掛け算割り算混ざってくると失敗も増えますから、『分けるは割り算』というのは刷り込んでおいて損はないと思いますよ。)
問題は、答えの書き方。
割り切れる割り算の答えは、これまでと同じですから悩みませんが、
あまりまで書くものとなると混乱は避けられません。
今日も何人もが?????を抱えて困ってました。
問題文をよく読むだけでなんとかなりそうなおこさんはおうちで何とかしてください。
ここから先はかなり荒っぽい教え方ですが・・
『質問文(?)』を探す方法。
「か。」がお尻についているのが『聞いていること』だから、まず「か」を見つけて
そこから線を前に引く。
点や丸の区切りで一度止め、その前の文に「何」がなければそこまで。
「何」という字があったら、その「何」まで線を引く。
すっごい方法でしょ。でも、これで一人、ダラダラつながった文章の中から、
質問文を見つけて、聞かれている事がなんだかわかるようになったんですよ。
『何』を利用する方法。
余りある割り算の文章題の場合、
『何人に分けられて、何個あまりますか。」
というような質問文になります。
この『何』に○で印をつけます。
で、自分で出した答えの数字(答えとあまりのふたつの数字です)を、それぞれの
『何』の上に書いて、そのまま答えの欄に書くんです。
この段階で、『どっちの数字?』と聞いてくる子もいます。
「あまり」という言葉に注目させてわかるようならそれで良し。
それでもわからないようなら、またまた具体物の登場かな。
明日のテストに間に合わせたいという目的なら、
「いいから、そのままの順番で書き込みなさい!」
でもいいかと・・・。
あまりを先に問う問題文はないですからね。
のんびりちゃんは『はじめて』に弱いです。
『分けると何個ですか?』という問題文にならすんなり答えられる子も、
『○こずつ分けると何人に分けられて何個あまりますか?』
となってしまうと、手も足も出なくなる事があります。
事前に体験しておくだけで大丈夫というお子さんも多いので
良かったらやってあげてください。
あと、もう1問、ひねった問題が出る事もあります。
あまりの出る割り算なのに、ちょうどの数を問う問題。
俗に『引っかけ』という奴です。
例えばこんな感じ。
38人の子供がいます。6人ずつ長いすに座ると
長いすはいくついりますか?
という問題。
これは、難しいので今の時点でできていなくてもあまり気にしない方がいいと思います。
深追いするとかえって混乱するかもしれないので、テスト直前に教えたほうがいいかどうか、その辺りは良く考えてくださいね。
のんびりちゃんは、
38÷6=6・・・2
と計算し、答えに6あまり2
と書いてしまいますが、それでも式のところで部分点はもらえますもんね。
うちは行けそうだと思う方は、「絵」を描いてみましょう。
問題文を絵にしていって、6人ずつかけた長いすを6個描き、
その横にあまった2人の子供を描く。
「この子達も座らなきゃいけないから、椅子は何個いるの?」
と振ってみます。
『7個』と答えても、それを答えの欄に書いていいのかどうか迷う子がいます。
もう一度質問文を読んで、大丈夫なんだと感じてもらいます。
そう、質問は『椅子の数を聞いている』という事が読み取れていないと難しいんですよね。
さて、この手の引っかけ問題、逆のパターンもあります。
41本の花を5本ずつの花束につくります。花束はいくつできますか?
41÷5=8・・・1
前の問題をやった後でこれをすると、
答え 9束
とやる子がいます。
絵を描いて確認しましょうね。
あまりがあるのにちょうどの数を問う問題の時には、答えより一つ増えるときと、答えの数のままの時があると知っておけば、テストでも安心してできる子がいます。
でも、一方でどうしてもこの問題の意味が良くわからない子がいます。
最初の問題には、
「子どもは全員椅子に座らなければならない。」「椅子は長いすしかない。」
という暗黙の了解が隠れています。
後の問題には、
「花束は何本もの花が一塊になって作られたものである。」「花束に使われる花は全部6本ずつでなければならない。」「あまった花は花束にはならない。」
という事が隠れています。
こうした事が、難なくわかる子もいれば、どうしてもわからない子がいます。
うちの子は「どうしてもわからない子」らしいと思っても焦らないで。
体験を積むことで、こうした「暗黙の了解」は身についてきます。
算数の問題をとおして、「こんなことを体験させてあげたらいいかも」
って考えてもらえたらいいなと思います。
我が家の呪文。
「できる事は積み残しなく。今できない事は働きかけを続けながら脳の成長を待つ。」
文章題の式作りと、答えの書き方という山があります。
「ずつ分ける」は『割り算』が刷り込まれていれば、立式は比較的容易だと思います。
あと、テストの一番上に『あまりある割り算』というタイトルが書いてあれば、まず間違いなく割り算でしょう。
のんびりちゃん達は、そういう事を頼りに案外簡単に立式までは持っていけます。
(まとめの問題になって、掛け算割り算混ざってくると失敗も増えますから、『分けるは割り算』というのは刷り込んでおいて損はないと思いますよ。)
問題は、答えの書き方。
割り切れる割り算の答えは、これまでと同じですから悩みませんが、
あまりまで書くものとなると混乱は避けられません。
今日も何人もが?????を抱えて困ってました。
問題文をよく読むだけでなんとかなりそうなおこさんはおうちで何とかしてください。
ここから先はかなり荒っぽい教え方ですが・・
『質問文(?)』を探す方法。
「か。」がお尻についているのが『聞いていること』だから、まず「か」を見つけて
そこから線を前に引く。
点や丸の区切りで一度止め、その前の文に「何」がなければそこまで。
「何」という字があったら、その「何」まで線を引く。
すっごい方法でしょ。でも、これで一人、ダラダラつながった文章の中から、
質問文を見つけて、聞かれている事がなんだかわかるようになったんですよ。
『何』を利用する方法。
余りある割り算の文章題の場合、
『何人に分けられて、何個あまりますか。」
というような質問文になります。
この『何』に○で印をつけます。
で、自分で出した答えの数字(答えとあまりのふたつの数字です)を、それぞれの
『何』の上に書いて、そのまま答えの欄に書くんです。
この段階で、『どっちの数字?』と聞いてくる子もいます。
「あまり」という言葉に注目させてわかるようならそれで良し。
それでもわからないようなら、またまた具体物の登場かな。
明日のテストに間に合わせたいという目的なら、
「いいから、そのままの順番で書き込みなさい!」
でもいいかと・・・。
あまりを先に問う問題文はないですからね。
のんびりちゃんは『はじめて』に弱いです。
『分けると何個ですか?』という問題文にならすんなり答えられる子も、
『○こずつ分けると何人に分けられて何個あまりますか?』
となってしまうと、手も足も出なくなる事があります。
事前に体験しておくだけで大丈夫というお子さんも多いので
良かったらやってあげてください。
あと、もう1問、ひねった問題が出る事もあります。
あまりの出る割り算なのに、ちょうどの数を問う問題。
俗に『引っかけ』という奴です。
例えばこんな感じ。
38人の子供がいます。6人ずつ長いすに座ると
長いすはいくついりますか?
という問題。
これは、難しいので今の時点でできていなくてもあまり気にしない方がいいと思います。
深追いするとかえって混乱するかもしれないので、テスト直前に教えたほうがいいかどうか、その辺りは良く考えてくださいね。
のんびりちゃんは、
38÷6=6・・・2
と計算し、答えに6あまり2
と書いてしまいますが、それでも式のところで部分点はもらえますもんね。
うちは行けそうだと思う方は、「絵」を描いてみましょう。
問題文を絵にしていって、6人ずつかけた長いすを6個描き、
その横にあまった2人の子供を描く。
「この子達も座らなきゃいけないから、椅子は何個いるの?」
と振ってみます。
『7個』と答えても、それを答えの欄に書いていいのかどうか迷う子がいます。
もう一度質問文を読んで、大丈夫なんだと感じてもらいます。
そう、質問は『椅子の数を聞いている』という事が読み取れていないと難しいんですよね。
さて、この手の引っかけ問題、逆のパターンもあります。
41本の花を5本ずつの花束につくります。花束はいくつできますか?
41÷5=8・・・1
前の問題をやった後でこれをすると、
答え 9束
とやる子がいます。
絵を描いて確認しましょうね。
あまりがあるのにちょうどの数を問う問題の時には、答えより一つ増えるときと、答えの数のままの時があると知っておけば、テストでも安心してできる子がいます。
でも、一方でどうしてもこの問題の意味が良くわからない子がいます。
最初の問題には、
「子どもは全員椅子に座らなければならない。」「椅子は長いすしかない。」
という暗黙の了解が隠れています。
後の問題には、
「花束は何本もの花が一塊になって作られたものである。」「花束に使われる花は全部6本ずつでなければならない。」「あまった花は花束にはならない。」
という事が隠れています。
こうした事が、難なくわかる子もいれば、どうしてもわからない子がいます。
うちの子は「どうしてもわからない子」らしいと思っても焦らないで。
体験を積むことで、こうした「暗黙の了解」は身についてきます。
算数の問題をとおして、「こんなことを体験させてあげたらいいかも」
って考えてもらえたらいいなと思います。
我が家の呪文。
「できる事は積み残しなく。今できない事は働きかけを続けながら脳の成長を待つ。」










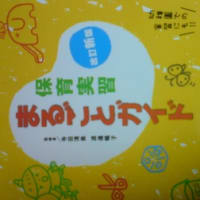




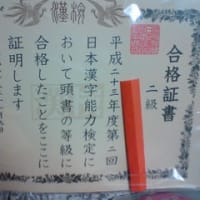




勝手ながら、自分のブログに紹介させていただきました。もしご迷惑でしたら、申し訳ございません。削除します。
どうぞよろしくおねがいいたします。
ひまわりさんのブログも拝見していて、
紹介してくださった、一つ前の記事、私も嬉かったですよ。
のんびりちゃんの子育てって、確かに、大変な部分があるんですけど(私の感覚では「大変」というより「メンドクサイ」なんですけどね)、
子どもが階段を一段上がったと思えたときの喜び
というか 感動というか 楽しさというか、
そういうものは確かに他のお母さん達よりたくさんもらえているのかなと思います。
それが、エネルギーになって、メンドクサイことが何より嫌いな私が、メンドクサイことを、こうしてしつこく続けていられるのかなって思うんですよ。
長く続く子育てです。おたがい自分の体を長持ちさせるように気をつけて、この時間を楽しみましょうね。