1年生の担当を数年続けています。
2年に一人くらいの割合で、
「これは、純粋LDかも・・・」
と思えるお子さんに当たります。
他の能力に比べて、明らかに「読み書き」の能力に
弱さのあるお子さんです。
毎年、ひらがなを全部覚えるまでに時間がかかるお子さんはいます。
鏡文字が出やすい子、小さな「つ」や、「や」「ゆ」「よ」のつく文字が
読めない子、一文字ずつの読み方がなかなか進化していかない子。
そんなお子さんは、毎年必ず複数入ってきます。
でも、その前段階である
ひらがなの「音」と「文字」がくっつかないお子さんは、
そう多くはありません。2,3年に一人程度いるかどうかだと思います。
こういう状況ならば、「専門家」が付きそうなものですが、
そうでないのが現状なので、毎日サポートできる私が
担任の先生と連携して、やっていくことになります。
今年は、そうしたお子さんが一人います。
6月初めの段階で、「つ」も「く」も読めないお子さん。
これまでのお子さん達に比べても、かなり厳しい方だと思いますが、
他の能力はそれほど低くありません。
どのようにサポートしようかと考える前に、
そのお子さんの状況を見極めなくてはいけません。
特に遅れが出ている
「連絡帳の書き写し」の時間に
毎回張り付くことにして、サポートしながら状況を確認しました。
するとね、縦につながって書かれた文の中で、
一文字一文字の区切りがどこなのか判別できていないということがわかりました。
一方で、区切りがわかれば、かなり上手に視写出来ることもわかりました。
ですので、「ひらがなドリル」のように「書く」だけの学習では
困難さがあまり見えなかったのですね。
まずは、ひらがな一字ずつの形をしっかり入れていくこと。
そして、その一文字ずつに、音を対応させる事を目的にサポート
していこうと考えました。
ひらがなドリルは、本人に困り感もないようですので、特にサポートはしません。
本人が困っている(であろう・・)連絡帳や、
6月ごろから増え始める「書く」活動の時に
なるべく横にいるようにします。
特に連絡帳は、毎日の「書く」活動ですので、
担任の先生に、その日連絡帳を書く時間を聞いて
必ず入るようにしました。
皆が連絡帳を書き始める頃、そのお子さんの横につきます。
「国語の教科書出してくれる?」と頼み、
その中の、「ひらがな」を一文字ずつ書いているページを出します。
どの教科書も、後ろのとじこみにひらがな一覧、カタカナ一覧があると思いますが、
それ以外でも「ひらがなの学習」のページに大きく出ているのではないかと思います。
このお子さんの場合、他の文字とくっついて見える様子がありましたので、
一覧表ではなく、「ひらがな学習」ページの、○で囲まれた文字を見せることにしました。
これだと、どこからどこまでが一つの文字なのかがわかりやすいからです。
先生が黒板に書いたものを、
一文字ずつ読みながら、手元の教科書で指さして書かせる。
「写し書き」は、苦手ではないお子さんなので
ストレスは少なくなります。
同時に、これまでただ「形」を写し取っていただけなのを
「文字と音」を意識させられると思ってのことです。
本人にも言わせたい。音を出しながら字を書かせたい。
でも、それはもっと後の事。
最初は、私が音を出せばいい。指をさして見せればいい。
そういう風に始めました。
やりながら、時々覚えている字がどのくらいあるかを
本人の負担にならない程度にさりげなく試してみます。
私が指さすのを少し遅らせた時、本人の目や手がどう動くのかで
覚えているかどうかはわかります。
毎日毎日。こうしてサポートを続けますが、
そう簡単に読めるようにはなりません。
毎日書いている「こくご」の「こ」でさえ、
なかなか入りません。
でも、私がサポートに入る前までは、
書ききれなくて、皆のように先生に見せに行けなかったのが、
自力で書いて見せに行けるようになったので、
本人、気分は良かったようです。
連絡帳の時には私が横につくということを
当たり前に受け止めてくれました。
連絡帳以外にも、「読む」「書く」という作業が発生しそうな時は、
なるべく隣につきました。
国語の音読も、彼の場合「暗記」で乗り切る様子がありましたが、
文字を指で追って、「一文字一音」を、なるべく
目で見えるようにしていきました。
そして半月以上たったころかな、
私がそうしてきたように、文字を書きながら音にする
いえ、音を出しながら文字を写そうとする様子が見られるようになりました。
教科書を指でなぞる時のやり方も、何となくズルズルっと指を動かしていたものが、
覚えた字のところで立ち止まって順番を確認する様子が見られるようになりました。
「1文字に1音が対応する」という感覚が少し入ってきたように思えます。
自分の名前の中にある文字も(名前は書けます)、他の場面で書かせようとすると
わからなくなってしまうお子さんでしたが、
最近、いくつかの文字に関しては、場面が変わっても音に対応してちゃんと書ける
ようになってきました。
数にすると、まだとても少ない文字でしかないですが、
階段を一歩上がったような気がするんです。
一文字一音という感覚がつかめたら、
例えば、あいうえお表から、自分の使いたい文字を探すことができる。
そこまで行けば、私がいない時でも
自分で文字を探して綴っていける。
繰り返せば、少し時間はかかってもひらがな全部を
頭にしまうことは可能だろうと思うのです。
2年に一人くらいの割合で、
「これは、純粋LDかも・・・」
と思えるお子さんに当たります。
他の能力に比べて、明らかに「読み書き」の能力に
弱さのあるお子さんです。
毎年、ひらがなを全部覚えるまでに時間がかかるお子さんはいます。
鏡文字が出やすい子、小さな「つ」や、「や」「ゆ」「よ」のつく文字が
読めない子、一文字ずつの読み方がなかなか進化していかない子。
そんなお子さんは、毎年必ず複数入ってきます。
でも、その前段階である
ひらがなの「音」と「文字」がくっつかないお子さんは、
そう多くはありません。2,3年に一人程度いるかどうかだと思います。
こういう状況ならば、「専門家」が付きそうなものですが、
そうでないのが現状なので、毎日サポートできる私が
担任の先生と連携して、やっていくことになります。
今年は、そうしたお子さんが一人います。
6月初めの段階で、「つ」も「く」も読めないお子さん。
これまでのお子さん達に比べても、かなり厳しい方だと思いますが、
他の能力はそれほど低くありません。
どのようにサポートしようかと考える前に、
そのお子さんの状況を見極めなくてはいけません。
特に遅れが出ている
「連絡帳の書き写し」の時間に
毎回張り付くことにして、サポートしながら状況を確認しました。
するとね、縦につながって書かれた文の中で、
一文字一文字の区切りがどこなのか判別できていないということがわかりました。
一方で、区切りがわかれば、かなり上手に視写出来ることもわかりました。
ですので、「ひらがなドリル」のように「書く」だけの学習では
困難さがあまり見えなかったのですね。
まずは、ひらがな一字ずつの形をしっかり入れていくこと。
そして、その一文字ずつに、音を対応させる事を目的にサポート
していこうと考えました。
ひらがなドリルは、本人に困り感もないようですので、特にサポートはしません。
本人が困っている(であろう・・)連絡帳や、
6月ごろから増え始める「書く」活動の時に
なるべく横にいるようにします。
特に連絡帳は、毎日の「書く」活動ですので、
担任の先生に、その日連絡帳を書く時間を聞いて
必ず入るようにしました。
皆が連絡帳を書き始める頃、そのお子さんの横につきます。
「国語の教科書出してくれる?」と頼み、
その中の、「ひらがな」を一文字ずつ書いているページを出します。
どの教科書も、後ろのとじこみにひらがな一覧、カタカナ一覧があると思いますが、
それ以外でも「ひらがなの学習」のページに大きく出ているのではないかと思います。
このお子さんの場合、他の文字とくっついて見える様子がありましたので、
一覧表ではなく、「ひらがな学習」ページの、○で囲まれた文字を見せることにしました。
これだと、どこからどこまでが一つの文字なのかがわかりやすいからです。
先生が黒板に書いたものを、
一文字ずつ読みながら、手元の教科書で指さして書かせる。
「写し書き」は、苦手ではないお子さんなので
ストレスは少なくなります。
同時に、これまでただ「形」を写し取っていただけなのを
「文字と音」を意識させられると思ってのことです。
本人にも言わせたい。音を出しながら字を書かせたい。
でも、それはもっと後の事。
最初は、私が音を出せばいい。指をさして見せればいい。
そういう風に始めました。
やりながら、時々覚えている字がどのくらいあるかを
本人の負担にならない程度にさりげなく試してみます。
私が指さすのを少し遅らせた時、本人の目や手がどう動くのかで
覚えているかどうかはわかります。
毎日毎日。こうしてサポートを続けますが、
そう簡単に読めるようにはなりません。
毎日書いている「こくご」の「こ」でさえ、
なかなか入りません。
でも、私がサポートに入る前までは、
書ききれなくて、皆のように先生に見せに行けなかったのが、
自力で書いて見せに行けるようになったので、
本人、気分は良かったようです。
連絡帳の時には私が横につくということを
当たり前に受け止めてくれました。
連絡帳以外にも、「読む」「書く」という作業が発生しそうな時は、
なるべく隣につきました。
国語の音読も、彼の場合「暗記」で乗り切る様子がありましたが、
文字を指で追って、「一文字一音」を、なるべく
目で見えるようにしていきました。
そして半月以上たったころかな、
私がそうしてきたように、文字を書きながら音にする
いえ、音を出しながら文字を写そうとする様子が見られるようになりました。
教科書を指でなぞる時のやり方も、何となくズルズルっと指を動かしていたものが、
覚えた字のところで立ち止まって順番を確認する様子が見られるようになりました。
「1文字に1音が対応する」という感覚が少し入ってきたように思えます。
自分の名前の中にある文字も(名前は書けます)、他の場面で書かせようとすると
わからなくなってしまうお子さんでしたが、
最近、いくつかの文字に関しては、場面が変わっても音に対応してちゃんと書ける
ようになってきました。
数にすると、まだとても少ない文字でしかないですが、
階段を一歩上がったような気がするんです。
一文字一音という感覚がつかめたら、
例えば、あいうえお表から、自分の使いたい文字を探すことができる。
そこまで行けば、私がいない時でも
自分で文字を探して綴っていける。
繰り返せば、少し時間はかかってもひらがな全部を
頭にしまうことは可能だろうと思うのです。










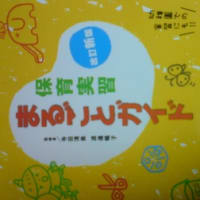




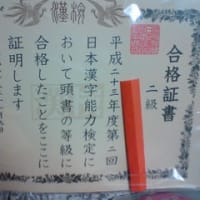




連携がうまくいけば、のんびり族自体も(のんびりじゃなくても)効率的にすすみそうな気がするし。幼稚園のときとは違って
学校の様子がわからない、わかれないジレンマに日々悩まされています。
のんびり娘のサポートをするのに、「学校でなにが行われているのか」がわからないことが苦痛で・・・その頃見つけた募集のお知らせ。娘の学校ではないけれど、今の学校の中身が分かれば手助けの役に立つかもと始めた仕事でした。
伝えても伝わらない。どの程度、どのように伝えたらうまく先生は動いてくれるのか。わからない。
辛いですよね。
少しでも参考になるようなことがかければいいのですが・・・。
このお子さんに関する事、また次に続けて書いていこうと思います。