7.環境分野への応用
近年の異常気象は化石燃料の大量消費による大気中のCO2等の濃度増加は紛れもない事実であり、温室効果ガスの排出抑制の具体的な行動を定めたものが「京都議定書」である。ここでは先進国の温室効果ガス排出の抑制義務が国ごとに定められた。京都議定書では国内努力による削減に加え、より柔軟な発想で世界全体の削減を進めようというスキームが用意された(京都メカニズム)。その一つが排出権取引である。アナリストによればこの市場は2010年までに3兆円規模に達すると予想されている。
このような時代的ニーズにより、衛星からの森林を撮影したスペクトル画像を解析し、単位面積当たりのCO2固定量を算出する研究が電力会社などで行われてきた。(財)電力中央研究所ではタイのトラート州にあるマングローブの森林の衛星画像から葉面積指数(LAI)を測定し、CO2吸収量を評価する実験を行っている。解析例を図7-1に示す。最近の事例では、文部科学省「人・自然・地球共生プロジェクト」の一環として、温暖化予測「日本モデル」作成のために、陸域生態系を地上観測から人工衛星によるリモートセンシングまで広範囲に観測する研究を進めている。

図7-1 人工衛星画像を利用したCO2吸収量の評価例 (HPより引用)
森林によるCO2固定量の予測には地上での正確な森林地図があればある程度評価できることから、㈱デジックでは「Live Forest」という森林管理用のソフトウェアを開発した。これは全国の森林組合で保有しているデータと航空写真から国内の森林地図を網羅したデータベースであるが、同社の中村社長によれば、2~3年にデータを更新するための費用が膨大であることと、森林組合で使用している地図の誤差は100m以上もあるなど精度が悪いことから、今後は安価な衛星画像への期待を高めているという(注:正確にはスペクトル画像が必要)。
もうひとつの応用として、不法投棄の早期発見に人工衛星を利用した研究事例がある。不法投棄は大きな社会問題でもあり、例えば豊島事件と呼ばれる土庄町豊島への約50万トンの廃棄物不法投棄事件ではその処理には10年間の年月と500億円の公費が投じられた。
循環型社会形成推進・廃棄物研究センターでは不法投棄の現場のスペクトルデータを地上で収集し、そのデータをもとにして衛星のスペクトルデータを解析することにより、不法投棄の現場を発見する実験を行っている。

図7-2 不法投棄現場でのスペクトル調査の様子 (HPより引用)
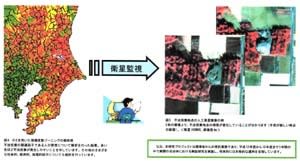
図7-3 不法投棄地点の衛星画像の例 (HPより引用)
近年の異常気象は化石燃料の大量消費による大気中のCO2等の濃度増加は紛れもない事実であり、温室効果ガスの排出抑制の具体的な行動を定めたものが「京都議定書」である。ここでは先進国の温室効果ガス排出の抑制義務が国ごとに定められた。京都議定書では国内努力による削減に加え、より柔軟な発想で世界全体の削減を進めようというスキームが用意された(京都メカニズム)。その一つが排出権取引である。アナリストによればこの市場は2010年までに3兆円規模に達すると予想されている。
このような時代的ニーズにより、衛星からの森林を撮影したスペクトル画像を解析し、単位面積当たりのCO2固定量を算出する研究が電力会社などで行われてきた。(財)電力中央研究所ではタイのトラート州にあるマングローブの森林の衛星画像から葉面積指数(LAI)を測定し、CO2吸収量を評価する実験を行っている。解析例を図7-1に示す。最近の事例では、文部科学省「人・自然・地球共生プロジェクト」の一環として、温暖化予測「日本モデル」作成のために、陸域生態系を地上観測から人工衛星によるリモートセンシングまで広範囲に観測する研究を進めている。

図7-1 人工衛星画像を利用したCO2吸収量の評価例 (HPより引用)
森林によるCO2固定量の予測には地上での正確な森林地図があればある程度評価できることから、㈱デジックでは「Live Forest」という森林管理用のソフトウェアを開発した。これは全国の森林組合で保有しているデータと航空写真から国内の森林地図を網羅したデータベースであるが、同社の中村社長によれば、2~3年にデータを更新するための費用が膨大であることと、森林組合で使用している地図の誤差は100m以上もあるなど精度が悪いことから、今後は安価な衛星画像への期待を高めているという(注:正確にはスペクトル画像が必要)。
もうひとつの応用として、不法投棄の早期発見に人工衛星を利用した研究事例がある。不法投棄は大きな社会問題でもあり、例えば豊島事件と呼ばれる土庄町豊島への約50万トンの廃棄物不法投棄事件ではその処理には10年間の年月と500億円の公費が投じられた。
循環型社会形成推進・廃棄物研究センターでは不法投棄の現場のスペクトルデータを地上で収集し、そのデータをもとにして衛星のスペクトルデータを解析することにより、不法投棄の現場を発見する実験を行っている。

図7-2 不法投棄現場でのスペクトル調査の様子 (HPより引用)
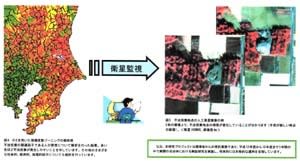
図7-3 不法投棄地点の衛星画像の例 (HPより引用)






















