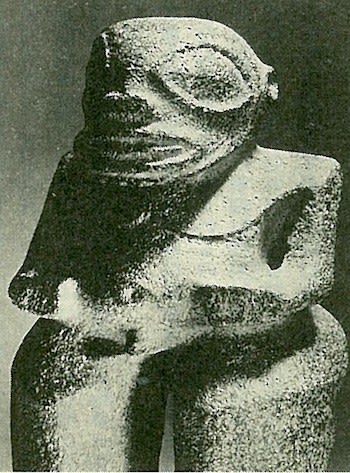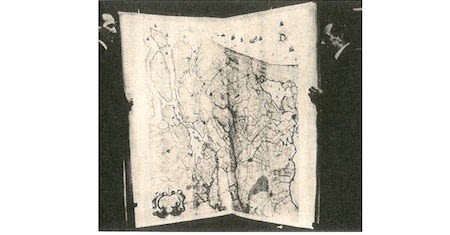シリーズの第8弾です。前回に引き続き「名字の謎」(森岡浩 ちくま文庫)をネタ元に、珍しい姓、ユニークな名字を中心に、その由来、由緒に敬意を表しつつご紹介します。なお、文末に、直近2回分へのリンクを貼っています。最後まで気軽にお付き合いください。
★1から億までー数字の名字★
数字のつく名字は多いです。数字の「一」だけで、「いち」、「かず」、「はじめ」と読む名字があります。「九」で「いちじく」と読ませる名字が、東京都に実在します。不思議な読み方をするのが、宮崎県にある「五六」で、「ふのぼり」って、絶対に読めません。
「四十」がつく珍しい名字がいくつかあります。「四十」(よと、しじゅう)、四十九(よとく)、四十物」(あいもの)などの例が挙げられています。中でも珍しいのは、「四十八願」と書いて「よいなら」と読む名字。戦国時代からある由緒ある名字で、仏教用語の四十八願(阿弥陀仏が法蔵比丘であったころ、一切衆生を救うために発した四十八の願い)に由来するとされています。仏教用語の「しじゅうはちがん」が、なぜ「よいなら」になったかは不明、と著者の言。
数字が3つ連続するのは、「一二三」(ひふみ)、「二三四」(ふみし)、「三九二」(みくに)、「七五三」(しめ)の4つを著者は確認しているとのことです。
大きい数字では、加賀百万石の城下町金沢には、ずばり「百万」という景気のいい名字があります。一番大きいのが、小豆島在住の「億」(おく)さん。なんとも景気のいい名字で、うらやましいです。
★ユニフォームからこぼれそうな名字★
昭和56年、大分県の日田林工高校からドラフト1位で、源五郎丸(げんごろうまる)という投手が、阪神タイガースに入団しました。甲子園には出場していませんが、九州大会で優勝するなど実力は折り紙付きでした。阪神ファンの私も、その珍しい名字とともに、大いに活躍を期待していたのをはっきり覚えています。初めてのキャンプを前にして、ちょっと話題になったのが、「GENGOROMARU」という11文字にもなる選手名が、ユニフォームに収まるかどうか、ということ。文字を小さくしてなんとか収めている画像を見つけてきました。

ところが、そのキャンプで足の筋肉を断裂してしまい、5年間の在籍期間中は1度も公式戦への出場の機会はありませんでした。活躍ぶりを見られなヵったのが返す返すも残念です。
★長い名字、短い名字★
短い方からいきましょう。紀(き)、井(い)、何(か)という例が挙げられています。私のサラリーマン時代、仕事上で「井」さんとお付き合いがありました。名刺には「いい」と振り仮名が打ってあって、私たちも「いいさん」とごく普通に呼んでいたのを思い出します。
長いほうです。難読姓辞典などには、「十二月三十一日」で「ひづめ」と読ませるのがよく載っているそうですが、著者によれば、実在は確認されてないそう。実在名字では、「勘解由小路」(かでのこうじ)という5文字の名字があります。京都の地名に由来する公家の名字で、ご子孫は山口県在住だそう。もうひとつは、埼玉県在住の「左衛門三郎」(さえもんさぶろう)という下の名前を二つ重ねたような名字です。朝廷の官僚に由来するのでは、と著者は推測しています。
★景気のいい名字★
「金持」という大変うらやましく、縁起のいい名字があります。伯耆国(現在の鳥取県)日野郡金持という地名に由来し、「かもち」と読みます。鎌倉時代の御家人に金持氏がいて、吾妻鏡にもその名が見えることから、由緒ある名字といえます。現在では、「かねもち」「かなもち」「かなじ」などの読み方があるそう。
おカネといえば、「一円」という名字があります。もともとは、近江国(現在の滋賀県)発祥の地名に由来し、一族が高知県に移って栄えました。「円」という貨幣単位がなかった江戸時代以前は、特に珍しい名字という認識はありませんでした。明治以降、「厘」「銭」の上の通貨単位になり、だいぶ有り難みが増しました。昭和の初期には、東京中どこでも1円という「円タク」も登場しました。
戦後、円が最小の通貨単位になり、有り難みは薄れましたが、この名字を一躍有名にしたのが、関西学院大学学長もつとめた法学者の一円教授(故人)です。なにしろ、下の名前が「一億」ですから。ただし、「かずお」と読ませます。漢字は豪快ですけど、読み方を遠慮したみたいで、ちょっと頬が緩みました。




















 <「奥の細道行脚之図」、芭蕉(左)と曾良>
<「奥の細道行脚之図」、芭蕉(左)と曾良>