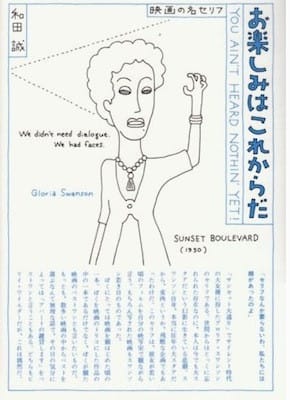休館が続いていた美術館も予約制の導入など工夫しながら、そろりそろりと再開しているようです。気になる展覧会もありますが、私は、もろもろのリスクを考え、「自粛」を続けています。
さて、若い頃はワクワクしながら足を運び、感動して帰ってくることも多かった美術展。ここ数年来、そのワクワク感があまりありません。名作といわれる作品は、だいぶ目にしてきたという(ちょっとエラソーな)事情もありますが、企画内容への物足りなさも漠然と感じています。
そんなこともあり、「美術展の不都合な真実」(古賀太 新潮新書)を手に取りました。著者は、新聞社などで日本美術の海外展開や展覧会企画に携わってきた人です。実務経験豊富な氏が、今の日本の「美術展業界」をどう見ているか、その一端をご紹介します。
日本には熱心なアートファンが多く、話題の展覧会は押すな押すなの大盛況です(でした)。世界的に見てどうなんでしょう?
「アート・ニュースペーパー」というロンドン発行の美術雑誌掲載の「2018年の世界の展覧会の1日あたりの入場者数ベスト10」が、同書で引用されています。
それによると、1位は、メトロポリタン美術館(ニューヨーク)の「天国的身体展」で、1万919人です。日本は6位(「東山魁夷展」(国立新美術館)6819人)と、9位(「縄文ー1万年の美の鼓動」(東京国立博物館)6648人)にランクインしています。前年は3つが入っていたとのことですから、まずまずの健闘ぶりです。
一方、同誌の「どの美術館・博物館に多くの観客が来たか」の記事では、年間入場者数でランク付けをしています。ルーヴル美術館の1020万人を筆頭に、故宮博物院(861万人)と続き、大英博物館は6位です。日本は、国立新博物館が、17位(299万人)にやっと登場します。
やはり、世界的な美術館・博物館は、「常設展」だけで十分に集客しています。膨大で質の高い収蔵品を誇り、建物も宏大です。ルーヴルの場合、6万平米の床面積があります。1日あたり3万人でも、混んでいるのはモナリザの展示室くらいで、これならゆったりと観賞できるはず。
日本の場合、国立クラスでも、常設展だけで、国内外から集客できるだけの収蔵品はありません。国立新美術館や東京都美術館も、収蔵品はなく、貸会場です。敷地も限られ、いきおい「企画展」頼みにならざるを得ません。
国内で観られるのですから、混むのは我慢するとして、あとは企画の中身次第、ということになります。が、その辺りの事情に最近はいろんな変化があるようです。
同書に「なぜ「○○美術館展」が多いのか」という章があります。確かに、2017年は、ランス、エルミタージュ、ボストン、2018年は、プラド、プーシキン、ルーブル、2019年は、コートルード、ハプスブルク、2020年は、ロンドン・ナショナルギャラリー、ボストンなどそうそうたる顔ぶれです。「ハプスブルク展」には私も足を運びました。

ハプスブルクと銘打ってますが、実は「ウィーン美術史美術館」と全面タイアップしています。ややマイナーな美術館名は表に出さず、誰もが知ってる名家の名を前面に立てる戦略なのですね。
さて、著者によるその裏事情です。展覧会といえば、新聞社やテレビ局の協賛などがつきもの。文化事業への関与というイメージアップが期待できます。美術館側も協賛金などの収入のほか、運営費用の一部を負担してもらえます。更に、広告宣伝までしてもらえます。広告代理店の参入が進んでいるもむべなるかなです。
「カネも出すけど、クチも出す」というのがビジネスですので、企画についても、協賛側主導になります。そこで「○○美術館展」です。
一館に絞ってスムーズな交渉が可能です。対価を払ったとしても(通常、美術館同士の貸し借りは無料)、その美術館の改修時期に合わせれば、名品の貸し出しも期待できます。相手美術館にとっても、改修の場合、その費用の一部がまかなえるのも利点です。
いい事ずくめみたいですが、美術館の学芸員(国立の場合は、研究員)にとっては、モチベーションが下がります。テーマを考え、何年もかけて、そのテーマに沿った作品の貸し出し交渉を続けていくという生き甲斐、やりがいを奪いかねません。ひいては、我が国美術界のレベル低下にもつながる、との著者の指摘には、大いに頷くところがあります。
それでもいい作品が来ればいいのですが、「たいした作品は来ない。レベルの高い作品は、2、3点のみの場合が多い」(同書から)とあります。冒頭のワクワク感のなさ、とも符合しているようです。
今の事態が終息すれば、美術館のブランドに惑わされず、企画内容を十分チェックして、出かけようと考えています。いい作品を見るのは好きだし、楽しいですので。
いかがでしたか?次回をお楽しみに。