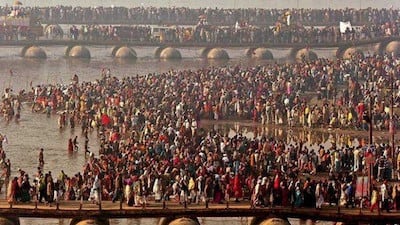先日は、お店で剣喜さんとご一緒になりました。最近倒産した出版取り次ぎ会社のこと、街の本屋さんのこと、若者の読書離れのことなど、いろんな話題で盛り上がりました。当「書きたい放題」へも貴重なアドバイスをいただきました。剣喜さんお奨めの「やってみなはれみとくんなはれ」(山口瞳、開高健著のサントリー社史 新潮文庫ほか)精神で、やっていこうと思います。引き続きご愛読ください。
さて、ベタな大阪弁のタイトルの本が話題に出たところで、毎度の「大阪弁講座」です。それでは、さっそく・・・
<いかれこれ>
今の若い人は使うのかな?あまり自信がない。「いかれポンチ」などという言い回しがあって、根っからの能天気なヤツのことを指す。それと関係があるかもしれない。物事が破綻したり、ひどい状況になったりした状態を表す言い回しで、自虐的に使うのがメイン、というのがいかにも大阪風。以前紹介した「わや」にも通じる部分がある。
「べろべろに酔うて帰ったもんやから、電信柱にデボチン(おでこ)をぶつけるは、財布は失くすはで、「いかれこれ」ですわ」
<なるほど>
どこが大阪弁やねん、とツッコミが入りそうですが・・・・・
確かに言葉としては、どうということない共通語。相手の言動に、感心したり、納得したり、賛意を表したりする表現です。こんな感じ。

ただ、関西圏では、ちょっと独特な使い方というか、使い途があるような気がするので、取り上げてみた次第。
なんといっても大阪は商売人の街。自分にとっては、先刻承知のことである、何も目新しい話でもない。心の内では「そんなん、知っとるわ~」。だけど、得意そうにしゃべってはるのは、一応お客さん(とかエライさん、とか、上司)。感心したふりして、相手を持ち上げておくのが得策かな~、というような計算が働いて、実に頻繁に使う関西人が多い。
芸人さんもやっぱり客商売。対談とか、やり取りとかを聞いていると、特にそう。そつのなさが際立つ。ズルさと奥ゆかしさが同居しているイヤらしさには、充分気をつけてください。
「先にお湯入れて、それから焼酎を注ぐのが本場九州の飲み方や。知らんかったやろ。そのほうが、焼酎の香りが立つねん」
「「なるほど」。それは知りまへんでしたわ。アンタ、なんでもよう知ってまんなぁ」
<味もシャシャリもない>
不味いことをいいたければ、「味もない」、大阪流に縮めて、「味ない」で事足りる。事実、味にうるさい大阪人はよく使う。
で、そこに「シャシャリ」という一言を添えて、不味さを一押ししてアピールするのが大阪流。
「愛想も「シャシャリ」もない」(愛想が極めて悪い、可愛げがない)という使い方もある。一体、「シャシャリ」とは何か、というのはよく分からない。いわく言い難いサムシングのことかなと勝手に想像している。そういえば「シャシャリ出る」(オレがオレが、とでしゃばる)という言い回しなんかもあるんだが、関係あるのかな?謎は深まるばかりである。ネイティブにとっても、大阪弁は奥が深い。
いかがでしたか?次回をお楽しみに。