
不定期に盛大にテング熱の訪れるわたくしですが、
最近諸事いきづまってしまっていまして、いまや天狗の世界に憧れる事この上ない。
小さい頃からマーク・ガスコインの『モンスター事典』やD&Dの『モンスターマニュアル』が大好きな子供でしたが、
日本の妖怪については何故か、鵺と天狗にしか興味がありませぬ。
天狗の伝承の世界は非常に奥深い。
天狗をただの妖怪扱いしている本を見るたびに、腹立たしく、
しかし、天狗様に対するアプローチはおそらく百通りはありましょうので、“口承文化としての”天狗様にしか興味のないわたくしも、能の世界とか心霊の世界とか禅の世界とか山の世界とか覗いてみるたびに、ちょっと肩が狭い思いもしてみたり。
でもいいんです。
わたしもそのうち絶対に本物のテングになってみせるからな。
わたくしが、「天狗の伝説をまとめてみよう」と思ったのは5年ぐらい前だったです。私の研究は、その後いろいろあって遅々として進んでいませんが、ここにきて焦燥を感じている。わたくしは今の食生活から見て、きっと長生きしませんので(笑)、今のうち、できることをしておかないとー。
天狗の世界に深く分け入りたい。
この5年間に天狗に関する本をいっぱい読んだのですが、
実を言うと実際に手にできる本って実に少ない。
まだ私の手にしていない天狗に触れた本は、世に幾万とあるのだと思います。
今後「もっと読むぞ」という決意をこめて、ここで“入門者としての”天狗の本の紹介を。

<知切光歳の本>
天狗の研究において、絶対に避けて通れない人が、知切光歳師です。
知切光歳師の天狗についての本は、『天狗考(上巻)』(1973年)、『天狗の研究』(1975年)、『圖聚天狗列伝(西日本編/東日本編)』(1978年)の4冊しかないのですが、そのどれもが力が入っていて、非常にエキサイティングです。
『天狗列伝』をネットで東西揃いで21000円で手に入れた話は、以前しましたよね。
「これさえあればなにも要らない」ってくらいの大部の本。
こんなに密度の濃い物を書くには、山に分け入り本を読み漁り人に会いまくり散財を繰り返し、きっと何十年もの探求が必要だったでしょう。
知切師でなければ書けなかった本です。そして、伝承の世界が失われた後の現在、類書は今後絶対に出ません。
しかしながら、「列伝」という性格上、世の中の「有名な」「高名な」ものを優先してのせてあるせいで、世にあまたある「よくあるたぐいの」「地域密着型の小話」は捨て去られている体はあります。(…とも言い切れず、そういうのも少なからず取り上げてあるのが知切氏の凄いところであるし、結局それが天狗の世界なのですが)結局の所、知切氏の腕を持ってしても、大天狗中の大天狗である天狗にも謎はあるし、諸国の小々とした天狗には触れていないものも多々あるので、私のようなものでもまだ付けいる隙はあると錯覚させる。
だがしかし、何度読んでもこの情報量には圧倒される。ここにしか書かれていない情報は多いし、知切師の考察も冴えに冴えを見せている。本当にスゴイです。
これまで地方の図書館を巡っていて、この本を見たことはありませぬ。ネット上書店で3まんえんを超えていたとしても、この本は絶対に「買い!」ですよん。
『天狗考』。以前、「天狗について調べよう」と思ったときに、今昔物語や宇治拾遺物語や源平盛衰記や太平記を熱心に読み込んで、天狗についての記述を全部抜き出そうとこころみたことがあったのですが、その後、この『天狗考上巻』を入手して読んでみて、絶望してしまいました。私がやろうとしたことは知切師が何十年も前にしていたのです。遙かな情報量を持って。
この本は凄い。
この本は3年くらい前に近くの古書店にあったのを見つけて買ったのですが、購入価格6000円。たけー(発売時(昭和48年)の定価は2300円)。ネットで検索すると1200えんくらいで買えるみたいです。
しかし、わたしはこの本を6千円で買ったことを後悔はしておりませんぞ。むしろそれ以上の価格の価値はあると思っているぐらいです。いづれ、私もここにある以上のことを諸書を読み込んで書いてみるぞ!
なお、この本は「上巻」なのですが、下巻は発刊されておりません。
この本を読んでも、完成度が高すぎて下巻がどんなのなのかまったく想像出来ない。
おそらく、この本の「下巻」にあたるのが『天狗の研究』と『天狗列伝』(東/西)の三冊なのだと思います。
<柳田國男の御本>

「今日本で幽冥という宗教のいちばん重な題目は天狗の問題だけれども、天狗の問題については徳川時代の随筆とか、明治になってからのいろいろな人の議論などに気をつけて見ていると皆な僕の気に食わぬ議論をしている。それはすなわち天狗という字義から解釈している。これは間違いきった話で、ランプとかテーブルとかいうように実質とその名称が一緒に輸入したというものではない。天狗という字は何から来ているとか、何に現われているとか、あるいは仏教のいわゆる何がそうであるというような事を言われるけれども、実質は元来あったので、そのあったものに後から天狗という名称を付けたのである。名称はその時代時代に依って付けるものであるからその字義に依って説明しようということはとうていできるものではない。だから僕は今までの多数の学者の議論は皆な採るに足らぬ説だと思っている」
「研究するのはその実質であって名称ではない。それで僕がなぜそんなものを研究しようという気になったかというと、どこの国の国民でも皆なめいめい特別の不可思議を持っている」
「仏教でいう、阿弥陀さんがありありと拝まれたというようなことは、天竺全国共通の妖怪談の輸入品だと思うから、重きを置かないが、とにかく日本には一種変った信仰がある」(『幽冥談』、明治38年)
柳田國男は著作の中にけっこうな量で「天狗」について触れていますが、この人は秋葉信仰とか仏教の宗派とか、天狗の名前とか、そういったことには全く興味が無いのです。にもかかわらず、天狗的な物の解釈についてはいろいろ言っていて、諸本はそれなりにバイブルではあります。
柳田國男については解説書も多々出ているので便利です。そもそも柳田國男は「天狗」を定義しない。初期の頃の柳田國男は「山人」という「異民族」が山中にいたと想定してその絡みで天狗をも語っていたのですが、その後「山人論」を諦めた後も山の中のいろいろな風習や諸人の体験やサンカ的な物を滔々と語っている。
柳田國男が活躍した明治後期~大正・昭和前期は人攫い・神隠しが頻繁に起きた世の中であったそうで、「天狗的なもの」も極めて身近だったんですね。
『遠野物語』『妖怪談義』『幽冥談』『山の人生』『山人論集成』から始めて、いろいろ読んでみましょう。
関係ないですが、柳田國男の出身地である兵庫県神埼郡福崎町は、柳田國男にちなんで『全国妖怪造形コンテスト』というのを行っているそうでした。その第一回(2014年)のお題が「天狗」。その応募作がどれもこれも秀逸でした。とくに「ジュニア部門」が涙が出るほどスバラしいものでした。これから子供向けに「怖くない天狗」を追求しなきゃならんのですけど、でも「子供向けの怖い天狗」も必要ではありますね。
<秋葉山三尺坊関係>

(1).『秋葉山三尺坊大権現 火坊天狗のふる里』
秋葉山秋葉寺 監修、野崎正幸 著(島津書房、1985年)
(2).『秋葉信仰の根元 三尺坊』
藍谷俊雄(村田書店、1996年)
秋葉山秋葉寺が刊行に関わっている、いわば「公式解説本」と言っても良い2冊。
(1)の方は秋葉寺52代(53代?)住職の藍谷賢龍師が企画し、(2)は息子の53代俊雄氏が自ら筆を執った著作。書いてある内容は互いを補完し合っているし、どちらの本も見るべきところが多いです。だが、自分で自分のことを語っているせいか、「公式設定」を作ることに熱心になりすぎていると感じることも多いです。
『火坊天狗のふる里』は「秋葉山の奥の院」について詳しく、『三尺坊』の方は巻末の「秋葉寺関係史料」がとても便利です。「秋葉山略縁起」(享保2年)が全文収録されています。
俊雄師ももう亡くなられているみたいですね。(秋葉神社に墓碑があった)
両書とも入手困難本ですが、浜松市の古本屋を巡っているとたまに見かけます。

『古道案内 信仰の道 秋葉街道 信州松本~遠州掛川 “古道を歩く”ための全行程詳細地図』
田中元二(白馬小谷研究社、2006年)
2008年頃に道の駅“花桃の里”で購入した本ですが、とても詳細で、山の中を車で巡るに当たってすごく役に立ちました。
名古尾集落にある「秋葉山奥の院」にはこの本が無かったらたどり着けなかったと思います。
「天狗に会いに」あるいは「塩を送りに」大昔からこんな山々の、信じられないくらいの高いところを通っていく街道があるんだなんとびっくりするばかりですけど、森町や浜松からならともかく、長野県の人が秋葉山を越えて行った遙々とした行程とその必要性を考えると(伊那谷の方が便利なのに)、日本人って凄いなあと思います。わたくしどもとしては、塩と天狗と川の関係も調べてみなければ成りますまい。


『遠江古蹟圖繪』
再影館藤長庚(明文出版社、1991年)
遠江国の天狗群を調べるには無くてはならぬ本です。
江戸時代に第2次天狗ブームがあった頃(享保年間)に当地在住の、学者ではないディレッタント(金持ち好事家)によって書かれたということが最も重要な点です。
「遠州十二天狗」の詳細が網羅され、逸話も豊富です。
さらに、明文出版社版には浜松地域史界の重鎮・神谷昌志氏による、かゆいところに手が届きまくる膨大な注解が付され、とんでもなく便利です。


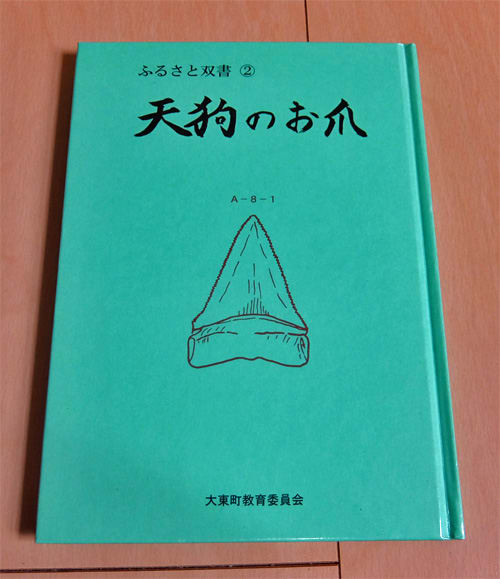

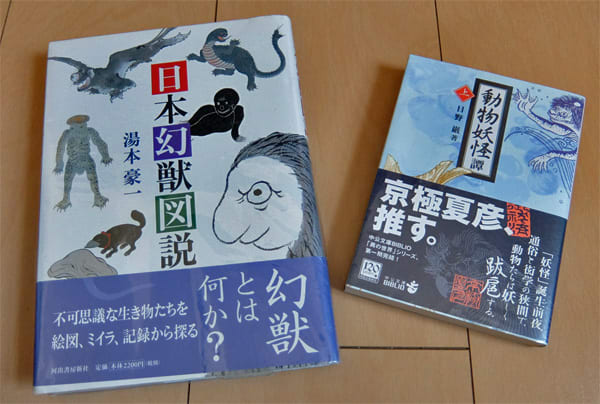




























随分前の記事に初コメント失礼します。
天狗の事にお詳しいのですね!
今後も覗かして頂きます!
私は、趣味でちょくちょく天狗のイラストを
描いてるのですが、四十八天狗の事が気になりまして、
この本を買おうか買わないか悩んでる所です…;
八天狗の一人『相模大山伯耆坊』は、
なぜ四十八天狗に名前が挙がってないのか?
所在不明の板遠山頓鈍坊ってどんなだ…と、
日々悶々としていますw
やはり手に入れられるのなら、手に入れたほうがいいのでしょうかね…
夜分に失礼致しました。((
同好の士に会うことはなかなか無いのでとても嬉しく思います。
知切光歳の4冊は今でも読んでいてとてもワクワクする4冊なので、ぜひとも手元においていただきたい最重要書です。ただ四十八天狗については、現在ネットで入手できる以上の情報は無いかもしれませんし、そうでもないかもしれませんけど。
「西と東のふたつの大山の天狗のひみつ」
は、知切師の御本の中で最も面白い箇所のひとつなので、ぜひともご自分で読んでいただきたく思うのですが、知切師の下した結論は、「天狗揃いの中で“八天狗”に上げられた室町初期の大山伯耆坊は伯耆の大仙に棲んでいたが、『天狗経』が唱えられた室町後期には、伯耆坊は大仙を去り行方不明になっていた。だから天狗経の四十八天狗には名が現れないのだ」ということです。
伯耆坊が相模大山に来たのは戦国時代頃~江戸初頭でしょうか。
一般に「崇徳上皇を慕って讃岐白峯に去った相模坊のあとの空白を襲って伯耆坊が相模大山の主となった」とされるので、それは平安後期ぐらいの話かと思っていたら、知切師はそこに数百年の隔絶があったと言う。面白いですね。(知切師は伯耆坊の遷移に南北朝の動乱の関与も仄めかしていますし、伯耆坊の行方不明のあと伯耆大仙の主が伯耆大仙清光坊に落ち着くまでに、数回の代替わりがあったとも書いています)
そもそも現在でも相模大山の天狗は「大天狗」「小天狗」と称され、「伯耆坊」という名前が出てくることはほとんど無いそうですよ。
板遠山頓鈍坊については、師は『圖聚天狗列伝』の長門普明鬼宿坊の項に書いています。
「天狗経四十八天狗の中には、初めのうちは、所在の不明な天狗が数狗あった。それを乏しい文献と勘と踏査によって順次解明し、現在も皆目不明なのはこの鬼宿坊と板遠山頓鈍坊という二狗のみとなった。しかも頓鈍坊というのは山も素性も一切分からないのに、鬼宿坊は長門国の天狗であることが分かっているだけでも、ひとつの手がかりになる。読者の方に重ねてお願い、板遠山頓鈍坊についても何か心当たりがあったら、ぜひともご教授をお願いしたい」
本当の知切師だったら僅かな手がかりだけで板遠山なんて容易に見つけてしまうはずなので、敢えてこう書いているってことは・・・ 余人にはもう二度と板遠山の謎を解き明かすことは出来ないのだと思います。
>私は、趣味でちょくちょく天狗のイラストを描いてるのですが、
わお!
どこかで開陳なされたりされてますか?
私もちょくちょく天狗の絵を描こうとしているのですけど、気力が持たず完成している物が無い。
創意を強く刺激される何かを欲っしております!
古本ショップで東日本編以外の3冊注文しました…!
この手に届く時が楽しみです…!!
はぁ~そういう謂れが…確か伯耆坊は、伯耆大山を去った理由が山に住む僧と武者が戦をし、山が荒れていくのをみて嫌気がさし、山から去ったんでしたっけ…それから数百年どこに居たのでしょうね…
長門普明鬼宿坊…山口県ですね。山口県には『鬼の岩』という伝説がありまして、これに関係があるのかもしれませんし、普明(フミョウ)を『フメイ』(不明)とかけて正体不明の天狗である という謂れなのかもしれない と考察というか想像が止まりませんw
まぁ、知切師がわからなかったとなると多分間違ってると思いますが…w
イラストはtwitterでちまちま描いているのですが、
『女体化』平たく言えば『萌えキャラ化』
的なものなので…罰当たりも甚だしい代物です…;
知切師の御本にさえ目を通しておけば、「私は天狗にとても詳しい」と豪語しても誰も文句を言えないほどの密度を持ったものなので、mayoさんの今後の天狗的なご活躍を祈念します。
知切師の著作をふまえ、それに触れられていない多々のことを考察することが楽しいんですよね。
>長門普明鬼宿坊
知切師は「長門には高名な天狗はまれ」と書いているのですが、調べてみると、天狗伝説は各地にそこそこありますね。でも鬼宿坊は名前が「鬼」なのですから、鬼伝説にも結びつけて考えたいところ。山口県は鬼伝説も多いのですね。
mayoさんの挙げられた角島の「鬼の岩」伝説は役行者の昔話に似ていますし、下関の鬼ヶ城とか、また「天狗経」は四国の石鎚修験と関係が深いと知切師が推測していることに関連して、下関市の「天狗乃宮」にも興味が湧いてきます。(蔵王権現は鬼にも見えますからね)。鬼であり天狗でもあったのは「前鬼・後鬼」と「三鬼坊」に限らないのかもしれません。それから、「天井が岳」と「狗留孫岳」をくっつけて「天狗」かな、と思ったり、そもそも狗留孫岳にも角島の鬼伝説によく似た天狗伝説があったのでした。
鬼には関係ないけど一番興味深く思ったのは、県北の「楊貴妃の里」で「火渡り神事が毎年行われている」ということでした。
★(参考);https://www.jstage.jst.go.jp/article/jgd/31/0/31_196/_pdf
でもどれも(知切師が指摘していますように)ちょっと弱いですね。
>板遠山頓鈍坊
そう考えると、この名前も「はてしなく板違いにして、頓知が鈍い」=「探してもムダ」、という言葉遊びなのかもしれませんね。中世に「板違い」なんて言葉があったかどうか知りませんけど。
「はんえんざんとんどんぼう」とヒラガナで書くと「ん」の配置がいかにも嘘くさい。
>女体化された天狗のイラスト
それはそれでいいですね。
四十八天狗の中の,黒眷属金比羅坊と象頭山金剛坊がどう考えても同一天狗のように思えて仕方がないです。
実際に,象頭山のふもとの金刀比羅神社(こんぴらさん)まで聞き取り調査に行きましたが,明確な違いがわかる情報を得ることができませんでした。
これら2つの天狗の明確な違いについてもしご存知でしたら教えて頂けないでしょうか。
なお,私が地元で信仰している「万灯寺」というお寺がある山(「伽藍山」)には,天狗伝説が残っています。地元の郷土史の「檀紙村誌」に掲載されています。名前は,「青光坊」と言います。大正時代に,石鎚権現の分霊が伽藍山に勧請され,今も地元の皆さんと石鎚権現・天狗ともども一緒に信仰しています。
もうすぐ坂出の天狗マラソンですね。
香川県は天狗がとても豊富な県ですから、そこにお住まいのyunaさんがとても羨ましいです。
さて、お尋ねの黒眷属金比羅坊と象頭山金剛坊についてですが、わたくしも「よくわからない」と言うしか無いです。(知切光歳も「わからない」(とくに黒眷属金比羅坊について)と言っているから)。
ただ、天狗研究家でこの両者を「同一人物」としている人はないです。象頭山の場合、それほど大きくないこの山に2人も大天狗がいるのが特徴的でありますが、2人の天狗のある山は、他に妙義山(上野妙義坊と妙義山日光坊)と筑波山(常陸筑波法印と紫尾山利久坊)がありますから、それと同様ぐらいに象頭山は特別な山なのは間違いないですね。知切光歳師は『天狗経』の成立を「戦国時代~江戸初期ぐらいに石鎚修験の人によって唱えられたもの」と推測していますが、であるからゆえに、石鎚山から近いところにある象頭山の2人の事を疑っていなかったと思います。
以下、『圖聚天狗列伝』の要約。
・「象頭山金剛坊」は、金刀比羅宮の公式見解でその前身を寛永年間の別当金光院の宥清法印であると断定されている。
・「黒眷属金比羅坊」は不明。“眷属”という語句の響きから宥清法印の弟子か孫弟子にあたる人が成ったものでないか。知切師も金比羅宮で黒眷属について尋ねてみたのだそうで、「おかしいことには金比羅坊は当の象頭山ではあまり知られていなくて、かえって遠く離れた関東地方から東北にかけて、金比羅さまの御使い天狗として知られていることである。そのことは一九の膝栗毛によっても知られよう。筆者がかつて琴平宮の神職に、金比羅坊について糺したところ、神職は知らないと首を振って「象頭山の天狗さんは金剛坊様です」とはっきりした返事が返ってきた。思うに金比羅宮ほどのにわか流行神となると、全国に勧請されてにわかに忙しくなり、、いくら金剛坊の通力をもってしても、一狗では手が回りかねて、眷属を増員し、手分けをして諸国の金比羅宮に配したのではあるまいか。そして最も大切な関東以北を、金比羅坊の所管に任じたのではないかということである」
・・・ここでわたしが解せないのは、金剛坊は寛永年間に天狗となった人であるとされていることです。『天狗経』は戦国~江戸初期の成立なんじゃなかったのかい。徳川家康が天狗となった「日光山東光坊」が「新参の天狗なので名だたる北関東の天狗たちからかなり舐められた」としているのに、もっと時代が新しい金剛坊が、そんな権勢を張ることはできたのでしょうか。
個人的には、宥清法印以前から、この山には大きな力を持った地神が何人もいて、宥清法印は代替わりでその地位を受け継いだのでは無いかと思います。
知切師も続く『神城騰雲と趣海坊』の項で、上記とは違うことを述べています。
神城騰雲という人は文化の頃に江戸で天狗に攫われて、天狗の世界を彷徨った人だそうで、その聞き書きが残っているのですが、讃岐の天狗について、「金比羅より以前、天地開けてよりの天狗有り。これ七人なり。金比羅は後に天狗になりたる人なれども、一体人間より成りたる上に位は天子なり」とある。天地創造の頃にいた7人の天狗のうちのひとりが金剛坊なのではないか。また、知切光歳は「崇徳院が金比羅の天狗であるなどありえない」と強く否定しているのですが、意外と金比羅坊の正体が崇徳院であるということもありえるのではないか。
一方で、“黒眷属”の「黒」とは何か、ということを考えますと、金比羅系の天狗が天狗としては珍しく、よく海上に現れて航海を守護することから考えて、俗説のように天竺から来たフカやワニと関係ある可能性もあるのではないか、、、 とわたくしは思うのです。
>なお,私が地元で信仰している「万灯寺」というお寺がある山(「伽藍山」)には,天狗伝説が残っています。地元の郷土史の「檀紙村誌」に掲載されています。名前は,「青光坊」と言います。
・・・万灯寺と青光坊と『檀紙村誌』について、ネットで調べてみても全然解らなかったので、詳しく教えて頂けますと嬉しいです。地域の地誌は住んでいる人にしかわかんないんですよね。