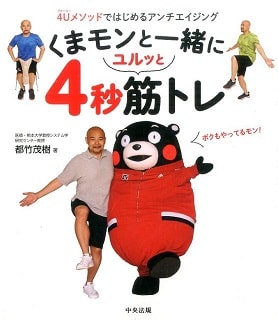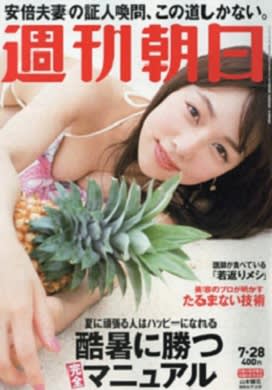普段よりも少しめかしたばばじじ14~5人が、総合福祉センター調理室に集まり、手作りの昼食会をガヤガヤと愉しむ。
名付けて「ランチカボチャの会」です。
みんなで昼ご飯を作り、完成品を食べ、ナツメロを歌い、絵本を読み聞かせてもらい、3時間。
会費が400円なのは会場費と水道光熱費が無料で、野菜類はおばば会員が庭先で丹精したものを使うからだ。

毎回、みんな満足してお開きになるが、森生には困ることが二つある。
まず、味付けが薄過ぎる。味噌汁なんか目玉が写るどころか、お椀の底が見える。
次に分量が多過ぎる。全体に作る量が多いので、食す分も増え、寝る前の体重が70㎏を超えてしまう。
おばばたちのツレヅレが、よくガマンしてるものよ。
だが今月は、塩味が要らない栗ご飯が主役だった。
おかずは鮭のバター焼き舞茸付、人参牛蒡蒟蒻の煮物、キャベツ胡瓜の塩揉み、冬瓜油揚げの味噌汁などてんこ盛り。
梅干しを想像しながら胃に押し込んだ。

一方、美味い栗ごはんは敢えて残し、用意しておいたタッパウェアに詰め、持ち帰り、夕餉に食したのである。
おかずは理想的な味にした、とろろ昆布の味噌汁だけで充分だった。
今年の栗はこれで食い収めかと思ってたら、嬉しいことが重なった。
時々、猫額亭に安否確認に現れる切株じぃさんが、到来物のお裾分け、と生栗を少し持ってきてくれた。
残り少ない日々である。二日もかかる渋皮煮は去年から止めている。簡単な茹で栗でガマンしよう。

なお、スーパーに、栗の茹で方を説明したカードがあった。じじぃはは1235を知らなかった。
1.栗を半日、陽に当てる。(甘みが増す)
2.その栗を半日、水に漬ける。
3.鍋たっぷりの湯を沸騰させ、塩を投入し、水から取り出した栗を投入する。(塩の分量は適当、らしい)
4.弱火にし、小栗なら2~30分、大栗なら4~50分茹でる。(灰汁が抜ける)
5.鍋がつめたくなって半日したら、栗を取り出す。(鬼皮が柔らかくなり、渋皮が剥がれ易くなる)
6.栗の底部分を包丁で切り離し、切り口から鬼皮と渋皮を剥がす。(崩れる場合もある)
これから上記に則り、茹で栗に挑戦するつもりです。
バンダナキャップのお求めはこちらにどうぞ。
170926