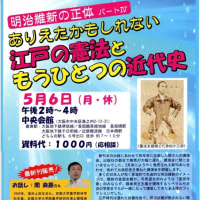最近、私が以前に『山林』という雑誌に書いた「『ウッド・ニューディール』で社会的共通資本を整備する」第1512号(2010年5月:43-51頁)という論文に関して何度か問い合わせをもらった。この論文は、当時の民主党政権が掲げていた「コンクリートから人へ」というスローガンを批判し、正しい公共事業を実施しようと論じたものであった。
安倍政権の公共事業拡大路線でいよいよ財政破たんが現実化するのではと危惧する声も一部で出始めている。私の考えは従来から変わらない。地域資源を使って地域に雇用と投資を促すという正しい公共事業を促進すればよいが、従来型の石油と鉄とコンクリートの外部資源依存型の公共事業のバラマキならば財政破たんにもつながりかねないのだ。私が以前に書いた論文の一部を引用したい。
***『山林』1512号(2010年5月)の拙稿より引用(43―51頁)***
鉄とコンクリートから木と土へ
民主党政権が掲げる「コンクリートから人へ」というスローガンは正しいのであろうか。自民党的な「鉄とコンクリート」の公共事業は、海外資源への依存度が高く、雇用吸収力も低く、民間投資への波及効果が低く、自然環境の劣化も激しかった。民主党の「コンクリートから人へ」の場合、公共事業費は削減し、浮いた予算で子供手当など直接的に家計を支援する政策を実行するということである。これによって確かに家計消費は増加する。しかし、民間投資への波及効果はないし、それによって完全雇用が実現できるわけでもない。また、消費が増えるといっても持続可能な循環型の消費行動につながるわけではないのである。
つまり自民・民主双方の財政政策に共に問題がある。鉄とコンクリートの公共事業も問題があるし、コンクリートから家計へのバラマキ路線にも問題があると言わざるを得ない。正しいスローガンは、「鉄とコンクリートから木と土へ」ではないだろうか。「鉄コン事業」を文字通りの「土木事業」に変えるのである。そうすれば、ケインズ型の完全雇用を目指しつつ、環境保全型産業で創造的な破壊を促し、地域資源を使って、地域で事業を興し、地域にお金を落とし、過疎化を防ぎながら、循環型社会をつくることが可能になろう。恐慌状態の今こそ、ルーズベルト大統領が実施した国土保全のための資源保全市民部隊の発想を取り入れるべきなのである。
(中略)
国の予算を投入して大量の間伐材を降ろすことは、間伐材の過剰供給と材価の値下がりをもたらすことになる。そこで、「川上」から運搬されてくる間伐材に見合うだけの木材需要を作り出す必要が発生する。そのために、公共建築を可能な限り木造化し、さらに公共施設で活用するエネルギー源を可能な限り木質バイオマスに転換せねばならない。ガードレール、橋、砂防堰堤など、従来は鉄が用いられていた財を可能な限り木材で代替していく必要もある。つまり、山から降ろしてくる間伐材に見合うだけの需要を、公的部門を中心にして計画的に作り出すのだ。
こういう主張をすると、すぐに「市場原理に反する」という反論が聞こえてきそうである。その考えこそ誤っている。万物の私有化・商品化を原則とする市場原理の下では、必然的に過剰供給の需要不足という、マクロ経済の不均衡を発生させる。ゆえに宇沢弘文は、自然環境・農林・インフラ・教育・医療・金融などは、豊かな環境と平等で文化的な暮らしを守るために、私有財部門から切り離して「社会的共通資本」という別部門の枠組みで社会的に管理し、もって有効需要を生み出してマクロ経済の需給バランスを調整せねばならないとしたのだ。それをして、はじめてマクロ経済は均衡し、同時に人々が安心して、ゆとりを持って生活できる条件が整うのである。
****引用終わり****
安倍政権の公共事業拡大路線でいよいよ財政破たんが現実化するのではと危惧する声も一部で出始めている。私の考えは従来から変わらない。地域資源を使って地域に雇用と投資を促すという正しい公共事業を促進すればよいが、従来型の石油と鉄とコンクリートの外部資源依存型の公共事業のバラマキならば財政破たんにもつながりかねないのだ。私が以前に書いた論文の一部を引用したい。
***『山林』1512号(2010年5月)の拙稿より引用(43―51頁)***
鉄とコンクリートから木と土へ
民主党政権が掲げる「コンクリートから人へ」というスローガンは正しいのであろうか。自民党的な「鉄とコンクリート」の公共事業は、海外資源への依存度が高く、雇用吸収力も低く、民間投資への波及効果が低く、自然環境の劣化も激しかった。民主党の「コンクリートから人へ」の場合、公共事業費は削減し、浮いた予算で子供手当など直接的に家計を支援する政策を実行するということである。これによって確かに家計消費は増加する。しかし、民間投資への波及効果はないし、それによって完全雇用が実現できるわけでもない。また、消費が増えるといっても持続可能な循環型の消費行動につながるわけではないのである。
つまり自民・民主双方の財政政策に共に問題がある。鉄とコンクリートの公共事業も問題があるし、コンクリートから家計へのバラマキ路線にも問題があると言わざるを得ない。正しいスローガンは、「鉄とコンクリートから木と土へ」ではないだろうか。「鉄コン事業」を文字通りの「土木事業」に変えるのである。そうすれば、ケインズ型の完全雇用を目指しつつ、環境保全型産業で創造的な破壊を促し、地域資源を使って、地域で事業を興し、地域にお金を落とし、過疎化を防ぎながら、循環型社会をつくることが可能になろう。恐慌状態の今こそ、ルーズベルト大統領が実施した国土保全のための資源保全市民部隊の発想を取り入れるべきなのである。
(中略)
国の予算を投入して大量の間伐材を降ろすことは、間伐材の過剰供給と材価の値下がりをもたらすことになる。そこで、「川上」から運搬されてくる間伐材に見合うだけの木材需要を作り出す必要が発生する。そのために、公共建築を可能な限り木造化し、さらに公共施設で活用するエネルギー源を可能な限り木質バイオマスに転換せねばならない。ガードレール、橋、砂防堰堤など、従来は鉄が用いられていた財を可能な限り木材で代替していく必要もある。つまり、山から降ろしてくる間伐材に見合うだけの需要を、公的部門を中心にして計画的に作り出すのだ。
こういう主張をすると、すぐに「市場原理に反する」という反論が聞こえてきそうである。その考えこそ誤っている。万物の私有化・商品化を原則とする市場原理の下では、必然的に過剰供給の需要不足という、マクロ経済の不均衡を発生させる。ゆえに宇沢弘文は、自然環境・農林・インフラ・教育・医療・金融などは、豊かな環境と平等で文化的な暮らしを守るために、私有財部門から切り離して「社会的共通資本」という別部門の枠組みで社会的に管理し、もって有効需要を生み出してマクロ経済の需給バランスを調整せねばならないとしたのだ。それをして、はじめてマクロ経済は均衡し、同時に人々が安心して、ゆとりを持って生活できる条件が整うのである。
****引用終わり****