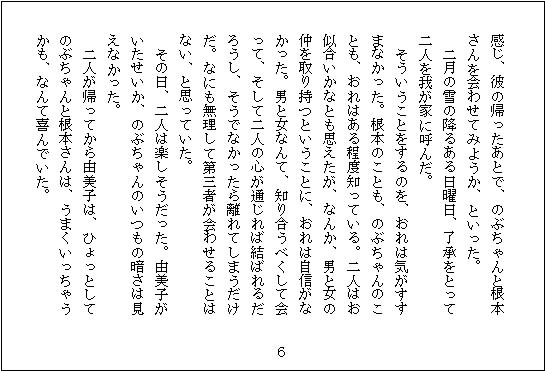今日、「女のいない男たち」(村上春樹著 文藝春秋社刊)を読み終えた。
この歳になると、なかなか文章を読むことが面倒くさくなっている。
小説を読むことは好きです。
それよりテレビを観ることがもっと好きな自分がいる。
これは、ちょっと哀しいなと思う。
ピアノの練習もしなければならない。
ケーナも吹きたい。
尺八もやらなければ、いやギターだって弾きたい。
現在も、1日に5,000歩は歩いている。
「女のいない男たち」の本の中には、次の短編小説がある。
1 ドライブ・マイ・カー 「文藝春秋」2013年12月号
2 イエスタデイ 「文藝春秋」2014年1月号
3 独立器官 「文藝春秋」2014年3月号
4 シェエラザード 「MONKEY」2014年2月15日発行・Vol.2
5 木野 「文藝春秋」2014年2月号
6 女のいない男たち (書き下ろし)
私の正直な気持ちを書きます。
今日、最後の「女のいない男たち」を読了した。
その前に読んだ他の短編の内容を覚えていないことに愕然とした。
69歳になった私の、これが現実です。
「ドライブ・マイ・カー」のことは、2/15の九想話に書きました。
「イエスタデイ」のことはまったくどのようなストーリーだったか覚えていない。
「独立器官」は、52歳の独身の医師が多くの女性と付き合っていたという話だった。
彼は恋なんかしないで、自由に生きたいと思っていた。
しかし、ひとりの女性に恋をしてしまい、死んでいく。
「シェエラザード」は、一度性交するたびに、不思議な話をしてくれる女性の話だ。
「木野」は、1日早く出張から家に戻ったら、妻とその男が裸でベッドで寝ていて、
主人公は妻と離婚して、会社を辞め「木野」といバーを開いた。
そこでのエピソードが書いてある。
「女のいない男たち」は、夜中1時過ぎにかかってきた電話で、
1人の女性が死んだことを知らされる。
その女性は14歳のときに知り合った女性だった。
そっから男がうだうだいろんなことを思う。
この本にある短編小説を、私は好きです。