朝日新聞の週末beに、「今さら聞けない+ ティッシュペーパー」という記事がありました。
ティッシュペーパーは、広葉樹と針葉樹をブレンドして作り、ヨーロッパより早く日本では鼻をかむ紙を使っていたのだそうです。
広葉樹(ユーカリ、ブナ)は、柔らかいけれど弱い
針葉樹(杉、松)は、固いが強い
「素材の配合をどうするかが大事」(日本製紙クレシアの担当者)
ティッシュは、もともと第一次世界大戦中に、脱脂綿の代用品として米国で開発されたのだそうです。
その後、1924年に化粧落としとして米国で発売され
1964年に、箱入りが発売された
鼻をかむ紙という点では、日本が先んじていて
17世紀に支倉常長がヨーロッパを訪問したとき、鼻をかむ紙を持っていったのだそうです。
「鼻をかんだ紙を街を街で捨てると、ヨーロッパ人が珍しがって集めたといわれています。
鼻をかむ紙や、化粧を落とす紙などは日本にすでにありました」 ということです。
----------------------------------
日本の鼻をかむ紙とは、懐紙(茶道で使うポケットサイズの紙)のようなものだったのでしょうか。
ヨーロッパ人が珍しがって集めたというのがおかしいです。
ウィキペディアを見ると、脱脂綿の代用品として開発されたティッシュは、第一次世界大戦が終わると大量に余ったため、
クリネックス社が、女性の化粧落としとして売り出した とありました。
ティッシュが化粧落としとは、どういうことだろうと不思議に思いました。
「ティッシュ 化粧落とし」で見てみると、
「メークおとしの使用量と使い方 - 資生堂」というサイトが2番目に出てきました。
(http://www.shiseido.co.jp/listener/html/cfe00101.htm参照)
「メークおとし」のやり方で、ジェル、オイル、クリーム、ローション、シートとタイプ別に説明されています。
クリームタイプのところに、
さくらんぼ大のクリームを顔全体に広げてなじませ、ティッシュでふきとる と書かれています。
そういえば、私が子どもの頃、母が化粧を落とすのに同様の方法を使っていました。
クリームタイプとセットで使うのですね。
懐紙とティッシュの関係はどうなのだろうと、「懐紙 ティッシュ」で検索してみました。
懐紙とティッシュの関係を述べたサイト等は見つけることができませんでしたが、
「懐紙」のウィキペディアが3番目に出てきて
「平安貴族から現代一般人にいたるまでメモ用紙、ハンカチ、ちり紙、便箋などの様々な用途で使われてきた(和紙#平安時代の紙文化も参照)」 とありました。
平安時代からなんですね、すばらしいです。
「和紙」の項目の「平安時代の紙文化」を見てみると、
「貴族は常に懐に紙を畳んで入れ、ハンカチのような用途の他に、菓子を取ったり、盃の縁をぬぐったり、即席の和歌を記すなどの用途にも使用し、当時の貴族の必需品であった」
まったく今のティッシュやハンカチの役目をしています。
今から1,000年も昔に使われていたのですね。
それまで唐紙と輸入物の紙を使っていたのが、平安時代に紙漉きの技術が確立し、紙が大量生産されるようになったようです。
世界に先がけて、平安時代から日本では懐紙が使われていたとは、嬉しい情報でした。


ティッシュペーパーは、広葉樹と針葉樹をブレンドして作り、ヨーロッパより早く日本では鼻をかむ紙を使っていたのだそうです。
広葉樹(ユーカリ、ブナ)は、柔らかいけれど弱い
針葉樹(杉、松)は、固いが強い
「素材の配合をどうするかが大事」(日本製紙クレシアの担当者)
ティッシュは、もともと第一次世界大戦中に、脱脂綿の代用品として米国で開発されたのだそうです。
その後、1924年に化粧落としとして米国で発売され
1964年に、箱入りが発売された
鼻をかむ紙という点では、日本が先んじていて
17世紀に支倉常長がヨーロッパを訪問したとき、鼻をかむ紙を持っていったのだそうです。
「鼻をかんだ紙を街を街で捨てると、ヨーロッパ人が珍しがって集めたといわれています。
鼻をかむ紙や、化粧を落とす紙などは日本にすでにありました」 ということです。
----------------------------------
日本の鼻をかむ紙とは、懐紙(茶道で使うポケットサイズの紙)のようなものだったのでしょうか。
ヨーロッパ人が珍しがって集めたというのがおかしいです。
ウィキペディアを見ると、脱脂綿の代用品として開発されたティッシュは、第一次世界大戦が終わると大量に余ったため、
クリネックス社が、女性の化粧落としとして売り出した とありました。
ティッシュが化粧落としとは、どういうことだろうと不思議に思いました。
「ティッシュ 化粧落とし」で見てみると、
「メークおとしの使用量と使い方 - 資生堂」というサイトが2番目に出てきました。
(http://www.shiseido.co.jp/listener/html/cfe00101.htm参照)
「メークおとし」のやり方で、ジェル、オイル、クリーム、ローション、シートとタイプ別に説明されています。
クリームタイプのところに、
さくらんぼ大のクリームを顔全体に広げてなじませ、ティッシュでふきとる と書かれています。
そういえば、私が子どもの頃、母が化粧を落とすのに同様の方法を使っていました。
クリームタイプとセットで使うのですね。
懐紙とティッシュの関係はどうなのだろうと、「懐紙 ティッシュ」で検索してみました。
懐紙とティッシュの関係を述べたサイト等は見つけることができませんでしたが、
「懐紙」のウィキペディアが3番目に出てきて
「平安貴族から現代一般人にいたるまでメモ用紙、ハンカチ、ちり紙、便箋などの様々な用途で使われてきた(和紙#平安時代の紙文化も参照)」 とありました。
平安時代からなんですね、すばらしいです。
「和紙」の項目の「平安時代の紙文化」を見てみると、
「貴族は常に懐に紙を畳んで入れ、ハンカチのような用途の他に、菓子を取ったり、盃の縁をぬぐったり、即席の和歌を記すなどの用途にも使用し、当時の貴族の必需品であった」
まったく今のティッシュやハンカチの役目をしています。
今から1,000年も昔に使われていたのですね。
それまで唐紙と輸入物の紙を使っていたのが、平安時代に紙漉きの技術が確立し、紙が大量生産されるようになったようです。
世界に先がけて、平安時代から日本では懐紙が使われていたとは、嬉しい情報でした。










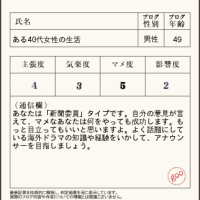
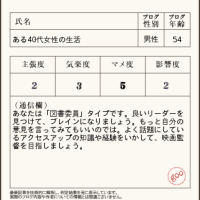





テッシュの歴史は古いのですね!
知りませんでした。
支倉常長!
まさに歴史ですね。
勉強になりました~。
ぽちっ
支倉常長は日本史の教科書で読んで以来、久しぶりに目にしました。
ティッシュの話題で取り上げられるとは、ですね。
いつもありがとうございます。
ぽちっ