2015年7月30日に発行された日本経済新聞紙の朝刊一面の見出し「がん最適治療 人工知能で 日本人向けに研究」を拝読しました。
日本IBMと東京大学医科学研究所は、最新鋭のIBMのコンピューター「ワトソン」を利用して、日本人向けのがん治療法を開発するという、新しい国際的な産学連携プロジェクトが始まるという内容です。
そのポイントは、IBMが開発した新型コンピューター「ワトソン」です。人間の言葉を理解し、文章を読んだりできる能力を持ち、大量データの中に潜む規則性を見いだすなどの能力を持っています。こうした人間の脳の仕組みをまねした情報処理の“デープラーニング”(深層学習)という人工知能(artificial intelligence)を利用して、がんの最適な治療法・方針を導きだそうというプロジェクトです。
日本経済新聞紙のWeb版である日本経済新聞 電子版では、見出し「がん最適治療 人工知能で 日本人向けに研究 日本IBM・東大」と報じています。
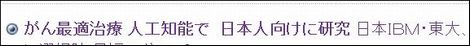
この記事では、まず日本IBMは国内外のがん治療などの論文や薬の効能などの最新データを「ワトソン」に入力し学習させます。東京大学医科学研究所は日本人のがん患者の血液やがん組織から採取した遺伝子データを、「ワトソン」に入力します。こうしたデータベースを基に、「ワトソン」は患者ごとに最適な薬剤や治療法の選択肢を提示する技術開発を目指します。
この記事を読んで、一般の方は「人工知能」の中身をどこまで理解できるのかを知りたいと感じました。この記事を読んでも、一般の方にとっては「人工知能」とは魔法の箱のようなもので、その仕組みを概略まででも知解できる人間の数はどのぐらいなのか興味がわきます。
かなり大胆にいえば、スマートフォンで採用されている“Sir”(アップル社のiPhone)やNTTドコモの“しゃべってコンシェル”などのサービスは、人工知能を利用しています。スマートフォンの利用者の中で、こうしたサービスの技術面での仕組みを理解できる方はどのぐらいなのでしょうか。
単なる利用者で済む方もいますが、スマートフォンの開発者として大まかには人工知能の仕組みを理解している方も不可欠でしょう。
話はさらに飛躍して、現在、自動車の自動ブレーキシステムが実用化されつつあります(初歩的なものは搭載されています)。これも広い意味での人工知能の利用技術です。つまり、自動車のブレーキシステムなどのシステム系開発者も、人工知能についての仕組みを理解していることが不可欠です。
最近呼んだ技術情報誌では、人工知能分野での“デープラーニング”(深層学習)の進化がここ数年間で大幅に進んだそうです。受け折りですが、“デープラーニング”(深層学習)の研究開発者ほど、人間と“デープラーニング”(深層学習)との競争では、悲観的です。将来、人間は“デープラーニング”(深層学習)に負け、人間が担当する仕事が限られると予言する研究開発者が増えているそうです。
“デープラーニング”(深層学習)と人工知能については、米国の方が日本に比べて、研究開発が先行しているとみている方が多いです。日本でも、人工知能分野での研究開発拠点として、国立研究開発法人産業技術総合研究所に人工知能研究センター(東京都江東区青海)を2015年5月1日に設立し、「人間と相互理解できる次世代人工知能技術」の研究開発態勢を整えました。この研究センターから未来に役に立つ人工知能応用技術が産まれることを願っています。
日本IBMと東京大学医科学研究所は、最新鋭のIBMのコンピューター「ワトソン」を利用して、日本人向けのがん治療法を開発するという、新しい国際的な産学連携プロジェクトが始まるという内容です。
そのポイントは、IBMが開発した新型コンピューター「ワトソン」です。人間の言葉を理解し、文章を読んだりできる能力を持ち、大量データの中に潜む規則性を見いだすなどの能力を持っています。こうした人間の脳の仕組みをまねした情報処理の“デープラーニング”(深層学習)という人工知能(artificial intelligence)を利用して、がんの最適な治療法・方針を導きだそうというプロジェクトです。
日本経済新聞紙のWeb版である日本経済新聞 電子版では、見出し「がん最適治療 人工知能で 日本人向けに研究 日本IBM・東大」と報じています。
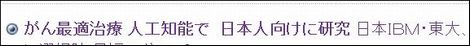
この記事では、まず日本IBMは国内外のがん治療などの論文や薬の効能などの最新データを「ワトソン」に入力し学習させます。東京大学医科学研究所は日本人のがん患者の血液やがん組織から採取した遺伝子データを、「ワトソン」に入力します。こうしたデータベースを基に、「ワトソン」は患者ごとに最適な薬剤や治療法の選択肢を提示する技術開発を目指します。
この記事を読んで、一般の方は「人工知能」の中身をどこまで理解できるのかを知りたいと感じました。この記事を読んでも、一般の方にとっては「人工知能」とは魔法の箱のようなもので、その仕組みを概略まででも知解できる人間の数はどのぐらいなのか興味がわきます。
かなり大胆にいえば、スマートフォンで採用されている“Sir”(アップル社のiPhone)やNTTドコモの“しゃべってコンシェル”などのサービスは、人工知能を利用しています。スマートフォンの利用者の中で、こうしたサービスの技術面での仕組みを理解できる方はどのぐらいなのでしょうか。
単なる利用者で済む方もいますが、スマートフォンの開発者として大まかには人工知能の仕組みを理解している方も不可欠でしょう。
話はさらに飛躍して、現在、自動車の自動ブレーキシステムが実用化されつつあります(初歩的なものは搭載されています)。これも広い意味での人工知能の利用技術です。つまり、自動車のブレーキシステムなどのシステム系開発者も、人工知能についての仕組みを理解していることが不可欠です。
最近呼んだ技術情報誌では、人工知能分野での“デープラーニング”(深層学習)の進化がここ数年間で大幅に進んだそうです。受け折りですが、“デープラーニング”(深層学習)の研究開発者ほど、人間と“デープラーニング”(深層学習)との競争では、悲観的です。将来、人間は“デープラーニング”(深層学習)に負け、人間が担当する仕事が限られると予言する研究開発者が増えているそうです。
“デープラーニング”(深層学習)と人工知能については、米国の方が日本に比べて、研究開発が先行しているとみている方が多いです。日本でも、人工知能分野での研究開発拠点として、国立研究開発法人産業技術総合研究所に人工知能研究センター(東京都江東区青海)を2015年5月1日に設立し、「人間と相互理解できる次世代人工知能技術」の研究開発態勢を整えました。この研究センターから未来に役に立つ人工知能応用技術が産まれることを願っています。

















人工知能とは何かは、普段は知らなくても済みます。でも、知らないうちに人工知能無しでは暮らせない人間が増えます。
現在の怪談なのでしょう?
こうしたことが起こらないように、人類は賢く生き延びるのでしょうか。
米国人は映画のターミネーターの世界をまったくの仮想とは思っていないとのうわさです。
日本企業も、このデープラーニングの研究を進めているのかお伺いしたいです。
コンピューター「ワトソン」の機能について、書いた記者もどの程度理解しているのかと感じました。
最近は、普通の方が知っている知識と、専門家が知っている知識の差がますます大きくなり、厳しい時代になっています。