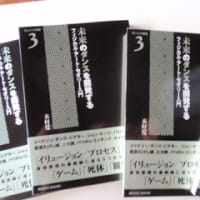8/18
『Review House 02』へ寄稿する文章がようやく完成。編集の方々を待たせに待たせた。ここから彼らのだめ出しをもらって書き直して正式に脱稿ということになるが、今回は、会田誠と遠藤一郎やChim↑Pomや加藤愛はどう違うのかという内容で一本書いた。自分を確認するような原稿になったと思う。「アイロニー」VS「痙攣」というか「モダニズム」VS「アヴァンギャルディズム」というか。
ペドロ・コスタ『骨』(1997)を見た。どんどん眠くなり、どんどんフォロー出来ない感が高まるものの、ずっと見ていたくもなって、ぼくにとってさしあたりペドロ・コスタ作品は、退屈だが吸引力のある映画といったところ(映画見る力が昔より衰えているのかも、リハビリリハビリ)。『血』にあった、古典的映画を意識したコード性は希薄になって、だから役者が何してんだかほとんどわからないショットが繋がっていく。『溶岩の家』については、古典的な映画の体系性とアフリカのポルトガル人という地政学的な事象とが、つかず離れず、その緊張が映画になっているように思ったのだけれど、今回は、映画力が古典性にあまりこだわらずに発揮されている気がした。コスタのことは、『ヴァンダの部屋』を見てからあらためて考えてみようと思う。
夜、久しぶりにゴールデンタイムのテレビ番組をボーっと見ていたら、「HEY!HEY!HEY!」に出ていたグラビアアイドル3人組が「口パクアイドル」と称して出ていた。『Review House 01』に「あて振りとしてのアート」というタイトルの文章を書いたぼくとしては、この辺り、気になる。歌は別の人が歌い、自分たちは歌っている振りをして踊るだけなのだという。実際パフォーマンスを見ていると、「口パク」も真剣にやっていないので、そこは本当に芸がないなーと思うが(これに比べればAneCanの押切もえがジェームス・ブラウンの口パクやっているのの方がずっと興味深い)、こういうビジュアル(視覚)とオーディオ(聴覚)の分離と接合、分身的な表現は、今後も様々試みられるのだろう。
8/19
朝、鈴木治行『語りもの』を聴いた。ちょっとこれはとてつもなく素晴らしいと思う。タイトル通り、音楽と「語り」が並置と混淆の状態になっていて、とくにキャッチーで面白いのは、「自己言及性」と本人が言っている手法で、音楽演奏を語りが実況するところ。例えば「演奏が始まる」などと冒頭で語られたりする。アンチイリュージョニズムの芸術にとって歌詞とは、何であり得るかという問いへのなるほど、もっともまっとうな回答だ。チェルフィッチュを思い返しもするが、ちょっと違うのは、チェルフィッチュの場合「フリータイムってのを始めます」と役者が言う時、まさに自分がこれから始める芝居というものを名指しするのだけれど、鈴木の語りが言及するのは音楽についてなのである。語りにとって隣の他人である音楽を語りの対象とするという発想が、妙な連想を膨らませる。音楽の分身-心霊。あと、物語の要点のようなものを淡々と話すようなところでは、「ああ、映画というのは、語るだけで成立するのか」と思った。映画がコードの体系で、イメージはそのコードを指し示す仕事をしているのならば(その仕事にイメージの仕事を思い切って短絡させてしまうなら)、コード(これは極めて言語的な存在だ)を言語に置き換えてそれをぽつり呟くだけで、映画は成立してしまうのだ。フィルムというマテリアルの代わりに、この映画では、頭のなかに浮かんだ映像がイメージとなる。ぼくはボクデスの「ムニャムニャくん」に、そうした言葉が聞く者の頭にイメージを喚起させてしまうという暴力の存在を読み取ってきたのだけれど、そうしたイメージの喚起力が映画となって迫ってくるのを鈴木の「語り」には感じたのだった。
ずっとレディ・メイド(既製品)、分身、幽霊、心霊について考えている。すべてはこの問題に行き着くのじゃないかというくらい気になる。幽霊はいる。というよりも幽霊しかいない。このことを、全てはコピーとみなすシミュラクル論、二次創作論etc.として捉えてもいいのだけれど、鳥瞰視的にではなく、見てしまった!という驚愕(背筋ぞくぞく)と共に考えること。すべて身体は幽霊体である。再認しかぼくたちには許されていない、ということなのか。
『Review House 02』へ寄稿する文章がようやく完成。編集の方々を待たせに待たせた。ここから彼らのだめ出しをもらって書き直して正式に脱稿ということになるが、今回は、会田誠と遠藤一郎やChim↑Pomや加藤愛はどう違うのかという内容で一本書いた。自分を確認するような原稿になったと思う。「アイロニー」VS「痙攣」というか「モダニズム」VS「アヴァンギャルディズム」というか。
ペドロ・コスタ『骨』(1997)を見た。どんどん眠くなり、どんどんフォロー出来ない感が高まるものの、ずっと見ていたくもなって、ぼくにとってさしあたりペドロ・コスタ作品は、退屈だが吸引力のある映画といったところ(映画見る力が昔より衰えているのかも、リハビリリハビリ)。『血』にあった、古典的映画を意識したコード性は希薄になって、だから役者が何してんだかほとんどわからないショットが繋がっていく。『溶岩の家』については、古典的な映画の体系性とアフリカのポルトガル人という地政学的な事象とが、つかず離れず、その緊張が映画になっているように思ったのだけれど、今回は、映画力が古典性にあまりこだわらずに発揮されている気がした。コスタのことは、『ヴァンダの部屋』を見てからあらためて考えてみようと思う。
夜、久しぶりにゴールデンタイムのテレビ番組をボーっと見ていたら、「HEY!HEY!HEY!」に出ていたグラビアアイドル3人組が「口パクアイドル」と称して出ていた。『Review House 01』に「あて振りとしてのアート」というタイトルの文章を書いたぼくとしては、この辺り、気になる。歌は別の人が歌い、自分たちは歌っている振りをして踊るだけなのだという。実際パフォーマンスを見ていると、「口パク」も真剣にやっていないので、そこは本当に芸がないなーと思うが(これに比べればAneCanの押切もえがジェームス・ブラウンの口パクやっているのの方がずっと興味深い)、こういうビジュアル(視覚)とオーディオ(聴覚)の分離と接合、分身的な表現は、今後も様々試みられるのだろう。
8/19
朝、鈴木治行『語りもの』を聴いた。ちょっとこれはとてつもなく素晴らしいと思う。タイトル通り、音楽と「語り」が並置と混淆の状態になっていて、とくにキャッチーで面白いのは、「自己言及性」と本人が言っている手法で、音楽演奏を語りが実況するところ。例えば「演奏が始まる」などと冒頭で語られたりする。アンチイリュージョニズムの芸術にとって歌詞とは、何であり得るかという問いへのなるほど、もっともまっとうな回答だ。チェルフィッチュを思い返しもするが、ちょっと違うのは、チェルフィッチュの場合「フリータイムってのを始めます」と役者が言う時、まさに自分がこれから始める芝居というものを名指しするのだけれど、鈴木の語りが言及するのは音楽についてなのである。語りにとって隣の他人である音楽を語りの対象とするという発想が、妙な連想を膨らませる。音楽の分身-心霊。あと、物語の要点のようなものを淡々と話すようなところでは、「ああ、映画というのは、語るだけで成立するのか」と思った。映画がコードの体系で、イメージはそのコードを指し示す仕事をしているのならば(その仕事にイメージの仕事を思い切って短絡させてしまうなら)、コード(これは極めて言語的な存在だ)を言語に置き換えてそれをぽつり呟くだけで、映画は成立してしまうのだ。フィルムというマテリアルの代わりに、この映画では、頭のなかに浮かんだ映像がイメージとなる。ぼくはボクデスの「ムニャムニャくん」に、そうした言葉が聞く者の頭にイメージを喚起させてしまうという暴力の存在を読み取ってきたのだけれど、そうしたイメージの喚起力が映画となって迫ってくるのを鈴木の「語り」には感じたのだった。
ずっとレディ・メイド(既製品)、分身、幽霊、心霊について考えている。すべてはこの問題に行き着くのじゃないかというくらい気になる。幽霊はいる。というよりも幽霊しかいない。このことを、全てはコピーとみなすシミュラクル論、二次創作論etc.として捉えてもいいのだけれど、鳥瞰視的にではなく、見てしまった!という驚愕(背筋ぞくぞく)と共に考えること。すべて身体は幽霊体である。再認しかぼくたちには許されていない、ということなのか。