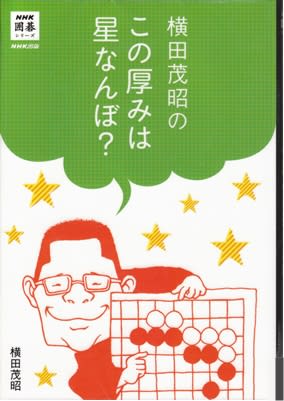昨晩、猿十番碁の後のチャットでhexaさんとasutoronさんに
棋書電子書籍化の魅力を熱く語ったのですが、
あまり伝わらなかったようでした(涙)。
このブログのアクセス数の推移をみても、
特に興味をもたれている印象はないですね。
ご両者曰く、
「どうせ電子書籍にしても読まないのだから、捨てちゃったら?」
それが出来ないから電子書籍化するんじゃんかよぉ(笑)!
まぁ、確かに電子書籍にしたからといって、
読むという保証はないですが、
断裁した本はさすがに保存意欲はなくなるし、
情報のキモは保存しているという安心もあるので、
断捨離…捨離のキッカケにはなると思うのですよ。
気が向いた時に読めるし…、この辺は性格もあるのかも。
またお二人は「労力に見合わない」と思っていらっしゃるようですが、
ここに苦労話を中心に記載しているのでそう思われたのかな?
ハッキリ断っておきますが設定に悩んでいるだけで
体裁が決まってしまえば電子書籍化は全然手間はかからないです!
実際、先週「囲碁将棋フォーカス」で広瀬プロの特集を観ながら
「この後、サッカー観にいくから道中のお供が欲しいな」
そこで王位戦の棋譜解説に入ったところを見計らって部屋に戻り、
「前田上級詰碁」(新書サイズ、152ページ)の電子書籍化。
断裁からスタートしてファイルの保存まで終わり、テレビをつけたところ、
ちょうどカナボーの浴衣鑑賞会「NHK囲碁講座」が始まったところでした。
つまり一冊を電子書籍化するのにかかる時間は10分~15分ぐらい。
一日一冊のペースなら全然日常的にできそうです。
これで部屋がスッキリするのだから、十分だと思うのですがどうでしょう?
知り合いの方でご希望があれば電子化やってあげますよ。
本気と書いてマジで。
棋書電子書籍化の魅力を熱く語ったのですが、
あまり伝わらなかったようでした(涙)。
このブログのアクセス数の推移をみても、
特に興味をもたれている印象はないですね。
ご両者曰く、
「どうせ電子書籍にしても読まないのだから、捨てちゃったら?」
それが出来ないから電子書籍化するんじゃんかよぉ(笑)!
まぁ、確かに電子書籍にしたからといって、
読むという保証はないですが、
断裁した本はさすがに保存意欲はなくなるし、
情報のキモは保存しているという安心もあるので、
断捨離…捨離のキッカケにはなると思うのですよ。
気が向いた時に読めるし…、この辺は性格もあるのかも。
またお二人は「労力に見合わない」と思っていらっしゃるようですが、
ここに苦労話を中心に記載しているのでそう思われたのかな?
ハッキリ断っておきますが設定に悩んでいるだけで
体裁が決まってしまえば電子書籍化は全然手間はかからないです!
実際、先週「囲碁将棋フォーカス」で広瀬プロの特集を観ながら
「この後、サッカー観にいくから道中のお供が欲しいな」
そこで王位戦の棋譜解説に入ったところを見計らって部屋に戻り、
「前田上級詰碁」(新書サイズ、152ページ)の電子書籍化。
断裁からスタートしてファイルの保存まで終わり、テレビをつけたところ、
ちょうど
つまり一冊を電子書籍化するのにかかる時間は10分~15分ぐらい。
一日一冊のペースなら全然日常的にできそうです。
これで部屋がスッキリするのだから、十分だと思うのですがどうでしょう?
知り合いの方でご希望があれば電子化やってあげますよ。
本気と書いてマジで。