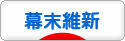母成峠古戦場の碑
前回更新した二本松城址と同じく、こちらもかなり前の2008年に訪問した古戦場なのですが、二本松城址の記事に便乗して更新させて頂きたいと思います。時間軸的には二本松城攻防戦の直後から母成峠攻防戦が始まりますので、二本松城址の記事の続きと思って頂ければ幸いです。
また二本松城址の記事でも書きましたが、母成峠・十六橋・戸ノ口原の各戦いについては、私がまだ戊辰会津戦争については詳しく調べていないので、今回の記事も二本松城址の記事同様に、簡単な説明になってしまう事をご了承下さい。
母成峠の戦い
二本松城攻防戦で勝利した新政府白河軍(会津追討白河口総督府)は、これで会津藩領の南東部から東部までを押さえる事に成功して、いよいよ会津藩領への侵攻を意図しました。一方会津藩の防衛体制は、これまでも白河から直接侵攻を受ける、猪苗代湖南岸の勢至堂口と大平口に守備兵を置いていました。しかし二本松城を新政府軍が攻略し、その後の八月上旬に郡山宿や須賀川宿と言った、奥州街道筋の宿場から同盟軍が駆逐された事により、猪苗代湖東岸の御霊櫃口や中山口、そして母成峠からも新政府軍は侵攻可能になったのです。
このように侵攻口が増えた新政府白河軍は、どのルートから会津藩領に攻め込むかを軍議します。この席上で猪苗代湖東岸のルートでは主街道である、御霊櫃口からの侵攻を主張した板垣退助と、母成峠からの侵攻を主張した伊知地正治の間で激論が交わされます。二人の口論は結局決裂し、一時は板垣と伊地知がそれぞれ別の部隊を率いて、個々に御霊櫃口と母成峠から侵攻すると言う状況にまでなりました。しかし長州藩士桃村発蔵が間に入って調停し、最終的には伊地知が主張する母成峠から全軍一丸での侵攻が決定したと言う有名なエピソードがあります。ただ不思議とこのエピソードは『防長回天史』には載っていません。尚、『防長維新関係者要覧』には桃村の役職を長州藩施条銃中間第一大隊二番中隊所属の教導、ないし半隊長と書かれていますが、そのような者が白河軍参謀の伊地知と板垣との口論に割って入る事が出来るものでしょうか?。第一大隊二番中隊中隊長の楢崎頼三なら判るのですが・・・。
閑話休題。そんな新政府軍の思惑に対して、新政府軍の侵攻ルートを想定出来ない会津藩は、各地に兵力を分散しており、母成峠には打ち合わせの為に鶴ヶ城城下に来ていた大鳥圭介を派遣します。母成峠に到着した大鳥は、かつて伊達政宗が芦名義広と摺上原で戦った際に、母成峠をルートとした事から、新政府軍が母成峠から侵攻する事を想定し、関ヶ原前後に築かれた防塁に増築し、合計三段にも渡る陣地を築きます。更に母成峠を検分した大鳥は、母成峠を守るには兵力が少ないと、子飼いの伝習第二大隊(会幕連合軍第二大隊ですが、以降は旧名の伝習第二大隊の呼称を使います)を呼び寄せるものの、会津藩兵と故郷を失った二本松藩兵は二本松奪回の為に、大鳥の不在(軍議の為に出張中)の八月二十日に伝習大隊を伴って出撃します。この攻撃はあっさり新政府軍に撃退され、更に会津藩兵と二本松藩兵が伝習大隊を置き去りにして逃亡した為、伝習大隊のみが大損害を受けて、伝習第二大隊士官の浅田惟季が重症を追うなどの損害を受けます。

母成峠第一陣地に築かれた、石積みの防塁。この防塁は大鳥軍によって築かれたのではなく、関ヶ原の際に上杉景勝により、ないしその前後に会津の領主だった蒲生氏郷か加藤嘉明によって築かれたと思われます。

大鳥には野戦築城の知識はあったものの、着任してから時間的にこれだけの石積みを築くのは無理でしょう。また会津藩兵と言う線も薄いと思います。会津藩兵はそれこそ白河口の他にも越後口や日光口にも出兵していますが、石積みの防塁が作られたような場所は他に無いので、白河口や越後口にでさえ築かれなかった石積みの防塁が、会津藩が軽視していた母成峠に築かれた可能性は無いでしょう。
母成峠攻撃に向かった新政府軍の編成は、伊地知と板垣が率いる本隊(薩摩藩兵7個中隊相当と3個砲兵隊、長州藩第一大隊・第四大隊合併中隊、土佐藩兵7個小隊と砲兵隊、佐土原藩兵2個小隊と砲兵隊)は母成峠本道を進みます。土佐藩谷干城と長州藩楢崎頼三が率いる右翼部隊(長州藩第一大隊二番中隊、土佐藩兵7個小隊)は迂回して、勝岩方向から母成峠を目指します。そして薩摩藩兵精鋭中の精鋭、城下士小銃隊6個中隊相当(鈴木武五郎1番隊、村田新八2番隊、篠原国許3番隊、川村純義4番隊、野津静雄5番隊、野津道貫6番隊)と大垣藩3個小隊による左翼部隊は更に大きく迂回して、母成峠の背後を衝くように進軍します。
これに対して会津側は、大鳥率いる伝習大隊と土方歳三率いる新撰組が、大鳥が築いた三段陣地による縦深陣で布陣し、その後方に会津藩兵・二本松藩兵・仙台藩兵等の”サムライ”が布陣します。しかしこれらのサムライは、決死の覚悟で布陣する伝習大隊や新撰組とは違い、今までの新政府軍との戦いですっかり怖気ついており、戦意は殆どありませんでした。
大鳥が縦深陣と言う、それまでの日本に無い戦術を披露すれば、新政府軍の方も薩摩藩砲兵隊長である大山巌が、砲兵の集中運用と言う、これまた当時の日本には無い戦術を披露します。こうして奇しくも母成峠の戦いは、新政府軍と大鳥軍が新戦術を激突させる戦いとなりました。
かくして翌八月二十一日払暁、遂に新政府軍は母成峠に攻撃を開始します。大山の率いる砲兵隊の集中砲撃は、石積みの防塁に布陣する大鳥軍を圧倒して、砲撃を受けた大鳥軍は早々と第二陣地に後退します。しかしこの後退は大鳥の規定路線、大鳥軍が後退した第一陣地に新政府軍本隊は侵入するものの、侵入したのは歩兵のみで、砲兵は展開する適当な空間が無い為に、砲撃をする事が出来ませんでした。砲兵の援護がない歩兵の攻撃は、大鳥軍が篭る第二陣地に阻まれます。この時点では大鳥の戦術が新政府軍を凌駕しており、大鳥の縦深陣の前に新政府軍本隊の攻撃は頓挫するかに見えました。
しかし新政府軍本隊の攻撃が頓挫していた正にその時、迂回進軍する新政府軍右翼部隊が第二陣地に側面から猛射撃を開始します。この右翼軍の攻撃の前に大鳥軍は崩れかけるものの、大鳥の指揮の下に必死に戦線を維持します。むしろ新政府軍右翼部隊の攻撃で浮き足立ったのは会津・仙台・二本松のサムライ達で、大鳥軍が必死に戦線を維持している中、サムライ達はさっさと後退してしまいます。後方に布陣する会津・仙台・二本松の諸藩兵に後退されると、背後に回られる危険性もある事から大鳥軍も後退し、第三陣地に退きました。
大鳥はこの第三陣地で新政府軍を防ごうと試みるものの、第二陣地には大山率いる砲兵隊が展開出来る空間があった為、大山率いる砲兵隊が再び猛砲撃を開始します。この砲撃の前に流石の大鳥軍も支え切れなくなりますが、先に戦線が崩壊したのはまたもや会津・仙台・二本松のサムライ達。大山率いる砲兵の猛砲撃の前に、すっかり恐怖に駆られたサムライ達は母成峠を捨てて逃亡を開始します。しかもサムライ達は自分達が逃亡するだけでは留まらず、自分達が安全に逃走出来るように、新政府軍の追撃を防ぐために退路に火を放ちます。しかしこの時点では大鳥率いる伝習第二大隊と新撰組がまだ戦闘中であり、辛うじて戦線を維持していたものの、背後に火の手が挙がった為に、彼らの奮戦もここまで撤退を開始します。ただし撤退を開始したと言っても、峠道にはサムライが放った火により通行が出来ず、止むを得ず伝習隊と新撰組はバラバラになり森の中を退却。指揮官の大鳥ですら、数人の兵士達と山中をさ迷うと言う悲惨な逃避行を行う事になるのです。
ある意味この母成峠の戦いにおいて大鳥と、大鳥率いる伝習隊と新撰組は最初から最後まで会津藩のサムライに足を引っ張られていたと言えましょう。

母成峠から二本松方面を見下ろして。新政府軍はこの方面から進軍してきました。
十六橋の戦い

現在の十六橋。当然ですが当時の物とは違います。
母成峠の攻防戦で勝利した新政府軍だったものの、薩摩藩兵最強の部隊でありながら、この戦いで何の貢献も出来なかった、左翼部隊の薩摩藩城下士小銃隊1番隊から6番隊の将兵達にとっては憤懣やる方ない勝利でした。特に4番隊長だった川村純義は汚名返上の念に燃え、母成峠が陥落した二十一日夜半から進軍を開始します。この川村率いる薩摩藩城下士小銃4番隊と、会津藩兵の間によって行われたのが十六橋の戦いですが、何故十六橋がそんなに大事なのかを説明させて頂きます。
十六橋は猪苗代湖北岸に流れ込む日橋川に架かっている橋であり、最短距離で猪苗代湖北岸を進軍して会津鶴ヶ城に攻め込むには、必ず通らないと行けない要所でした。逆に会津藩からすれば十六橋を突破されてしまうと、敵軍を防げるような地形は他になく、新政府軍にとっても会津藩兵にとっても、かならず確保しなくてはいけない要所だったのです。
このような要所の十六橋ですが、ここを巡る戦いが行われたのは、会津藩の判断ミスが重なった為です。まず最初の判断ミスは猪苗代城の自落です。母成峠から十六橋までは、何も遮る物が無かった訳ではなく、猪苗代湖北岸には猪苗代城が有りました。母成峠を突破したとしても、新政府軍が十六橋を目指すにはこの城を攻め落とす必要があり、この城を守っていれば、その間に十六橋を破壊して新政府軍を足止め出来る十分な時間がありました。しかし母成峠の敗戦を知った会津のサムライ達は、恐怖に駆られて戦いもせずに猪苗代城を自焼させて逃亡します。おかげで川村率いる四番隊は、無人の野を進むが如く十六橋を目指す事が出来たのです。
会津藩の判断ミスのもう一つは、情報収集力の無さです。武士道精神に溢れていたと言われる会津藩ですが、情報に関しては軽視していたらしく、鶴ヶ城の会津藩主松平容保以下の藩首脳部が母成峠陥落を知ったのは、翌日の二十二日午後の事と伝えられます。母成峠陥落を知った会津藩首脳部は、慌てて十六橋破壊の為に奇勝隊や白虎隊士中2番隊を派遣するものの、これらの部隊が十六橋に到着し、橋の破壊を始めたのとほぼ同時に川村率いる薩摩藩城下士小銃4番隊もまた十六橋が到着しました。すかさず川村4番隊は、十六橋を破壊中の会津藩兵に射撃を開始、この銃撃により会津藩兵が敗走した事により、新政府軍は十六橋の確保に成功。鶴ヶ城に突入する橋頭堡を確保する事に成功したのです。

現在の十六橋
戸ノ口原の戦い

戸ノ口原古戦場の碑
十六橋を確保した新政府軍は、翌二十三日にいよいよ会津鶴ヶ城を目指し侵攻を開始します。この新政府軍と白虎隊士中2番隊が激突したのが、戸ノ口原の戦いです。世間の人気が高い白虎士中2番隊が参戦した事で、知名度の高い戸ノ口原の戦いですが、戦いその物は新政府軍の掃討戦と呼ぶべきものでした。白虎士中2番隊は塹壕と胸壁に篭り新政府軍を迎撃したものの、戸ノ口原は平野であり、散開攻撃する新政府軍の前に白虎士中2番隊は蹂躙されます。そもそも十六橋を突破された時点で、会津藩の防衛ラインは崩壊しており、この戸ノ口原の戦いは、藩主容保が鶴ヶ城に逃走するまでの時間稼ぎをする戦いでしかありませんでした。

現在の戸ノ口原
以上、母成峠・十六橋・戸ノ口原古戦場の紹介と、簡単にですがこの三つの戦いの説明を書かせて頂きました。私としてはこの三つの戦いについて、「サムライと歩兵との戦い」との認識を持っています。
多くの会津ファンが主張するとおり、確かに会津藩士は武士道精神を持っており、会津藩士は正しくラストサムライであったと言えましょう。しかし一方でサムライと言うのは近代戦をするのに全くもって不向きな存在なのです。まず武士道精神と言うのは士農工商の身分差意識をベースにしているので、身分差別意識の激しい物でした。そしてこの身分差別意識から、会津のサムライ達は農町民出身の伝習隊を見下し、伝習隊と協力して戦うどころか、終始伝習大隊の足を引っ張っり続けていたのです。
また精神論ばかり振りかざし、大鳥の進言にも耳を傾けず、余計な攻勢を行い、母成峠攻防戦の前に折角の伝習隊の戦力を消耗させたり、情報収集力の無さから十六橋破壊の判断が遅れたなどの、会津藩の情報軽視の傾向は旧日本軍を髣髴させます。
一方の今回紹介した三つの戦いで、新政府軍の主力となった薩摩・長州・土佐の三藩兵は、侍から歩兵(及び砲兵)に脱皮する事に成功したと言えましょう。そして母成峠や十六橋の戦いで、サムライがいかに近代戦に向かないと言うのを実証した一方で、薩長土の歩兵は近代戦で会津のサムライを鎧袖一触で撃破したのです。実際会津側で善戦したのは大鳥軍の歩兵だけであり、歩兵に対抗出来るのは歩兵だけと言うのを、今回紹介した戦いでは実証したと言えましょう。
訪問日:2008年5月08日