戊辰野州戦争戦争後期の戦いである、板室古戦場や大田原城址、及び周辺の古戦場を、先週末に大山師匠と梅原さんと訪れてきました。現在記事作成中の野州戦争第四章でこの板室・大田原城の戦いを扱う予定なので、その記事に使う画像を撮影してしたのですが、年内には記事が完成しそうもないので、何枚か画像だけ紹介させて頂きたいと思います。
本来の今旅行の行程は、一日目が大田原城址~黒羽城址~白河関門跡、二日目が板室~塩野崎~関谷~大網~那須塩原だったのですが、今回のブログでは実際の戊辰野州戦争の時系列順に画像を紹介させて頂きます。また板室・大田原城の戦いの説明は、今回は概略のみに留めさせて頂きますので、詳細は野州戦争第四章の記事完成までお待ち下さい。
日光退去後会津藩領田島宿で、大鳥圭介率いる旧幕府軍は会津藩兵と合流して、会幕連合軍として四個大隊に再編成しました。この内第二大隊と第三大隊が、今市宿方面で板垣退助率いる新政府東山道軍と交戦したのは、野州戦争第三章の記事で書かせて頂きましたが、第一大隊と第四大隊の半分が出兵したのが、今回訪れた板室・大田原方面です。
秋月登之助率いる会幕連合軍第一大隊は、会津領大峠を通り那須山中の三斗小屋宿を拠点として、閏四月下旬より奥州街道を街道を伺う姿勢を見せました。また同第四大隊の半分である旧草風隊は那須塩原方面に進出、こちらも奥州街道を伺う姿勢を見せました。
一方の宇都宮城に在城していた新政府東山道軍参謀の伊知地正治は、新政府奥羽鎮撫総督府参謀の世良修蔵より援軍要請を受けた事もあり、白河城を目指し北上を開始します。当時宇都宮城と白河城の中間地点には大田原城が位置しており、伊地知が到着する前に大田原城には新政府軍の先発部隊が駐屯していました。
その先発部隊の元に、第四大隊草風隊の情報が入り、先発部隊は閏四月十六日に関谷村・大網陣屋領の草風隊を急襲し、草風隊を撃破しました。

大網陣屋領の現況、画像左側が渓谷になっており、右側は山地の為、塩原方面に向かう道はこの道だけでした。
しかし今度は三斗小屋宿の第一大隊が、会津東街道を進軍し板室宿まで進出している事が大田原城に報告されます。これを聞いた大田原城の新政府軍が、板室方面に出発(尚、この板室攻撃の決断に、どれだけ伊地知が関わっているかが、第四章の記事作成で重視したいと思います)。同二十一日に塩野崎村で第一大隊の先鋒部隊を撃破します。

旧塩野崎村の薬王寺。塩野崎村の戦いはこの薬王寺の付近で行われたらしく、新政府軍と会幕連合軍共にこの薬王寺を宿陣地としました。
翌二十二日、新政府軍は板室宿方面に進軍し、新政府軍と会幕連合軍は那珂川を挟んで交戦する。地の利を得た会幕連合軍は善戦したものの、新政府軍の別働隊が現在の板室温泉街の方から攻撃した為、会幕連合軍第一大隊は三斗小屋宿に撤退する。

板室古戦場の全景。左手前の谷底の集落が油井村で、新政府軍はこの唯村の谷上辺りに布陣して、画面右の崖の上に布陣した会幕連合軍第一大隊と対峙しました。画面では見えませんが、両軍が対峙した谷底には那珂川が流れていて、両軍の進出を妨げていました。尚、画面右上の山岳地帯の裏側に三斗小屋宿は位置しています。
余談ながら、板室古戦場の全景を見渡せるこの画像を個人的には気に入っており、今まで撮影した中で一番のベストショットと思っています(^^;)

谷底の那珂川から、会幕連合軍が布陣した崖上を見上げて。

会幕連合軍が布陣した崖上に建てられた、板室の戦いで戦死者の慰霊碑。「右、ろくとち(六斗地)。左、いたむろ(板室)」と掘られており、追分に位置する道標としても活用されていたと言うのが伝わってきます。
板室・大網の会幕連合軍を撃破して、奥州街道の安全を確保した伊地知は、その後北上を再開し、五月一日奥州の玄関口である白河城を陥落させます。
そんな伊地知が白河城を攻略した翌日の五月二日、三斗小屋宿を出発した会幕連合軍第一大隊と会津藩兵が大田原城に攻めかかります。大網・板室で会幕連合軍を破った薩摩藩兵・長州藩兵・忍藩兵と言った新政府軍の主力は、伊地知が全て率いて白河城に行ってしまった為、大田原城には大田原藩兵しか居なく、その大田原藩兵も白河城の後方拠点とされた鍋掛村と芦野村に出兵していた為、城内には百名ほどしか居ない状況で会幕連合軍の攻撃を受けたのです(会幕連合軍は800~1000人と伝えられます)。
大田原藩兵は鍋掛村と芦野村に駐屯する藩兵を呼び寄せて防戦しますが、多勢に無勢は変わらず、大田原城は遂に陥落した・・・となりそうなものですが、実際には会幕連合軍は攻めあぐねます。結局大雨が降り両軍とも銃砲が使用不能になったり、大田原城内作事小屋の火薬が爆発したりなどのアクシデントが続いた末、会幕連合軍も大田原藩兵も大田原城から撤退と言う何とも締まらない結末でこの戦いは終了します。
この後会幕連合軍第一大隊と第四大隊が攻勢に出る事はなく、奥州街道の確保を巡る戦いは終了しました。

大田原藩兵が防衛ラインとした経塚付近の現況。右端に見えるのは経塚稲荷。

北方から見た大田原城址と、水堀の役目も果たした蛇尾川。

大田原城址から、大田原市街を見下ろして。

大田原城攻防戦で激戦となった坂下門付近。
戊辰戦争の戦いの中で、ただでさえ知名度の低い野州戦争ですが、板室・大田原城の戦いはその中でも知名度が低い戦いだと思います。しかし結果的とは言え、板室・大田原城の戦いは奥州街道を確保出来るかの戦いの様相を示しました。伊知地正治率いる新政府東山道軍は五月一日に白河城を奥羽列藩同盟軍から奪取して、結果これが戊辰会津戦争の勝敗を決する事になります。しかし、もし五月二日の大田原城攻防戦で会幕連合軍が大田原城を攻略しておれば、白河城の伊地知隊は補給戦を分断され、すぐに白河城を失う事は無くても、戦況は余談を許さない事態になっていた可能性は高いと思います。
このように板室・大田原城の戦い、特に大田原城攻防戦は戊辰会津戦争の戦局を左右し兼ねない戦いだったと思いますので、もっと重視されても良い戦いだったのではないでしょうか。今回は簡単な概略のみに留まらせて頂きましたが、そのような知名度の低い板室・大田原城の戦いの記事を現在作成中です。
本編とは関係有りませんが、今回の旅行で改めて三月の地震の凄さを実感しました。

画像は大山巌墓所での崩れた石灯籠ですが、ここだけではなく、今回旅行したあちこちで崩れた石垣や石灯籠、山崩れの跡を多数見ました。栃木中部の宇都宮と比べると、栃木北部の被害は大きく、あの大震災の被害の大きさを改めて実感しました。
真面目な事を書いた後で申し訳ありませんが、今回の旅行で個人的に衝撃的だった事。私は高校時代に住んでいた寮で出されたウナギがあまりにも不味かった為、以降ウナギ嫌いを称していました。しかし今回の旅行中「うなぎ家 割烹いとう」でうな重を食べた時、その味に絶句。私が高校の時に食べたのは、ウナギに似た別の魚らしい、そしてこんな美味しい食べ物を今まで敬遠していた事に後悔した次第です。こうしてウナギの美味しさに目覚めた私ですが、大山師匠曰く「東京でこれくらいのレベルのウナギを食べようとすると、五千円近くするよ」。どうやら私が再びウナギの美味しさを味わえるのは遠い未来の模様です・・・(涙)

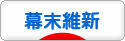
にほんブログ村










![]()


































































