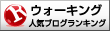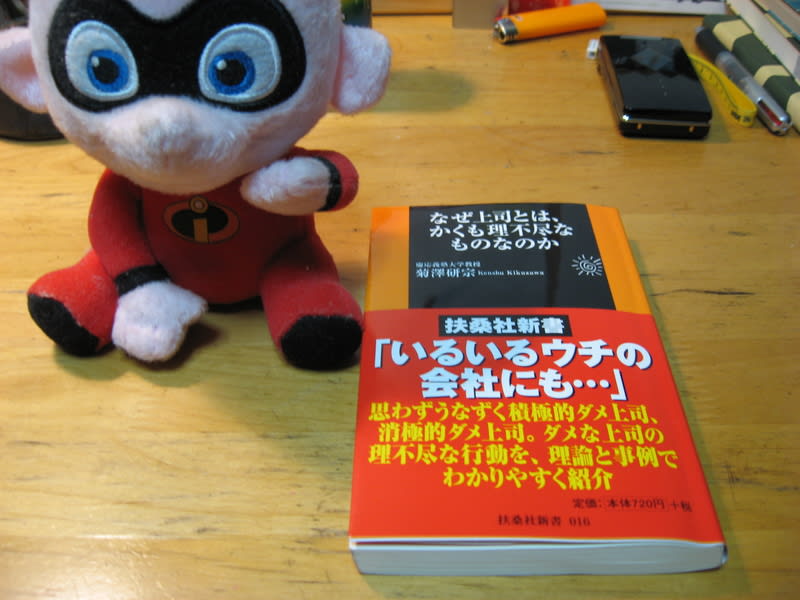
菊澤研宗著
なぜ上司はとは、かくも理不尽なものなのか
千葉駅で電車待ちしてる時本屋へ入ってすぐに目にとびこんで買ってしまいました、購買欲そそるこのタイトル
慶応大学経済学部教授であり、さすがに理論的にタイトルをといていました、理論としてはエージェンシー理論 取引コスト理論 所有権理論から解明していく・・なるほどこうも理論的なんだな上司の理不尽さは!
本から抜粋します。
時代の変遷とともに社会環境 ビジネス環境が変化しているにもかかわらず、過去の栄光や成功体験を持ち出して、積極果敢に陣頭指揮を執ろうとする、がんばるダメな上司もいるものです。このような上司のもとで働く部下は、時代遅れの仕事の仕方や企画を押し付けられるばかりではなく、今の時代に即した仕事の仕方は否定され、今の時代をにらんだ企画をことごとくボツにされることになります。
会社のブランドイメージが低下したり、経営資源が乏しくなったり、マーケット規模が縮小したりしてもなお会社が全盛期であったころの感覚で仕事をすすめようとするのです。この手の上司は共通した一つの特徴があります。それはかって会社の力によって達成した仕事を自分の能力であると勘違いしていることです。彼らのもうひとつの傾向を見出すことができます。彼らは、仕事がうまくいけば自分の能力のたまものであると自認し、それを周囲に認めさせようとがんばります。その一方で、仕事がうまくいかなかった場合は、しきりに会社のブランド力や企業体力の低下を口にするのです。
ここがおもしろい!
仕事の能力に自信をもってない社員は・・・どんな無駄な会議であっても、それが大きい会議であればあるほど、そこに出席すれば上層部に顔を覚えてもらえる。そういった思惑がはたらくのです。仕事の能力に自信を持てない50%の社員はそう考えるのです。
それでその会議に出席した社員はどうするかといえば、ひたすら、おとなしく席に座ってるだけです。決してあくびをしたりよそ見をしたりせず、発言するエグゼクテイブの顔をきちんと見つめ、冗談には笑いでこたえ 時には首を縦にふって「すばらしい」といわんばかりにうなずき、メモをとる・・・
ほんまにこんなの ある ある ですね!いるいる会議でこんな感じのやつ(笑)