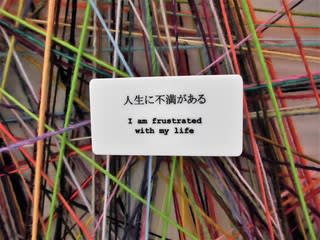今週は営業日が4日しかないので、久々の休日移動で東京に向かうことになった。朝、バスに乗って(歩くと25分くらいかかるのね)、JR琴似駅へ。
さすがに今日は混雑しておらず、座って札幌駅へ。しかしながら、ここから急に電車が混雑し始めた。服装や荷物を見る限り、遅い夏休みか、この3連休を札幌で過ごしたのかと思える人が多い。スーツを着ている私は浮きまくって、新千歳空港へ。
今日乗る飛行機はほぼ満席だったが、かなり前方席の窓側で、あまり圧力を感じないで過ごす。普段ならば寝るケースであるが、たまたま読んでいた本が強烈に面白く、読み続けたまま羽田空港へ。
羽田ではまだ雨が降っている。モノレールに乗り、浜松町へ。さらに上野に移動したときには、幸いなことに雨は上がっていた。
休日移動と言えば、今日の一発目はこちらである。
■東京都美術館「コートールド美術館展」。
ポール・セザンヌ「鉢植えの花と果物」:物の配置と軸線が気になる、幾何学的作品。
ポール・セザンヌ「カード遊びをする人々」:ガシッと男おとこした作品。塗残しがあるのも粋な感じさえ。
アンリ・ルソー「税関」:自らが勤めていた税関を描いた唯一の作品だそうだが、架空の風景らしい。
ピエール=オーギュスト・ルノワール「春、シャトゥー」:草むらで背中を向けて立つ人。これは素敵なルノワールだ。
ピエール=オーギュスト・ルノワール「桟敷席」:これも傑作だよなあ。
エドガー・ドガ「舞台上の二人の踊り子」:奥に踊り子を描き、手前に広いスペースがある。ここに踊り子が移動してくる、動きを予想させる作品。
エドゥアール・マネ「草上の朝食」:オルセー美術館にある同名作品の背景を検討するために描いた作品らしい。まさかあの作品がと思って驚いた。
エドゥアール・マネ「フォリー=ベルジェールのバー」:やや虚ろな顔をした女性バーテンダーが描かれた、非常に有名な作品。画の正面に行くためにしばらく待っていると、まるでバーカウンターで酒の注文をするために待っているかのようだ。ぜひ注文で一言交わして、彼女を微笑ませたい気になる(←これって恋?)。ちなみにカウンターの上の酒瓶はバスペールエール、シャンパン、緑色のリキュール(どこかで見たことがあるような)など、ここで酒を頼んだら、何が飲めるのかなあ(多分、氷が潤沢に無いから、辛いかもな)。

オノレ・ドーミエ「ドン・キホーテとサンチョ・パンサ」:黒い塊のような二人と馬。異星のサイボーグかのようだ。
エドガー・ドガ「窓辺の女」:逆光で顔が見えない女性。母のような、滅茶苦茶イイ女のような。
エドガー・ドガ「傘をさす女性」:水墨画のような未完に見える作品。やはりすごい。
ポール・セザンヌ「曲がり道」:この未完成な塗りにして、セザンヌ100%の作品。
ジョルジュ・スーラ「クールブヴォワの橋」:静寂の中、煙突から登る煙だけが動きを示している。
ジョルジュ・スーラ「釣り人」:点描ではないが、絵になるワンカットを描かせたらスーラは凄いね。
ポール・ゴーガン「テ・レリオア」:民族的なものを単に物珍しく描くだけではなく、象徴としている。もちろんそれが、文明による勘違いだとしてもだ。
ポール・ナッシュ「サミュエル・コートールドの蔵書票」:デザインカッコいい。
あらためて、ドガ、スーラ、ゴーガンの素晴らしさが分かった気がする。しかし、そんな中でもやはり心に迫るのは、マネの「フォリー=ベルジェールのバー」だ。これはきっと、私がバー好きだからだろう。

今日の上野はこのくらいにしておいて、京橋に移動。
■TODA BUILDING「TOKYO 2021 un/real engine-慰霊のエンジニアリング」。「2021年以降を考えるために」というサブタイトルがついた建築展(終了済)と美術展が近く建て替え工事が始まるTODA BUILDINGで開催されていた。
入場は無料だが、事前にインターネット申し込みが必要だという今風の展覧会。時間がありそうだったので、申し込んでおいたのだ。展示は大きく二つに分かれおり、一つ目は「祝祭の国」と名前がついている。1964年の東京オリンピック、1970年の大阪万博を通して、2021年以降を占うような展示らしい。
藤元明「2026」。祝祭の後には廃墟の予感しかないのか。

檜皮一彦「hiwadrome:type THE END spec5 CODE:invisible circus」。何がタイトルなのやらさっぱり分からない。

弓指寛治「黒い盆踊り」。祝祭のような、禍々しいような。

キュンチョメ「日陰の太陽」「行方不明の太陽」。やはり万博モチーフが目立つ。

「万博ベンチ」は本当に1970年に制作されたものらしい。

やっぱり現代美術って分かるような、分からないような…。
続いて「災害の国」へ。思えば私が生まれてからも、日本は災害の連続であった。展示作品は見ると気になるものが多いのだが、写真撮影するという感じでもない。特に渡邉英徳「「忘れない」震災犠牲者の行動記録」という作品は、東日本大震災で犠牲になった人の死の直前の行動を可視化したデジタルアーカイブで、必要なことなのかもしれないが、平静には見ることができない。
SIDE CORE「意味のない徹夜」。

地下鉄駅まで歩こうとすると、アーティゾンミュージアム(もとはブリジストン美術館)の建物が見えてきた。

こんなスケールで建て替えするんだったのか。ちょっと驚いた。