
八幡町をゆく(29) 農民運動家、行政長蔵(1)
彼(行政長蔵:ゆきまさちょうぞう)は第一次世界大戦で、にわかに景気の造船関係の仕事にありつき、そして神戸で唯一の労働組合であった友愛会に参加しました。
そして、賀川豊彦(かがわとよひこ)の指導で労働問題を熱心に学ぴ、大正10年(1921)のストライキには、最高幹部の一人として陣頭に立ちました。
第一次世界大戦の反動としての恐慌は、労働者の大量解雇、賃金の引き下げとなって、労働者の生活を圧迫しました。
そして、その不滴は 1921年まず大阪で爆発し、次いで神戸の川崎・三菱の三万の労働者を中心に、神戸製鋼、台湾製糖、ダンロップゴムをはじめ多くの中小工場を包み込んで、全神戸をゆるがし、戦前日本最大の45日間にわたる大争議へと広がっていきました。
そして、7月10日、東京のメーデーでさえ2、000も集まらない当時にあって、35、000人の大デモストレーションを繰り広げました。
結局、争議(ストライキ)は、姫路からの軍隊などの派遣により鎮圧され、そして川崎・三菱両造船所だけでも1000名の解雇者を出し、ストライキは敗北に終わりましたが、当時闘いに立ち上がりつつあった農民運動に大きな影響を与えました。
行政長蔵は投獄を免れたものの、解雇されました。長蔵は加古川に帰るや刃物研ぎの道具を一式を買い、自転車で生活費を橡ぎながら村々を回り、農民と語りあい、社会主義思想を説いて小作人の目を開かせていきました。
そんな行政を賀川豊彦は、日本農民組合が結成されるや、その仕事に専念させました 賀川豊彦の小説『壁の声を聞く時』の中に次のような一節があります。
この雪野のモデルは行政長蔵です。
・・・雪野鷹蔵、彼は、菜葉服の上にぶてぶての外套を着、足にゴム靴をはき、村から村へと小作人組合の組織に歩いきました。やれ、小作料の逓減運動だと言っては引っ張り出され、組合の発会式だといっては出て行きました。
いくら刑事を尾行させても、いくら讐察署長を以て農民をおどかしても、あまり効果がなく、 組合員は毎日増えていきました。
*写真:川崎・三菱の労働争議(1921年)



















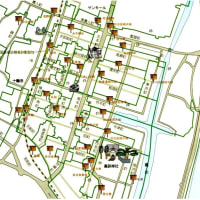






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます