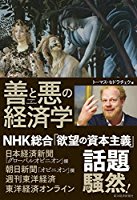
トーマス・セドラチェクのこの本「善と悪の経済学 ギルガメッシュ叙事詩からウォール街占拠の経済的意味の探求Economics of Good and Evil: The Quest for Economic Meaning from Gilgamesh to Wall Street 」 は、壮大な人類の経済および経済史の歴史の物語である。
セドラチェクの問題意識は、ギルガメッシュから説き起こして、
どんな経済学でも、結局のところは善悪を扱っている。現代の主流派経済学は、この善悪の判断のみならず、一切の価値判断や主観的意見あるいは信仰を何としてでも避けようと躍起になっている。経済学、さらに科学全般は、善悪と袂を分かち、実証主義や価値中立性を目指すことを望んでいるが、科学を含め、人間のあらゆる活動には倫理がつきまとい、最早、善悪に無知でいることはできない。経済学の根本的な部分は、苦悩、非効率、無知、社会的不平等などは悪とされ、取り除くべきだとされ、どんな科学においても、逃れたいと言う願い、この規範的判断に基づいている。歴史の大半を通じて、倫理と経済学は、緊密に関連付けられ、切り離して考えることはまずなかった。「善は報われるのか」と言う基本的な問いを提示して、経済学の「善悪軸」を探求して、現代の主流派経済学を考察する。と言うことである。
本書を通じて、セドラチェクは、経済学の精神あるいは魂を探してきたが、今や、道具が生命を獲得し道具に支配される、人間に仕えるべきものが生命を持ち、独自の論理を持って立ち向かってくる。それを恐れて、経済学者は、経済学から意味や倫理や規範性を抜き取り、経済学から、魂を抜き取ってしまった。不当にも意味を剥ぎ取られてしまった今日の支配的な「成長資本主義」から脱皮しなければならない。と説く。
今直面しているのは、資本主義の危機ではなく、成長資本主義(数千年の西洋文明の発展を見れば、こう名付けるしかない)の危機である。
つねに成長するのが当然だとする見方に慣れていて、成長が万事を解決してくれると信じ切ってきたが、最早、経済は成長しなくなった。
我々は、長期にわたるゼロ成長に備えるべきで、景気刺激策に頼らない自立的な回復が復活したら、できるだけ早く、次の危機が襲ってくる前に、既存の公的債務を減らすことが至上命令となる。
セドラチェクは、経済成長については認めているが、最早、経済成長が望めなくなったので、成長を目指すことを前提にした経済成長経済学を排すべしと言っているのである。
旧約聖書の時代より欲望の歴史は始まっており、人間はどれほど持っていてもなお多くを求めて消費に囚われ、快楽主義的プログラム(供給増)を選び、禁欲主義的プログラム(需要減)を退け続けてきた。
ギルガメッシュ以来、これまで判明した世界のどの文明の歴史においても、現代以上に豊かだった時代はない。したがって、もう物質的な快適さはよしとし、物質的繁栄が齎す幸福を躍起になって求めるのは止めなければならない。
なぜなら、成長が止まった経済で、物質的目標を追求する経済政策は、必ず借金へと突き進む。常に借金を背負っていたら、経済危機によって被る痛手は一段と深刻になる。次の危機が来る前に借金を返さず、過去の教訓から学ばずに自己満足に浸っていると、無防備で次の危機を迎えることになり壊滅的な打撃を受ける。
現代の経済学は、新しい考えの一部を捨てて、古い考え、すなわち、恒久的な不満足を断ち切り、人為的に作り出された社会的経済的な不足を排除し、既に持っているものへの充足と感謝を取り戻すべきである。と言うのである。
もう一つ、現代経済学に対するセドラチェクの重要な指摘は、
経済学は、経済学者が認めている以上に、規範的な要素を多く含んでいて、他の学問、例えば哲学、神学、人類学、歴史学、文化史、心理学、社会学等々と深い結びつきがあり、多くの接点があることで、経済学と言う大きな器には、価値中立的で倫理的判断を避け、実証的で記述志向であり、数学的モデルに依拠する還元主義的・分析的アプローチと言った主流派経済学よりも、もっともっと多くのものが詰まっている。と言う見解である。
経済学は数学的理解よりももっともっと幅の広い魅力的な物語だと、経済と経済学の魂を求めて、スミスの見えざる手の導きやケインズのアニマルスピリットなど、興味深いトピックスを交え、善と悪を検証しながら、数千年の世界経済史を展開するスケールの大きさは流石で面白い。
セドラチェクの展開する議論については、ほぼ、現在の欧米日の先進国の経済の現状を説いているので、殆ど異存はない。
しかし、経済成長に関する見解には、これまで、このブログでも書き続けてきたが、本当に、経済成長が止まったのか、あるいは、別な経済成長の形があるのではないかとか、多少、疑問を感じてはいるが、これについては稿を改めたい。
英文ウィキペディアによると、この本は、中欧最古の母校カレル大学Charles University in Pragueに、学位論文として提出したのだが、科学的価値に疑問として拒否されたものの改訂版だと言うから面白い。
セドラチェクは、数学傾斜傾向の数理経済学を徹底的に批判しているので、カレル大学の主流もそうであったのであろう、哲学的宗教的で叙述的なスケールの大きなセドラチェク経済学が、科学的一点張りでないところに価値があるにも拘わらず、理解されなかったのかも知れないと思う。
セドラチェクは、学生時代にハヴェル大統領の経済アドバイザーとなった元東欧の共産主義国家チェコの経済学者ではあるが、幼少年期には、5年フィンランド、4年デンマークに在住して、インターナショナルスクールで学んでおり、ベルリンの壁崩壊後に、青少年期を送っており、スカラシップを得てイェール大学で学んでいるので、東西両陣営の経済を知っており、その意味でも、貴重な経済学書である。
私は、ベルリンの壁崩壊直後とその少し後、2回プラハを訪れているが、世界一美しい都だと思っている。
モルダウ河畔の小高い丘に建つプラハ城を仰ぐ絵のように美しい風景を思い出しながら、この本を読ませてもらった。
セドラチェクの問題意識は、ギルガメッシュから説き起こして、
どんな経済学でも、結局のところは善悪を扱っている。現代の主流派経済学は、この善悪の判断のみならず、一切の価値判断や主観的意見あるいは信仰を何としてでも避けようと躍起になっている。経済学、さらに科学全般は、善悪と袂を分かち、実証主義や価値中立性を目指すことを望んでいるが、科学を含め、人間のあらゆる活動には倫理がつきまとい、最早、善悪に無知でいることはできない。経済学の根本的な部分は、苦悩、非効率、無知、社会的不平等などは悪とされ、取り除くべきだとされ、どんな科学においても、逃れたいと言う願い、この規範的判断に基づいている。歴史の大半を通じて、倫理と経済学は、緊密に関連付けられ、切り離して考えることはまずなかった。「善は報われるのか」と言う基本的な問いを提示して、経済学の「善悪軸」を探求して、現代の主流派経済学を考察する。と言うことである。
本書を通じて、セドラチェクは、経済学の精神あるいは魂を探してきたが、今や、道具が生命を獲得し道具に支配される、人間に仕えるべきものが生命を持ち、独自の論理を持って立ち向かってくる。それを恐れて、経済学者は、経済学から意味や倫理や規範性を抜き取り、経済学から、魂を抜き取ってしまった。不当にも意味を剥ぎ取られてしまった今日の支配的な「成長資本主義」から脱皮しなければならない。と説く。
今直面しているのは、資本主義の危機ではなく、成長資本主義(数千年の西洋文明の発展を見れば、こう名付けるしかない)の危機である。
つねに成長するのが当然だとする見方に慣れていて、成長が万事を解決してくれると信じ切ってきたが、最早、経済は成長しなくなった。
我々は、長期にわたるゼロ成長に備えるべきで、景気刺激策に頼らない自立的な回復が復活したら、できるだけ早く、次の危機が襲ってくる前に、既存の公的債務を減らすことが至上命令となる。
セドラチェクは、経済成長については認めているが、最早、経済成長が望めなくなったので、成長を目指すことを前提にした経済成長経済学を排すべしと言っているのである。
旧約聖書の時代より欲望の歴史は始まっており、人間はどれほど持っていてもなお多くを求めて消費に囚われ、快楽主義的プログラム(供給増)を選び、禁欲主義的プログラム(需要減)を退け続けてきた。
ギルガメッシュ以来、これまで判明した世界のどの文明の歴史においても、現代以上に豊かだった時代はない。したがって、もう物質的な快適さはよしとし、物質的繁栄が齎す幸福を躍起になって求めるのは止めなければならない。
なぜなら、成長が止まった経済で、物質的目標を追求する経済政策は、必ず借金へと突き進む。常に借金を背負っていたら、経済危機によって被る痛手は一段と深刻になる。次の危機が来る前に借金を返さず、過去の教訓から学ばずに自己満足に浸っていると、無防備で次の危機を迎えることになり壊滅的な打撃を受ける。
現代の経済学は、新しい考えの一部を捨てて、古い考え、すなわち、恒久的な不満足を断ち切り、人為的に作り出された社会的経済的な不足を排除し、既に持っているものへの充足と感謝を取り戻すべきである。と言うのである。
もう一つ、現代経済学に対するセドラチェクの重要な指摘は、
経済学は、経済学者が認めている以上に、規範的な要素を多く含んでいて、他の学問、例えば哲学、神学、人類学、歴史学、文化史、心理学、社会学等々と深い結びつきがあり、多くの接点があることで、経済学と言う大きな器には、価値中立的で倫理的判断を避け、実証的で記述志向であり、数学的モデルに依拠する還元主義的・分析的アプローチと言った主流派経済学よりも、もっともっと多くのものが詰まっている。と言う見解である。
経済学は数学的理解よりももっともっと幅の広い魅力的な物語だと、経済と経済学の魂を求めて、スミスの見えざる手の導きやケインズのアニマルスピリットなど、興味深いトピックスを交え、善と悪を検証しながら、数千年の世界経済史を展開するスケールの大きさは流石で面白い。
セドラチェクの展開する議論については、ほぼ、現在の欧米日の先進国の経済の現状を説いているので、殆ど異存はない。
しかし、経済成長に関する見解には、これまで、このブログでも書き続けてきたが、本当に、経済成長が止まったのか、あるいは、別な経済成長の形があるのではないかとか、多少、疑問を感じてはいるが、これについては稿を改めたい。
英文ウィキペディアによると、この本は、中欧最古の母校カレル大学Charles University in Pragueに、学位論文として提出したのだが、科学的価値に疑問として拒否されたものの改訂版だと言うから面白い。
セドラチェクは、数学傾斜傾向の数理経済学を徹底的に批判しているので、カレル大学の主流もそうであったのであろう、哲学的宗教的で叙述的なスケールの大きなセドラチェク経済学が、科学的一点張りでないところに価値があるにも拘わらず、理解されなかったのかも知れないと思う。
セドラチェクは、学生時代にハヴェル大統領の経済アドバイザーとなった元東欧の共産主義国家チェコの経済学者ではあるが、幼少年期には、5年フィンランド、4年デンマークに在住して、インターナショナルスクールで学んでおり、ベルリンの壁崩壊後に、青少年期を送っており、スカラシップを得てイェール大学で学んでいるので、東西両陣営の経済を知っており、その意味でも、貴重な経済学書である。
私は、ベルリンの壁崩壊直後とその少し後、2回プラハを訪れているが、世界一美しい都だと思っている。
モルダウ河畔の小高い丘に建つプラハ城を仰ぐ絵のように美しい風景を思い出しながら、この本を読ませてもらった。
























