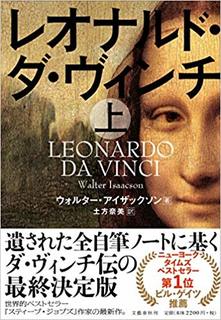
ダ・ヴィンチは、自分は正式な教育を受けていないので、「教養のない男」と言われるが、自らの経験から学ぶしかなく、「経験の信徒」であると言い切り、モノを見ず、古い文献からの借り物の知識しか語れない人々を非難していた。
生涯を通じて、与えられた知識よりも、経験を重んじる姿勢を貫き、これは、古代ギリシャや古代ローマの学問を再発見・再評価した典型的なルネサンス人との明らかな違いであったという。
世界最古の大学ボローニャ大学の創立が、1088年であるから、フィレンツェやミラノにも大学はあったはずだが、ダ・ヴィンチのように、若くして画家の工房に入った画家の卵にとっては、徒弟奉公で、オン・ザ・ジョブトレイニングで知識や技術を学ぶのが普通であった筈である。
しかし、ミラノの新しい学びの環境で、学者の共通言語であるラテン語の独習に乗り出してからは、過去から受け継がれてきた貴重な知識を見下す態度は次第に退化し、それに、グーテンベルクの印刷術が普及して膨大な書物が出版されていたので、ダ・ヴィンチの蔵書は、40冊、更に70冊と一気に増えて、軍事設備、農業、音楽、外科、アリストテレスの自然学やギリシャの古典、イソップ寓話集等々多岐に亘り、知人友人から必要な専門書を求めるなどして、独学独習に励んで、
自らの経験と並んで、確立した知識も尊重し、それ以上に重要なのは、科学の進歩は両者の対話から生まれることを知ったことで、それが知識は実験と理論の対話から生まれることがあると言う気付きに繋がった。
書物から知識を吸収し始めてから、経験的エビデンスだけでなく、理論的枠組みも研究の拠り所とする重要性と、両者が相互補完的なアプローチであることに気づいて、理論と実験の関係をきちんと評価すべく並々ならぬ努力をしたと言う。
経験と理論の融合は、遠近法の研究でも実感したようで、物が遠ざかるほど小さく見えることは観察で確認したが、大きさと距離の関係を公式化する時には幾何学を使ったのである。
しかし、いずれにしろ、ダ・ヴィンチの実験や実地研究は、半端ではなく、人間や動物を正確に描くためには、その内部を理解する必要があると、解剖学に熱中して、その描写は精緻を極めており、人物の動きはすべてその心の意思を表現しなければならないと、心と体はどう結びつくのか、徹底的に検証して、この哲学を、「最後の晩餐」などに、芸術史上最も見事に体現したと言うのである。
「芸術における最高位は絵画である」と言うダ・ヴィンチの見解が興味深い。
ミラノのスファルツァ城で行われた、幾何学、彫刻、音楽、絵画、詩歌のどれに相対的優位があるか、討論の夕べ「パラゴーネ」で、科学的および審美的観点から、芸術の最高位であると絵画を徹底的に擁護したと言う。
絵画を、光学と言う科学的探究や遠近法と言う数学的概念を結び付けて、芸術と科学が如何に密接に結びついているかを訴え、真のクリエイティビティには、観察と想像を結び付け、現実と空想の境界をぼかして行く能力が必要であり、その両方を描くのが偉大な絵画であると熱弁を振るったのである。
画家、科学者、技術者、軍師、舞台演出家、哲学者、どれをとっても、ダ・ヴィンチのマルチ・タレントぶりを示しているが、芸術と科学・技術を融合して素晴らしい絵画を描いた画家は、ダ・ヴィンチが最右翼であろう。
三次元の世界を平面で表現するためには、遠近法や光学の理解が必須であり、絵画は、数学に基づく科学であり、手を動かす作業であると同時に知的な営みである。絵画は、芸術であるばかりではなく、科学である。と言うのである。
さらに、絵画は、知性だけではなく、想像力も必要であり、空想と現実がお互いに助け合って、融合すると、自然の創造物のみならず、自然が生み出せなかった総てを生み出す創造性が湧き起こる。と言うのだが、
ダ・ヴィンチが、このように主張するのも、「モナ・リザ」を観れば分かると言うことであろう。
先に、著者が、ダ・ヴィンチが、イノベーターであると捉えていることに言及したが、これらのダ・ヴィンチの生き様や哲学は、まさに、メディチ・エフェクトの発露であって、creativityを生み出す権化のようなものであり、それが、期せずして、イタリア・ルネサンスと言う土壌で、華開いたというのは、人類にとって、幸せだったと言うべきであろう。
しかし、絵画は、芸術であり、科学であると言いながら、やはり、ダ・ヴィンチを凌駕して上を行く画家が生まれてこないと言うことは、科学や技術と言うよりも、芸術が勝っていると言うことかも知れない。
生涯を通じて、与えられた知識よりも、経験を重んじる姿勢を貫き、これは、古代ギリシャや古代ローマの学問を再発見・再評価した典型的なルネサンス人との明らかな違いであったという。
世界最古の大学ボローニャ大学の創立が、1088年であるから、フィレンツェやミラノにも大学はあったはずだが、ダ・ヴィンチのように、若くして画家の工房に入った画家の卵にとっては、徒弟奉公で、オン・ザ・ジョブトレイニングで知識や技術を学ぶのが普通であった筈である。
しかし、ミラノの新しい学びの環境で、学者の共通言語であるラテン語の独習に乗り出してからは、過去から受け継がれてきた貴重な知識を見下す態度は次第に退化し、それに、グーテンベルクの印刷術が普及して膨大な書物が出版されていたので、ダ・ヴィンチの蔵書は、40冊、更に70冊と一気に増えて、軍事設備、農業、音楽、外科、アリストテレスの自然学やギリシャの古典、イソップ寓話集等々多岐に亘り、知人友人から必要な専門書を求めるなどして、独学独習に励んで、
自らの経験と並んで、確立した知識も尊重し、それ以上に重要なのは、科学の進歩は両者の対話から生まれることを知ったことで、それが知識は実験と理論の対話から生まれることがあると言う気付きに繋がった。
書物から知識を吸収し始めてから、経験的エビデンスだけでなく、理論的枠組みも研究の拠り所とする重要性と、両者が相互補完的なアプローチであることに気づいて、理論と実験の関係をきちんと評価すべく並々ならぬ努力をしたと言う。
経験と理論の融合は、遠近法の研究でも実感したようで、物が遠ざかるほど小さく見えることは観察で確認したが、大きさと距離の関係を公式化する時には幾何学を使ったのである。
しかし、いずれにしろ、ダ・ヴィンチの実験や実地研究は、半端ではなく、人間や動物を正確に描くためには、その内部を理解する必要があると、解剖学に熱中して、その描写は精緻を極めており、人物の動きはすべてその心の意思を表現しなければならないと、心と体はどう結びつくのか、徹底的に検証して、この哲学を、「最後の晩餐」などに、芸術史上最も見事に体現したと言うのである。
「芸術における最高位は絵画である」と言うダ・ヴィンチの見解が興味深い。
ミラノのスファルツァ城で行われた、幾何学、彫刻、音楽、絵画、詩歌のどれに相対的優位があるか、討論の夕べ「パラゴーネ」で、科学的および審美的観点から、芸術の最高位であると絵画を徹底的に擁護したと言う。
絵画を、光学と言う科学的探究や遠近法と言う数学的概念を結び付けて、芸術と科学が如何に密接に結びついているかを訴え、真のクリエイティビティには、観察と想像を結び付け、現実と空想の境界をぼかして行く能力が必要であり、その両方を描くのが偉大な絵画であると熱弁を振るったのである。
画家、科学者、技術者、軍師、舞台演出家、哲学者、どれをとっても、ダ・ヴィンチのマルチ・タレントぶりを示しているが、芸術と科学・技術を融合して素晴らしい絵画を描いた画家は、ダ・ヴィンチが最右翼であろう。
三次元の世界を平面で表現するためには、遠近法や光学の理解が必須であり、絵画は、数学に基づく科学であり、手を動かす作業であると同時に知的な営みである。絵画は、芸術であるばかりではなく、科学である。と言うのである。
さらに、絵画は、知性だけではなく、想像力も必要であり、空想と現実がお互いに助け合って、融合すると、自然の創造物のみならず、自然が生み出せなかった総てを生み出す創造性が湧き起こる。と言うのだが、
ダ・ヴィンチが、このように主張するのも、「モナ・リザ」を観れば分かると言うことであろう。
先に、著者が、ダ・ヴィンチが、イノベーターであると捉えていることに言及したが、これらのダ・ヴィンチの生き様や哲学は、まさに、メディチ・エフェクトの発露であって、creativityを生み出す権化のようなものであり、それが、期せずして、イタリア・ルネサンスと言う土壌で、華開いたというのは、人類にとって、幸せだったと言うべきであろう。
しかし、絵画は、芸術であり、科学であると言いながら、やはり、ダ・ヴィンチを凌駕して上を行く画家が生まれてこないと言うことは、科学や技術と言うよりも、芸術が勝っていると言うことかも知れない。























