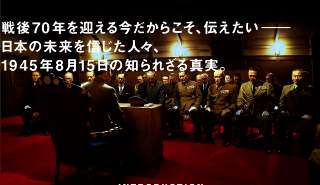
先日、映画「日本のいちばん長い日(1967版)」をレビューしたが、現在上映中の同名の新しい映画を見に出かけた。
半藤一利の小説をベースにしている映画であるので、ストーリーは殆ど同じなのだが、半世紀を経ているので、ニュアンスなり映画化への姿勢などに、かなり差が出いて興味深かった。
まず、天皇陛下の登場だが、1967年版は、天皇の姿をはっきりと描写するのは恐れ多いと言う当時の風潮を慮って、天皇(8代松本幸四郎)の姿は殆ど隠れて見えなかったのだが、今回の映画では、天皇(本木雅弘)が、普通の登場人物として現われて、人間天皇として描かれていることで、主要登場人物である鈴木貫太郎首相(山崎努)や阿南惟幾(陸軍大臣:役所広司)との心の交流までも鮮やかに表現している。
監督・脚本の原田眞人が、インタビューで、先の1967年版で岡本喜八監督が、”当時(作品を作るにあたって)やりたいけどやれなかったことがあるだろうと、そこのところを受け継いで作っていきたい”、と言っているのだが、その表れであろう。
それでも、”昭和天皇は正面に出てくることが出来ました。ですが、その昭和天皇を囲んでいる状況というのは、まだ日本の映画では出ていないんです。そういうことをこれからどんどん語る、いろんな形で議論できる、そういう社会になっていったらいいな”と言っており、終戦、そして、それに纏わる天皇の描き方には、日本歴史上に微妙な側面があるのであろう。
この2作品には、色々と違いがあって興味深いのだが、原田作品では、人間天皇としての鮮やかさに加えて、鈴木首相や阿南陸相の家族たちの人間模様などもかなり丁寧に描かれていて、例えば、阿南陸相の場合に、空襲で大打撃を受けた帝国ホテルで式を挙げた娘の結婚式が無事であったかどうかと天皇が聞かれるシーンとか、戦死した息子の死の様子を知りたがっていた陸相に、部下が訪れて来て聞いた様子を伝えたくて電話をかけたり必死になって戦下を皇居に走る妻(神野三鈴)の様子など、克明に描写している。
この息子の戦死は、この映画では、陸相が絶えず写真を携えていて、切腹の場にも登場するので非常に大切なサブテーマとなっていて、部下から聞いた様子を一刻も早く陸相に伝えて喜ばせたいと必死の妻の電話の伝言にも、永久の別れを告げて家を出たので電話も出来ず、一度だけ電話に手をかけるが中断されてしまい、妻は、死の床に眠る仏に向かって語りかける。
もう一つ気付いたのは、迫水久常(内閣書記官長:堤真一)の扱い方で、本作品では、重要人物の一人として登場しており、先の重厚な感じの加藤武と違って、堤は、中々人間味のある補佐役を丁寧に演じていた。
さらに言えば、元々重要な役割を果たした二人の大臣の扱い方にも差があり、原田作品はさらりと流している感じだが、
ポッダム宣言受諾に関しては、東郷茂徳(外務大臣:宮口精二 今回は、近童弐吉)の案に従ったのだが、東郷の役作りについては、宮口の存在感が抜群であり、もう一人阿南と双璧の米内光政(海軍大臣:山村聰、今回は、中村育二)についても、山村の風格あってこそ、三船敏郎の阿南に対峙出来たのであると思ったのだが、どうであろうか。
森赳中将(第一師団長)についても、高橋耕次郎も上手いのだが、島田正吾の役者魂の凄まじさとその風格は、余人をもって代えがたい迫力があった。
本作品には、東条英機(陸軍大将:中嶋しゅう)が登場し、硬派ぶりを見せるのだが、天皇陛下に、サザエ問答を仕掛けて、知的水準の歴然たる差を見せつけられるシーンがあって、非常に面白い。
ところで、私自身の正直な感想なのだが、そのようなドラマを交えずに、史実を直球勝負でストレートに表現して、ポッダム宣言以降、広島長崎への原爆投下、和平交渉を依頼したソ連の日ソ中立条約の破棄によって窮地に追い詰められた日本の断末魔を描いている点では、岡本喜八作品の方が、剛直で骨太であり、分かり易く表現しているし、インパクトがあるように思う。
サブストーリーの挿入も、岡本作品では、厚木三〇二航空隊の司令小薗海軍大佐の徹底抗戦指示や、東京警備軍横浜警備隊長佐々木大尉の一個大隊を率いての首相官邸などの襲撃、児玉基地の中野少将の房総沖の敵機動部隊への特攻攻撃など、当時のチグハグな戦局を描いて悲壮性を出していて良い。
劇作りの手法も違っていて、岡本作品では、横浜警備隊長佐々木大尉の首相官邸の襲撃も、順を追って映像化されているので良く分かるが、原田作品では、佐々木大尉(松山ケンイチ)率いる一団が首相官邸を襲う場面が急に出て来て、迫水内閣書記官長を追い出したシーンのようにしか思えない。
岡本作品は、話の筋を追うのに非常に丁寧だが、原田作品は、断片的なシーンを、どんどん積み重ねて重層的にストーリーを展開しているので、カラフルで面白いけれど、歴史的事実をかなり知っていて、岡本作品を見て筋も分かっている私でも、ストーリーを追うのに多少苦痛を感じたので、若い人たちは、どう見たのであろうか興味がある。
クーデターの首謀者である青年将校の畑中健二(陸軍少佐:松坂桃李)の描き方で面白いのは、NHKを占拠して、反乱軍の国土決戦決意を放送しようとする試みで、岡本作品では、畑中少佐( 黒沢年男)の命令を館野守男放送員:加山雄三)がピストルを突きつけられてもビクともせずに抵抗して失敗するのだが、原田作品では、保木放送局員:戸田恵梨香)が、電源を切って遮断する中を、マイクの前に立って絶叫調で檄を飛ばす畑中少佐の哀れさが出色で感動的である。
畑中少佐の主義主張や行動の表現がやや曖昧であるきらいはあったが、決然として節を貫く凛とした姿勢など、松坂は、実に上手く演じていて、流石であった。
「日本のいちばんながい日」と言う最も深刻でエポックメイキングなストーリーをテーマにしながら、ある意味では、カラッとしたドキュメンタリー・タッチに比重を置いた描き方をするか、或いは、人間的な苦悩や喜びを交えた血の通ったヒューマン・タッチの劇作りをするか、微妙なところだが、2作品を鑑賞して、より、歴史の真実に近づいたような気がして良かったと思っている。
本作品は、原田監督の考え抜いた上での緻密さと細心の注意を払って作り上げられた映画で、ドラマチックでヒューマンなストーリー展開が、大きなテーマを包み込んで爽やかな感じがする。
人間天皇と鈴木貫太郎、そして、阿南陸相との阿吽の信頼関係と心の交流が軸となって、終戦処理に向かう怒涛のように大きく逆巻く歴史の転換点を描き切って感動的である。
主役である
岡本作品での、阿南の三船敏郎、鈴木総理の笠智衆も忘れがたいが、
本作品の、阿南惟(陸軍大臣)の役所広司、昭和天皇の本木雅弘、鈴木貫太郎(首相)の山崎努
恐らく、最高の役者の登場であって、これ以上は望み得ないであろう。
半藤一利の小説をベースにしている映画であるので、ストーリーは殆ど同じなのだが、半世紀を経ているので、ニュアンスなり映画化への姿勢などに、かなり差が出いて興味深かった。
まず、天皇陛下の登場だが、1967年版は、天皇の姿をはっきりと描写するのは恐れ多いと言う当時の風潮を慮って、天皇(8代松本幸四郎)の姿は殆ど隠れて見えなかったのだが、今回の映画では、天皇(本木雅弘)が、普通の登場人物として現われて、人間天皇として描かれていることで、主要登場人物である鈴木貫太郎首相(山崎努)や阿南惟幾(陸軍大臣:役所広司)との心の交流までも鮮やかに表現している。
監督・脚本の原田眞人が、インタビューで、先の1967年版で岡本喜八監督が、”当時(作品を作るにあたって)やりたいけどやれなかったことがあるだろうと、そこのところを受け継いで作っていきたい”、と言っているのだが、その表れであろう。
それでも、”昭和天皇は正面に出てくることが出来ました。ですが、その昭和天皇を囲んでいる状況というのは、まだ日本の映画では出ていないんです。そういうことをこれからどんどん語る、いろんな形で議論できる、そういう社会になっていったらいいな”と言っており、終戦、そして、それに纏わる天皇の描き方には、日本歴史上に微妙な側面があるのであろう。
この2作品には、色々と違いがあって興味深いのだが、原田作品では、人間天皇としての鮮やかさに加えて、鈴木首相や阿南陸相の家族たちの人間模様などもかなり丁寧に描かれていて、例えば、阿南陸相の場合に、空襲で大打撃を受けた帝国ホテルで式を挙げた娘の結婚式が無事であったかどうかと天皇が聞かれるシーンとか、戦死した息子の死の様子を知りたがっていた陸相に、部下が訪れて来て聞いた様子を伝えたくて電話をかけたり必死になって戦下を皇居に走る妻(神野三鈴)の様子など、克明に描写している。
この息子の戦死は、この映画では、陸相が絶えず写真を携えていて、切腹の場にも登場するので非常に大切なサブテーマとなっていて、部下から聞いた様子を一刻も早く陸相に伝えて喜ばせたいと必死の妻の電話の伝言にも、永久の別れを告げて家を出たので電話も出来ず、一度だけ電話に手をかけるが中断されてしまい、妻は、死の床に眠る仏に向かって語りかける。
もう一つ気付いたのは、迫水久常(内閣書記官長:堤真一)の扱い方で、本作品では、重要人物の一人として登場しており、先の重厚な感じの加藤武と違って、堤は、中々人間味のある補佐役を丁寧に演じていた。
さらに言えば、元々重要な役割を果たした二人の大臣の扱い方にも差があり、原田作品はさらりと流している感じだが、
ポッダム宣言受諾に関しては、東郷茂徳(外務大臣:宮口精二 今回は、近童弐吉)の案に従ったのだが、東郷の役作りについては、宮口の存在感が抜群であり、もう一人阿南と双璧の米内光政(海軍大臣:山村聰、今回は、中村育二)についても、山村の風格あってこそ、三船敏郎の阿南に対峙出来たのであると思ったのだが、どうであろうか。
森赳中将(第一師団長)についても、高橋耕次郎も上手いのだが、島田正吾の役者魂の凄まじさとその風格は、余人をもって代えがたい迫力があった。
本作品には、東条英機(陸軍大将:中嶋しゅう)が登場し、硬派ぶりを見せるのだが、天皇陛下に、サザエ問答を仕掛けて、知的水準の歴然たる差を見せつけられるシーンがあって、非常に面白い。
ところで、私自身の正直な感想なのだが、そのようなドラマを交えずに、史実を直球勝負でストレートに表現して、ポッダム宣言以降、広島長崎への原爆投下、和平交渉を依頼したソ連の日ソ中立条約の破棄によって窮地に追い詰められた日本の断末魔を描いている点では、岡本喜八作品の方が、剛直で骨太であり、分かり易く表現しているし、インパクトがあるように思う。
サブストーリーの挿入も、岡本作品では、厚木三〇二航空隊の司令小薗海軍大佐の徹底抗戦指示や、東京警備軍横浜警備隊長佐々木大尉の一個大隊を率いての首相官邸などの襲撃、児玉基地の中野少将の房総沖の敵機動部隊への特攻攻撃など、当時のチグハグな戦局を描いて悲壮性を出していて良い。
劇作りの手法も違っていて、岡本作品では、横浜警備隊長佐々木大尉の首相官邸の襲撃も、順を追って映像化されているので良く分かるが、原田作品では、佐々木大尉(松山ケンイチ)率いる一団が首相官邸を襲う場面が急に出て来て、迫水内閣書記官長を追い出したシーンのようにしか思えない。
岡本作品は、話の筋を追うのに非常に丁寧だが、原田作品は、断片的なシーンを、どんどん積み重ねて重層的にストーリーを展開しているので、カラフルで面白いけれど、歴史的事実をかなり知っていて、岡本作品を見て筋も分かっている私でも、ストーリーを追うのに多少苦痛を感じたので、若い人たちは、どう見たのであろうか興味がある。
クーデターの首謀者である青年将校の畑中健二(陸軍少佐:松坂桃李)の描き方で面白いのは、NHKを占拠して、反乱軍の国土決戦決意を放送しようとする試みで、岡本作品では、畑中少佐( 黒沢年男)の命令を館野守男放送員:加山雄三)がピストルを突きつけられてもビクともせずに抵抗して失敗するのだが、原田作品では、保木放送局員:戸田恵梨香)が、電源を切って遮断する中を、マイクの前に立って絶叫調で檄を飛ばす畑中少佐の哀れさが出色で感動的である。
畑中少佐の主義主張や行動の表現がやや曖昧であるきらいはあったが、決然として節を貫く凛とした姿勢など、松坂は、実に上手く演じていて、流石であった。
「日本のいちばんながい日」と言う最も深刻でエポックメイキングなストーリーをテーマにしながら、ある意味では、カラッとしたドキュメンタリー・タッチに比重を置いた描き方をするか、或いは、人間的な苦悩や喜びを交えた血の通ったヒューマン・タッチの劇作りをするか、微妙なところだが、2作品を鑑賞して、より、歴史の真実に近づいたような気がして良かったと思っている。
本作品は、原田監督の考え抜いた上での緻密さと細心の注意を払って作り上げられた映画で、ドラマチックでヒューマンなストーリー展開が、大きなテーマを包み込んで爽やかな感じがする。
人間天皇と鈴木貫太郎、そして、阿南陸相との阿吽の信頼関係と心の交流が軸となって、終戦処理に向かう怒涛のように大きく逆巻く歴史の転換点を描き切って感動的である。
主役である
岡本作品での、阿南の三船敏郎、鈴木総理の笠智衆も忘れがたいが、
本作品の、阿南惟(陸軍大臣)の役所広司、昭和天皇の本木雅弘、鈴木貫太郎(首相)の山崎努
恐らく、最高の役者の登場であって、これ以上は望み得ないであろう。
























アメリカの属国、つまり家来国家 日本! アメりカの洗脳広告代理店、電通による、テレビ、新聞、週刊誌、ラジオ等の、マスコミを使った偏向報道で、見事な国民洗脳をされ続ける日本人は、自分自身の脳、すなわち思考そのものを点検せよ! さらにネット洗脳システムのツイッターやフェイスブックの利用、まとめサイトには注意が必要である。 我々はハッ、と気付いて、常に注意深く、用心して、警戒し、疑いながら生きれば、騙されることはない。 すべてを疑うべきなのだ!