最近話題の『ウェブ進化論』を読みました。
著者もあとがきで
「こういうロジックで語れば、ネット世界を理解しない人たちにも説明できる」実例として・・・
と言っているように、"WEB2.0"などと言われても何のことやら、という私にもネットの世界ではこういうことが起きているんだ、と何となくわかるような感じにさせてくれる本です。
また、著者は同時に、この本の読み方としてつぎのような注意をしています。
頭の片隅で気にはなっていても、自らネット上で試行錯誤することによって、ウェブ進化の世界観を構築する時間はない。そんな方々が、もしこの本を手にとってくださったとすれば、第一章で触れた「アナロジーで理解しようとしてはいけない」というファインマン教授の言葉を改めて思い出してほしいと思う。
ファインマン教授というのは量子力学の研究でノーベル物理学賞を受賞した理論物理学者です、(話はそれますがファインマン教授の自伝 『ご冗談でしょう、ファインマンさん』は本人の飄々とした人柄と他の天才物理学者たちとの交流を生き生きと描いていておすすめです)、著者は言います。
ファインマンはこの教科書の第五巻「量子力学」の冒頭で、これから自分が量子力学をどう教えていくつもりなのか、学生の立場で言えば量子力学を学ぶときのもっとも大切な姿勢について、こう書いている。
「”量子力学”は物質と光の性質を詳細に記述し、とくに原子的なスケールにおける現象を記述するものである。その大きさが非常に小さいものは、諸君が日常直接に経験するどのようなものにも全く似ていない。それらは波動のようにふるまうこともなく、また、粒子のようにふるまうこともない。雲にも、玉突きの玉にも、バネにつけたおもりにも、また、諸君がこれまで見たことのある何ものにも似ていないのである。」
「この章では、その不可思議な性質の基本的な要素を、そのもっとも奇妙な側面をとらえて、真正面から直接、攻めることにする。古典的な方法で説明する事の不可能な、絶対に不可能な現象をえらんで、それを調べようというのである。そうすることにより、ズバリ量子力学の核心にふれようというわけである。実際、それはミステリー以外の何ものでもない。その考え方がうまくゆく理由を”説明する”ことによりそのミステリーをなくしてしまうことはできない。ただ、その考え方がどのようにうまくゆくかを述べるだけである。」
ファインマンは、これまでニュートン力学を学んできた学生に、量子力学で扱う対象を「がこれまで見たことのある何ものにも似ていないの」と肝に銘じて丸ごと理解しなければならない、ニュートン力学からのアナロジーで理解しようとしてはいけない、と強く釘を刺しているのである。
ニュートン力学の世界から見た量子力学の世界と同様に、リアル世界からネット世界を見れば、それは「不可思議」「奇妙」「ミステリー」以外の何ものでもなく、その異質性や不思議さをそのまま飲み込んで理解するほかない。
ファインマン先生、やはりいいことをおっしゃいます。
本書ではグーグルが構築しようとしているもの(世界観)を中心に「ネットの向こう側」で起きていることが語られています。
日本で発達した楽天やYAHOO JAPANのような「ネットを使ってリアルの世界のビジネスをする」というのでなく「ネットの向こう側」ですべてが完結する世界というのは今までと全然違った価値観に基づいているんだよ、という話です。
見たこともないもの、に対しては清少納言のように「海月(くらげ)のななり」と一言で返してみるという手もあるのですが、僕自身簡単に総括できるほどの知識もないですし、「よくわからないかもしれないが面白そうだからとりあえず聞いてみよう」といういいかげんなスタンスは得意技でもあるので、筆者の言う通りにとりあえずそのまま飲み込んでみました。
とはいえ「リアルの世界」の発想にどっぷり浸かっている身としてはどこまで理解できたかはよくわかりませんけど。
PS
「アナロジーでの理解」で思ったのが、SF映画やアニメでの宇宙空間での戦争シーン。
昔から疑問だったのですが、本来無重力空間であれば、敵対する艦隊同士は正対だけしていればいいのに、ほとんどすべての映画・アニメでは「上」も同じ方向なんですよね。
(艦隊の正面をOX軸、右方向をOY軸、上方向をOZ軸とした場合、A艦隊とB艦隊が正対しているときにはそれぞれのOX方向のベクトルの角度は180度になるわけですが、別にOZ軸が平行(「上」が同じ)だったりする必要ってない、ということです)
やはり地球の重力を前提にした世界観の影響が払拭できない、ということなんでしょうか
(それとも単に作品として観にくくなるからだけかもしれませんが)
 |
ウェブ進化論 本当の大変化はこれから始まる |
 |
ご冗談でしょう、ファインマンさん〈上〉 |















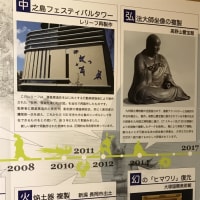
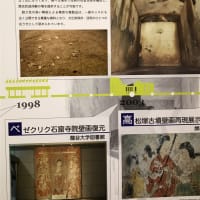








たとえばWikipediaが信頼に足るかというようなところですね(誤りという点ではエンサイクロベディア・ブリタニカと同程度、という「ネイチャー」誌のレポートが物議をかもしているようです)
ここは何となくわかるようなわからないようなところです。
著者は「衆愚」の例えに対して「1億なら衆愚かもしれないが(go2c註:「総表現社会」のリテラシーを持った)1000万ならどうだ」と言ってますが、PSE法の経済産業省の部長のblog炎上などを見ると、逆に僕自身は10億なら(=多ければ多いほど)逆に自浄作用・自律修正が働くようにも思うのですが。
原爆を開発していた時のエピソードで、「ウランを手に持ってみたら暖かかった」というのがあったような気がします。核実験も、かなり間近で観察しているし、「ヒロシマ以前」の科学者の世界ですね。(・・・そう、「本は」おもしろいんです、確かに)
量子力学について書いてあったことも、憶えています。印象的ですよね。たしか、相対性理論についても、そういうように説明してある本があったような気がします。
ずっと続いている科学史の延長上に出てきたものであると同時に、まったく違う質のものでもあるというのは、量子力学自体が「量子のふるまい」と同じのようで、おもしろいです。
科学史の類のものは理論の説明だけ読んでいるとだんだん宗教じみて見えてきます。「彼等は実験をしているのだ」という事を時々は思い出さないと・・・。
「ウェブ進化論」も、ちょっと立ち読みしました。ブログについて書いてあるところだけ読みましたが、共感できる感じでした。・・・買ってみようかな。