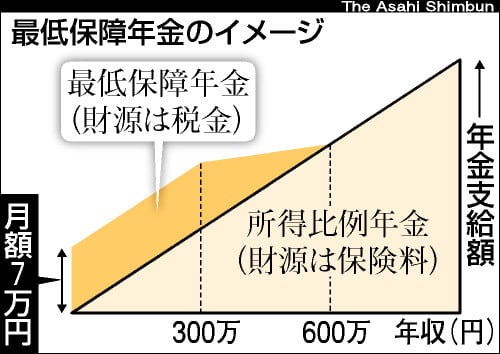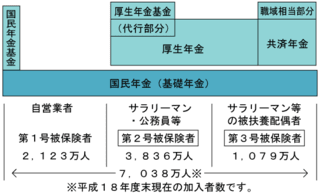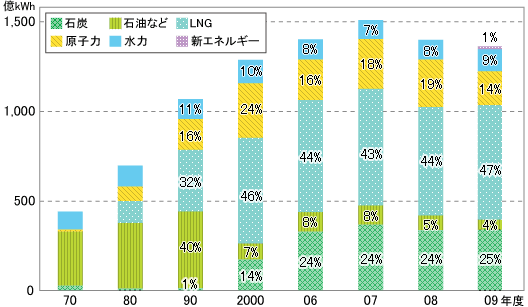文学界、もとい「文學界」4月号のつづき。
80年代から活躍してきた二人がこの30年を振り返ると共にこれからを語ってます。
二人とも還暦を過ぎて、歳を取て見えてきたことについての話なども味わい深いです。
まずは昭和の総括
高橋 昭和の最後は昭和64年=平成元年、つまり昭和天皇が亡くなった年なんだけど、その年には手塚治虫と美空ひばりも亡くなっている。つまり、同じ時期に天皇が三人死んだ。昭和を代表する各ジャンルの天皇が--そもそも昭和は各ジャンルに天皇をもつ天皇制だったこと自体が驚きなんだけれど--同時にいなくなったんですよ。しかもそれが経済の動きと連動していて、天皇が亡くなった翌年に株価も頭打ちになって、バブルがはじけた。その後は20年間ずっと下がりっぱなしなんだよね。
ほんと、平成は下がり局面なのが普通になってきてて、そのへんが団塊ジュニアや就職氷河期世代のマインド形成にも影響していますよね。
そもそも「平成」:Flat=現状維持という目標設定がよくなかったのかもしれない。
もしドラッガーが年号を考えたら・・・?
歳を取ってわかること。
高橋 そもそも「わかる」ということには、「言っていることがわかる」の他に、「フィジカルにわかる」ということがあると思うんですね。鶴見(俊輔)さんの本がなぜ面白いのかというと、一言で言えば「経験」があるからなんです。つまり、その人のフィルターを通して語られる。フィルターを通して出てくる言葉というのは、そうでない言葉と比べて、全然重みが違う。言ってみれば、経験は神様みたいなもので、たとえ言っていることが無茶苦茶だとしてもなぜ説得力があるのかというと、「自分の人生」という戦場の中でコントロールができているからです。
糸井 「頭でわかる」と「身体でわかる」は別のことですよね。・・・実は今日、ぼくが「ほぼ日」に書いたのが、人が死んだときには生き残った人の方が寂しいと言うけれど、実は「死んだ人の方が寂しいんだよ」っていうことなんです。それは10年前にはわからなかったことなんだけど、でも今なら「死んだ人の方が寂しい」とわかる。死んだ人の気持ちをくみつつお墓参りをするっていうのは、だから本当にすごいことなんだなと思うんですよね。
高橋 ・・・今までの小説はほとんどが青春文学だからです。青春文学はほとんど死を考えない。あったとしても自殺で、死は突然、なんですね。明治以来、森鴎外も夏目漱石もみんな早くに死んでしまった。だから小島(信夫)さんも古井(由吉)さんも、谷川俊太郎さんにもそんなところがあるけれど、「自分の死」がテーマになるというのは最近の話なんですね。死は突然くるものではなくて、徐々にボケてきて、身体も動かなくなってきて、言っていることも意味不明になってくる、そういう途中経過をたどるものなんだということが、ようやくわかってきた。
・・・ちょうど若い頃に経済がマックスの昭和を生き、緩やかに衰えていけるというのは恵まれていると思いますね。
糸井 ・・・ぼくは・・・年をとるにつれて・・・「見つける目」を見つけてしまったから、若いときより面白いものがいっぱい見つかるわけ。昔ならこれでおしまい、って言えたのに、その遊び場が好きになってきて、「さよなら」したくなくなるんですよ。
高橋 ・・・今は、みんなそういう「遊び場」を見つけているんじゃないかな。
糸井 日本には定年っていう便利なものがあって、定年と退職を重ねていけるでしょう。人生のおしまい感を味わえるような目盛りを差し出されると、一度考えざるをえなくなりますね。
前半部分はさておき、後半部分については世代間で異論があるところだと思うし、だから団塊の世代はいいんだよなぁ、とか、もっと若い世代からは僕のような「昭和のサラリーマン」は気楽だったよなぁ言われそうな気がします。
しかも、団塊の世代サラリーマンの中で「遊び場」を見つけて定年をポジティブに捕らえている人ってそれほど多くないように思います。
まだまだ右肩上がりの昭和を引きずっていて「忙しい」ことに価値を見出しながら、老後をどうやって忙しくしようかと考えているように思います。
「右肩下がり」について
糸井 景気が悪くなっても生き延びる方法はいくらでもあるんだけど、つまらなくなるのと景気が悪くなるのは、間違いなく関係してきますね。「良薬は口に苦し」、ではないけれど、みんな、つまらないことのほうがもうかる、苦しいことの方がお金になると考える。「面白いことやっていて儲かるわけがないじゃない」、その幻想たるやすごいんじゃないですか。
実は景気がいいときは、地味でつまらないことの方が簡単で需給関係もよく競合もしないので儲かったりするんですよね。
景気が悪くなると、すぐ「リストラ」「経費節減」「選択と集中」とか「コンプライアンス過剰」になる。東日本大震災でサプライ・チェーンにも冗長性が必要だということが明らかになったにもかかわらず、業績は気にしなければならないので、なかなかつらいところです。(東電の賠償問題でよく言われる「徹底したリストラ」と安全性の確保のトレードオフの関係はどう考えてるんだろう。)
業績の四半期毎の開示をやめたら、かなりの節電対策になるんじゃないでしょうか。
糸井重里がコピーライターから「ほぼ日」に転じて
糸井 ・・・早い遅いじゃないんですね。そこしか場所がなかった。思いついたアイディアを友達に話すと面白いといってくれるんだけど、たとえば、面白い企画があります、って言って文學界編集部に電話をかけても載せてくれないでしょう。世の中はそうはできていない(笑)・・・だから、ぼくは海の中に住み続けられなくて上陸せざるを得なかった両生類みたいなものですよ(笑)。希望に満ちて進化した生物なんていないんですから。ただちょっとずるいのは、まだコピーライターをやっていて、そこでした仕事をこちらに向ければいいなと加減ができたことですね。要するに肺呼吸とエラ呼吸が両方できた。
高橋 ・・・ぼくがそれ(インターネットに進んだこと)よりも面白いと思うのは、糸井さんが会社を作ったことなんですね。会社を作るというのはたくさんの社員、つまり子どもを抱えるわけだから面倒でしょう。それまでのコピーライターという仕事は基本的には一人なわけで、誰の面倒を見なくてもいいし、誰からも面倒を見られなくてよかった。それが人を集めて自分でみんなの責任もとるという共同作業に移行していった。そのことが面白かったんです。
糸井 それは、すごく段階を踏んでいると思いますよ。・・・たとえば15人で会議をするとしたら14人のチーム対ぼく一人なわけで、相手14人よりもぼく一人のほうが力があると思っていいかな、と。それが僕の飯のタネだったんです。ところが徐々に、14人のチームも14人がそれぞれに機能しているんだということがわかってくるようになった。チームとしての仕事がとてもよくなってきて、ぼくがチームリーダーでもないのに、この人たちがいてよかった、皆ありがとうね、という気持ちになることが多くなっていったんです。
糸井 ・・・でも会社をやっていると、アイディアを生む前提として「知識の量」というものがそもそも必要なのかどうかあやしくなってくる。それぞれの分量が少なくても良い仕組みがあれば、すごい力が出るんですよ。
ここはサラリーマンにも参考になる。
大企業のサラリーマンが起業や転職をしても上手くいかないと言われるが、ビジネスが上手くいくにはオペレーション・組織作りも大事で、そこについては今まで大きな組織に乗っかっていただけなので、実はノウハウがなかったりする。なので他人の力を合わせて集団で力を発揮するのでなく個人でどうにかしようと「他人には任せられない」モードになってしまったり、(もっとひどいと)「乗っかり型管理職」になってしまうのだろう。
必要に応じて徐々に大きくしていったので組織というものを考えることができたのかもしれない。
そして小説はどこに行くか
高橋 ・・・今までの小説の多くは青春小説で個人主義、つまり中心にあったのが「自分」だったんですね。「ルック・アット・ミー」が基本で、若くして失敗したら死ぬ、という枠内で終わっている。では長生きしたらどうするか?漱石はちょっと書きかけたんだけど、結婚して二人でなんとかやっていく、という方向で落ち着いてしまったから、その先の共同体のあり方については書いていないんです。
では今まで、なぜ個人だけで小説が成り立っていたかというと、「家」とか「社会」がかっちりしていたからです。否定できない共同体があるから、個人が成り立つ。
・・・昔は「一人」を威張れたけれど、今は「一人」すら、あやしい。世界とか家がぼんやりしているから、そこから出ることにはもはや意味がなくて、個人にスポットを当てると、はっきりしない小説になる。・・・この百年間「家」が壊れ、ルールが壊れ、国家が壊れた。・・・そして今、一人では生きていけないという単純な事実が残った。
糸井 ・・・今までの「家族」とは違っていいんだけど、それにかわる新しい「ホーム」がないとダメなんだと思う。・・・独身の独り者にだって、ホームはあるんですよ。大きくなりすぎると邪魔になるけれど、育てるもの。だから「ホーム」っていうのは重要な概念だと思うんだけど、その中に含まれているの大切なものは、「ストーリー」ですよね。
高橋 それはつまりエピソードのある世界、ですよね。・・・全てに日付も場所もある、エピソードを提供できることはものすごく強いですよね。
・・・小説が何を作っているかというと、そのいちばん大きなものは、エピソードだと思うんですよ。小説の中にあるエピソードがさながら自分のもののように感じられる。あの日、自分も同じものを見た、というような同時代の感覚をもたせる。それは小説の大きな仕事のうちの一つですよね。・・・「出版社が厳しい」「小説が厳しい」というのは一面ではまったくその通りだと思う反面、ぼくは全然絶望もしていない。だって、人は共同体もエピソードも絶対必要としている。今はそういう意味で、みんな「家」をなくしたホームレス状態だけど、小説というのは--政治も、宗教もそうかもしれないけど--もういちど「家」を作り出すことができるはずで、では誰がどんな形で新しい共同体の形を作るのか、というのが競争といえば競争だし、仕事といえば仕事ですよね。
政治・宗教でも「家」や「共同体」の「復権」「復活」というのはキーワードになりそうですが、こちらはそういう行動の美名に惑わされず、出来上がりが何を目指しているかをよく注目しないといけないですね。