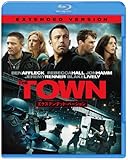監督のオリバー・ストーンの意図はわかりませんが、自分にない他人の持つ資源をなんらかの形で得ようとするという点では、「強欲」も「社会貢献」も「愛」も同根なんだということがわかる映画です。
(以下ほとんどストーリーを明らかにしてしまうので、それをご承知の上お読みください)
前作『ウォール街』でインサイダー取引で捕まったマイケル・ダグラス演じるゴードン・ゲッコーが刑務所から出所するところから始まります。
その後ゲッコーは著書を著し、サブプライム・ローンがバブルだと指摘し、講演で「今やファンドマネジャーは他人の金を高いリスクの投資につぎ込むことで自らの報酬を得ている」と警鐘を鳴らす金融評論家として脚光を浴びます。
(ゲッコーは投資する資金がないのでそうやって糊口をしのぐしかないという事情もあります。)
それは、一匹狼の投資家が自らの手金で勝負していた1980年代のスタイルから見ると、庶民や年金(これも元をたどれば庶民)の金を投資銀行がファンドと言うかたちで吸い上げる時代のほうがより不健全だと見えたのかもしれません。
(正確に言えばゲッコーは自らの投資のためにインサイダー取引に手を染めたわけですが、昔はそのように「不健全さ」がわかりやすかったのに対して、現在ではそれが表に出にくいということでしょう)
一方で主人公ジェイコブ(『トランスフォーマー』のシャイア・ラブーフ)は投資銀行に勤務し、ゲッコーの娘(ウィニー、ゲッコーを嫌い、非営利のニュースサイトを運営)と婚約しています。
ところがジェイコブの投資銀行はサブプライム崩壊の過程で倒産し、さらに(この間はいろいろあるのですが)彼が投資先として支援していた常温核融合技術(のようなもの?)の会社が資金繰り難に陥ります。
ゲッコーとウィニーの仲を取り持とうとしていたジェイコブは、ゲッコーからウィニーのためにスイスの銀行に信託財産として1億ドルを隠していること、それはウィニーが24歳になるまでは引き出せないが、ウィニー(受益者)とゲッコー(委託者)の同意で契約を解除すれば引き出し可能なことを聞きます。
そして「父親の汚れた金なんて」と嫌がるウィニーをジェイコブは「地球の未来のために、(僕のために)その金の一部を役立ててくれ」と説得します。
ところが、ウィニーが銀行でサインをしたあと、ゲッコーは自分がサインをして手元に資金を手にするや否や、その資金を投資先に振り込まず、それを元に自らの投資会社をつくり、サブプライムの崩壊をとらまえて一気に資金を10億ドルに増やし、さらに自らのヘッジファンドを立ち上げます。
この辺はゲッコーの面目躍如です。
一方ジェイコブはウィニーに別れを切り出され、投資先の会社は資金難に陥ります。
はめられた当初はゲッコーを激しく非難したジェイコブですが最後にゲッコーのオフィスを訪れ、非難する代わりにウィニーがジェイコブの子供を妊娠していることを告げます。
(でいろいろあって)最終的にはゲッコーはジェイコブはウィニーのよりを戻すために自ら投資会社に出資することを告げ、最後はみんなハッピーエンドになります。
ネットでレビューをみると最後のハッピーエンドが中途半端だという感想が多いようですが、よく考えるとジェイコブの行動は突っ込みどころ満載です。
・ジェイコブは最初から最後まで核融合会社に自分の金は1セントも投資していない。すべて顧客やガールフレンド(の父親)の金
・なおかつ相当ハイリスクな投資であり、しかもウィニーに持ちかけたのは自らの尻拭いをしてもらおうというもの。
・ジェイコブはゲッコーに資金を持ち逃げされたときに、ウイニーの金(そもそもはゲッコーの資産隠しの金)なのにあたかもゲッコーが自分の金を奪ったかのように激昂する(そもそも同じ業界の奴がはめられて逆切れしてるだけなんですが...)。
・ジェイコブは最終的には1セントも使わずにウィニーともよりを戻せたし核融合会社も救えて一番字ハッピー。
つまり、ジェイコブこそがゲッコー言うところの最近の投資銀行員の行動(他人の金でハイリスクな投資をし本人は報酬を得る)を一貫して実践しているわけ。
一方で、ゲッコーにとってみれば、資産が10倍に増えたあとであれば、その一部を投資するのは懐がほとんど痛まないわけで、それで娘との関係が修復するのなら安い投資なわけです。
そうするとウィニーは
・献身的なボーイフレンドの努力によって父親とも和解できた幸せな女性
なのか
・自分の欲得で動く男二人に振り回された挙句に本来自分が得るべき預金も失ったにもかかわらず丸め込まれてしまったお人よしの女性
なのかわからなくなってしまいますね。
では、ジェイコブは悪い奴なのか?
(ここで「愛はお金では買えない」という話は今回はひとまず置きます。)
ジェイコブの行動のポイントは、あたかも他人の金を投資させるために全身全霊をつくして説得し、一度コミットをえたらあたかもそれが自分の金であるかのように執着することにあります。
これを「情熱と努力と創意工夫と集中力」と言い換えれば、商売で成功する一つのコツでもあります。要するにジェイコブは商売上手なだけなのかもしれません。
ところで「他人の金を使う」ということ広くとらえると、自分にかけているもの(資産・技術・能力など)を他人から補うという日常よく見られる行動のひとつとも考えられます。
足りないものを補うためには対価として貨幣を払うこともあれば(これが日常生活ではほとんどを占めます)、互酬のこともあれば(親戚や友達づきあいがそうですね)、「善意にすがる」(親子・恋人関係)こともあるわけです。
竹内久美子流にいえば、親の庇護をうける子供が可愛さをアピールしたり、自らの遺伝子を残すために異性を獲得しようとしたりするのも同じです。
そう考えると、前作から一貫してゲッコーが問いかけている
「強欲は悪か?」
という問いがよみがえってきます。
「欠けているものを補う」ことを否定したら人間の社会生活は成り立ちません。
(うろ覚えですが、マルクスも『経済学・哲学草稿』で「人間は受苦的な存在であることこそが、本来回復すべき情熱、人間の生の根源的な意味だ」というようなことを言っていたような-引用の文脈が違っていたらすみません-)
問題は何が欠けているか、という欲求が人によって違う(違いすぎる)ことです。
一方で上の命題は「強欲」に「過ぎたる欲求を持つ」という善悪・価値判断にかかわる意味を持たせるとトートロジーになってしまいます。
愛と新エネルギーへの投資用の資金を同時に得ようとするジェイコブの行動は「強欲」なのでしょうか、それとも「善」の行動なのでしょうか。
そうやっていろいろ考えるきっかけとしてはおもしろい映画だと思いました。
PS
前作のチャーリー・シーンが「その後」として一場面だけ登場して、けっこう笑えます。