日本の近代資本主義が明治以後にあっという間に世界レベルまで構築されていったことの背景には、以前に紹介した国際派日本人養成講座からの転載記事『日本人のDNAには過去400年以上にわたる市場経済システムの経験が組み込まれている。』にも書きましたように、江戸時代にすでにその基礎となる市場経済の仕組みや、また商人達の信用を重視する商道ともいうべきものが確立されていたからでした。今回はその更に江戸のシステムの源泉ともいうべき思想です。
■1.日本の近代資本主義の源泉■
西欧が2百年を費やした近代資本主義社会の構築を、日本がわずか百年足らずで成し遂げた原動力はどこにあったのか、の研究が、インド哲学・仏教研究の国際的な権威である中村元博士と経済学者の大野信三博士によって進められた。
社会・経済学者マックス・ウェーバーは「西洋資本主義のシステムは、キリスト教の一宗派である清教の『どのような職業も神の召命である』とする職業倫理と、禁欲的・合理的な経済倫理によって支えられている」との学説を立て、これが広く受け入れられていた。
そして両博士が、日本の近代資本主義の源泉として発見したのが、江戸時代初期の禅僧・鈴木正三(しょうさん)であった。
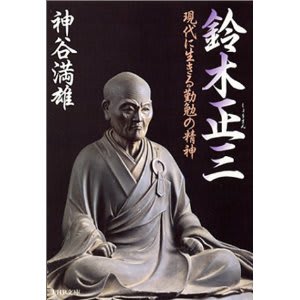
■2.なぜ他人と自己、生と死という対立があるのか■
正三は天正7(1579)年、三河の国の足助(あすけ)庄の地侍の家に生まれた。信長が倒れる3年前であった。
少年時代に、近所のお寺で僧の講話を聞く事がほとんど唯一の学問だったようだ。
天正18(1590)年、正三が12歳の年に、鈴木一党は家康の関東移封に従って、上総の塩子に移住した。
ある日の夜もふけたころ、自宅の犬がしきりに吠えてい る。戸外に出てみると、別に変わったこともない。その時、 晴れた夜空を仰いで、正三はしみじみといった。
一天平等にしてなんの差別もないのに、われわれ人間に は、なぜ他人と自己、生と死というようなことがあるのか。自己と他人との対立を超越し、生と死の対立を打破して、大自在の境地を得たい。その導きとなる教えは仏法をおいて他にはない。
■3.「衆生の恩」■
しかし、正三は、俗世を離れて一人悟りを求める、というような生き方は選ばなかった。
慶長5(1600)年、22歳の正三は初陣として、関ヶ原を目指して徳川秀忠の軍に加わった。さらに36歳の時には大坂冬の陣、翌年の夏の陣に参加した。この間、足助の庄の地に2百石を拝領する旗本に取り立てられた。秀忠軍の先陣として、白兵戦や鉄砲攻撃などの修羅場をくぐり抜け、軍功をたてたものと思われる。
天下統一を果たすと、徳川幕府は元号を元和(げんな)と改めて、一国一城令、武家諸法度、禁中並公家諸法度、寺院諸法度などを制定し、平和な国づくりのための布石を次々と打っていった。
この頃、正三は旗本として大坂城を警護する仕事についていたが、その自由時間に最初の著作『盲安杖』をまとめた。「盲人の安心のための杖」という意味である。これは、儒学を信奉する同僚から「仏法は世法に背く(仏法は隠遁などを奨励して世を良くすることにつながらない)」と言われたので、その反論としてまとめたものである。
正三は、この中で天地の恩、師の恩、国王の恩、父母の恩と並んで「衆生の恩」もあると説いている。衆生の恩とは「農人の恩、諸職人の恩、衣類紡績の恩、商人の恩、一切の所作、互いに相助け合っている恩」と説明し、この事を理解して、諸人とわけへだてなくつき合うべきだと説いている。
諸人が日常生活を営めるのも、農民が米を作ってくれたり、職人が衣服を作ってくれたり、商人がそれらを流通してくれるからであり、「一切の所作(すべての仕事)」が「互いに相助け合って」世の中が成り立っている、という考え方である。
こうした「仏法」なら、世法を正しく導くものであろう。正三の志もそこにあった。この思想が世間を導けば、平和な社会が到来し、「他人と自己」「生と死」の対立という矛盾も和らいでいくだろう。
この『盲安杖』は、徳川時代を通じて庶民大衆の修養の参考書としてかなり流布したという。
■4.「己をすてて大利に至る」■
旗本として大坂城を警護するなどという仕事は、当時の社会にあってはエリートの地位であって、安楽な一生が保証されていた。しかし、正三の自らの思想がそれを許さなかった。第2代将軍・秀忠を中心とする江戸幕府が築きつつあった新しい平和な社会の建設に、自由な思想家として貢献していこうという志を抱いたのである。
元和6(1620)年、正三は42歳にして、武士の身分を捨て、禅僧として出家した。正三研究の第一人者神谷満雄博士は、その動機について、こう述べている。
それは今後、君恩に報いるための実践的な仏法興隆と、仏教倫理によって民衆を教化することを治国の基本におくという壮大な事業への参画・推進を生涯にわたる自らの「天職」として、実践していこうとする決意であった。
幕府には、自らの出家を「曲事(まがこと)と思召めさば、御成敗あれ」と切腹覚悟で届け出た。それを聞いた老中が将軍に「ふと道心を起し候」と報告した所、秀忠は「それは道心というではない。隠居じゃまでよ」と答えた。「出家」でなく「隠居」とされたことによって、養子の重長が正三の跡目を継ぐことができた。
秀忠は、関ヶ原以来20年も仕えてきた正三の人となりをよく知って、その出家の志を見通していたのかも知れない。
『盲安杖』には、「小利を捨てて大利にいたれ」という項目があり、「いたれる人は、誠のために身命をなげうって、名利にとどまらず、己をすてて大利に至る」と説いていた。正三はそれを実行したのである。
■5.士農工商のそれぞれの役割■
この後、正三は大和の法隆寺など各地を巡り、高僧に教えを乞うたり、自らの思想を説いて回った。寛永8(1631)年、53歳の正三は紀州の熊野を訪れ、和歌山の加納氏邸で武士に法話を行い、求めに応じて『武士日用』を書いた。「日用」とは、「毎日使うもの」という意味で、武士としての生き方をさりげない形で説いた。
これに続いて正三は、『農人日用』『職人日用』『商人日用』を書き上げ、あわせて『四民日用』とした。「士農工商」といえば、我々はすぐに身分差別制度と短絡してしまうが、正三は、それぞれが異なる社会的な役割を持って、社会を成り立たせていると考えた。『職人日用』には、以下の一節がある。
鍛冶番匠をはじめとして、諸職人なくしては、世界の用いる所、調うべからず。武士なくして世治まるべからず。農人なくして世界の食物あるべからず。商人なくして世界の自由、成るべからず。
鍛冶屋などの職人がいなくては、世の中は様々な道具を調えることができない。武士なくしては世の中の秩序が保てない。農民がいなくては食べ物が得られない。商人がいなくては、様ざまなものを自在に流通させることができない。こうして諸々の職業がお互いに助け合って、世の中が成り立っている、と。
■6.「何の事業もみな仏行なり」■
四民が互いに助け合って世の中を支えている姿に、正三は「何の事業もみな仏行なり」として「仏行」そのものだと見なした。たとえば『農民日用』ではこう説いている。
それ、農人と生を受けしことは天より授けたまわる世界養育の役人なり。さればこの身を一筋に天道に任せたてまつり、かりにも身のためを思わずして、まさに天道の奉公に農業をなし、五穀を作り出して仏陀神明を祭り、万民の命をたすけ、虫類などにいたるまで施すべしと大誓願をなして、ひと鍬ひと鍬に、南無阿弥陀仏、なむあみだ仏と唱え、一鎌一鎌に住して、他念なく農業をなさんには、田畑も清浄の地となり、五穀も清浄食となって、食する人、煩悩を消滅するの薬なるべし。
(農民と生まれたことは、天から任命されて世界を養う役人となるということである。したがって自分の身を一筋に天道に任せて、かりそめにも自分の事を考えず、天道への奉公として農業をなし、五穀を作って仏陀神明を祭り、万民の命を助け、虫類などに至るまで施しを行おうと大誓願をなして、一鍬入れる毎に、南無阿弥陀仏と仏を唱え、一鎌毎に心を入れて、一心に農業に勤しめば、田畑も清浄の地となり、五穀も清浄の食べ物となって、食べる人の煩悩を消滅させる薬になる。)
「仏行」とは、俗世間を出家した僧侶のみが行う宗教的行事ではなく、一般人が自らの仕事に打ち込む、その日常生活そのものにあるとした。
■7.商人の志■
さらに、その「仏行」は世のため人のためでなく、自分自身に内在する仏性を引き出すための「修業」に他ならない、と。『商人日用』では、こう説いている。
その身をなげうって、一筋に国土のため万民のためと思い入れて、自国のものを他国に移し、他国のものをわが国に持ち来りて・・・山々を越えて、身心を責め、大河小河を渡って心を清め、漫々たる海上に船をうかぶる時は、この身を捨てて念仏し、一生はただ浮世の旅なる事を観じて、一切執着を捨て、欲をはなれ商いせんには、諸天これを守護し、神明利生を施して、得利もすぐれ、福徳充満の人となる。
(その身を捧げて、一筋に国土のため万民のためと決心して、自国の物産を他国に売り、他国の物産をわが国に買い入れて・・・山々を越えて心身を鍛え、大河小河を渡って心を清め、満々たる海上に船を浮かべる時は、この身を思わずして念仏を唱え、一生はただ浮世の旅である事を悟って、一切の執着を捨て、欲を離れて商いをするには、諸天が商いを守護し、神の明らかな徳で助けてくれるので、利益もあがり、徳の豊かな人になる。)
物を右から左に流すだけで利潤を得るなどと、蔑まれていた商人たちの中にも、これを読んで、自らの職業に励むことが、自己を高め、充実した人生への道だと知って、いよいよ事業に励む人も少なくなかったであろう。
士農工商と職業こそ違えど、人はみな心中に仏性を持っているのであり、自らの職業に打ち込むことで、その仏性を開発し、世のため人のために尽くせる、という考え方は、人間はすべて平等である、という近代的な人間観につながっていた。
■8.「一筋に正直の道」」■
商人にとって、商売に精進することが「仏行」であるとすれば、そこから得られる利潤をどう考えるのか? 武家上がりの正三は、剛毅果断にも次のように説いた。
売買せん人は、まず得利の増すべき心づかいを修行すべし。その心づかいと言うは他の事にあらず。身命を天道になげうって、一筋に正直の道を学ぶべし。
(売買をしようとする人は、まず利益を増す心づかいを修業すべきである。その心づかいとはほかでもない。身命を天道に捧げて、一筋に正直の道を学ぶべきである。)
商売が「仏行」である以上、まず利益が上がるように心づかいを学ぶべきだと言う。それも人を騙して利益を上げよう、と言うのではなく、「一筋に正直の道」を踏み外さずに利益を増すよう学ぶべきだ、という。
現代でも耐震偽装やらで人を騙して巨利を上げた事件があったが、こうした輩があまりに多くては世の中が立ちゆかない。「一筋に正直の道」こそ、信用や契約など近代産業社会を支える基盤なのである。
■9.近代資本主義社会の構築を成し遂げた原動力■
正三の主張は、わが国でもっとも早く商業利潤の倫理的正当性を説いたもので、これが約百年後に開花する石門心学に流れ込んで、「商人の利潤は武士の俸禄と同じく、正当な報酬である」と主張されるようになった。石門心学はその最盛期には、全国34藩に180カ所もの講舎が作られ、大々的にその教えを広めた。
江戸期の商人や職人たちはこうした思想を学んで、自らの仕事が単に収入を得るための手段ではなく、自己を高め世の中に尽くす「道」であると考えることで、生き甲斐をもって日々の仕事に取り組む事ができた。さらにそれが「一筋に正直の道」でなければならないという教えは、約束を守る、信用を重んずる、など近代社会の基盤の確立につながった。
ちなみに正三の同時代の宗教改革指導者ジャン・カルヴァンは、職業を神から与えられたものであるとし、商業利潤を認めて、中小商工業者から多くの支持を得ていた。近代商工業の思想的幕開けは、西欧と日本とでほぼ同時期に起こった。
西欧諸国が2百年を費やした近代資本主義社会の構築を、明治以降の日本がわずか百年足らずで成し遂げた原動力は、正三の思想から生じたのである。
国際派日本人養成講座より
■1.日本の近代資本主義の源泉■
西欧が2百年を費やした近代資本主義社会の構築を、日本がわずか百年足らずで成し遂げた原動力はどこにあったのか、の研究が、インド哲学・仏教研究の国際的な権威である中村元博士と経済学者の大野信三博士によって進められた。
社会・経済学者マックス・ウェーバーは「西洋資本主義のシステムは、キリスト教の一宗派である清教の『どのような職業も神の召命である』とする職業倫理と、禁欲的・合理的な経済倫理によって支えられている」との学説を立て、これが広く受け入れられていた。
そして両博士が、日本の近代資本主義の源泉として発見したのが、江戸時代初期の禅僧・鈴木正三(しょうさん)であった。
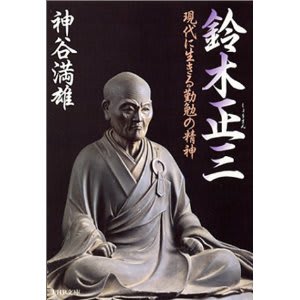
■2.なぜ他人と自己、生と死という対立があるのか■
正三は天正7(1579)年、三河の国の足助(あすけ)庄の地侍の家に生まれた。信長が倒れる3年前であった。
少年時代に、近所のお寺で僧の講話を聞く事がほとんど唯一の学問だったようだ。
天正18(1590)年、正三が12歳の年に、鈴木一党は家康の関東移封に従って、上総の塩子に移住した。
ある日の夜もふけたころ、自宅の犬がしきりに吠えてい る。戸外に出てみると、別に変わったこともない。その時、 晴れた夜空を仰いで、正三はしみじみといった。
一天平等にしてなんの差別もないのに、われわれ人間に は、なぜ他人と自己、生と死というようなことがあるのか。自己と他人との対立を超越し、生と死の対立を打破して、大自在の境地を得たい。その導きとなる教えは仏法をおいて他にはない。
■3.「衆生の恩」■
しかし、正三は、俗世を離れて一人悟りを求める、というような生き方は選ばなかった。
慶長5(1600)年、22歳の正三は初陣として、関ヶ原を目指して徳川秀忠の軍に加わった。さらに36歳の時には大坂冬の陣、翌年の夏の陣に参加した。この間、足助の庄の地に2百石を拝領する旗本に取り立てられた。秀忠軍の先陣として、白兵戦や鉄砲攻撃などの修羅場をくぐり抜け、軍功をたてたものと思われる。
天下統一を果たすと、徳川幕府は元号を元和(げんな)と改めて、一国一城令、武家諸法度、禁中並公家諸法度、寺院諸法度などを制定し、平和な国づくりのための布石を次々と打っていった。
この頃、正三は旗本として大坂城を警護する仕事についていたが、その自由時間に最初の著作『盲安杖』をまとめた。「盲人の安心のための杖」という意味である。これは、儒学を信奉する同僚から「仏法は世法に背く(仏法は隠遁などを奨励して世を良くすることにつながらない)」と言われたので、その反論としてまとめたものである。
正三は、この中で天地の恩、師の恩、国王の恩、父母の恩と並んで「衆生の恩」もあると説いている。衆生の恩とは「農人の恩、諸職人の恩、衣類紡績の恩、商人の恩、一切の所作、互いに相助け合っている恩」と説明し、この事を理解して、諸人とわけへだてなくつき合うべきだと説いている。
諸人が日常生活を営めるのも、農民が米を作ってくれたり、職人が衣服を作ってくれたり、商人がそれらを流通してくれるからであり、「一切の所作(すべての仕事)」が「互いに相助け合って」世の中が成り立っている、という考え方である。
こうした「仏法」なら、世法を正しく導くものであろう。正三の志もそこにあった。この思想が世間を導けば、平和な社会が到来し、「他人と自己」「生と死」の対立という矛盾も和らいでいくだろう。
この『盲安杖』は、徳川時代を通じて庶民大衆の修養の参考書としてかなり流布したという。
■4.「己をすてて大利に至る」■
旗本として大坂城を警護するなどという仕事は、当時の社会にあってはエリートの地位であって、安楽な一生が保証されていた。しかし、正三の自らの思想がそれを許さなかった。第2代将軍・秀忠を中心とする江戸幕府が築きつつあった新しい平和な社会の建設に、自由な思想家として貢献していこうという志を抱いたのである。
元和6(1620)年、正三は42歳にして、武士の身分を捨て、禅僧として出家した。正三研究の第一人者神谷満雄博士は、その動機について、こう述べている。
それは今後、君恩に報いるための実践的な仏法興隆と、仏教倫理によって民衆を教化することを治国の基本におくという壮大な事業への参画・推進を生涯にわたる自らの「天職」として、実践していこうとする決意であった。
幕府には、自らの出家を「曲事(まがこと)と思召めさば、御成敗あれ」と切腹覚悟で届け出た。それを聞いた老中が将軍に「ふと道心を起し候」と報告した所、秀忠は「それは道心というではない。隠居じゃまでよ」と答えた。「出家」でなく「隠居」とされたことによって、養子の重長が正三の跡目を継ぐことができた。
秀忠は、関ヶ原以来20年も仕えてきた正三の人となりをよく知って、その出家の志を見通していたのかも知れない。
『盲安杖』には、「小利を捨てて大利にいたれ」という項目があり、「いたれる人は、誠のために身命をなげうって、名利にとどまらず、己をすてて大利に至る」と説いていた。正三はそれを実行したのである。
■5.士農工商のそれぞれの役割■
この後、正三は大和の法隆寺など各地を巡り、高僧に教えを乞うたり、自らの思想を説いて回った。寛永8(1631)年、53歳の正三は紀州の熊野を訪れ、和歌山の加納氏邸で武士に法話を行い、求めに応じて『武士日用』を書いた。「日用」とは、「毎日使うもの」という意味で、武士としての生き方をさりげない形で説いた。
これに続いて正三は、『農人日用』『職人日用』『商人日用』を書き上げ、あわせて『四民日用』とした。「士農工商」といえば、我々はすぐに身分差別制度と短絡してしまうが、正三は、それぞれが異なる社会的な役割を持って、社会を成り立たせていると考えた。『職人日用』には、以下の一節がある。
鍛冶番匠をはじめとして、諸職人なくしては、世界の用いる所、調うべからず。武士なくして世治まるべからず。農人なくして世界の食物あるべからず。商人なくして世界の自由、成るべからず。
鍛冶屋などの職人がいなくては、世の中は様々な道具を調えることができない。武士なくしては世の中の秩序が保てない。農民がいなくては食べ物が得られない。商人がいなくては、様ざまなものを自在に流通させることができない。こうして諸々の職業がお互いに助け合って、世の中が成り立っている、と。
■6.「何の事業もみな仏行なり」■
四民が互いに助け合って世の中を支えている姿に、正三は「何の事業もみな仏行なり」として「仏行」そのものだと見なした。たとえば『農民日用』ではこう説いている。
それ、農人と生を受けしことは天より授けたまわる世界養育の役人なり。さればこの身を一筋に天道に任せたてまつり、かりにも身のためを思わずして、まさに天道の奉公に農業をなし、五穀を作り出して仏陀神明を祭り、万民の命をたすけ、虫類などにいたるまで施すべしと大誓願をなして、ひと鍬ひと鍬に、南無阿弥陀仏、なむあみだ仏と唱え、一鎌一鎌に住して、他念なく農業をなさんには、田畑も清浄の地となり、五穀も清浄食となって、食する人、煩悩を消滅するの薬なるべし。
(農民と生まれたことは、天から任命されて世界を養う役人となるということである。したがって自分の身を一筋に天道に任せて、かりそめにも自分の事を考えず、天道への奉公として農業をなし、五穀を作って仏陀神明を祭り、万民の命を助け、虫類などに至るまで施しを行おうと大誓願をなして、一鍬入れる毎に、南無阿弥陀仏と仏を唱え、一鎌毎に心を入れて、一心に農業に勤しめば、田畑も清浄の地となり、五穀も清浄の食べ物となって、食べる人の煩悩を消滅させる薬になる。)
「仏行」とは、俗世間を出家した僧侶のみが行う宗教的行事ではなく、一般人が自らの仕事に打ち込む、その日常生活そのものにあるとした。
■7.商人の志■
さらに、その「仏行」は世のため人のためでなく、自分自身に内在する仏性を引き出すための「修業」に他ならない、と。『商人日用』では、こう説いている。
その身をなげうって、一筋に国土のため万民のためと思い入れて、自国のものを他国に移し、他国のものをわが国に持ち来りて・・・山々を越えて、身心を責め、大河小河を渡って心を清め、漫々たる海上に船をうかぶる時は、この身を捨てて念仏し、一生はただ浮世の旅なる事を観じて、一切執着を捨て、欲をはなれ商いせんには、諸天これを守護し、神明利生を施して、得利もすぐれ、福徳充満の人となる。
(その身を捧げて、一筋に国土のため万民のためと決心して、自国の物産を他国に売り、他国の物産をわが国に買い入れて・・・山々を越えて心身を鍛え、大河小河を渡って心を清め、満々たる海上に船を浮かべる時は、この身を思わずして念仏を唱え、一生はただ浮世の旅である事を悟って、一切の執着を捨て、欲を離れて商いをするには、諸天が商いを守護し、神の明らかな徳で助けてくれるので、利益もあがり、徳の豊かな人になる。)
物を右から左に流すだけで利潤を得るなどと、蔑まれていた商人たちの中にも、これを読んで、自らの職業に励むことが、自己を高め、充実した人生への道だと知って、いよいよ事業に励む人も少なくなかったであろう。
士農工商と職業こそ違えど、人はみな心中に仏性を持っているのであり、自らの職業に打ち込むことで、その仏性を開発し、世のため人のために尽くせる、という考え方は、人間はすべて平等である、という近代的な人間観につながっていた。
■8.「一筋に正直の道」」■
商人にとって、商売に精進することが「仏行」であるとすれば、そこから得られる利潤をどう考えるのか? 武家上がりの正三は、剛毅果断にも次のように説いた。
売買せん人は、まず得利の増すべき心づかいを修行すべし。その心づかいと言うは他の事にあらず。身命を天道になげうって、一筋に正直の道を学ぶべし。
(売買をしようとする人は、まず利益を増す心づかいを修業すべきである。その心づかいとはほかでもない。身命を天道に捧げて、一筋に正直の道を学ぶべきである。)
商売が「仏行」である以上、まず利益が上がるように心づかいを学ぶべきだと言う。それも人を騙して利益を上げよう、と言うのではなく、「一筋に正直の道」を踏み外さずに利益を増すよう学ぶべきだ、という。
現代でも耐震偽装やらで人を騙して巨利を上げた事件があったが、こうした輩があまりに多くては世の中が立ちゆかない。「一筋に正直の道」こそ、信用や契約など近代産業社会を支える基盤なのである。
■9.近代資本主義社会の構築を成し遂げた原動力■
正三の主張は、わが国でもっとも早く商業利潤の倫理的正当性を説いたもので、これが約百年後に開花する石門心学に流れ込んで、「商人の利潤は武士の俸禄と同じく、正当な報酬である」と主張されるようになった。石門心学はその最盛期には、全国34藩に180カ所もの講舎が作られ、大々的にその教えを広めた。
江戸期の商人や職人たちはこうした思想を学んで、自らの仕事が単に収入を得るための手段ではなく、自己を高め世の中に尽くす「道」であると考えることで、生き甲斐をもって日々の仕事に取り組む事ができた。さらにそれが「一筋に正直の道」でなければならないという教えは、約束を守る、信用を重んずる、など近代社会の基盤の確立につながった。
ちなみに正三の同時代の宗教改革指導者ジャン・カルヴァンは、職業を神から与えられたものであるとし、商業利潤を認めて、中小商工業者から多くの支持を得ていた。近代商工業の思想的幕開けは、西欧と日本とでほぼ同時期に起こった。
西欧諸国が2百年を費やした近代資本主義社会の構築を、明治以降の日本がわずか百年足らずで成し遂げた原動力は、正三の思想から生じたのである。
国際派日本人養成講座より



















