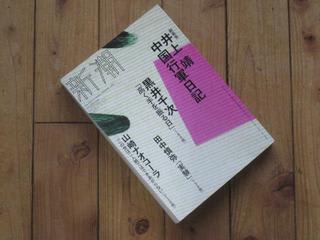*左;利休ー茶室の謎;瀬地山澪子著、創元社2000年発行。表紙カバーが茶室の土壁の手触りです。右;こういう特集の雑誌は買ってしまいます。美術手帖、2009年11月号。
*左;利休ー茶室の謎;瀬地山澪子著、創元社2000年発行。表紙カバーが茶室の土壁の手触りです。右;こういう特集の雑誌は買ってしまいます。美術手帖、2009年11月号。
先日、ヨコハマでブラブラしていた時、伊勢崎町の<なぎさ書房>で買ったものの一冊です。
茶の湯の祖、千利休について、いくつかの番組を作った、NHKのディレクター瀬地山澪子さんの本です。
わが国の茶道に脈々と伝えられている、千利休の伝説、茶の湯の伝統・心にも抵触するようで、大変面白かったのです。
日本独自の世界、千利休が到達した<総合美>の世界が、実は、朝鮮(韓国)古来からの生活様式であった、というのです。
ウチの家人は、40年ほど続けている茶の湯好きです。従って、私も、時にお茶を飲みます。旅先では、著名な茶室を訪ね、骨董屋を覗き、お土産に茶の湯目線で和菓子を買います。近年、建築家やアーティストが<現代の茶の湯を展開>しているイベントなんかによく行きます。<例えば、ここにあります>
中国の茶を飲む習慣(喫茶)が、日本に入ってきて、日本独自の茶道(茶の湯)という芸術にまで昇華したといわれています。
茶を飲む空間=茶室、茶を飲む道具=茶碗、茶を飲む空気=自然観など、茶にまつわる全てが、洗練され、無駄をそぎ落とした芸術だといわれるのです。
平安貴族風の、荘厳華美に飲んでいたそれまでの茶(主と客が同座することのない殿中や書院における豪華な茶の湯)を、簡素な<侘び茶>にたどり着かせたのが、茶の湯の大成者・千利休です。<侘び>という新しい美意識を作ったのです。
千利休が作った茶室が、現在ただひとつ残っています。京都府・大山崎の<待庵・たいあん>(国宝)です。 <写真など、ここにあります>
 *待庵の内部、二畳敷の茶室(上記のWEBから)
*待庵の内部、二畳敷の茶室(上記のWEBから)
 **待庵の二畳敷の茶室(本書から)
**待庵の二畳敷の茶室(本書から)
待庵は、例えば、<二畳敷きの極小空間に込められた、深遠な思想>、<主と客のみが対峙し得る二畳敷きにまで空間を狭めたのです>などと解説されます。
待庵の特徴を乱暴にいえば、
①二畳敷きという極小空間
②土壁でかこった部屋で柱を見せない(それまでの、木の部屋から土の部屋に)
③入り口が、にじり口(立って入れない高さ)
です。
これらの特徴を持った、居住空間は、朝鮮古来からの民家であるというのです。
それを<発見>し、発表したのが、本書の著者、NHK大阪、京都にいた瀬地山澪子さんです。
瀬地山さんは、そのことを、NHK総合テレビ「歴史誕生」で、「利休茶室の謎―天下一宗匠の切腹」という番組にしたのです。放映は、1989年11月24日でした。
そっくりな朝鮮民家を見つけます。土壁の狭いウチなんて、どこにもあった朝鮮の貧しい民のウチそのものなのです。土壁も、出入り口の小ささも、皆、寒い朝鮮ならでは工夫なのです。
瀬地山さんは、そのことを丁寧に説明しています。
もうひとつ。茶会には、2種の茶室が使われます。広間と小間(こま)です。大勢が座ることできる広間と、少人数が座れる小間です。この小間(こま)は、高麗「こうらい=こま」からきているというのです。神社の高麗犬=こま犬と同じです。文献に、狭く作った茶室が<こまがこい=高麗がこい>とあることを見つけます。小間は、高麗(高麗風な部屋=小さい部屋)なのです。
日本オリジナルな、茶道空間、茶道世界は、朝鮮文化からも大きく影響されているようです。千利休が、どのように、具体的に朝鮮文化(朝鮮民俗)の影響を受けたのかも考察されています。
読み進む中に、秀吉の朝鮮征圧の野望にあたりました。
文禄慶長の役は、利休切腹後一年たった、1592年4月に始まり、1598年、秀吉の死によって終結するまで、足掛け7年に及んだのです。
<その間、女性を含む数万の朝鮮の人々を拉致連行し、多くの文物を略奪した。連行された人々による文化の伝搬・創造・略奪物の効用などは想像以上の多岐にわたり、日本近世文化の形成に大きな意味を持つに至った(瀬地山澪子さん)>
【おまけ】
 *江戸時代、著名な茶室研究に、<起し絵図>という立体図面が作られました。東京国立博物館の所蔵です。
*江戸時代、著名な茶室研究に、<起し絵図>という立体図面が作られました。東京国立博物館の所蔵です。
*瀬地山澪子さんは、1937年;生まれ、1960年;NHK大阪放送局に入局、1997年;定年退職、1999年;病室で最後まで著作の執筆に意欲を燃やすが、享年62歳で逝去。
*肺がんだったのです。発見されたとき末期でもう手術できなかったそうです。闘病中の執筆で、あとがきは、ご主人さんです。ガンもちの私は涙ボロボロ気分です。
*今、NHK教育テレビでは、各流派の茶道教室番組がありますが、1960年代、茶の湯作法(お点前)が初めてテレビ番組になった時のディレクターが瀬地山澪子さんだそうです。
*茶の湯好きのウチの家人にこの話をしたら、そのテレビ番組を見ていますよ、と。私は、その年代は、いつも<働いていて>テレビなんか見ていません。
*暖かくなったら<待庵>に行ってみようか。<私は、行っていますよ>との返事でした。
*書きたくない【おまけ】;私が子どもの頃に育ったウチも、土壁で覆われたウチでした。この間まで、日本でも、田舎の貧しいウチは、みなそうだったように思います。
【ディレクター瀬地山澪子さんの放映番組】
NHKTV-NHK特集「京都・表千家―わび茶の世界」1987年1月放送
NHKTV-歴史誕生「利休茶室の謎―天下一宗匠の切腹」1989年11月放送
NHKTV-ETV8「利休再発見―茶の湯政道」1990年3月放送
NHKTV-ETV8「利休再発見―異風美の創造」1990年3月放送
NHKTV-特集番組「虜囚の人々―秀吉・文禄慶長の役」1993年3月放送
 *春日部駅につらなって貼られたポスター。東武鉄道の元社長つながりでしょう。
*春日部駅につらなって貼られたポスター。東武鉄道の元社長つながりでしょう。 *右の書は、<山々黄落事如何>、まさに今の季節です。展示の中で、字が読めないというものだから買ったガイドブック1000円。
*右の書は、<山々黄落事如何>、まさに今の季節です。展示の中で、字が読めないというものだから買ったガイドブック1000円。