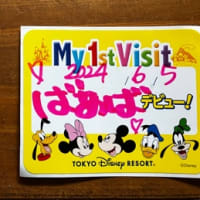「ちりく」と読むらしいこの神社は、福岡県との県境にある。
なんと目の前にある川(名前はわからないけど)この川が昔の筑後川だったのね。
その昔の筑後川が県境だったので、今の筑後川だと、県境がぐねぐねと曲がっているんだ。ふむふむφ(.. )
この鳥居は慶長14年(1609年)鍋島藩祖鍋島直茂公によって奉納されたもので、笠木と島木及び柱貫は、すべて三本継ぎとなっています。島木は、形式化して笠木と一体となり、木鼻は揺るやかに沿ってします。柱の上部には台輪があり、柱の下部は張り出して生け込みとなっていて、肥前鳥居の特色をよく備えています。県内に広く分布している石造肥前鳥居のうち古いものの一つにあたります。(教育委員会看板より)


御祭神 應神天皇,仲哀天皇,神功皇后
合祀 難波皇子,宇治皇子,住吉明神,武内宿禰
由緒
724年、聖武天皇の勅を奉じて、養父郡司、壬生春成が、この地に社殿を造営したと伝へている。以来、本宮は宇佐神宮の五所別宮の一と称せられ、朝廷からも厚く尊崇を受けた。
1609年には後陽成天皇より「肥前国総廟一宮鎮守千栗八幡大菩薩」の勅額を賜った。中世以降は肥前国一宮と呼ばれている。(看板より)


450年の楠(右)と350年のホルトノキ(左)

千栗八幡宮摂社 武雄神社
ご祭神 武雄心命
第八代孝元天皇の皇子彦太忍信命の子。祭祀・占(ト)を司る任に当たり、第一二代景行天皇にお仕えした臣下で高良大社のご祭神武内宿禰は御子である。他に相殿の神として天之忍穂耳命(あめのおしほみみのみこと)、菅原道真、伊弉諾尊、高木神(高御産巣日神たかみむすびのかみ)が祀られている。
由緒
創建は詳らかではないが、室町時代に書かれたと言われている「千栗八幡宮縁起絵」の境内図の中に「武雄社」がみられるところから、それ以前から信仰されていたと考えられる。 (看板より)

ずっと先に見えるのが久留米の街と高良山。
高良大社と千栗八幡宮で、この筑後平野を見張っていたらしい。
もうちょっと鮮明に見えて欲しかったな~
そして、平安時代後期より肥前国一宮を称してきたが、近世になって式内社河上神社(現 與止日女神社)との間で一宮の称が争われた

おやま~そして今は両方とも一宮なのね。

古賀稔彦をも育てたという石段。150段。1段1段の高さもあるし、ずれているところもあって、きついわ~
なんと目の前にある川(名前はわからないけど)この川が昔の筑後川だったのね。
その昔の筑後川が県境だったので、今の筑後川だと、県境がぐねぐねと曲がっているんだ。ふむふむφ(.. )
この鳥居は慶長14年(1609年)鍋島藩祖鍋島直茂公によって奉納されたもので、笠木と島木及び柱貫は、すべて三本継ぎとなっています。島木は、形式化して笠木と一体となり、木鼻は揺るやかに沿ってします。柱の上部には台輪があり、柱の下部は張り出して生け込みとなっていて、肥前鳥居の特色をよく備えています。県内に広く分布している石造肥前鳥居のうち古いものの一つにあたります。(教育委員会看板より)


御祭神 應神天皇,仲哀天皇,神功皇后
合祀 難波皇子,宇治皇子,住吉明神,武内宿禰
由緒
724年、聖武天皇の勅を奉じて、養父郡司、壬生春成が、この地に社殿を造営したと伝へている。以来、本宮は宇佐神宮の五所別宮の一と称せられ、朝廷からも厚く尊崇を受けた。
1609年には後陽成天皇より「肥前国総廟一宮鎮守千栗八幡大菩薩」の勅額を賜った。中世以降は肥前国一宮と呼ばれている。(看板より)


450年の楠(右)と350年のホルトノキ(左)

千栗八幡宮摂社 武雄神社
ご祭神 武雄心命
第八代孝元天皇の皇子彦太忍信命の子。祭祀・占(ト)を司る任に当たり、第一二代景行天皇にお仕えした臣下で高良大社のご祭神武内宿禰は御子である。他に相殿の神として天之忍穂耳命(あめのおしほみみのみこと)、菅原道真、伊弉諾尊、高木神(高御産巣日神たかみむすびのかみ)が祀られている。
由緒
創建は詳らかではないが、室町時代に書かれたと言われている「千栗八幡宮縁起絵」の境内図の中に「武雄社」がみられるところから、それ以前から信仰されていたと考えられる。 (看板より)

ずっと先に見えるのが久留米の街と高良山。
高良大社と千栗八幡宮で、この筑後平野を見張っていたらしい。
もうちょっと鮮明に見えて欲しかったな~
そして、平安時代後期より肥前国一宮を称してきたが、近世になって式内社河上神社(現 與止日女神社)との間で一宮の称が争われた


おやま~そして今は両方とも一宮なのね。

古賀稔彦をも育てたという石段。150段。1段1段の高さもあるし、ずれているところもあって、きついわ~