月刊《秘伝》という武道雑誌があります。これまで何度か黒岩洋志雄先生の講習会の様子を記事に採りあげ、技法の解説等もしてこられていますが、先般の11月号では先生の合気道技法の要諦を紹介しています。先生のそのような技法は、ある確信によって支えられています。その確信とは何か、それを考えるためのよすがとして、昔の資料を引っ張り出してきました。
その資料というのは、先生が指導されている立教大学合気道会で以前刊行されていた会報です(このブログにコメントをお寄せくださったことのあるBook様もご自身のウェブサイトで紹介されていました。なお、わたし自身は立教大学関係者ではありません)。
その中から、1983年に、先生へのインタビューをもとに文章を起し、同会報に掲載されたものを、このブログの読者の皆様にもお読みいただきたい旨、先生にお話をし、お許しをいただきましたので、通常のブログのナンバーとしてではなく、いつもわたしの駄文にお付き合いいただいている皆様に感謝の意味を込め、お歳暮がわりにお贈りしたいと思います。
口述筆記ですから、先生の気負いのない、淡々とした口調がよく伝わると思います。そこから先生の確信たるものをお読み取りください。
なお、できるだけ原文に忠実に記しますが、原文は複数の筆耕者の手によると思われ、文中、用字、用語、文体に若干の異同があることを踏まえ、また、読みやすさを考えて、行替えや句読点等も合わせて変更を行っている部分があることをお断りしておきます。
====================================
『 常 識 』
師範 黒岩 洋志雄
《 今回は、先生が三年程前から目を患われて、読み書きに支障をきたされたので、お話を録音したテープより抜粋・編集という形となりました 》
― まず最初に前号(立教大学合気道会創立20周年記念号:筆者註)の続きということで、お話をお願いします ―
* 以前に書きました《あたりまえのこと》と《虚と実》についてのことで意味がちょっとわかりにくいことがありますので、これを簡単に言いますと、《あたりまえのこと》の意味は、どういうことかというと、よく我々が経験することですけど、小舟に乗ってサオでつきながら舟をすすませる時にですね、サオが泥にささってしまうと抜けなくなっちゃう……。その時にみんな、あわててサオを抜こうとするわけです。ところが抜こうとすることによって、自分の足で舟を蹴とばして、水の中に落ちてしまうことがあるんですね。だから、サオが泥の中にうまった場合、それをパッと放すことが大事なんですね。それを一所懸命つかまえて抜こうとすることが、実は誤りなんですね。
その時ですね、手をパッと放して、それから今度は手でもって、ゆっくり漕いでですね、もどってきて改めてサオを抜けばいいんです。それを我々どうしても、とっさの場合にそのサオを抜こうとして、一所懸命そのサオにとらわれちゃう。そうすると、結局、川の中にドボンと落っこっちゃうってことなんですね。
それを《あたりまえのこと》に書いたわけです。つまり、合気道の稽古においても、大事なことは、相手の手を一所懸命持っていることに執着しないことで、いつでも、その相手の手を放すことに気がつかなくてはいけないんです。
― では次に、《虚と実》について解説をお願いします ―
* すべて、この世の中には裏と表があって、我々は、その両面に気がつかなきゃいけないんだけれども、どうしても片面だけを見たがる傾向があって、その結果いろいろな間違いが起きるんです。と、いいますのはね、その片面を、非常に、おおげさに言えば神秘化してね、改まった形で表現しますとね、それが《虚》ですね、ええ。
その《虚》っていうのは、《仮り》ですね。その仮りのことを本物と思っちゃうことが多いんですね。だから、一番最後に書いたんですけれど、せめて《ごきぶりホイホイ》ぐらいのことはやらなくっちゃいけない。
それでちょっと、《ごきぶりホイホイ》という意味がわからないと思うんで、ちょっとここで説明したいと思います。《ごきぶりホイホイ》というのは、これは文章の中にも書きましたけど、合気道をやっている由美かおるさんが宣伝して大ヒットをとばした商品ですね。
で、この商品は、どういうことかっていうと、これが《実の世界》なんです。ゴキブリの家があって、家のほうに接着剤がついている。そこにゴキブリが来て、その中に入ることによって、中についてる接着剤につかまってしまう。だからこの製品は世の中に通用する、つまり《実》なんです。
ところがですね、これをですね、合気的というと、まあちょっと問題ありますけれど、合気的に解釈すると、こういうことになっちゃうんですね。ゴキブリの家があって、そこにゴキブリが来る。家の前に接着剤があるんですね。で、その接着剤をですね、ゴキブリが勝手に自分の手にくっつけてですね、それで家の中に入ってですね、「ああ、くっついた、つかまっちゃった、つかまっちゃった」ってのが、いわゆる《虚》の世界なんですね。
だから、ここのところをはっきり気がつかないと大変なことになるんですね。そして、その接着剤的な役目を果たしているのが、我々がうっかりすると迷いの元になる《気》という言葉なんですね。
ですから、稽古中にですね、「気を出してやれ」、「気を結べばできるんだ」とか、「気を出せば相手の手ははずれないんだ」というのは、これは、とんでもない間違いでね、実は受け身のほうがですね、自分で相手につかまっちゃってる癖がついちゃってるんです。ということは、受け身のほうがですね、自分の手に接着剤をくっつけてることになるんですよ。そこのところをはっきり認識して稽古しませんと世の中に通用しないわけです。
それが、いま言いましたね、あの《ごきぶりホイホイ》というのは、いわゆる投げるほうなんですよ。そこに主導権があるわけです。
ところが、《虚》の稽古の特徴はですね、受け身をとるほうが、つまりゴキブリに主導権があるのに、投げるほうに主導権があるような錯覚を起すんです。ですから、前に書いた《虚と実》と《あたりまえのこと》で述べた、大事なことは、すべて、物事に執着したり、とらわれてはいけないっていうことなのです。
合気道の稽古では、型を通して稽古するものですから、それにとらわれてしまうことが一番いけないんですね。ですから、そういった執着っていうものを捨てるためには、その執着っていうものを経験してみないとわからないんで、まず、人間はとらわれることによって、逆にとらわれないことを感じて、それを身に付けなければいけないんです。
― ところで、今年は開祖の生誕百年にあたり、合気の道を修行する者にとりましては、誠に喜ばしい限りでございますが、先生が開祖の下に入門なさったのはいつ頃ですか ―
* ちょっと覚えてないんですが、昭和二十年代でした。ずいぶん昔になりますね。その頃は稽古にみえる方も非常に少なくて、いつも10人か、多くても15人くらいで、暮の忘年会の時に、開祖を中心にして輪を作って、ミカン二つとせんべい二枚で忘年会をやった覚えがあるんですね。その時の人数からいって、全員そろっても30人くらいじゃなかったですかね。
― 今年は新人部員が6人入りましたが、新入生に何か一言ございましたら、お願いしたいのですが ―
* よく、《石の上にも三年》といいますね。三年間辛抱すれば、必ず報われるという意味に使われますが、本当は二、三年のうちに“何か”を感じなければ、それ以上やっても無駄ということなんです。
“何か”っていうのは、まず、習っていることに疑問を感ずる、つまり、習い事の形式に不自然さを感じないか、ということですね。すべて物事には完全ということはないんですから、その疑問を解くために努力することが必要なんです。なんにも疑問を持たないで二、三年を過ごすようでは、将来の進歩は期待できないですね。三年も過ぎちゃうとね、それ以降は流されてしまって。初めのころはたしかに多少疑問とか持ったとしても、それを二、三年のうちに解決しないと、その解決するということが“何か”を感じるということなんですけど、それをしないと、その後の修行は他人の猿真似でしかなくて、個性を持ったものは生まれません。
極端に言えば、無意味な、自己満足的なものになっちゃって、そんなんじゃ物事の進歩には寄与しませんね。自分が習うことに対して「これでいいのかな」、「こういう意味なのかな」と疑問をぶつけることが本当の素直さっていうものであって、言われたことをただありがたがっているだけでは本当の素直とは言えないんですよ。
でもね、初心者の場合、客観的にそれを批判できないでしょ。だから教えるほうがどんなに間違った、常識をはずれたことを言っても、それを素直に、そのまま受け取ってしまいがちなんです。そうして、疑問を持たないことが習慣になっちゃうんですよ。
― さきほどの《不自然さ》ということについて説明をお願いします ―
* 習い事の師匠っていうのは、弟子にちゃんと教えるってことはしないで、自分から盗めと指導するとか、本当のことは教えないとかいいますね。そうすると、自分がさんざん苦労して、工夫、研究して身に付けたものを簡単に教えられるかっていうことで、非常にケチくさく聞こえますけどそうではないんですね。それだけ自分が研鑽したものを大切にしているということなんです。
なぜかというとね、弟子にもいろいろありますでしょ。自分でよく研究するタイプやそういうことはせずにただ教わりに通ってくるタイプなんかがね。そんな中で、弟子に師匠を選ぶ権利や自由があるのと同じで、師匠にだって弟子を選ぶ権利や自由があるんですね。大勢の弟子の中でも、自分を本当に理解して、意向を後々に伝えてくれるような、そんな才能のある弟子はそうざらにはいないんですね。そんな才能のない弟子たちに大事な本当のことを教える必要があるかってことですよね。
本当のこととか大切なことっていうのは、簡単な、あたりまえのことでね、少しも面白くないんですよ。でも、その、なんだそんなことか、と言われるようなことが実は大事なことなんですね。いかにももっともらしいことを言うと、興味を示して、やりがいを感じたりするものだから、えてして反対のことを言って、弟子の興味をひくってことはあるでしょうね。
師匠とすれば、弟子がすべて自分の真意をわかってくれるとは思っちゃいないけれど、逆のことを言ったとしても気づいてくれるのが本当の弟子であって、虚を真実と取り違えて喜んでいるのは、そう言っちゃ悪いですけど月謝を払ってくれる弟子にしかすぎないってことです。 (ちなみに黒岩先生は月謝をいただいての指導はされていません、…と思います。かつて盛んに稽古に通っていた頃でもわたしは払ったことがないもので。:筆者註)
そこで大切なことは、弟子たちが師匠の真意をどう感じるかということでね、真意を教えても曲解するような弟子には初めから教えないほうがいいんです。わからない連中に真実を曲解されることのほうがこわいことですから。反対、あるいは方向違いのことを教えても、気づいてひき返してくるのが本当の弟子なんじゃないですか。
ですからね、教えられたことを土台として、つまり、仮に不自然なことをそのまま教えられても、それに気づいて、それを土台にして新しいものを作り出さなければこの世の中では進歩しないんですね。
ただ、ここで注意しなくちゃならないことは、良い師匠に習ったからといって一足飛びに上達するものではないってことです。最初になにかを始めた人っていうのは天才的なものを持っていて、その上に努力、研究したんですから、我々凡人には到底とどかない高嶺の花ですけどさ、ここで一言加えますとね、一般的に言われる言葉で《名選手、必ずしも名コーチ、名監督ならず》ということを思い出すことも必要なんです。有名な人に習ったからといって、その人が伸びると限ったわけではありませんからね。要は本人の努力であって、はっきり言えば、師匠と弟子の上達とは無関係なんです。
でもね、良い師匠っていうのは一番大切なことを一番初めに示してくれるんですよ。これが基本であって、極意なんです。我々は極意というと特別のことを連想しますけれど、それは、ものの見方、考え方のことなの。物事は初めのところでそれをはっきりわかっていないと、極意を求めてあっちこっち探し回って、現代版チルチル・ミチルみたいなことになっちゃう。
たとえて言えば、算盤では最初に珠のはじき方を教わりますでしょ。これが基本であり極意なわけですよ。習練を積んだ算盤の名手は、特別な珠のはじき方をしているんじゃなくて、初めに習った基本を正確に速くやっているにすぎないんです。正確に速くやることは本人の努力であって、当人にとってはそれが自然のことで、あたりまえなんだけど、我々はそれを見て摩訶不思議のテクニックがあるんじゃないかと勘違いして、それを求めてしまうんですね。
今の時代はえてして、あたりまえのことを言うとバカにされて、意味のわからない観念的なことを言うともっともらしく聞こえて尊敬されるってことがあるんですね。でも、この世の中においてはあたりまえのことが特許を取れるんであって、観念的なものじゃ特許なんて取れません。そんなのは世の中に通用しないもので、えてしてその人の独りよがりになる場合が多いんじゃないですか。
― ところで、合気道におきましては一教、四方投げが基本と言われていますが、それはどういう点においてでしょうか ―
* 一教とか四方投げということを一つの技と考えて、これを鍛錬してしまいますとね、後でとんでもないことになっちゃうんですよ。一教の意味はね、自分のほうから見ると相手を《縦》に崩すということなの。二教、三教、四教は一教からの移動であって、別の言葉で言うと、一教は上段の崩し、二教は中段、三教は下段、四教は着地っていうことですね。
それから、四方投げっていうのは、自分のほうから見ると相手を《横》に崩すということなんですね。そこに今度は自分の動きが加わって深さが出て、いわゆる奥行が出てくるから、螺旋に動くわけです。
そこで、一教の意味は、相手の重心を縦に崩すことであって、それから四方投げというのは相手の体勢を横に崩すことになるわけ。ここに、縦と横でもって陰陽が出てくるわけね。
もともと、この陰陽っていうのは別々のものじゃなくって、一つのものが見方によって変わっただけなんですよ。ですからね、例えばここに横の棒を置いて、「これは横だ」って言うけど、自分が寝っころがって見れば縦に見える。ですから、もともとは一つのものなんですよ。それが縦に表れたり横に表れたりするんだけれど、本体は一つなんですね。そこのところがはっきり、一教の意味するもの、四方投げの意味するものがわからないまま、二年、三年たっちゃうと、結局ただ単なる形式的な練習に陥ってしまうことになるわけです。
合気の場合において、通常基本技として一教、四方投げという言葉を使いますけどね、大事なことは一教から四教までは縦の動き、それから四方投げは横の動きと解釈しなければいけないんです。
でも、はじめから相手を縦に崩そうとか、横に崩そうとか考えること自体が本来は不可能なことでね。やはり、この世の中っていうのは現実的にものを考えなくちゃならないし、自分一人がこの世の中に住んでいるわけじゃないんだから、たえず他との接触によって物事が表されるわけ。ですからね、自分に対する相手の動きに自分を合わせることによって、結果的に縦に表れたり横に表れたりするんで、それを縦の動きはこうだ、横の動きはこうだというふうな、一つの固定観念を持って解釈すると、どうしてもとらわれた形になっちゃうわけです。
― ところで、先生が合気道に疑問を持たれたのはいつ頃ですか ―
* 私は合気道に入ってその時に疑問を持ってしまって、それはどういうことかというと、まず、先輩の稽古の相手をして、手を持つと先輩がパッと動いた拍子に手がはずれてしまったわけね。そうすると、「しっかり持って」と言うわけ。しっかり持てば持つほどはずれてしまう。それで、その時の僕の感覚では、…皆さんが知っているように僕はもともと拳闘のほうから入ったし、若い時はあんまり他人に自慢できないことばかりやってたんですけどさ…、結局、相手の手をいつまでも持っているってことが全然考えられなっかたわけね。だから、本来だったら相手を持った手がパッとはずれちゃったら、そのまま殴っちゃえばいいわけなんだけど、どうして合気道は手を放してはいけないのかって疑問を感じたのが、まあ一日目。
それから二日、三日たっていくうちに、これは手を持っていることに何か意味があるんじゃないかなと、そしたら徹底的に相手の手を持ってやろうと思ったわけね。そういうふうに手を持っていくっていうのは、相手が動いた時に自分の足をパッと送らないと、実は相手の手を放してしまうわけね。だから自分の手を相手の手から放さないためには、絶えず自分の足を送って身体を動かしていないと、相手の手を握っていることは不可能なわけですね。
そうすると、持っているということが、どういう意味があるのかと考えて、こういうと非常に語弊がありますけれど、「あ、合気道っていうのは本当のことを教えているんじゃないな、稽古っていうのは、いわゆる本当のことじゃないな」ってことに気づいたわけですね。
ですから、稽古と実際は違うわけで、実際になるためには稽古によっていろんな体のバランスやなにかを作らなくてはなかなかできませんからね。だからそのための一つの段階として稽古というものがあるんで、稽古というのは、いわゆる《虚》ということで、これは約束事なのね。ところが、実際というのは約束がないわけだから、相手の手を持っているということ自体があり得ないのね。ただ、稽古のときは相手の手を持っているということが必要なんです。で、ここのところに一週間目くらいに気づいたわけですね。
それから、さっき言ったように徹底的に相手の手を持っていくことによって、受け身っていう意味が自分なりにわかったわけです。どういうことかといえば、受け身っていうのは、相手に投げられてたたきつけられたショックをやわらげるんじゃなくて、相手の動きを殺しちゃうのが、いわゆる受け身であって、結局、畳の上に転がるというのは投げた相手の動きを殺してしまえば、いくら相手に結果的に投げられた形をとっても、自分がショックを受けることがなんでもないわけね。そういった点で受け身の意味にも気づいたわけ。受け身っていうのは、相手の技を殺すことで、たたきつけられたショックをやわらげることではないわけね。
ちょうどその頃は若かったし、いきがっちゃったわけね。それで、もし変なのが、たとえば道場破りがきたら、戦わなくてはならないなんて、独りよがりの変な意識があったわけね。そうすると、合気に疑問だらけになっちゃったわけね。で、もし柔道のやつがきたらどうしたら良いだろうと思って、これは柔道で投げられなくてはいけないと思って、新大久保の道場に3ヶ月間通ったわけですよ。そのかわり、技は一つも覚えませんでしたけど。ただ、徹底的に投げられてね。投げられるとき、相手の一瞬のすきを見て、ここで殴ればいいと、それを研究しに3ヶ月通ったわけ。だから柔道の技は一つも覚えてないわけ。
それから今度は、なんといったって重心を崩すことが大事なんだからというんで、アマチュアレスリングを研究しに行ったんだね。で、たまたま僕の出身高校が、アマチュアレスリングが強かったんで、先輩面して、ちょっとやらせてくれって行ったわけね。そしたら一番軽いクラスのやつがきて、一発タックルでひっくり返されちゃってね。押さえられて全然動けなかった。その頃僕は、目方が80キロくらいで、むこうは40キロそこそこ。それで、これは大変だとあわてちゃったわけね。タックルっていうのは、ある意味で相手の身体にパッと飛び込んだ入り身ですからね。これはタックルを覚えなくちゃいけないというんで、高校のアマチュアレスリングへしばらく行ったわけです。
だけどこれも、決してレスリングなんて今さら習ったって間に合わないから、レスリングのやつがきたらどうすればやっつけられるかってことを研究したわけ。で、そういうことが一つの今の考え方の土台になっちゃったわけですね。ですから、よく僕らがやる投げ技っていうのは、実はタックルなんですね。ただ、たまたま体勢としては、足が入っていって、手で襟首をつかんでいるから投げになるわけね。
それからやっぱりもう一つ言えることは、前にやっていたボクシングのフックとかアッパーカットっていうのは、合気道的に考えてみたら、フックに相当するのは四方投げで、一教に相当するのはアッパーカット。これは体勢的に見て、そういうことがわかったわけね。
開祖は、「合気は全ての物を見るもとだ」とよく言われました。それは、合気をやっていれば全てがわかるんじゃなくて、合気をやることによって、全てに共通点を見出すことができるんだということですね。そして、共通点を見出すということは、他を理解できるということであり、応用できるということです。そこから結局今日のやり方が出たわけですね。
― 合気道の将来についてどう思われますか ―
* 極論すればね、合気道は植芝(盛平:筆者註)先生によってつくられ、植芝先生が亡くなったことによって消滅したんです。合気道といえるのは創始者である植芝先生のみいえるのであって、開祖に触れることのできた弟子たちは、開祖から何を学んだか、何を盗んだかであってね、開祖のほんの一部を感じただけであって、開祖の一部分のミニチュアでしかないわけ。開祖と同格、同列ではないんですよ。本来、合気道といえるのは植芝先生だけであって、弟子たちは、だれだれの合気道、その人の程度の合気道というべきであって、最近、巷でよく聞く、《正しい合気道》などというのは、開祖以外の人間の言えることではないの。弟子たちが、自分の合気道が正しいなんていうのは、開祖に対して無礼千万のことなんです。私の、自分の程度に応じた合気道ということが正しいんですね。
開祖は偉大ですからね、一人の弟子が全てを踏襲することなどできるもんじゃありませんから、大勢の弟子たちが、その人その人の才能の程度に応じて自分の合気道をやればいいんですよ。中には客観的に見て不自然なことや錯覚もありますけどね、その人が正しいと思っているならそれはまあ仕方がないことなんですね。
現在合気道を習っているほぼ100パーセントの人たちは生前の開祖を見たことがなくて、幸いにも開祖に触れることのできた、直接に指導を受けたことのある人は0パーセントに等しいのが現状なんですね。古い人々が、「私は開祖から直に教えを受けた」なんて誇らしげに語ったりしてね、またそれが、その人を権威づけるような時代は既に終わりにきてるんですよ。
これからは古い弟子たちが、開祖から何を感じたか何を吸収したかで、開祖を知らない後輩の人々から批判されたり評価されたりする時代にきてるわけ。すでにね、開祖を知らない世代の指導者がたくさん出てきていて、その人々の時代に移行しているのであって、もう開祖を知っている弟子たちが威張っている時代ではありませんよ。開祖を知らなければ合気道を指導できないなんてことはなくって、むしろ、開祖を知らない世代から優秀な指導者が出てくることが必要なんです。
そのためには、古い弟子たちが、新しい人々にどのような伝え方をするかが、これからの合気道の発展につながる必要重大事なんです。
― 最後に、《技》についての見解をお聞かせください ―
* 習い事でよく、技を習えばとか、技を身につければとかいうことをよく聞きますけどね、技は独立して一人歩きするものではないの。その人、個人のものなわけね。その前にまず、《型》、《形》、《技》それぞれを理解することが必要なわけ。《型》っていうのはね、合理的な動きのコースおよびルールを示すものなの。《形》っていうのは、人間が《型》を表現したもの。《技》は《形》×人間、この場合の人間っていうのは修錬の程度っていうことですけど、これを理解することが必要なのね。
たとえば、電算機にあてはめてみると、電算機が型であって、人間がキーを押すことによって電算機が作動するのが形で、電算機を操作する人の修錬の度合いによって電算機が活用されのが技になるわけ。電算機の扱いが下手な人は能率も低いけど、上手な人は能率が上がるわけですよ。電算機がどんなに合理的にできていても扱う人の修錬の程度によって能率に高い低いが現れるのと同じ。これは、あたりまえであって、誰にもわかることでしょ。扱う人の個々のものなんですよ。
ある人が道場に見学に来たとしますでしょ。そこで初心者ばかりで四方投げや一教を下手くそにやっていたとすると、その人は、四方投げや一教をなんとくだらないと思いますね。有段者ばかりがやっているのを見ると、なんと素晴らしいと感心するでしょ。ですからね、どんなに合理的にできた電算機でも、型でも、使う人の程度によって決まるのであってね、電算機や技が一人歩きすることはないんですね。
ところが我々は、優秀な電算機を買えば、どんな計算でもできるように思うのと同様に、四方投げや一教を知れば、それですぐに相手を投げられると錯覚するわけ。電算機も四方投げも、ただ持っていたり知っているといっても何の価値もないんですよ。ですからね、基本である四方投げや一教を、いたずらに、初心者に大切だ大事だと、かたちばかり練習させても、合理的な意味を教えなければ、それこそ意味がなくって、むしろ害があるんですよ。
基本の稽古は技を練習するのではなくて、型を通して各人が自分の技をつくるんです。たとえば、図形は直線が大切だといって、直線が正しく描ければ円や三角、四角などが描けると思って直線ばかり描いているのは間違いでしょ。その反対に、直線の大切さを知るために三角や四角やその他をいろいろと描きながら直線の大切さを理解することが大切なんです。
だから、いろいろな形を経験することでね、一教、四方投げの大切さがわかってくるんですね。同時に、どんな動きも形も一教であり四方投げであること、つまり一つの動きの変化にすぎないっていうことがわかってくるの。
従って、稽古で、一教、四方投げその他の基本といわれるものばかりやるのは愚の骨頂でね、一教がわかればすべてがわかるなんていうのに至っては、これはもうどうしようもない病気ということになるね。
小学校の算数でも応用問題をどんどんやるのは、応用問題は基本の展開なんだから基本を確認することになるからでしょ。稽古でもいろいろな形を経験することによって基本の大切さが理解されてくるわけです。もっとも、基本ばかりやっていれば、教えるほうにとっては楽ですけどね。
さっき、技っていうのは《形×人間》だと言いましたけど、試合のあるものは必ず人の名前が付いてるんですね。たとえば、柔道を習っている人はだれでも内股っていうのを知っていて、練習もするでしょ。でもね、山下の内股っていいますし、同様に相撲なら千代の富士の上手投げといいます。けっして、内股、上手投げという技を知っているから強いとは言わない。ということは、型をその人なりに使いこなすのが技ということなわけ。型は教えられても中身は自分で作るしかないんです。また、山下選手や千代の富士関とそっくり同じ格好やかたちをすれば、どんな相手でも投げることができると思う人は通常いないんですけどさ、案外、試合のない世界の人の中には、それができると思っている人がいるんですよ。試合のない世界では型を絶対視する傾向があって、その結果なんですね。
教えるほうは型を通してしか教える方法はないんですが、えてして教わるほうは、教えるほうのしぐさや癖ばかりを真似てしまう傾向があって、肝心な基本、型を見逃してしまうんですね。ですからね、教えるほうが、型や基本の意味を具体的に理解させることが大事なわけ。
もう一つ、背広を例にとって言うとね、日常の生活での人間の動作が活動的に、能率的になるように合理的に作られているのが背広の型、原型でね、それを着る一人ひとりの体型にによってS、M、Lとかその他のサイズになるのが形で、その人の体格に合った服をどう着こなすかっていうのがその人の技なのね。どんなサイズも合理的な原型っていうものから作られているわけ。それでもって、さらに服を求める人の好みで、着心地の良さ、これは能率性とか合理性ね、それとブランド、これは知名度だけど、これを求めるか、あるいは派手なアクセサリーや付属品みたいな神秘性に目を奪われるかによって、背広の選び方も多少違ってくるわけです。
合気道においても、その人が何を求めるかによって同じことが言えるのね。でもね、どんなに高価な材質や縫製であってもさ、その人の体型に合わなくてブカブカではどうしようもないでしょ。大人が子供服を着ては身体の自由が奪われますよね。反対に、子供が大人の服を着ても自由が奪われますよ。大人の場合は視野の狭さっていうか頭の固さで、子供の場合は大きすぎで分不相応っていうか、もてあましちゃうよね。そしてまた、同じサイズのものを大人、子供に関係なく着せられては、着せられるほうが迷惑っていうもんです。その人に合った服を着て、ということはその人の程度に応じて、その人なりに活動することが常識なんです。合気道もまったく同じなんですよ。
物事を説明するのに、高尚な宗教や哲学や理論に依らなければ理解できない、解決できないなんてことはないの。合気も同じことで、目の前にあることで説明できなくちゃいけないし、むしろそういうことが必要なんです。材料はいくらでもありますよ。たとえばほら、いま流行っているタモリの《ワ》で十分に説明できるんですよ。ワは《和》であって《輪》でしょ。和は考え方つまり精神や心で、輪は見方つまり理論や肉体ですよ。
====================================
原文はまだこの先も続くようですが、私の手元にあるのは以上です。しかし、黒岩先生のお考えの最も肝心なところは、ここまでで十分お汲み取りいただけたのではないかと思います。
先生は、すでに1983年の時点で、開祖の直弟子だからと威張ってる時代ではないとおっしゃっていますが、そうは言ってもやはりそのようなお立場の方でないとわからないこともたくさんあるように思われます。
それからさらに25年経ち、本部師範を務められた方で今なお現役で指導されているのは、黒岩先生より年長の方では多田宏先生くらいになってしまいました。後に続くわたしたちが、今こそそのような先生方から何を学ぶべきか、そこに合気道の将来がかかっているということを本文で先生はおっしゃっています。
読者の皆様それぞれがお考えいただき、弛まぬ精進の末、ご自分の合気道を確立されますよう期待いたします。












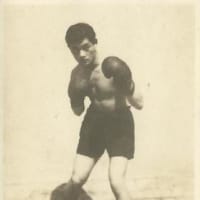
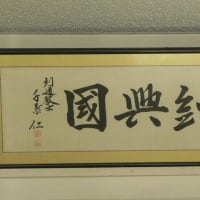
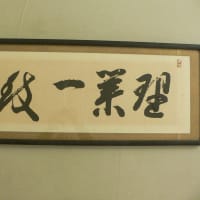





非常に勉強になりました。
私は実践的な武道として合気道に興味がありましたので、
当初は型稽古には疑問でした。
技の意味を合理的に説明していただける、素晴らしい先生に
出会うことができましたので、虚の稽古の重要性も理解できました。
しかし、合気道はいろんな人がいろんなことを言うので、
体の動かし方や基本動作の意味を理解していない人は
混乱して、なんとなくやってしまうような気がします。
開祖は「技は無限」とおっしゃっていますが、それは基礎が
あってこそだと思います。
技の振付を習うよりも、体捌きを学ぶ方が、逆に上達への
近道だと私は思います。
これからも、初心を忘れずに、常に疑問を持って稽古に
精進したいと思います。
今回の記事を喜んでいただいて、とても嬉しく思います。
自分で読み返しても、なるほどなと納得するようなことがたくさんありました。自分が《選ばれた弟子》なのかどうかは実に微妙なところですがね。
体捌きは、おっしゃる通りとても大切なものだと思います。そのため、わたくしの稽古でも、体捌きの根幹である足遣いを重視しています。
初心者様は、そのお名前のわりには、よくおできになる方なのだろうと思っていましたが、コメントの終わりのところの、《初心をわすれず》ということがその由来なのだとわかりました。
やっぱり、初心や初手が大切なんですよね。
お考えの趣は理解できます。わたくしは、先生の技法やお話は授ける相手を選ぶ性質のものだという認識を持っており、そういう意味からすると、《破》の段階にあるひとにこそふさわしいのかもしれません。
わたくしにはかつて、未熟者ながら疑問だらけの合気道に見切りをつけようかと考えていた時期があります。それでもなんとか疑問を解こうと、あっちの先生こっちの先生と巡り歩いたものでした。1週間に8人の先生の指導を受けたこともありました。
そんな中で出会ったのが道場の先輩の紹介で伺った黒岩先生で、そこで、それまで見たことも聞いたこともない理論や技法を示され、合気道の価値を再認識したという経験があります。
駄弁になりますが、わたくしは先生が指導されている立教大学合気道会の皆さんの前で次のようなことを言ったことがあります。それは、『皆さんは不幸です。なぜならば、皆さんは合気道入門の最初のところから先生の指導を受けているからです。それでは合気道に疑問を持つこともなく、疑問がないのであれば、それへの解答もないからです。なぜ先生の理法が素晴らしいかは、よその合気道をやってみるとわかります』というようなことでした。それこそお節介というものですが、わたくしの本音でもあります。
先生ご自身もおっしゃっているように、黒岩理論が絶対だなどというべきものではありませんが、そのような視点から合気道を捉えておられる方が他に見当たらない現状では、すぐれて貴重な理法として、わたくしは大切にしていきたいと考えています。
>一教とか四方投げということを一つの技と考えて、これを鍛錬してしまいますとね、後でとんでもないことになっちゃうんですよ。一教の意味はね、自分のほうから見ると相手を《縦》に崩すということなの。・・・それから、四方投げっていうのは、自分のほうから見ると相手を《横》に崩すということなんですね。そこに今度は自分の動きが加わって深さが出て、いわゆる奥行が出てくるから、螺旋に動くわけです。
つまりは、一教とか四方投げとか個別に考えるではなく、縦の崩し、横の崩しを学ぶということで考えたほうがいいということですか?
例えば、呼吸投げにもその縦や横の崩しの要素が入っているし、特に多人数掛けの場合、通常稽古している技とは異なるような投げ方捌き方にも、それらの「崩し」が関係するということでしょうか?
尤も、必ずしも「崩し」が関与しない場合もあるとは思いますが。
現在は氣という用語を発しただけで、神秘、難解、独善、眉唾という反応の見られることが目立ってきていると感じますし、昔ほど氣と言わなくなっているようにも思います。黒岩師範が、あるとき突然「合氣道は氣の武道だ」とおっしゃったとすればどうでしょうか。今思えば不思議なことですが、師(故人)は30年近い指導の中でたった一度こうやって氣という語を使われました。その後でまたいつものように黙々と私たちを畳にめり込ませるような、それでいて絶妙の紙一重の差で体を気遣ってくれる指導をされました。それ以後私は次第に、深い吸気で上肢を伸ばして開いたときを、氣を出すと言い、十分息を吐いて上肢をゆったりと丹田に降ろしたときを、気を入れると略するようになりました。もっと省略して氣を出すことを陽の氣、氣を入れることを陰の氣と指導稽古のときに咄嗟に出ます(古いんでしょうかね)。一教の裏で受けの上腕に取りの上肢が十分に伸びていない瞬間は、「(左手は)陽」とか「氣を出せ」とか言ってしまいます。単なる深呼吸ではなく、このようなイメージをあえて持ちながら呼吸を行うとき、これを単独動作の呼吸法とよんでいます。上肢を伸ばせば息を吸い、体の中心に腕を引き寄せるときは自然に息を吐く、あるいは息を吸えば上肢が伸び、吐けば上肢が弛緩して丹田に戻る。あたりまえのことが身に付けられるよう、合氣体操の一部として行っています。もちろん呼吸や緊張・弛緩を維持できるように稽古としてイメージするだけで、氣の存在が物理的に技を作っているような観念までは持ち得ません。
おっしゃる意味、よくわかりました。
黒岩先生は通常の稽古で気という言葉を使いませんでした。技法説明に≪気≫を乱発しておられたある方に対する、それこそアンチテーゼだったのかもしれませんが、気そのものを否定しておられたわけではありません。
いずれにしても、気は合気道の理念における中核的観念であり、だからこそ大事に取り扱われるべきものでありましょう。それが変に重宝に使われて、合理的説明をしないのは指導者の怠慢だと思っております(最新項でもちょっと触れていますが)。
その点、katsuhayahi 様の言葉と技法の関係性に得心いたしました。それと、真剣に合気道に取り組んでおられる様子も伝わってまいりました。
そのようなことも含め、ここにコメントをお寄せくださる方々から教えられることは多く、スタンスに若干の差異があるのは当然のこととして、同じ道を歩む者どうし、刺激しあい、尊重しあう間柄でありたいと願っております。