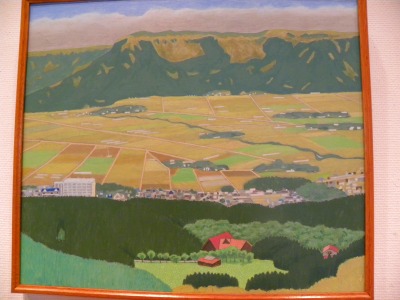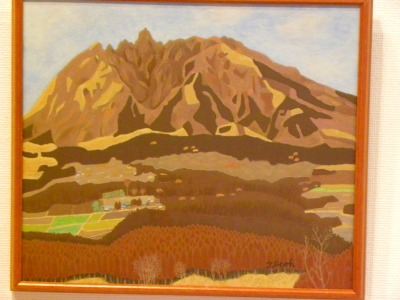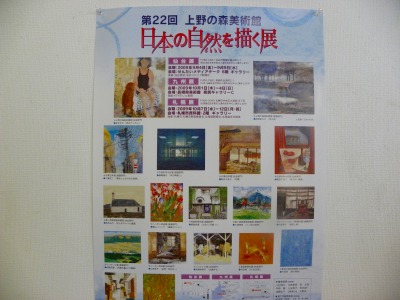“うめんつあん”の指導を受けて「ハタケシメジ」を植えた。

この袋の中に菌床が入っている。ムラサキシメジの時と同じだ。
袋から出した菌床を並べ、板で枠をして回りに土を入れる。

上に鹿沼土をかけて水をかける。

最後に乾燥を防ぐために、刈っておいたススキをかけて終了。
それから、1個植えをして菌が広がっていかないかを実験。

このほか、鹿沼土を使わないで畑の土だけでも実験をする予定。
また、浜の畑にも植えてみようとも考えている。
実験ができるって楽しいなぁ・・・

この袋の中に菌床が入っている。ムラサキシメジの時と同じだ。
袋から出した菌床を並べ、板で枠をして回りに土を入れる。

上に鹿沼土をかけて水をかける。

最後に乾燥を防ぐために、刈っておいたススキをかけて終了。
それから、1個植えをして菌が広がっていかないかを実験。

このほか、鹿沼土を使わないで畑の土だけでも実験をする予定。
また、浜の畑にも植えてみようとも考えている。
実験ができるって楽しいなぁ・・・