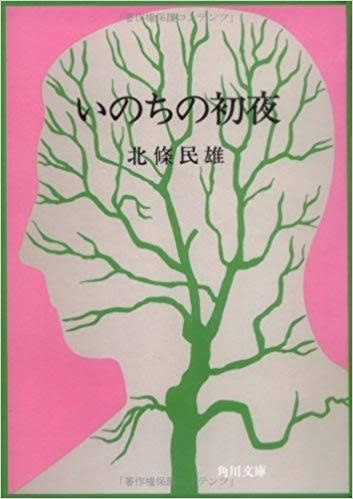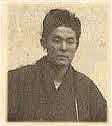ハンセン病(らい病)の特効薬として有名なプロミン。
人類の歴史と共に存在し、絶対に治らない病気として知られ、
その恐ろしさから、悪魔の様に嫌われ忌避され続けた病気、らい病。

1873年、ノルウェーのアルマウェル・ハンセンが(らい菌)を発見しました。
それによって、遺伝と言われたらい病が、
らい菌による伝染病である事が分かったのですが、
らい病は、遺伝病であるという迷信がくつがえるには至らず、
その迷信ゆえに多くのらい病患者達は悲惨な思いの中で生きるしかありませんでした。
人々は何とか治療薬は無いものかと試行錯誤しましたが、
結局どうにもなりませんでした。
特効薬の発見により治る病気になるまでは膨大な時間がかかりました。

治療薬を開発したくても、試験管での培養が出来ないので、お手上げでした。
唯一、培養が可能だったのはアルマジロを試験管に見立てての方法でした。
それでも特効薬開発には至りません。

大風子(だいふうし)という木の種から採った薬(大風子油)がありました。
大風子油を筋肉に注射するのですがとても痛く、効き目があるのかも分かりません。
しかし殆んど治療にはならず気休め程度でした。
そうと分かってはいても他に方法が無いのですから、人々はそれをやるしかなかったのです。
とても痛い大風子油治療などやっても意味は無いと、
サジを投げあきらめる患者も多数いました。
人の尻の肉を食べると治る言われ、実際に殺されて食べられてしまった人もいたのです。
つまり、らい病というのはそのくらい治らない病気だったのです。
特効薬が発見されたのは偶然からでした。

ハンセン病と結核とは、マイコバクテリウム属の細菌(らい菌と、結核菌)
によって引き起こされる事が既に知られていた事に目を付け、
アメリカ、ルイジアナ州のカーヴィルにあった、
国立ハンセン病療養所のガイ・ヘンリー・ファジェット医師は、
1937年に最初にプロミンを合成した、
パーク・デイヴィス社の医師達から情報を集め、
プロミンに類似した薬「スルオーキソンナトリウム」で、人体への治験を開始しました。
その結果、プロミンがハンセン病治療に有効である事が分かったのです。
それは、まさに奇跡と呼ばれるほどの効果を発揮し、
ハンセン病患者達に絶大な希望を与えたのです。
それは「カーヴィルの奇跡」と言われました。
1941年、新しく導入した薬プロミンが、
遂に恐るべき業病、らい病(ハンセン病)の歴史を塗り替えたのです。
日本では1943年(昭和18年)東大医学部の、
石館守三郎教授が、プロミンの合成に成功しました。
日本では。1907年(明治40年)から、ハンセン病患者を
収容する隔離施設を設け、
ハンセン病患者はそこから一歩も外に出る事を禁じられました。
何も悪い事をした訳でもないのに、患者達への扱いは犯罪者なみでした。
特効薬によって感染の危険性が無くなってからも政府は法律を変えず、
隔離政策を撤廃したのは1996年になってからで、
時の厚生大臣、菅直人が正式に謝罪をしました。
しかし、あまりにも長期間人権無視政策を続け、数多くの悲劇を生みました。
らい菌の感染力はとても弱く、感染しても発病に至らない事が大多数です。
例え感染が分かっても特効薬により、過去の病気になりました。
しかし、暑い国では未だに発病患者がいるのです。
そしてハンセン病患者への偏見が完全に払拭されたとは言えない国もまだ存在します。
ハンセン病(らい病)は人類が経験した病気でも、
トップクラスの恐ろしさと、悲劇を生み続けた病気でした。
この恐ろしい病気が治る様になった事は、本当に素晴らしい出来事です。
人類の歴史と共に存在し、絶対に治らない病気として知られ、
その恐ろしさから、悪魔の様に嫌われ忌避され続けた病気、らい病。

1873年、ノルウェーのアルマウェル・ハンセンが(らい菌)を発見しました。
それによって、遺伝と言われたらい病が、
らい菌による伝染病である事が分かったのですが、
らい病は、遺伝病であるという迷信がくつがえるには至らず、
その迷信ゆえに多くのらい病患者達は悲惨な思いの中で生きるしかありませんでした。
人々は何とか治療薬は無いものかと試行錯誤しましたが、
結局どうにもなりませんでした。
特効薬の発見により治る病気になるまでは膨大な時間がかかりました。

治療薬を開発したくても、試験管での培養が出来ないので、お手上げでした。
唯一、培養が可能だったのはアルマジロを試験管に見立てての方法でした。
それでも特効薬開発には至りません。

大風子(だいふうし)という木の種から採った薬(大風子油)がありました。
大風子油を筋肉に注射するのですがとても痛く、効き目があるのかも分かりません。
しかし殆んど治療にはならず気休め程度でした。
そうと分かってはいても他に方法が無いのですから、人々はそれをやるしかなかったのです。
とても痛い大風子油治療などやっても意味は無いと、
サジを投げあきらめる患者も多数いました。
人の尻の肉を食べると治る言われ、実際に殺されて食べられてしまった人もいたのです。
つまり、らい病というのはそのくらい治らない病気だったのです。
特効薬が発見されたのは偶然からでした。

ハンセン病と結核とは、マイコバクテリウム属の細菌(らい菌と、結核菌)
によって引き起こされる事が既に知られていた事に目を付け、
アメリカ、ルイジアナ州のカーヴィルにあった、
国立ハンセン病療養所のガイ・ヘンリー・ファジェット医師は、
1937年に最初にプロミンを合成した、
パーク・デイヴィス社の医師達から情報を集め、
プロミンに類似した薬「スルオーキソンナトリウム」で、人体への治験を開始しました。
その結果、プロミンがハンセン病治療に有効である事が分かったのです。
それは、まさに奇跡と呼ばれるほどの効果を発揮し、
ハンセン病患者達に絶大な希望を与えたのです。
それは「カーヴィルの奇跡」と言われました。
1941年、新しく導入した薬プロミンが、
遂に恐るべき業病、らい病(ハンセン病)の歴史を塗り替えたのです。
日本では1943年(昭和18年)東大医学部の、
石館守三郎教授が、プロミンの合成に成功しました。
日本では。1907年(明治40年)から、ハンセン病患者を
収容する隔離施設を設け、
ハンセン病患者はそこから一歩も外に出る事を禁じられました。
何も悪い事をした訳でもないのに、患者達への扱いは犯罪者なみでした。
特効薬によって感染の危険性が無くなってからも政府は法律を変えず、
隔離政策を撤廃したのは1996年になってからで、
時の厚生大臣、菅直人が正式に謝罪をしました。
しかし、あまりにも長期間人権無視政策を続け、数多くの悲劇を生みました。
らい菌の感染力はとても弱く、感染しても発病に至らない事が大多数です。
例え感染が分かっても特効薬により、過去の病気になりました。
しかし、暑い国では未だに発病患者がいるのです。
そしてハンセン病患者への偏見が完全に払拭されたとは言えない国もまだ存在します。
ハンセン病(らい病)は人類が経験した病気でも、
トップクラスの恐ろしさと、悲劇を生み続けた病気でした。
この恐ろしい病気が治る様になった事は、本当に素晴らしい出来事です。