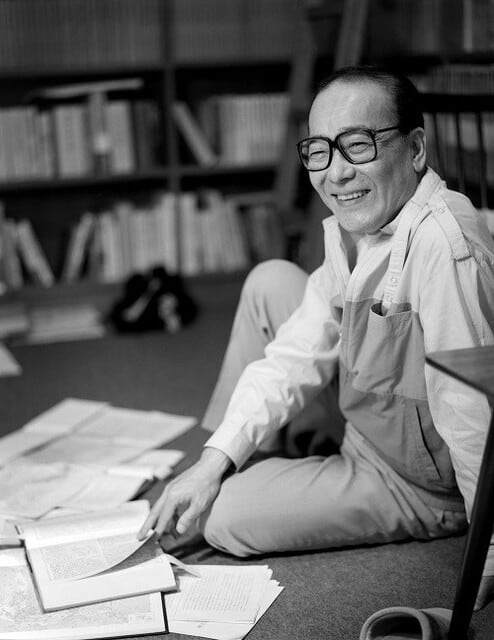集英社の、少年少女世界名作の森15「巌窟王」を買いました。
日本では「巌窟王」として通っていますが、これの元本は「モンテクリスト伯」です。
私が初めてこの本を読んだのは、中学生の時だったと思います。
その頃あった「中学生コース」あるいは「中学時代」
といった月刊誌の付録の小冊子だった様な気がします。
それは勿論ペラペラの紙質もわら半紙みたいな本だったと思います。
しかし、たったそれだけの本に私は心を奪われて、夢中になって読んだのでした。
その思い出が強烈で、18か19歳くらいの時に、
いよいよ本物の「モンテクリスト伯」を買いました。
文庫本サイズで全7巻の大作です。
もう、それこそ寝食を忘れて、夜も寝ずに、目を真っ赤にして読みまくりました。
読み終わるのに何日かかったか記憶にありませんが、
全てを読み切った時の感動、呆然として頭の中がカラッポになってしまいました。
本を読んであれほど感動した事は、後にも先にありません。
それから、もう一回か2回くらい読み返したのかも知れません。
40歳くらいの時だったか、知り合った、あれは通産省の役人だったかに、
その感動を語り、彼にその本を貸したのですが、
色々生活の変化などがあって、彼とも有耶無耶になってしまい、
その本はそれっきりになってしまったのです。
その残念さ、無念さが心にずっと尾を引いてしまいました。
それでそれを買い直しました。
税込み7000円以上したのですが、嬉しかったですね~。
心が純粋な時代に感動した本は、忘れられるものではありません。
それから読み直す事、今回で多分5回目。
まだ3巻目ですが・・そんな時、フト思ったのです。
「あのダイジェスト版の(巌窟王)を読み直したいと」
と言うのは、ダイジェスト版の方が分り易いという一面があるのです。
元本では哲学的会話で分りにくい場面も、
「あ、つまりこういった事が言いたかったんだな」とか、
19世紀当時のフランス、イタリアの政情などが理解しやすかったり、
金銭感覚が現代と比較しやすかったり、
金銭感覚が理解出来ていないと、小説としては失格なんですね。
例えば千フラン・・これは100万円と書き換えると、
「あ~、なるほどそういった価値か」と理解度が深まるのです。
そういった意味でもダイジェスト版には、かなりの価値があります。
当時のパリの人口は約90万人。
と言えば、つまり現在の仙台市くらいなんだなとか、
パリ、マルセイユ、ジェノバ、モンテクリスト島、ローマといった位置関係、
その距離(当時の移動手段は馬車)だった事を考えると、
その時間、日数などが具体的に分かるのです。
ダイジェスト版は1時間か1時間半もあれば読み切ってしまいます。
ですが、中学生だった私は、たったこれだけの本に夢中になり、
それが後々の人生にまで影響を与える事に、本の持つ(凄さ)を感じるのです。
我が妻エリカ殿は、こんなカタカナばかりの小説など見向きもしません。
彼女は江戸時代に酔っています。
それはそれとして認めない訳にはいきません。
ですが、これはヨーロッパの物語です。
それを日本人などがテレビにしたり映画にしたり、
そういった馬鹿げた行為だけは絶対に許せません。
それは、宮本武蔵と佐々木小次郎の巌流島の決闘。
徳川と豊臣が天下を競った関ケ原の合戦を、白人たちが演じているのと同じで、
あまりの愚劣さに言葉もありません。
どうか、こういった絶対的な勘違いだけは、やめにして頂きたい。
汚らわしいのです。
こういった圧倒的な本を読むと、
毎日テレビでやっているサスペンスドラマの薄っぺらさが気になります。
犯人を逮捕した時点でドラマは円満に終了。
しかし、犯人に家族を、家庭を取り返しの尽かない状態にされた被害者は、
それで(満足・気が済む)のでしょうか?
そこには被害者達の(悩める心)が無い気がします。
巌窟王(モンテクリスト伯)はそこからが本当のドラマなんです。
今回は5回目の読破ですが、
まだ多分・・・あるのかも知れません。