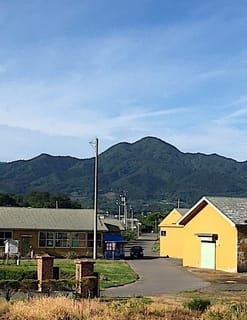またまた名久井農業高校自慢のモモが学校に並びました。
先月下旬に販売されていたのは「あかつき」という品種。
皆さんが期待しているのはこれから収穫は始まる「川中島」。
実はこのモモは、この2つのモモの間を埋める品種で「まどか」といいます。
資料ではこのまどか、品種登録がされておらず
そのかわり「まどか」という名前を商標登録しているとあります。
真偽はわかりませんが、そうだとしたらなかなか面白い品種です。
さて大昔、夏休みの学校に地元の小学生から電話がかかってきました。
農場長の先生が電話に出たのですが、モモについての質問とのことでした。
聞き耳を立てて聞いていると、質問内容がもれ聞こえてきました。
なんと質問は「どうしてモモのタネは赤いのか」。
農業の先生方がたくさん近辺にいましたが
みんな顔を見合って首を振っています。
なぜ赤いのか、そういえば果肉にも赤い筋があります。
でもなぜ赤いのかは考えたこともありません。
あの時、小学生から出された宿題は
恥ずかしながらまだ解けていません。
先月下旬に販売されていたのは「あかつき」という品種。
皆さんが期待しているのはこれから収穫は始まる「川中島」。
実はこのモモは、この2つのモモの間を埋める品種で「まどか」といいます。
資料ではこのまどか、品種登録がされておらず
そのかわり「まどか」という名前を商標登録しているとあります。
真偽はわかりませんが、そうだとしたらなかなか面白い品種です。
さて大昔、夏休みの学校に地元の小学生から電話がかかってきました。
農場長の先生が電話に出たのですが、モモについての質問とのことでした。
聞き耳を立てて聞いていると、質問内容がもれ聞こえてきました。
なんと質問は「どうしてモモのタネは赤いのか」。
農業の先生方がたくさん近辺にいましたが
みんな顔を見合って首を振っています。
なぜ赤いのか、そういえば果肉にも赤い筋があります。
でもなぜ赤いのかは考えたこともありません。
あの時、小学生から出された宿題は
恥ずかしながらまだ解けていません。