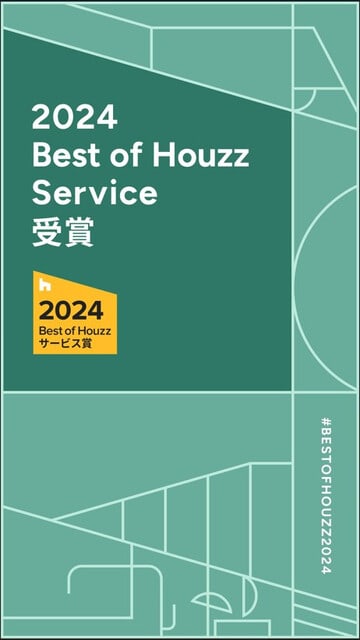奈良で暮らすという選択肢。

※ガレージライフと広い庭で過ごす風景と遊びを楽しむ家

※LDKから続くウッドデッキはテラス的な空間としてBBQやブランチ、自立ハンモックなどで遊びのスペースに

※夜の静かな時間に灯りの風情を愉しみつつ星空を眺める憩いの暮らし提案
新築や中古住宅を購入しての
リフォームについて、
奈良県外から奈良への移住について
ご相談をいただく事もあります。

※明日香村の広大な風景と風情を満喫する和の暮らし

※日常的なゆとりを心地よく愉しむ夜の灯りや静かな夜の時間を提案
奈良公園や東大寺、明日香の風景や
吉野の歴史等
観光資源がたくさん保有する古都・奈良。
最近は個性的なお店も増え、
ますます注目度も高まっています。
自然にも恵まれた環境や、
関西都市圏へのアクセスの良さもあり、
「暮らす街」としても
年々人気が高まってきています。
実際、やまぐち建築設計室で
設計監理を手掛けさせていただいた
すまい手OB様・OG様の中にも
奈良に住み、
大阪や京都で働くという
暮らし方をされている方も多くいらっしゃいます。
また、
自然を身近に感じられる環境や景色が多く、
その上都市圏に比べると
土地や物件も比較的手頃な価格で、
「理想の暮らし」を手に入れやすいのも、
奈良ならではだったりします。
そこで、
これからの暮らしを考えはじめたとき
「奈良で暮らすこと」に
興味をお持ちの方を対象に、
自分たちが理想とする方々。
暮らしやライフスタイルをまずはじっくりとお聞きし、
住まいづくりのお手伝いを致します。
もちろん、
暮らすという視点での
街の魅力も合わせてお伝えできればと思います。
土地・物件探しから、
新築注文住宅、
戸建て・マンションリノベーションまでご相談可能です。
「暮らす」という視点での奈良の街の良さとは?
①比較的ゆったりとした敷地が多く、
伸び伸びと暮らせる
都市部では狭小地が多く、
庭や2台以上の駐車場の
確保も難しいのが現状です。
奈良では、
比較的ゆったりとした敷地が多く、
場所にもよりますが
お隣さんとの距離も十分に確保されます。
お庭やテラスも取れるので、
BBQやガレージライフ、
プール遊び等も。
②無理のない資金計画
都市圏に比べると比較的手頃な価格で、
物件や土地を
手に入れることが可能なため、
ご予算の中で、
理想の住まいづくり
やりたかったことが実現しやすいです。
③暮らしやすい生活環境
自然や緑に囲まれた環境だったり、
生活圏も近かったりしても
比較的ゆったりと過ごすことができます。
また住宅街であっても、
道幅も広く取られている地域も多いため
運転が苦手な方でも安心感のある地域も多いです。
都市機能(スーパーや病院、銀行など)も充実しており、
日常生活にも環境の良い状態で
馴染むことも出来ます。
④関西都市圏までのアクセスの良さ
大阪中心部まで、
電車で約20分(近鉄生駒駅より急行の場合)でいけます。
通勤通学にも便利な街です。
参考:JR王寺駅〜JR難波まで、約30分、
大和八木駅〜鶴橋駅まで、約40分
奈良での暮らしを
イメージしてみませんか?
住まいの新築・リフォーム
リノベーションのご相談・ご質問・ご依頼は
■やまぐち建築設計室■
気軽にご連絡ください。
-------------------------------------
■やまぐち建築設計室■
建築家 山口哲央
奈良県橿原市縄手町387-4(1階)
-------------------------------------