最後の演説のシーン。英文で紹介します。
I'm sorry but I don't want to be an Emperor. That's not my business.
I don't want to rule or conquer anyone.
I should like to help everyone if possible, Jew, gentile, black man, white.
We all want to help one another, human beings are like that.
We all want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another.
In this world there is room for everyone and the earth is rich and can provide for everyone.
The way of life can be free and beautiful. But we have lost the way.
Greed has poisoned men's souls has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed.
We have developed speed but we have shut ourselves in, machinery that gives abundance has left us in want.
Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind.
We think too much and feel too little,
more than machinery we need humanity,
more than cleverness we need kindness and gentleness,
without these qualities, life will be violent and all will be lost.
The aeroplane and the radio have brought us closer together.
The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood for the unity of us all.
Even now my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women and little children,
victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.
To those who can hear me, I say "Do not despair".
The misery that is now upon us is but the passing of greed,
the bitterness of men who fear the way of human progress,
the hate of men will pass and dictators die,
and the power they took from the people will return to the people,
and so long as men die, liberty will never perish.
Soldiers, Don't give yourselves to brutes,
men who despise you and enslave you - who regiment your lives,
tell you what to do, what to think and what to feel,
who drill you, diet you, treat you as cattle, as cannon fodder.
Don't give yourselves to these unnatural men, machine men, with machine minds and machine hearts.
You are not machines. You are not cattle.
You are men.
You have the love of humanity in your hearts.
You don't hate, only the unloved hate. Only the unloved and the unnatural.
Soldiers! Don't fight for slavery, fight for liberty.
In the seventeenth chapter of Saint Luke it is written "the kingdom of God is within man" -
not one man, nor a group of men - but in all men - in you, the people.
You the people have the power, the power to create machines, the power to create happiness.
You the people have the power to make life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.
Then in the name of democracy let's use that power - let us all unite.
Let us fight for a new world,
a decent world that will give men a chance to work, that will give you the future and old age and security.
By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie.
They do not fulfil their promise, they never will.
Dictators free themselves but they enslave the people.
Now let us fight to fulfil that promise.
Let us fight to free the world, to do away with national barriers, do away with greed, with hate and intolerance.
Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness.
Soldiers! In the name of democracy, let us all unite!
Hannah, can you hear me?
Wherever you are, look up Hannah.
The clouds are lifting, the sun is breaking through.
We are coming out of the darkness into the light.
We are coming into a new world.
A kind new world where men will rise above their hate, their greed and their brutality.
Look up Hannah.
The soul of man has been given wings - and at last he is beginning to fly.
He is flying into the rainbow - into the light of hope, into the future,
the glorious future that belongs to you, to me, and to all of us.
Look up hunna. Look up.

申し訳ないが、私は皇帝になどなりたくない。私には関わりのないことだ。支配も征服もしたくない。できることなら、皆を助けたい。ユダヤ人も、ユダヤ人以外も、黒人も、白人も。私たちは皆、助け合いたいのだ。人間とはそういうものなんだ。お互いの幸福と寄り添いたいのだ……。お互いの不幸ではなく。憎み合ったり、見下し合ったりしたくないのだ。世界で全人類が暮らせ、大地は豊かで、皆に恵みを与えてくれる。人生は自由で美しい。
しかし、私たちは生き方を見失ってしまった。欲が人の魂を毒し……。憎しみと共に世界を閉鎖し……。不幸、惨劇へと私たちを行進させた。私たちはスピードを開発し、自分たち自身を孤立させた。ゆとりを与えてくれる機械により、貧困を作り上げてしまった。知識は私たちを皮肉にし、知恵は私たちを冷たく、無情にした。私たちは考え過ぎ……。感じなさ過ぎる。
機械よりも、人類愛が必要なのだ。賢さよりも、優しさ、思いやりが必要なのだ。そういう感性なしでは、世の中は暴力で満ち、全てが失われてしまう。飛行機やラジオが、私たちの距離を縮めてくれた。そんな発明の本質は、人間の良心に呼びかけ、世界がひとつになることを呼びかける。
今も、私の声は世界中の何百万の人々のもとに届いている。何百万もの絶望した男性たち、小さな子供たち。人々を苦しめる組織の犠牲者たち。罪のない人たちを投獄させる者たち。私の声が聞こえている人たちに言う……。絶望してはいけない。私たちに覆いかぶさる不幸は、単に過ぎ去る貪欲であり、人間の進歩を恐れる者たちの憎悪なのだ。
憎しみは消え去り、独裁者たちは死に絶えるであろう。人々から奪いとられた権力は、人々のもとに返されるだろう。決して人間が永遠に生きないように、決して自由が滅びることもない。
兵士たちよ。獣たちに身を託してはいけない。君たちを見下し、奴隷にし、人生を操る者たちは、君たちが何をし、考え、感じるかを指図する。君たちを鍛え、食事を制限する者たちは、君たちを家畜として、ただのコマとして扱うのだ。身を託してはいけない。そんな自然に反する者たちなどに。機械人間たち……。機械のマインドを持ち、機械の心を持つ者たちなどに。
君たちは機械じゃない。君たちは家畜じゃない。君たちは人間だ。心に人類愛を持った人間だ。憎んではいけない。愛されない者が憎むのだ。愛されず、自然に反するものだけだ。
兵士よ。奴隷を作るために闘うな。自由のために闘え。『ルカによる福音書』の17章に、「神の国は人間の中にある」とある。ひとりの人間ではなく、一部の人間でもなく、全ての人間なのだ。君たちの中になんだ。君たち、人々は力を持っているんだ。機械を作り上げる力、幸福を作る力を持っているんだ。君たち、人々が持つ力が、人生を自由に、美しくし、人生を素晴らしい冒険にするのだ。
民主国家の名のもとに、その力を使おうではないか。皆でひとつになろう。新しい世界のために闘おう。常識ある世界のために。皆に雇用の機会を与えてくれ、君たちに未来を与えてくれ、老後に安定を与えてくれる世界のために。そんな約束をして、獣たちも権力を伸ばしてきた。しかし、奴らは嘘つきだ。奴らは約束を果たさない。これからも果たしはしない。独裁者たちは自分たちを自由にし、人々を奴隷にする。
今こそ、闘おう。約束を実現させるために。闘おう。世界を自由にするために。国境のバリアをなくすため。欲望を失くし、嫌悪と苦難を失くすために。理性のある世界のために闘おう。科学と進歩が全人類の幸福へ、導いてくれる世界のために。兵士たちよ。民主国家の名のもとに、皆でひとつになろう。
※ハンナに対して、希望を捨てないよう語りかける。絶望に打ちひしがれ地に伏していたハンナはゆっくりと立ち上がり、空を見つめるシーンで物語は幕を閉じる。
















 若かりし頃のタケシ。
若かりし頃のタケシ。 原作である内田百閒の作品自体(登場人物の名は、映画と同じく「中砂」。)も、夕刻時分の、夢か現かまどろみの世界のようで、語り手のみならず読者も背筋が寒くなるような印象。さすが内田ワールド、短編ながら独特の奥行きをもっていて、次第に語りの世界に引きずり込まれる。
原作である内田百閒の作品自体(登場人物の名は、映画と同じく「中砂」。)も、夕刻時分の、夢か現かまどろみの世界のようで、語り手のみならず読者も背筋が寒くなるような印象。さすが内田ワールド、短編ながら独特の奥行きをもっていて、次第に語りの世界に引きずり込まれる。






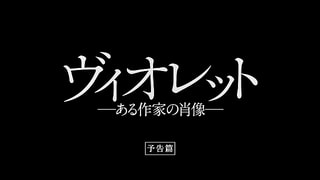

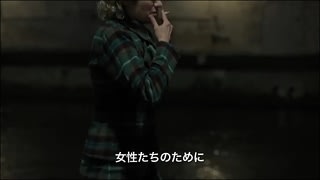



 イーとの性行為を意識して友人にはじめて身をまかせる。
イーとの性行為を意識して友人にはじめて身をまかせる。













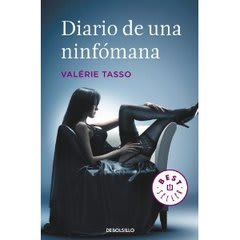 (「Amazon」より)
(「Amazon」より)














 観客みんなを巻き込んでの演奏会。
観客みんなを巻き込んでの演奏会。 終幕近く、ニューヨーク・フィルの常任指揮者・音楽監督のズービン・メータメータを呼び、絶賛。
終幕近く、ニューヨーク・フィルの常任指揮者・音楽監督のズービン・メータメータを呼び、絶賛。







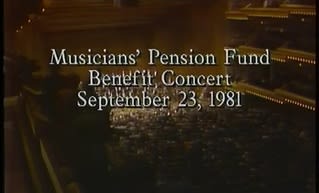
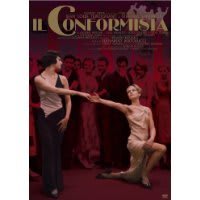
 マルチェロ(ジャン=ルイ・トランティニャン)
マルチェロ(ジャン=ルイ・トランティニャン) ジュリア(ステファニア・サンドレッリ)
ジュリア(ステファニア・サンドレッリ) アンナ(ドミニク・サンダ)
アンナ(ドミニク・サンダ)

 より拝借しました。
より拝借しました。 堀辰雄「風立ちぬ」。
堀辰雄「風立ちぬ」。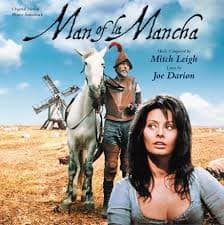 1972年製作「ラ・マンチャの男」ピーター・オトゥール、ソフィア・ローレン出演。
1972年製作「ラ・マンチャの男」ピーター・オトゥール、ソフィア・ローレン出演。

 『GONE WITH THE WIND』。名画の誉れ高い。
『GONE WITH THE WIND』。名画の誉れ高い。



 結婚式の晩、サッチモとの共演。
結婚式の晩、サッチモとの共演。 ありきたりの行進曲から「セントルイスブルース」を行進曲風にアレンジして演奏。行進する兵隊が生き生きと。
ありきたりの行進曲から「セントルイスブルース」を行進曲風にアレンジして演奏。行進する兵隊が生き生きと。 慰問の演奏。
慰問の演奏。 空襲警報が鳴り響いても、演奏を中断しない。
空襲警報が鳴り響いても、演奏を中断しない。






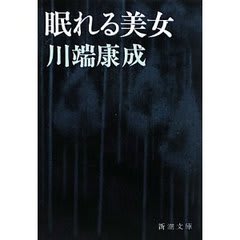 『眠れる美女』(川端康成)新潮文庫
『眠れる美女』(川端康成)新潮文庫


