
先日の山形Q定期で、わざわざ東京から聴きに来て下さった方がいました。それも前回に引き続きです。ありがたいのはそれだけではありません・・・こんな素晴らしいお土産まで。酒飲み冥利に・・・いや、演奏家冥利に尽きますな。
ということで、愛知の銘酒「蓬莱泉」の特別純米「可」。三段階評価のC判定、「優・良・可」の一番下の「可」ではありません。「べし」と読みます。・・・一体、どのへんが「べし」なのか?それは、飲んでみてのお楽しみ。
全然関係ない話に飛びますが、世の中の指揮者には、協奏曲の上手い人と、そうでない人がいます。良い指揮者は、交響曲も協奏曲も上手いに違いない・・・と思うと、そうでもないのです。
協奏曲のCDを買う時には、まず間違いなく、ソリストで選びますよね。背表紙にも、「ハイフェッツ」とか「アルゲリッチ」とは書いてありますが、指揮者の名前までは無い。そこで手にとって裏を見ると、小さく、聞いたことのない指揮者の名前があったりする。
「誰だよこれ・・・さては、ソリストに予算つかいすぎて、安い無名指揮者で浮かしたな」
これは違います。カラヤンだったらもっと良い演奏だったかというと、決してそういうことはない。グールドとバーンスタインのような「歴史的不和」が貴重な記録として遺る面白さはあるかも知れませんが、それは作品本来の素晴らしさにはマイナス要素になります。
「音楽はこうでなければならない」とばかりにオーケストラを「管理」し、自分の思うままに動かして名演をするタイプの指揮者は、個性の強いソリストとは、なかなかうまくゆかないものです。かといって、「何事もソリスト様の仰せのままに」というタイプでは、やはりオーケストラから良い音をひきだすことはできません。それ以前に指揮者としてダメな人だし、ソリストにとっても、むしろ邪魔になる。
では、どういう指揮者が「協奏曲が上手い」のか。それはつまり、「懐の深さ」であり、音楽的なキャパシティーの広い人だと思います。だから押しつけがない。こういう人は交響曲をやっても、オーケストラから主体的な生き生きした音楽をひきだします。
古くて申し訳ないのですが、例を挙げるとすれば、オーマンディとか。往年の名盤にはよく名前がありますので、無名どころか堂々たる巨匠ですが、きっと懐の深い「良い人」だと思います。熱狂的なファンは少ないが、どんな時も安心して気持ちよく聴いていられる。語弊があるといけないので名前は出しませんが、日本人にもこういう意味で「良い指揮者」はたくさんいます。
話がずいぶん長くなってしまいまいたが、つまりこれが、蓬莱泉「可」の感想でございます。「べし」とはつまり「こうでなければならない」の「不可」が無いということなのでしょう。どんな料理にも合うし、意識せずに飲めるタイプ。かと言って無味無臭系ではなく、米の味もしっかり感じられるが、でしゃばらない。キャパの広い酒です。(・・・オーマンディよりはサッパリしてるか)。
気持ちよく堪能しました。
ということで、愛知の銘酒「蓬莱泉」の特別純米「可」。三段階評価のC判定、「優・良・可」の一番下の「可」ではありません。「べし」と読みます。・・・一体、どのへんが「べし」なのか?それは、飲んでみてのお楽しみ。
全然関係ない話に飛びますが、世の中の指揮者には、協奏曲の上手い人と、そうでない人がいます。良い指揮者は、交響曲も協奏曲も上手いに違いない・・・と思うと、そうでもないのです。
協奏曲のCDを買う時には、まず間違いなく、ソリストで選びますよね。背表紙にも、「ハイフェッツ」とか「アルゲリッチ」とは書いてありますが、指揮者の名前までは無い。そこで手にとって裏を見ると、小さく、聞いたことのない指揮者の名前があったりする。
「誰だよこれ・・・さては、ソリストに予算つかいすぎて、安い無名指揮者で浮かしたな」
これは違います。カラヤンだったらもっと良い演奏だったかというと、決してそういうことはない。グールドとバーンスタインのような「歴史的不和」が貴重な記録として遺る面白さはあるかも知れませんが、それは作品本来の素晴らしさにはマイナス要素になります。
「音楽はこうでなければならない」とばかりにオーケストラを「管理」し、自分の思うままに動かして名演をするタイプの指揮者は、個性の強いソリストとは、なかなかうまくゆかないものです。かといって、「何事もソリスト様の仰せのままに」というタイプでは、やはりオーケストラから良い音をひきだすことはできません。それ以前に指揮者としてダメな人だし、ソリストにとっても、むしろ邪魔になる。
では、どういう指揮者が「協奏曲が上手い」のか。それはつまり、「懐の深さ」であり、音楽的なキャパシティーの広い人だと思います。だから押しつけがない。こういう人は交響曲をやっても、オーケストラから主体的な生き生きした音楽をひきだします。
古くて申し訳ないのですが、例を挙げるとすれば、オーマンディとか。往年の名盤にはよく名前がありますので、無名どころか堂々たる巨匠ですが、きっと懐の深い「良い人」だと思います。熱狂的なファンは少ないが、どんな時も安心して気持ちよく聴いていられる。語弊があるといけないので名前は出しませんが、日本人にもこういう意味で「良い指揮者」はたくさんいます。
話がずいぶん長くなってしまいまいたが、つまりこれが、蓬莱泉「可」の感想でございます。「べし」とはつまり「こうでなければならない」の「不可」が無いということなのでしょう。どんな料理にも合うし、意識せずに飲めるタイプ。かと言って無味無臭系ではなく、米の味もしっかり感じられるが、でしゃばらない。キャパの広い酒です。(・・・オーマンディよりはサッパリしてるか)。
気持ちよく堪能しました。












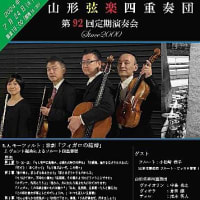

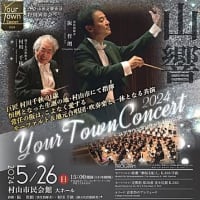










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます