メインテキスト:無着成恭編『山びこ学校』(初版は青銅社昭和26年。岩波文庫版平成7年)
サブテキスト:佐野眞一『遠い「山びこ」 無着成恭と教え子たちの四十年』(文藝春秋平成4年)
「僕の家は貧乏で、山元村の中でもいちばんぐらい貧乏です」と、1949(昭和24)年12月16日の日付のある作文「母の死とその後」は書き出されている。筆者は江口江一、この時山元中学校の二年生だった。極貧の中、六歳の時にまず父を亡くし、その後三人の子どもを育てながら働きづめに働いてきた母も死んだ。弟と妹は親類にもらってもらい、家には江一と74歳の祖母しかいなくなってしまった。母は、「江一さえ一人前になれば」と口癖のように言っていたが、母がどんなに一所懸命働いても借金が増えるばかりだったものを、自分が同じぐらい働けば、いや、母の倍働いたとして、暮らしは楽になるのだろうか、と江一は疑問を持つ。江口家の収入は、三段歩(約30a、900坪)の畑から家庭用の菜園に使っている部分を引いたところで取れる葉煙草で、その取れ高は毎年ほぼ決まっている。それを売った収入で、米などの必需品を買い、税金を納めた場合には、村からの扶助があってもなお、借金をしなければ生活できない。貧乏生活から抜け出すことができないのは、当たり前のことだったのだ。
最大の問題は田がないことで、もしも不作で誰も米を売ってくれなくなれば、飢え死にするしかない。だから田がほしいと思うのだが、自分が買えば、売った人は今の自分ような苦労をしなければならないのではないか。驚くべきことに、この少年はそこまで考えている。
担任の無着成恭からは、より差し迫った問題を訊かれる。江一は二学期になってからもう一ヶ月半も学校を休んでいる。仕事が忙しいからだ。いつになったら一段落して、登校できるようになるのか。無着に言われて計画表を作ってみると、十二月には一回か、よくても二回ぐらいしか来られないことがわかった。無着はその計画表をクラスの佐藤籐三郎など、主だった者に見せ、「なんとかならんのか」と問うと、佐藤は「できる。おらだの組はできる」と力強く答える。そして土曜日にクラスの者たちが江一の家へ来て、一人では何日もかかる仕事を一日で終えてしまった。感激した江一は、作文の終わり近くにこう記している。
明日はお母さんの三十五日です。お母さんにこのことを報告します。そして、お母さんのように貧乏のために苦しんで生きていかかなければならないのはなぜか、お母さんのように働いてもなぜゼニがたまらなかったのか、しんけんに勉強することを約束したい思っています。私が田を買えば、売った人が、僕のお母さんのような不幸な目にあわなければならないのじゃないか、という考え方がまちがっているかどうかも勉強したいと思います。
以上簡単に要約したところからも、これが圧倒的な感動を呼ぶ作文だったことは理解されるだろう。感動の理由を列挙すると、次のようになるだろうか。
(1)わずか13歳の子どもの肩にのしかかる、困難な生活の圧倒的なリアリズム。
(2)地域の者たちが力を合わせれば、その困難な生活も改善できるのではないか、と明るい希望を抱かせる。
(3)筆者の江一の目は自分の生活状況の冷静な分析に及んでいる。この目はやがて、社会全体の矛盾の発見、さらには改革を志すところまで及ぶのではないかと期待される。
現在でも詩文集『山びこ学校』のエッセンスを示すと言われている「母の死とその後」だが、同書の出版に先駆けて活字になっている。昭和25年、日本教職員組合(日教組)と教科書研究協議会の主催による第一回全国生徒児童作文コンクールに山形県教組によって応募され、文部大臣賞を受賞したからである。
江口の担任教師無着成恭は、昭和23年、新採教師として山形県の山元中学区に赴任した。二十一歳だった。翌24年に教え子の中学二年生たちの詩文集『きかんしゃ』第1号を手作りのガリ版刷りで発行。「母の死とその後」はその第2号に載った。『山びこ学校』は全部で16号出たこの『きかんしゃ』から抜粋、編集して出来上がったものだった 。
佐野眞一の著書を頼りに、もう少し遡った背景を見ておこう。
山形県は戦前から生活綴方運動の指導者村山俊太郎や国分一太郎を排出し、いわゆる北方性教育の本拠地と目されていた。しかし、同県の禅寺に生まれた無着は、教師になった時点では、これらの教育方法とは無縁だった。彼は同じ山形でも自分が継ぐべき寺がある本沢村に戻り、そこで教師兼住職をしながら、青年たちの文化運動のリーダーを務めることが夢であった。案に相違して山元村に赴任してから、この寒村の子どもたちをどう教育したらいいのか悩み、旧知の山形新聞編集員の須藤克三から国分一太郎を紹介され、そこで初めて綴方=作文教育という方法に目覚めることになった。
しかし、指導者の経歴や資質以上に重要なのは、終戦直後にそれまでの修身・公民・地理・歴史を廃して始められた「社会科」の存在ではなかったかと思う。この科目の創設は、昭和21年4月に提出されたアメリカ教育使節団の報告書に基づき、日本の教育の「民主化」を目指した方策のうち、いわば目玉になるものだった。それだけに、これを具体的にどう教えるかについては、たいへんな苦労を経なければならなかった。昭和22年5月には小学校用の「学習指導要領社会科編(Ⅰ)」が、6月には中学高校用の「学習指導要領社会科編(Ⅱ)」が出ており、実施はこの年の9月、つまり学年の途中から、というのもたいへん異例だった。
無着自身が、この新しい教科である社会科を専門とする教師だった。『山びこ学校』初版の「あとがき―子どもと共に生活して―」で、次のように書いている。
社会科の教科書の一つ『日本のなかの生活』中の「日本のいなか」【註、たぶん、『日本のいなかの生活』として昭和24年に刊行されたものの前身だと思われる】のまえがきには「この教科書は、わが国のいなかの生活がどのように営まれてきたか、その生活に改善を要する方面としてはどんなことがあるかを、学習するに役立つように書かれたものである」のだから、「いなかに住む生徒は、改めて自分たちの村の生活をふりかえって見てその欠点を除き、新しいいなかの社会をつくりあげるように努力することがたいせつである」云々と書かれていた。そこで無着が「文部省の考えの深さに驚いた」などと述べているのは皮肉であろう、と百合出版版(昭和30年刊行)の「解説」で国分一太郎は述べている。
それはそうと、では、どうやったら教科書に書かれているような努力を生徒にさせたらいいのか、そのやり方として発見されたのが綴方だったのだ、と無着は言う。例えば、
(a)ある生徒が、隣人の話として、「息子を教育したんで、百姓がいやになり、その家はつぶれてしまった」と綴方に書いてくる。
(b)では、「教育を受けるとなぜ百姓がいやになるのだろう」と生徒たちに問いかける。
(c)生徒たちからは、「百姓はつらい仕事だから」「百姓は馬鹿でもできるから」「百姓はあまり物を知らないほうがよい」などなどの答えが返ってくる。議論が煮詰まると、概ね、「百姓は働く割には儲からないからだ」というところに落ち着く。
(d)それは本当にそうなのか、ということになって、米や繭や葉煙草の価格から肥料や農具の値段などを、班が作られて分担して調べられ、計算されて、実際に「百姓は割損」であることが実証される。
(e)すると、「やはり百姓はあまり考えると馬鹿らしくてできなくなり、といって他に仕事も見つからないのだから、あまり考えないほうがいい」という悲観的な考えが出てくる一方で、「損をしても働かねばならないなんて、そんな馬鹿な話があるものではない。百姓は損をしなくてもすむように頑張るべきだ」という意見も現れる。これに無着は思わず「そうだ、そうだ」と怒鳴る。
(f)しかし、では、どうすれば百姓の仕事が割損にならないようにすむのか、という点になると、当然ながらそう簡単にはいかない。すべての前提として、いったいなぜこんな社会状況になっているのかが検討されなくてはならない。社会科の教科書だけではなく、さまざまな本を読んで一応、第一、かつての身分制度があった時代の社会習慣や考え方がまだ残っている(このことは、他の綴方からも確認される)。第二、諸外国に比べて日本の耕地面積は狭いので、生産高も低い。この二つは、農村を豊かにするために大きな障害になっていることはつきとめられる。
(g)第二の点の解決策としては、耕地面積あたりの生産性を高めることが改善策として考えられるが、それには機械化が必要であろう。しかし、一軒で機械を所有すれば、その費用だけでも割高なので、何軒かで共同で使うようにすればいいのだが、その場合、「共同責任は無責任」ということで、みんなの機械がぞんざいに扱われるようなことがあってはなんにもならない(これまた、ある子の綴方に出てくる)。
(h)以上から、次の二つが今後の農村にとって大事であることが確認される。
1 農民をもっと金持ちにすること。
2 農民はもっと共同のものを大事にして、自分だけよければよいという考えを捨てること。
作文とクラス討議を通じて、ここまで生徒を導いた無着の教育実践には、改めて目を見張る思いがさせられる。もちろんここでの作文=綴方とは、一つの作品として仕上げられることが重要なのではなく、文章にするために客観的・分析的にものごとを見る目を養い、文章にすることによって考えをまとめ、出来上がった文章を他人に読んでもらうことで、自分の考えをさまざまな角度から検討する、その材料になることが一番重要なのだった。これはまた、終戦直後、主にアメリカから求められた民主主義的な教育は、この日本で、具体的にはどのように展開されるべきか、一つの明確な回答を出したものでもあった。
しかし、見事であればあるだけ、危うさもあった。
一つには、『山びこ学校』は有名になり過ぎた。これも佐野によると、売り上げは発行二年間で十二万部に達し、26年の一年間だけでもこれを取り上げた新聞・雑誌は百を超し、知識人であれば誰もがこれについて一言以上あるべきだ、という雰囲気にさえあったという。中学生の文集がここまで話題になるのは世界的に見て稀であろう。それというのも、戦争に敗れた後の新生日本のあるべき姿を底辺から希求する、貴重な声がここにあると考えられたからだろう。
ただし、それもこれも、外部から見た話である。作品の舞台となった山元村の住民からすれば、惨めな貧窮状態が全国に曝されるようなのは、面白くないと感じられる場合もあったろう。
それ以上に、今から見ても「こんなことをバラして大丈夫だったのか?」と思える内容の文章もある。たぶん無着の手になる「作者紹介」で「愛される理論家」と評されている川合義憲の一連の作文など、彼が実際に見聞したいわゆるヤミによる商品売買が、赤裸々に描かれている。駐在だって、炭などをヤミで買ったことがある。それでも、時には農家を摘発する。川合の家は大丈夫だったらしいが、こんなことを書いて、と父母からは叱責された。それが活字になった。おかげで我々は貴重な記録を目にすることができるのだが、直接の当事者である川合家の人々や関係者に、これを「教育」の一環として理解しろと言っても、無理な話ではある。
それから、当然予想されることだが、無着の教育によって、子どもたちは社会に対する批判的な目を身に付ける。作文ではそれは、村の大人たちへの直接の批判として現れる。批判されれば、その内容の適否以前に、中学生のガキが、何を生意気な、と今の大人でも(大半がこのときの山元中学校の生徒より年下になるわけだが)反感を持つだろう。それはただちに、彼らの指導者である無着への反感となる。昭和26年と言えばサンフランシスコ講和条約が署名された年だが、朝鮮戦争後に方向転換したGHQによるレッド・パージの記憶はまだ生々しいものとしてあった。そこで無着は「アカではないか」と言われることもあった。
昭和28年、ウイーンで世界教育会議が開催されると、無着はその出席者の一人に選ばれた。帰途、羽仁五郎のすすめで、日本の当局には無断で東欧に入り、さらにはモスクワに迎えられて、モスクワ放送に出演した。当然大騒ぎとなり、この事件がきっかけで無着は村を逐われることになった。こうして無着成恭の公立学校教員生活は五年で終わったのである。
たぶん今でも、『山びこ学校』を読めば、その教育のすばらしさを否定する人は稀であろう。しかし、では、自分の子どもにこのような教育を施してもらいたいか、となると話は別になるだろう。
山元中学校の生徒たちの手になる作文の迫力は、なんと言っても彼らが中学生であっても生産の担い手であったことに由来する。つまり、彼らの家のほとんどが農家であって、小さいときから野良仕事の手伝いをすることは、この頃までは当たり前であった。前述した農業社会の現状への疑問も、彼らにとっては少しも抽象的な話ではなく、生活の中でぶつからねばならない切実なものとしてあった。労働人口の八割以上が勤め人となり、家庭と生産現場がほぼ完全に分離された現在では、この教育実践の土台は完全に消えている、と言える。
それに付随して次のことは指摘されなければならないだろう。江口江一を初め、日本全国の農村の子どもたちが苦しんでいたのは、結局貧乏だからだ。「貧乏綴方」という悪口は、『山びこ学校』以前から、綴方運動に対しては言われていたようだ。彼らは貧乏だからこそ興味深いのじゃないか、というわけである。それはともかくとして、経済状態が改善され、子どもが、江口のような苦しみを嘗めないほうが、優れた文章が出るよりもっといいと、普通には考えられるだろう。
その後の日本で、改善はなされた。しかしそれは、山元中学時代の無着や彼の生徒たちが望んでいた方向とは違うものだった。岩波文庫版のあとがきでは、無着はこう言っている。
明治維新のとき自らを後進国と自認した日本は、軍隊が強くなれば世界は認めるだろうということで、天皇を絶対なる神であると措定し軍国主義で日本人の心をコントロールしてきました。それが崩れた一瞬のすきにできたのが『山びこ学校』です。しかし、池田首相の所得倍増論をきっかけに、こんどは、お金もちになれば世界中が認めるだろうということで経済主義教育につっぱしり、いじめ、登校拒否、オウム教などの今日的状況を作りあげているわけです。
いじめや登校拒否やオウム真理教などが「経済主義教育」の結果生まれたと言うにしては、もっといくつも補助線を引かねばならないと私は思うが、経済状況に限っても、戦後日本社会の歩みを完全に肯定することなどできないとも思う。経済的発展とはあくまで商工業に関するものであって、農林水産業、いわゆる第一次産業は完全に置き去りにされた。地方は過疎化が進み、山元中学校は平成19年に廃校になっている。
この歪みと犠牲の上での繁栄なのだが、問題は、このやり方以外には、貧乏人が多少とも豊かになる道を人類が発見していないところにある。山元中学校の生徒たちが作文製作と討議の結果たどり着いた理想的な農村のイメージは、社会主義国の集団農場に直結しそうだが、周知のようにこれは、ソ連でも中国でも成功しなかった。無着の教育実践をストレートに現在に生かそう、などと簡単に言うことはできない。
何よりも無着自身が、山形を去って東京の明星学園の教師になってから、同じような実践を続けることはなかった。この後の彼の教師・タレントとしての活動の跡を詳しくたどるのはここではやめるが、最終的には学校教育そのものに絶望したようだ。明星学園内部での種々の対立の結果、昭和58年に教壇を去り、盟友だった遠藤豊(明星学園小中学校校長を務めた。同じ時期、無着は同校教頭だった)を校長として自由の森学園が開校(昭和60年)されても、そこに加わることはなかった。
それにつけても、「一瞬のすきにできた」とは、無着もわかっているなあ、と思う。軍国主義が終わり、経済主義がまだ始まらない狭間に咲いた美しい教育の夢の花、それが『山びこ学校』だったのである。夢は消えても、現実の学校は残っている。そこを多少ともよくしていこうと思ったら、かつての思い出に耽るより、なぜそれが今成り立たないのか、その諸事情を熟考することこそ正道であろうと思う。
サブテキスト:佐野眞一『遠い「山びこ」 無着成恭と教え子たちの四十年』(文藝春秋平成4年)
「僕の家は貧乏で、山元村の中でもいちばんぐらい貧乏です」と、1949(昭和24)年12月16日の日付のある作文「母の死とその後」は書き出されている。筆者は江口江一、この時山元中学校の二年生だった。極貧の中、六歳の時にまず父を亡くし、その後三人の子どもを育てながら働きづめに働いてきた母も死んだ。弟と妹は親類にもらってもらい、家には江一と74歳の祖母しかいなくなってしまった。母は、「江一さえ一人前になれば」と口癖のように言っていたが、母がどんなに一所懸命働いても借金が増えるばかりだったものを、自分が同じぐらい働けば、いや、母の倍働いたとして、暮らしは楽になるのだろうか、と江一は疑問を持つ。江口家の収入は、三段歩(約30a、900坪)の畑から家庭用の菜園に使っている部分を引いたところで取れる葉煙草で、その取れ高は毎年ほぼ決まっている。それを売った収入で、米などの必需品を買い、税金を納めた場合には、村からの扶助があってもなお、借金をしなければ生活できない。貧乏生活から抜け出すことができないのは、当たり前のことだったのだ。
最大の問題は田がないことで、もしも不作で誰も米を売ってくれなくなれば、飢え死にするしかない。だから田がほしいと思うのだが、自分が買えば、売った人は今の自分ような苦労をしなければならないのではないか。驚くべきことに、この少年はそこまで考えている。
担任の無着成恭からは、より差し迫った問題を訊かれる。江一は二学期になってからもう一ヶ月半も学校を休んでいる。仕事が忙しいからだ。いつになったら一段落して、登校できるようになるのか。無着に言われて計画表を作ってみると、十二月には一回か、よくても二回ぐらいしか来られないことがわかった。無着はその計画表をクラスの佐藤籐三郎など、主だった者に見せ、「なんとかならんのか」と問うと、佐藤は「できる。おらだの組はできる」と力強く答える。そして土曜日にクラスの者たちが江一の家へ来て、一人では何日もかかる仕事を一日で終えてしまった。感激した江一は、作文の終わり近くにこう記している。
明日はお母さんの三十五日です。お母さんにこのことを報告します。そして、お母さんのように貧乏のために苦しんで生きていかかなければならないのはなぜか、お母さんのように働いてもなぜゼニがたまらなかったのか、しんけんに勉強することを約束したい思っています。私が田を買えば、売った人が、僕のお母さんのような不幸な目にあわなければならないのじゃないか、という考え方がまちがっているかどうかも勉強したいと思います。
以上簡単に要約したところからも、これが圧倒的な感動を呼ぶ作文だったことは理解されるだろう。感動の理由を列挙すると、次のようになるだろうか。
(1)わずか13歳の子どもの肩にのしかかる、困難な生活の圧倒的なリアリズム。
(2)地域の者たちが力を合わせれば、その困難な生活も改善できるのではないか、と明るい希望を抱かせる。
(3)筆者の江一の目は自分の生活状況の冷静な分析に及んでいる。この目はやがて、社会全体の矛盾の発見、さらには改革を志すところまで及ぶのではないかと期待される。
現在でも詩文集『山びこ学校』のエッセンスを示すと言われている「母の死とその後」だが、同書の出版に先駆けて活字になっている。昭和25年、日本教職員組合(日教組)と教科書研究協議会の主催による第一回全国生徒児童作文コンクールに山形県教組によって応募され、文部大臣賞を受賞したからである。
江口の担任教師無着成恭は、昭和23年、新採教師として山形県の山元中学区に赴任した。二十一歳だった。翌24年に教え子の中学二年生たちの詩文集『きかんしゃ』第1号を手作りのガリ版刷りで発行。「母の死とその後」はその第2号に載った。『山びこ学校』は全部で16号出たこの『きかんしゃ』から抜粋、編集して出来上がったものだった 。
佐野眞一の著書を頼りに、もう少し遡った背景を見ておこう。
山形県は戦前から生活綴方運動の指導者村山俊太郎や国分一太郎を排出し、いわゆる北方性教育の本拠地と目されていた。しかし、同県の禅寺に生まれた無着は、教師になった時点では、これらの教育方法とは無縁だった。彼は同じ山形でも自分が継ぐべき寺がある本沢村に戻り、そこで教師兼住職をしながら、青年たちの文化運動のリーダーを務めることが夢であった。案に相違して山元村に赴任してから、この寒村の子どもたちをどう教育したらいいのか悩み、旧知の山形新聞編集員の須藤克三から国分一太郎を紹介され、そこで初めて綴方=作文教育という方法に目覚めることになった。
しかし、指導者の経歴や資質以上に重要なのは、終戦直後にそれまでの修身・公民・地理・歴史を廃して始められた「社会科」の存在ではなかったかと思う。この科目の創設は、昭和21年4月に提出されたアメリカ教育使節団の報告書に基づき、日本の教育の「民主化」を目指した方策のうち、いわば目玉になるものだった。それだけに、これを具体的にどう教えるかについては、たいへんな苦労を経なければならなかった。昭和22年5月には小学校用の「学習指導要領社会科編(Ⅰ)」が、6月には中学高校用の「学習指導要領社会科編(Ⅱ)」が出ており、実施はこの年の9月、つまり学年の途中から、というのもたいへん異例だった。
無着自身が、この新しい教科である社会科を専門とする教師だった。『山びこ学校』初版の「あとがき―子どもと共に生活して―」で、次のように書いている。
社会科の教科書の一つ『日本のなかの生活』中の「日本のいなか」【註、たぶん、『日本のいなかの生活』として昭和24年に刊行されたものの前身だと思われる】のまえがきには「この教科書は、わが国のいなかの生活がどのように営まれてきたか、その生活に改善を要する方面としてはどんなことがあるかを、学習するに役立つように書かれたものである」のだから、「いなかに住む生徒は、改めて自分たちの村の生活をふりかえって見てその欠点を除き、新しいいなかの社会をつくりあげるように努力することがたいせつである」云々と書かれていた。そこで無着が「文部省の考えの深さに驚いた」などと述べているのは皮肉であろう、と百合出版版(昭和30年刊行)の「解説」で国分一太郎は述べている。
それはそうと、では、どうやったら教科書に書かれているような努力を生徒にさせたらいいのか、そのやり方として発見されたのが綴方だったのだ、と無着は言う。例えば、
(a)ある生徒が、隣人の話として、「息子を教育したんで、百姓がいやになり、その家はつぶれてしまった」と綴方に書いてくる。
(b)では、「教育を受けるとなぜ百姓がいやになるのだろう」と生徒たちに問いかける。
(c)生徒たちからは、「百姓はつらい仕事だから」「百姓は馬鹿でもできるから」「百姓はあまり物を知らないほうがよい」などなどの答えが返ってくる。議論が煮詰まると、概ね、「百姓は働く割には儲からないからだ」というところに落ち着く。
(d)それは本当にそうなのか、ということになって、米や繭や葉煙草の価格から肥料や農具の値段などを、班が作られて分担して調べられ、計算されて、実際に「百姓は割損」であることが実証される。
(e)すると、「やはり百姓はあまり考えると馬鹿らしくてできなくなり、といって他に仕事も見つからないのだから、あまり考えないほうがいい」という悲観的な考えが出てくる一方で、「損をしても働かねばならないなんて、そんな馬鹿な話があるものではない。百姓は損をしなくてもすむように頑張るべきだ」という意見も現れる。これに無着は思わず「そうだ、そうだ」と怒鳴る。
(f)しかし、では、どうすれば百姓の仕事が割損にならないようにすむのか、という点になると、当然ながらそう簡単にはいかない。すべての前提として、いったいなぜこんな社会状況になっているのかが検討されなくてはならない。社会科の教科書だけではなく、さまざまな本を読んで一応、第一、かつての身分制度があった時代の社会習慣や考え方がまだ残っている(このことは、他の綴方からも確認される)。第二、諸外国に比べて日本の耕地面積は狭いので、生産高も低い。この二つは、農村を豊かにするために大きな障害になっていることはつきとめられる。
(g)第二の点の解決策としては、耕地面積あたりの生産性を高めることが改善策として考えられるが、それには機械化が必要であろう。しかし、一軒で機械を所有すれば、その費用だけでも割高なので、何軒かで共同で使うようにすればいいのだが、その場合、「共同責任は無責任」ということで、みんなの機械がぞんざいに扱われるようなことがあってはなんにもならない(これまた、ある子の綴方に出てくる)。
(h)以上から、次の二つが今後の農村にとって大事であることが確認される。
1 農民をもっと金持ちにすること。
2 農民はもっと共同のものを大事にして、自分だけよければよいという考えを捨てること。
作文とクラス討議を通じて、ここまで生徒を導いた無着の教育実践には、改めて目を見張る思いがさせられる。もちろんここでの作文=綴方とは、一つの作品として仕上げられることが重要なのではなく、文章にするために客観的・分析的にものごとを見る目を養い、文章にすることによって考えをまとめ、出来上がった文章を他人に読んでもらうことで、自分の考えをさまざまな角度から検討する、その材料になることが一番重要なのだった。これはまた、終戦直後、主にアメリカから求められた民主主義的な教育は、この日本で、具体的にはどのように展開されるべきか、一つの明確な回答を出したものでもあった。
しかし、見事であればあるだけ、危うさもあった。
一つには、『山びこ学校』は有名になり過ぎた。これも佐野によると、売り上げは発行二年間で十二万部に達し、26年の一年間だけでもこれを取り上げた新聞・雑誌は百を超し、知識人であれば誰もがこれについて一言以上あるべきだ、という雰囲気にさえあったという。中学生の文集がここまで話題になるのは世界的に見て稀であろう。それというのも、戦争に敗れた後の新生日本のあるべき姿を底辺から希求する、貴重な声がここにあると考えられたからだろう。
ただし、それもこれも、外部から見た話である。作品の舞台となった山元村の住民からすれば、惨めな貧窮状態が全国に曝されるようなのは、面白くないと感じられる場合もあったろう。
それ以上に、今から見ても「こんなことをバラして大丈夫だったのか?」と思える内容の文章もある。たぶん無着の手になる「作者紹介」で「愛される理論家」と評されている川合義憲の一連の作文など、彼が実際に見聞したいわゆるヤミによる商品売買が、赤裸々に描かれている。駐在だって、炭などをヤミで買ったことがある。それでも、時には農家を摘発する。川合の家は大丈夫だったらしいが、こんなことを書いて、と父母からは叱責された。それが活字になった。おかげで我々は貴重な記録を目にすることができるのだが、直接の当事者である川合家の人々や関係者に、これを「教育」の一環として理解しろと言っても、無理な話ではある。
それから、当然予想されることだが、無着の教育によって、子どもたちは社会に対する批判的な目を身に付ける。作文ではそれは、村の大人たちへの直接の批判として現れる。批判されれば、その内容の適否以前に、中学生のガキが、何を生意気な、と今の大人でも(大半がこのときの山元中学校の生徒より年下になるわけだが)反感を持つだろう。それはただちに、彼らの指導者である無着への反感となる。昭和26年と言えばサンフランシスコ講和条約が署名された年だが、朝鮮戦争後に方向転換したGHQによるレッド・パージの記憶はまだ生々しいものとしてあった。そこで無着は「アカではないか」と言われることもあった。
昭和28年、ウイーンで世界教育会議が開催されると、無着はその出席者の一人に選ばれた。帰途、羽仁五郎のすすめで、日本の当局には無断で東欧に入り、さらにはモスクワに迎えられて、モスクワ放送に出演した。当然大騒ぎとなり、この事件がきっかけで無着は村を逐われることになった。こうして無着成恭の公立学校教員生活は五年で終わったのである。
たぶん今でも、『山びこ学校』を読めば、その教育のすばらしさを否定する人は稀であろう。しかし、では、自分の子どもにこのような教育を施してもらいたいか、となると話は別になるだろう。
山元中学校の生徒たちの手になる作文の迫力は、なんと言っても彼らが中学生であっても生産の担い手であったことに由来する。つまり、彼らの家のほとんどが農家であって、小さいときから野良仕事の手伝いをすることは、この頃までは当たり前であった。前述した農業社会の現状への疑問も、彼らにとっては少しも抽象的な話ではなく、生活の中でぶつからねばならない切実なものとしてあった。労働人口の八割以上が勤め人となり、家庭と生産現場がほぼ完全に分離された現在では、この教育実践の土台は完全に消えている、と言える。
それに付随して次のことは指摘されなければならないだろう。江口江一を初め、日本全国の農村の子どもたちが苦しんでいたのは、結局貧乏だからだ。「貧乏綴方」という悪口は、『山びこ学校』以前から、綴方運動に対しては言われていたようだ。彼らは貧乏だからこそ興味深いのじゃないか、というわけである。それはともかくとして、経済状態が改善され、子どもが、江口のような苦しみを嘗めないほうが、優れた文章が出るよりもっといいと、普通には考えられるだろう。
その後の日本で、改善はなされた。しかしそれは、山元中学時代の無着や彼の生徒たちが望んでいた方向とは違うものだった。岩波文庫版のあとがきでは、無着はこう言っている。
明治維新のとき自らを後進国と自認した日本は、軍隊が強くなれば世界は認めるだろうということで、天皇を絶対なる神であると措定し軍国主義で日本人の心をコントロールしてきました。それが崩れた一瞬のすきにできたのが『山びこ学校』です。しかし、池田首相の所得倍増論をきっかけに、こんどは、お金もちになれば世界中が認めるだろうということで経済主義教育につっぱしり、いじめ、登校拒否、オウム教などの今日的状況を作りあげているわけです。
いじめや登校拒否やオウム真理教などが「経済主義教育」の結果生まれたと言うにしては、もっといくつも補助線を引かねばならないと私は思うが、経済状況に限っても、戦後日本社会の歩みを完全に肯定することなどできないとも思う。経済的発展とはあくまで商工業に関するものであって、農林水産業、いわゆる第一次産業は完全に置き去りにされた。地方は過疎化が進み、山元中学校は平成19年に廃校になっている。
この歪みと犠牲の上での繁栄なのだが、問題は、このやり方以外には、貧乏人が多少とも豊かになる道を人類が発見していないところにある。山元中学校の生徒たちが作文製作と討議の結果たどり着いた理想的な農村のイメージは、社会主義国の集団農場に直結しそうだが、周知のようにこれは、ソ連でも中国でも成功しなかった。無着の教育実践をストレートに現在に生かそう、などと簡単に言うことはできない。
何よりも無着自身が、山形を去って東京の明星学園の教師になってから、同じような実践を続けることはなかった。この後の彼の教師・タレントとしての活動の跡を詳しくたどるのはここではやめるが、最終的には学校教育そのものに絶望したようだ。明星学園内部での種々の対立の結果、昭和58年に教壇を去り、盟友だった遠藤豊(明星学園小中学校校長を務めた。同じ時期、無着は同校教頭だった)を校長として自由の森学園が開校(昭和60年)されても、そこに加わることはなかった。
それにつけても、「一瞬のすきにできた」とは、無着もわかっているなあ、と思う。軍国主義が終わり、経済主義がまだ始まらない狭間に咲いた美しい教育の夢の花、それが『山びこ学校』だったのである。夢は消えても、現実の学校は残っている。そこを多少ともよくしていこうと思ったら、かつての思い出に耽るより、なぜそれが今成り立たないのか、その諸事情を熟考することこそ正道であろうと思う。













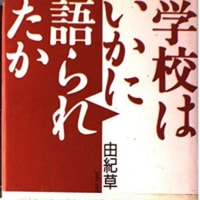
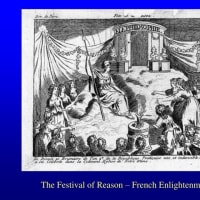










さて御コメントを拝読して、今更ながら「山びこ学校」の輝かしさに思い至ったように感じました。
こう言っても御言葉を返すことにはならないと思いますが、
「彼は、あの現象を理解するには若すぎており、時代はあまりに混沌とし、教育を理解するには、時期が早すぎた、つまり、何も分らなかったのかもしれ」
ないからこそ、あの達成があったのだと思います。
明星学園以後の無着氏は、教師として成功したのかどうか、
明星学園母親グループ著となっている『無着先生との12年戦争』などを読むと、かなりの葛藤を経なければならなかったことは明らかですね。
「なにをすべきであったのか」はわかりません、自分一個のことすら、教師として何をすべきか、よくわからないのですから。
庄司さんは何を期して小学校を始められたのですか。
無着先生は、「人はなぜ学ぶのか」を探そうとすべきであったのではないでしょうか。学びと経済は、ほとんど関係のないことです。つまり、無着先生の経済至上主義の教育に負けたという答えは、間違いです。私の小学校ではやまびこ学校と同じ現象が起こっています。起こり得ないことが起こり、基礎知識が見えない。自由な学びです。やまびこ学校で、無着は、指導に行き詰まり、自由に文を綴ることを求めたのです。退路を絶たれた子どもたちは、自由の中で詩や作文に彼らのエネルギーを注いだのです。自由に学ぶことを認められた子供は無限のエネルギーを発するのです。それは、知識とは言えないのでしょう。やまびこ学校の現象は、戦後の隙間に起こったのではなく、自由が与えられた瞬間に起こったのでしょう。
できたら具体的に、庄司さんから見た無着成恭像を語っていただきたいものだと感じました。
私ももちろん、文献に書かれている限りでの無着しか知りませんので。
もちろんお時間のある時でけっこうですので、できたらよろしくお願いします。
しかし、教育現場の問題は、複雑になる一方で、混沌としています。いつか必ず、無着のやまびこ学校のような現象が起らないとも限りません。
その時こそ、同じ轍を踏まないため、真の教育とは、学びとは、教師とはを議論しなければならないのだと思います。
教育は、政治や経済、世論に左右されてはならないのです。ただそこに好奇心に飢えた子どもがいるだけなのですから。
そして、子どもは、何事にも束縛されず自由に学ぶ権利と環境を保障されるべきなのです。
いまの日本の教育は、教育産業、政治家、世論にがんじがらめにあっています。ここを変えない限り日本の教育改革はあり得ません。
あるとすれば、山元村を再現する事でしょう。原点から視点を変えてやり直してみれば良いのです。それは、自由な学びです。
一応、お考えに絡むかな、と思えることを勝手に申しますと。
私は、教育もまた、「社会的な事業である」という当たり前(でしょう? 社会がなければ教育の要請も、従ってまた必要性も生じようがありませんので)の前提から出発しています。ですから、教育がそのときの社会情勢や経済状態から無縁であり得るはずはない、とまず考えます。
次に、教育とは、どんなものであっても、必ず大人の都合から割り出され、子どもには「押し付ける」ものだと考えます。
例えば、子どもに英語を学ばせるのは、そのほうが本人のためになる、と思ってのことでしょうが、とりあえず、そう思うのは大人です。子どものほうが自分から、自主的に、学ぶことを決める、なんてあり得ないのです。
まあしかし、日本語を習得した子どもはやがて、周囲の大人の願いとは別に、勝手にゲームやアニメに夢中になったりしますが。これは、ゲームやアニメの制作者である大人から間接的な教育を受けているのだとみなすことができますね。
このメディアは現在非常に発達しておりますが、規模は小さくとも、「子ども」という存在が社会で認知されてからは普遍的に、どこにでも見られた現象だと思います。私も「テレビばかり見ないで勉強しろ」と言われ続けて育った世代ですし、そう言った親もまた、その親から「遊んでばかりいやがって」と叱られていたようですね。
言いたいことはこうです。子どもは、いかにも、自由に、何かを学ぶでしょう。しかし、現に私の子どもがそうであるように、「妖怪ウオッチ」の世界にばかり詳しくなっても、そのまま放っておいていいんだ、と考える親は稀でしょう。もしいたら、それは無責任であり、教育放棄だ、と言われるでしょう。
これを踏まえた上で、「子どもは、何事にも束縛されず自由に学ぶ権利と環境を保障されるべき」とは具体的にはどういう意味になりますか?
また、「山元村を再現する」とはどういうことですか? 「山びこ学校」の実践をもう一度ということ? 前のコメントでは、庄司さんはあれには批判的なのだな、と思っていたのですが。
どうか、愚かな私のために、なるべく噛み砕いて、具体的に御考えを述べていただけませんか?
先ず、教育は、社会的事業であるという考えは、私たちの考えと異なります。教育は、人としての倫理なのです。
社会がなければ教育もないのではなく、教育がなければ社会がないのです。つまり、教育が社会に依存しているのではなく社会が教育に依存しているのでしょう。その意味では、教育と社会情勢や経済状態とは無縁ではないのかもしれません。しかし、教育が社会や経済を形作っている事は間違いありません。
国を作っているのは、人であり、人を作るのは、教育です。つまり、教育が破綻すれば、国が破綻します。しかし、立派な人間は、立派な社会で育つのです。人と社会は、そのような関係にあるのでしょう。大人は、教育現場が乱れると直ぐ子どものせいにする。やれ集中力が足りないとか、努力が足りまいとか、根気がないとか、遊んでばかりいるとか、なんとかかんとか。しかし、子どもが乱れるのは、社会が乱れているからなので、本質的には子どもとは関係ないのです。
次に、教育とは、個々の意識から始まります。人がある事に意識しその事に好奇心を持ち、その事について学び、知識とし、それを使うまでを教育とすると近代教育論(福田誠治先生)では述べています。つまり、ここのどこにも押し付けるとか詰め込むという理論は存在しないのです。
何かを教える事が本人のためになるという大人の考えは、なんと抽象的な言葉でしょう。具体的に何のためになるのかと言う事が大切なのです。そうすると『何のための学ぶのか』という疑問が起ります。『学ぶとは何か』この事は、近代哲学者オリビエ・ルブールが書いています。しかも、どうも彼の教育哲学を実践しているのが北欧の教育らしい(私の考え)のです。近代哲学者オリビエ・ルブールは、アランの教育論に影響されているらしいのですが、わたしも教育者としてのアランは、ソクラテス以上の存在と思います。アランのような教育者は希な存在で、参考になり様がないのかもしれませんが、フィンランドや北欧では、幼稚園の先生にさえ、大学院の修士課程や博士課程を要求し、何百倍の競争を経て、2年程の実習を経た後に教壇に立つのです。福田誠治先生のフィンランド教育やオリビエ・ルブールの本『学びとは何か』を読んでみる事をお勧めします。子ども(人)は、自ら学ぶ事が出来るのです。なぜなら、人類は、自ら学ぶ事で進化してきたのですから。子どもは、意識から始まり、主体的に学ぶのです。物事を意識し、好奇心を抱き学びへと変化するのです。好奇心を持ち合わせていない子ども等存在しないと言っても良いでしょう。好奇心は、脳が活動すると同時に生まれてすぐに発生します。その時の好奇心は、原始的(素朴)で、本能や感覚的なものなのでしょう。石を池に投げる、花を摘む、落書きをする等々、学びとは、この素朴な好奇心からいかに知的な好奇心へと転換するか、なのです。素朴な好奇心は、何かを学んでいるにしても、いたずらしたり、ふざけたり、遊んだりしているだけにすぎません。それなりに楽しく平和な時間なのでしょう。しかし、知的な好奇心からの学びは、社会に影響を及ぼす程の知識を生み出します。知的な好奇心を体験した子どもは、アニメやゲームにはあまり興味を示しません。アニメやゲームに夢中になる子のほとんどが他にやる事がないからと答えるのです。アニメやゲームに変わる知的な好奇心を与えてやるとほとんどの子どもは、それらを忘れます。
子どもは大人や教師からは、何も学ばないのです。いや、大人や教師は、子どもに何も教える事がないのです。子どもは、学校からはなにもまなばない。この一連の考えをオリビ・ルブールはいっているのですが、この事に異議を唱える人はあまりいないようです。勉強しろと言っても無駄ですし、遊んでばかりいてもいいのかもしれません。つまり、子どもに押し付けても何も得る事はないのです。子ども自身がなぜ学ぶのかを自覚しない限り、なにを施しても無駄な事です。もし、押しつけられて何かの知識を得たとしても何の価値もないのです。なぜならそれらは、他人の知識なのですから。知識には概ね2つあります。ひとつは、他人に教えられて覚えた知識、もうひとつは、自ら調べ学んだ知識、どうすれば、自ら学ぶのか。簡単です。教えなければ良いのです。
しかし、教えなければ、全ての子どもが学ぶのかというと、そんな事はありえません。幼児期の素朴な好奇心から、知的な好奇心への転換が起り、学びを意識し、考え、知識とし、その価値を自覚すれば、人はなぜ学ぶのかを理解するのでしょう。教師は、教えるのではなく、そこ支援し導くのです。
難しいとは、思わないでください。とても、たのしいことです。福田先生や太田先生は、北欧の教育には、根底に哲学が根ざしている、日本の教育には、それがないと言いました。子どもの学びに無関心な大人は、最悪です。問題は、子どもの学び(生き方)との関わり方なのでしょう。
子どもの自由な学びと権利の具体例とは、学びの始まりの好奇心なのでしょう。好奇心は、何かを意識する事から始まります。問題は、この意識するという事にあるようです。意識する。感じる。この事は、なにが意識し感じるのかというと人間の脳です。脳の何かというと脳細胞(ニューロン)です。しかし、脳細胞は、単なるタンパク質(物質)なのであるから、物質には、意識があるのかというと答えが出ない。この疑問は、長年の脳科学者や哲学者、物理学者の悩みの種であったようです。心とか意識についての研究があまり進んでいなかったのは、この事が原因だったようですが、量子力学の研究が進んでニューロンの動きが分るにつれ、考えることや感じることの仕組みも理解されてきたようです。どうも、脳のクオリアという器官がニューロンの活動を感じたり考えたりする分類を司っているらしいのです。最近脳科学者は、このクオリアを心としようと定義しているらしい。
難しいと思わないでください。とても、面白い事なのですから。つまり、自由な学び、自由に考えるとは、何千億のニューロンが何千兆の反応をくり返し行っている事、それをクオリアが判断している。これが人間なのです。つまり、自由な学びの権利と環境を保障する事は、人間である事を保障する事なのです。何千億のニューロンの何千兆の反応に教師の教えが関わる等考えない方が良いのかもしれません。
山元村の再現は、もっと分りにくいかもしれません。私は当時あの場所に住んでいたのです。あの貧しさは、何物も変える事は出来ないと皆が漠然と信じていました。なぜかは分らない。考えもつかない。しかし、何かをしなければならない。それが分らない。そういう時代(場所)だったのです。しかし、そういう同じ意識を村人全てが共有し助け合い生きていたのです。ここに、無着の奇跡が起った。ほとんど、隔離された小さな山村であったから存在したのでしょう。これが何万人の町だったら意識はバラバラだったに違いありません。山元村の再現とは、小さな村、住民の意識が同じでそれを共有し、お互いが助け合いながら生活する事です。国や大きな自治体を変える事は、不可能です。しかし、小さな村を作りそこで、学びの社会を作る事は可能です。富士山の麓には、ドクタービリッジとか、ペンション村とか、合宿村とかが存在しかすが、世界には宗教とは違ういろんな形、目的の私的、公的な村が存在します。ここでの意識は、経済や政治ではなく、子どもの『自由な学び』としましょう。視点を変えるのです。そうすれば、やまびこ学校のような学びが別の形で起るかもしれません。その時こそ、やまびこ学校の子ども達の“分らない、どうすれば良い”という悲痛な叫びに答えなのければなりません。人は、なぜ学ぶのか。人であるからか。『私は人間である。故に私は学ぶ』のか。では、人は、何のために学ぶのか。
学ぶとは何か。これを理解するには、人類の進化、哲学書、物理学、脳科学、言葉の発達、社会学等々、読みあさり、世界の学校の学びを見、熟練者の技を見、聞き、常に疑問を抱き、己を知る事でしょう。学びとは、人間の本質に迫る事です。私なぞ、虫けらみたいなものでなんの知識もありませんが世界中を回り、多くの本を読みました。分った事は、小さなアリでも噛み付けば巨人もそれを意識する事です。行動を起こせば、何かが起る。
お答えとして、愚考を述べたく思います。以下は私が二十代の頃からこだわってきて、拙い頭を使って「自から調べ学んだ」結果なのですが、改めて庄司さんのお考えにぶつかり、それに対応して書こうとすると、案外に難しく、おかげでお返事をさしあげるのがすっかり遅れてしまいました。
また、現場教師兼言説者としての私には、積もりに積もった怨念のようなものがあって、この分野では遠慮ということができません。失礼な言い方になることもあるのは、あらかじめお許しを願っておきます。
最初に、
「教育は、人としての倫理なのです」「社会がなければ教育もないのではなく、教育がなければ社会がないのです」
の部分は、根本的には卵―鶏関係になるでしょう。倫理は、私たち人間が社会的存在であるところから要請されてくるのです。自分一人で生きているとしたら、それこそ全く自由自在、どんな倫理も道徳もいりますまい。また、人は人間の社会に生まれ育って、そこで最広義の教育(大部分が無意識のうちに行われます)を受けて初めて人となる。最少の社会もない、つまり他の人間との接触が全くない状態で、十歳以上まで育った子は、生物的な種は人類であっても、内面的には別の存在となる。これはアヴェロンの野生児の一件で実際にも証明されております。もちろん次には、その教育を受けた人たちが社会を運営するのだから、「教育がなければ社会がない」「教育が社会に依存しているのではなく社会が教育に依存している」というのはまちがいではありません。
とは言え、時間的順番で言えば、まず必ず社会があって、しかる後に個人がある。この実態を無視して教育を考えることはできないでしょう。
しかしどうも、福田誠治氏や太田(尭、ですか?)氏ら、日本の教育学者は、この基本的な事実を否定するまではいかなくても、できるだけ軽視しようとしているらしい。これを重視すると、教育は社会の側から個人に降りてくるもので、必ず幾分かは「押しつけ」「つめこみ」に見える要素はある、それを忌避したいからなのかな、と私は感じておりました。そして、それは卑劣である、とも。教育を実践するうえで一番難しく、一番いやなところは親や教師の、いわゆる現場任せにして、たまに悩みを訴えられると、「まあ、うまくやってください。(理論的には)できるはずなんですから」などと言う。これではこちら(現場側)も、早々に相手にする気がなくなるのは当然ではないですか。
ただ、私も馬齢を重ねたおかげで、少しは寛大に見られるようになりました。
「人はなぜ学ぶか」←「知的好奇心があるから」
この論理(?)は例えば以下と同型ですね。
「人はなぜ食べるか」←「食欲があるから」
まちがいではないです。だって、トートロジーなんだから。
ここから出発して、「人がある食物を意識しその食物に好奇心を持ち、その食物を食べ、栄養素とし、それを使うまでを食事とする」などと定義したり、人が食事をしたりある食物に食欲を感じるとき脳のどの部分がどのように活性化するか、叙述したりする。これ、いかにも学問らしいですね。
実際の子育て上で悩むのは、「この種の食物は体にいいことはわかっているのだが、子どもがなかなか食べてくれない」というようなことですが、こうなると個別具体的でその分卑近になり、学問の対象にはふさわしくない。だから学問にその答えを期待してもむだだ。それとは別に、昔から、まるで民間療法のように、各家庭や共同体で工夫され伝えられてきた「子どもが食べやすい調理法」などがあるので、それから学んで、個別にやるしかない。こういうふうに、学問はあまり実際の役には立たないが、むしろそこにこそ存在価値があるのかも知れない。そう思えるようにはなりました。
かく言う私もまた、
「子どもは大人や教師からは、何も学ばないのです。いや、大人や教師は、子どもに何も教える事がないのです。子どもは、学校からはなにもまなばない」
には賛成します。学ぶ、とは根本的に主体的な活動ですから、自己教育以外の教育にはまず意味がない。教師はただその支援ができるだけだ。それはそうです、基本的には。
ただしかし、近代社会なら必ず学校はある。子どもはそこへ通うのが当然だと考えられている。いや、学校こそが、近代において見出された「子ども時代」を社会的に確定する、それが第一の機能だ、と申してもいいでしょう。それで、ごく当然のこととして子どもは学校へ通う。通えば、これまたごく当然のこととして、「勉強」と総称されることをやらされる。当たり前なんだから、これをとりわけ「強制」だなどとは誰も思わなくてすむ。そのためにも学校という制度は有効です。
しかし子どもの目から見たら? 毎日一定時間同じ場所に行って特定の時間には、学び方はさまざまにもせよ、特定のことを勉強させられる。「別に学ぶのがいやだってんじゃないけど、今は他のことがしたいんだよ」などと訴えても、それは許されない。強制ではないのですか? 逆に、その程度の強制もなしで、子どもは今の社会で必要とされる知識を必ず学ぶものでしょうか?
庄司さんの作られた学校にはそのような強制もないのですか? A・S・ニールの、世界初のフリースクールであるサマーヒルに関して、誰かが、「しかしサマーヒルも、『学校へ行かない自由』はないから、完全に自由とは言い難い」と批判しているという話をどこかで読みましたが、庄司さんの学校では生徒はどの程度に自由なんでしょうか? 言い換えると、「自由な学びの権利と環境を保障する」とは、具体的にはどんなことなんですか?
さらにまた、「教育」である以上、現在の大人の考えからのバイアスが全くかかっていない知識を学ぶなんて、不可能ではないでしょうか? アニメやゲームは本当の意味で知的好奇心を満たすものではない、と言ったところで、それ自体が大人の見方であるわけでして。その大人の中にも、宮崎駿氏や堀井雄二氏など、充分に知的であった上で、アニメやゲームに終始関わり続け、現に社会に影響をもたらした人もいるわけで。
意地悪でこんなことを申し上げているわけではないですよ。自分の遠い昔の記憶に照らしても、子どもというのはこの種のごまかしには非常に敏感なのです。裏切られて、無駄に傷つくぐらいなら、最初から、これは「押しつけ」だよ、とはっきりさせたほうがまだしもよい。心からそう感じますので。
また、教師はどうなんでしょう? 教師は、子どもが学びたがったら、支援する。支援しようにも、ある教科を最初から学びたがらなかったり、途中で学びたがらなくなったとしても、それは教師の責任ではないのだから、放っておいてもよい。そうお考えですか? 「それでは教師失格だ」なんぞと非難される恐れがあったら、教師は、あの手この手で生徒に勉強させようと、つまりは学習を強制しようとする、少なくともそのそぶりだけはする、しかなくなるわけですよね?
やまびこ学校の奇跡とは、おっしゃるように、小さな山村だからできたことでしょう。もう一つ、「極度の貧しさ」という、何とかしたいとは誰もが願う共通課題があったことも大きいですね。現在、都会でなくても、一般にそういう共通課題はない。宗教的理念もなく、何を学ぶのかの共通理解もなく、ただ「自由な学び」だけで何かをしようというのは、無理がありそうに思います。サマーヒルにだって、「反権威」「純粋な民主主義」という理念はあるのです。
因みに私は、この種の試みは、たいてい、人間の生来のエゴイズムに目をつぶる結果、とてもグロテスクなものになりがちではないか、と感じます。が、あまり長々と自分の見解を語ると庄司さんとの対話にはなりませんので、今回はこのへんでやめます。