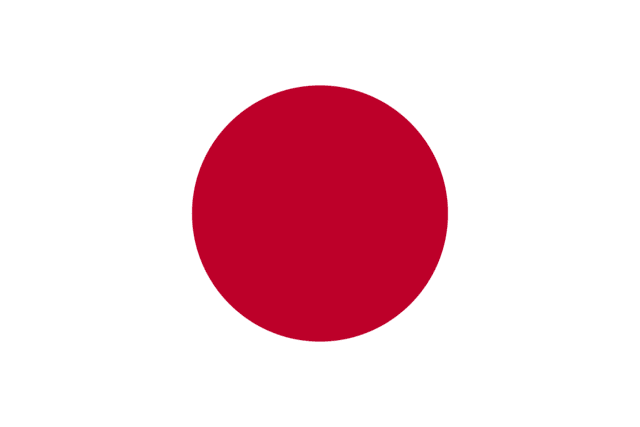
前回記事「憲法改正(9条改正と自衛の定義)」でいろいろ考えたのですが、安全保障論を考えれれば考えるほど面倒くさいな!と思うようになりました。これまでの考察を元にいっそのこと2項削除を真剣に考えてみたらどうなるのか。
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
要は戦力不保持と交戦権の否定に政策的な拒否感がある人が多いのでしょう。あまり否定論がない1項は自衛を旨とする自衛隊の肯定と見ます。そう考えると交戦権の否定はついでに過ぎず(自衛はできます。自衛隊が明記されたら交戦権の否定はなお関係ありません)、問題の核心は戦力不保持と書いているから、持てない装備があるということに尽きるのかもしれません。
前回調べで持てない装備とは「大陸間弾道ミサイル(ICBM)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母」です。特に引っかかるのは攻撃型空母でヘリ空母一択に軍事的合理性があるのかということになります。長距離戦略爆撃機も何で駄目なんだという感じもあります。破壊力がある戦力こそ抑止力があるとも考えられます。まぁNBCといった大量破壊兵器に手を出すのは国際社会で生きられなくなりそうですから、逆効果ですが。ICBMは大量破壊兵器とセットでしょうから、日本がやる意味はないと思いますが、大量破壊兵器をやらないなら、可能性があっても(どうせやらないから)問題はないのかもしれません。・・・どうなんでしょうね。これらの兵器の必要性ってどの程度でしょうか。まぁこれぐらいなら自衛隊明記でいいような気もしますが。
本当のところもっと安全保障論で気になっていることがあって、ニュークリアシェアリングの可能性です。これは完全に自衛の問題です。要は攻撃されたら効率よくミサイル攻撃してしまう訳です。ポイントは核武装国にはならないということだと思います。だとしたら現行憲法でニュークリアシェアリングによる核武装は可能だと考えざるを得ません。戦力と思うかもしれませんが、ニュークリアシェアリングによる核は保持してないってことになるんじゃないでしょうか。誰が保持しているかと言えばアメリカとか。ニュークリアシェアリングで核を保持していると認定されるならば、ドイツは核武装国だったということになります(ですからニュークリアシェアリングを核武装の文脈で語ることが誤りです)。核実験もしてないのに。ただ単に借りていただけという理論構成のような気がします。まぁ2項がない方がつっこまれにくいかもしれませんが、核武装じゃないんだから戦力な訳ありません。
もう一つ以前実は気になっていたのが集団安全保障です。日本がNATOに誘われている感じになっていますが、集団安全保障に参加できないので選択肢が狭まっている感じです。集団安全保障は別に悪いものではないので、これを取っ払っておくに越したことはありません。まぁ大西洋の戦争に日本が参加するというような話は現実的ではありませんが、アジアの防衛で集団安全保障の選択肢がないのは気にならないではありません。別にアメリカがやると思うかもしれませんが、アメリカがアジアでやったら日本も結局巻き込まれるので一緒のような気もするんですよね。なら一緒にやった方が安全性が高まるというか。日本は元々南シナ海で訓練している国でアジアの海を守るのは規定路線のような気もします。アメリカの同盟国は東南アジアに今は存在しないようですが、可能性を確保するに越したことはありません。検討した上で外交安全保障上の理由で要らないのであれば、まぁそれでいいと思いますが、憲法上の制約で害子安全保障上政策上必要なのにやれないのだったら残念だなという気もします。憲法上の根拠ですが、ウィキペディア「集団安全保障」を確認すると、「日本は、集団安全保障への参加について、武力の行使や武力による威嚇を伴う場合は、憲法9条が許容する「必要最小限度の範囲」を超えるため許されないとの解釈を取っている。一方、集団安全保障は「国連加盟国の義務」であり、憲法上は制約されないと総理大臣私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」は主張している」ということです。国権の発動はしていませんから、1項と集団安全保障が矛盾している訳ではないのは確かなのかもしれません。
ここまで考えてみると、基本的には現在の加憲案でいいような気もしますね。まぁ着弾してからの反撃も怪しいというような現在の懸念が加憲案で払拭されるならばですが。筆者の解釈は筆者の解釈に過ぎません。
ただひとつだけどうしても気になることがあります。戦力の定義で裁判所に余計な口出しをされないか、国民に分かりやすいかです。これを解釈で処理するのがあんまり(多分)法律論的によろしくないんじゃないかと。ここで現行の加憲案を振り返ってみると・・・
>我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。
・・・ですから、この3項に合致する実力部隊の装備は全部戦力ではないと解釈したらどうでしょうか?結局のところ兵器は応用が効きます。自衛のための装備でも侵略に使えることは元より自明です。ですからひとまず自衛をフルスペックで認めて(平和維持のために最大効率で抑止力を認めて)、侵略のための体制整備もしないし訓練もしないしそうした団体に無条件で参加しないとします。実際のところ、(紛争解決のため)先制攻撃をしなければいいのであれば、1項があればそれで事足りますし、相手に手を出させるための挑発も1項を残しておけば禁止されているということになります。1項がありながら、それをやってしまうというなら、もうそんな国は何をやっても駄目だと言わざるを得ません。筆者は日本不信論の反日派でありませんし、誰それが総理大臣ならやりかねない等と疑っていませんから、そういう有り得ない妄想による因縁は反日派の皆さんに任せておこうと思っています。
集団安全保障との絡みをここでもう一度検討すると、やはり湾岸戦争のイメージが強いと思います。ただ結論から言えば、やはりこの類の戦争に参加するという話は現状絶対アウトだと思います。でも3項案を見れば我が国の平和と独立を守りと書いています。じゃあOKなのかと言えば、集団安全保障は結局理論上バーターで何処まででも行ってしまいそうですから、明快に否定しておいた方が良さそうです。集団的自衛権だけなら、中東まで出て行って戦争で前線に立つのようなことは基本的にないと考えられます(既に考察済みですが、アフガニスタン戦争は自衛の定義から対テロ戦争だから参加できないということになります。気になる方は前回記事をお読みください)。まぁ可能性が狭まるのは残念ですが、筆者はやはり(アジアでも)現状で集団安全保障をしないとしておきます。集団的自衛権を認めるというのは事実上の周辺事態条項ではないでしょうか?思考実験だけならアメリカ本土が攻められる事態も考えられますが、誰が攻めるのかという話です。よって攻められそうにもない国・団体と集団的自衛をするのであれば(要はアメリカが入らない枠組みを問題外とすれば)、実際問題戦争に巻き込まれず抑止力を高められるという話になります(しつこいようですが対テロ戦争は除外していますし、集団安全保障も排除しています)。美味い話に見えるかもしれませんが、日本も(日米同盟もありますし)「攻められそうにもない」強い国であるということを忘れてはなりません。いずれにせよその辺は相手がある話なのであって、想定すべきはアメリカだけということになります。
掃海艇の派遣は石油が止るんですから存立危機事態でしょうが、通商破壊戦を仕掛けられたら(海軍はそれが主要な目的のようです)、戦争するのも自衛のひとつとは言えそうです。ただこの辺は自衛の定義(急迫性、違法性、必要性、相当性、均衡性)の範囲内ということですね。海上封鎖への対抗は自衛の範囲内です。某国の問題に関して言えば、集団的安全保障ではない国連の義務という考え方です。少なくとも瀬取り対策は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求していますし、国権を発動していませんし、武力による威嚇又は武力の行使をしている訳ではありません。まぁ誰も問題にしていませんから、別に一々考察しなくていいのかもしれませんが。南シナ海の問題に関して言えば、アメリカも今のところ領土問題に関わろうという話ではありませんね。
後は大量破壊兵器をどう考えるかですが、大量破壊兵器は国際的に禁止の動きが強烈で、これを戦力と解釈すれば良さそうです。「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」なければなりませんしね。これで随分スッキリしました。結局現行案の解釈次第(現状と全く同じでは意味が小さく分かりにくい)ですが、やはり現行案でいいんじゃないかということになります。以下念のため現行案で改憲されると(政府・自民党はそうは言ってないようですが、筆者の考え方では)どうなるかまとめておきます。
①自衛は全て認められる。攻撃されたら間違いなく反撃できる。ただし自衛に要件(急迫性、違法性、必要性、相当性、均衡性)があって自衛の名の下に何でも出来るということにはならない。
②個別的自衛権だけでなく、集団的自衛権も認められる。ただし自衛の要件はここでも守らなければならない。疑えばキリはないが、現実には9条が盾になっており、事前の説明が覆ると考えられない。
③集団安全保障はしない。集団的自衛だけで良い。日本は自衛に深く関わる核の傘という例外を除き、現状で(日米同盟以外の枠組みへの参加がなければ)事実上バーターで援軍に行かない(日本駐留以外の国連軍に巻き込まれる可能性はない。まぁ敵国ですんで)。
④戦力とは大量破壊兵器である。大量破壊兵器を日本が開発し所持することは無い。
⑤以上の解釈を守る限り違憲の疑いは全く無い。
以上です。軍法だけは落とした感じですが、9条に関係ないんでこれは止むを得ません。後、サイバー戦争とか反撃オンリーで大丈夫かという論点も有り得ますが、自衛だけで論争になる現状でここまでがMAXと考えます。
一晩経って追記。9条解釈を明記しておけば、凄くいい気もします。つまり既に明記されている必要性以外(必要に応じて~)も憲法に書き込んでおくと学者や裁判官の勝手な解釈を防げますし、国民も誤解しません(明記してれば、民間などが勝手に研究してくれるオマケつき)。具体的には例えば「急迫性、違法性を踏まえて」「相当性、均衡性を考慮し」を追加。これで自衛を理由に拡大解釈されてきた説を撃退します(広く国民を説得します)。それでも「疑いを払拭できない」とか言われたら何もできません。クレーマーとはなるべく関わらず。
自衛と書いてますから集団的自衛権云々は書きません。当然自衛の定義を満たしていれば全て認められます。シンプルイズベスト。しつこいようですが、力の強いものに言われたら~とか言ったところで実際戦後何もしなかったでしょ。同じく集団安全保障云々も書きません。「我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つため」が世界平和を守るための戦争参加を否定しているからです。国際社会から見れば何とも情けない話ですが、日本は国連に敵国認定されていますし、久しく自衛のみが仕事でしたから、それでいいんだろうと思います。結局のところG7でアジアの国は日本だけなのであって、アメリカに対抗するモンスターが隣国に現れた現状で世界平和を守る余裕なんて全く無いとも言えます。当面この現状が変わる見込みもありません。前衛に立たなければ、これまで通り治安維持活動による「戦争参加」は有り得ます。正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求しなければなりませんし、国権を発動している訳でもありませんから、参加しないというのが無い話です。戦争は戦争だろうと因縁つけられてきましたが、作戦立案に関わっていませんし、戦争の要件を十分満たしていないというのは確かです。ハッキリ言えば何処からどう見ても全くの治安維持活動です。これは防災で自衛隊派遣するのと同じなのであって、自衛隊が制限されているのは戦争に関わる部分に過ぎません。ただ戦地での治安維持活動は非常に危険を伴うことは確かです。この定義だと治安維持活動の拡大の懸念は出てきます。ただ「軍隊」の本来業務は治安維持活動ではありません。ですから警察に出来ないレベルの治安維持活動は軍隊業務だとして自衛以外は否定しておくことになりそうです。よく考えてみれば海外の国は我が国でもありませんが、緊急事態条項も治安出動を考慮せず防災に絞っているようであり、国内においてもその辺は想定外というか憲法上治安を理由に軍隊を出す国ではないということになります(ナチスの事例で結局治安を口実にしたのが問題です)。じゃあイラクの平和維持活動とは何かと言えば、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し国権の発動ではない」治安維持活動です。レベルとしては警察の機動隊レベルぐらいならOKではないでしょうか。警察がやれるような治安維持活動は軍隊業務ではないということです。じゃあ警察が行けと言われたところで警察は海外で仕事をする組織ではありません。防災にしろ危機管理のプロとして何でも屋をするのは自衛隊の仕事です。自衛隊の装備は機動隊を超えている部分もありますが、戦車や自走砲を持っていって砲撃するのようなことが無ければ誤解は生じないと考えます。装甲車に関して言えば機動隊も持っているようです(特型警備車)。逆に言えば、機動隊がやるような仕事は自衛隊も海外でやれますということにはなります。さすがに自衛隊ほどの組織が機動隊に出来ることも出来ませんとは筆者は言えません。憲法上の根拠は(書き込めば)「相当性、均衡性」になるでしょうか。何かを理由に拡大した業務を行うことはこれに反するということです。海外での治安維持活動を行うために派遣したのに、それが戦争業務の遂行になってはなりません。戦争参加しているに違いないというのは断っておきますが100%の難癖です。その論法を認めれば日本は物資を売り基地を提供したので朝鮮戦争に参加したということになりますし、資金を提供したので湾岸戦争に参加したということになります(感謝されなかった事件とは何だったのでしょうか?)。戦争業務の遂行が戦争参加です。これが普通の定義で他の解釈は有り得ません。繰り返しますが治安維持を口実にした軍隊活動とは治安当局に出来ない仕事をすることです。この例外は海外での治安維持活動ということになります(警察に海外での仕事をする法的根拠が無いのでしょう)。防災(消防が災害対処の実働部隊と言えます)も含め自衛隊は本来業務でない仕事も行える危機管理のプロ組織ですが、本来業務の自衛戦争以外では量的にはともかく質的にプロ以上の仕事をしません。治安を理由に自衛隊がフル活動をすることを想定するなら、緊急事態条項に治安を入れてシッカリ議論しましょうということになります。掃海艇の派遣は自衛隊にしかできない業務ですが、シーレーンの封鎖は我が国の存立危機事態と言え(国及び国民の安全の正に危機です)、「相当性、均衡性を考慮」すれば、機雷除去が自衛隊の任務なのであって、それ以上のこと(首都を叩くのようなこと)はしないと言えるんでしょう。港を叩くのような話がグレーゾーンで何とも言えませんが、海自はヘリ空母を保持しF-35bの導入も決まっており南シナ海でも訓練してきたことは指摘しておかねばなりません。機雷除去の仕事をしながら、機雷をまく船をどうにもしないのはどうでしょうか。
戦力の定義は揉めますんで、現状の3項案に更に加憲して決着を図るべきです。具体案としては「国際社会に禁じられた大量破壊兵器を我が国は所持しない」です。我が国はというのは核(大量破壊兵器)の傘で守られることは排除しないということです。向こうは持っている訳ですから。国際社会に禁じられたの明記が必要なのは、破壊力を基準にしたら裁判所に安全保障政策の実権を与えるのを防ぐためであり、誰も(多くのものが)問題にしていないものを日本だけが問題にするのような戦後レジームの奇観を防ぐためです。実務上は後から禁止されたら不味い新しい兵器の開発は諸外国に任せようということにはなります(皆が持っているレベルを超えず性能が良いという難しい課題があるということにはなります)(よって破壊力の追及は難しいかもしれません)(まぁ防衛装備の機能は破壊力だけではありませんし、他国が開発して受け入れられた装備を買うことも出来ますし、何にせよ(猛追している国がいるようですが)一番強い国が同盟国です)。また実務上は太洋を超えて自衛戦争をするような装備の導入・体制整備もなさそうです(サイバー戦争だけは地球の裏側まで近隣と同様の扱いです)(宇宙戦争は日本の平和的宇宙利用を守る仕事は考えられます。具体的には日本の衛星破壊に対応することは禁じられるべきとは思えません)。安全保障政策上持てる可能性を保持したい人もいらっしゃるかもしれませんが、戦力条項があって現状で持てていません。万難排して何が何でも可能性を確保したところで、日本が今から核実験をしたり生物兵器の開発したり出来るでしょうか?
そういう訳でこうしたことが明記されれば違憲論が教科書に記載されることはなくなり、憲法学者がああだこうだ言ってくることは少なくなっていくんだろうと思います。結果的に国民の理解も広がってくると考えます。
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
要は戦力不保持と交戦権の否定に政策的な拒否感がある人が多いのでしょう。あまり否定論がない1項は自衛を旨とする自衛隊の肯定と見ます。そう考えると交戦権の否定はついでに過ぎず(自衛はできます。自衛隊が明記されたら交戦権の否定はなお関係ありません)、問題の核心は戦力不保持と書いているから、持てない装備があるということに尽きるのかもしれません。
前回調べで持てない装備とは「大陸間弾道ミサイル(ICBM)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母」です。特に引っかかるのは攻撃型空母でヘリ空母一択に軍事的合理性があるのかということになります。長距離戦略爆撃機も何で駄目なんだという感じもあります。破壊力がある戦力こそ抑止力があるとも考えられます。まぁNBCといった大量破壊兵器に手を出すのは国際社会で生きられなくなりそうですから、逆効果ですが。ICBMは大量破壊兵器とセットでしょうから、日本がやる意味はないと思いますが、大量破壊兵器をやらないなら、可能性があっても(どうせやらないから)問題はないのかもしれません。・・・どうなんでしょうね。これらの兵器の必要性ってどの程度でしょうか。まぁこれぐらいなら自衛隊明記でいいような気もしますが。
本当のところもっと安全保障論で気になっていることがあって、ニュークリアシェアリングの可能性です。これは完全に自衛の問題です。要は攻撃されたら効率よくミサイル攻撃してしまう訳です。ポイントは核武装国にはならないということだと思います。だとしたら現行憲法でニュークリアシェアリングによる核武装は可能だと考えざるを得ません。戦力と思うかもしれませんが、ニュークリアシェアリングによる核は保持してないってことになるんじゃないでしょうか。誰が保持しているかと言えばアメリカとか。ニュークリアシェアリングで核を保持していると認定されるならば、ドイツは核武装国だったということになります(ですからニュークリアシェアリングを核武装の文脈で語ることが誤りです)。核実験もしてないのに。ただ単に借りていただけという理論構成のような気がします。まぁ2項がない方がつっこまれにくいかもしれませんが、核武装じゃないんだから戦力な訳ありません。
もう一つ以前実は気になっていたのが集団安全保障です。日本がNATOに誘われている感じになっていますが、集団安全保障に参加できないので選択肢が狭まっている感じです。集団安全保障は別に悪いものではないので、これを取っ払っておくに越したことはありません。まぁ大西洋の戦争に日本が参加するというような話は現実的ではありませんが、アジアの防衛で集団安全保障の選択肢がないのは気にならないではありません。別にアメリカがやると思うかもしれませんが、アメリカがアジアでやったら日本も結局巻き込まれるので一緒のような気もするんですよね。なら一緒にやった方が安全性が高まるというか。日本は元々南シナ海で訓練している国でアジアの海を守るのは規定路線のような気もします。アメリカの同盟国は東南アジアに今は存在しないようですが、可能性を確保するに越したことはありません。検討した上で外交安全保障上の理由で要らないのであれば、まぁそれでいいと思いますが、憲法上の制約で害子安全保障上政策上必要なのにやれないのだったら残念だなという気もします。憲法上の根拠ですが、ウィキペディア「集団安全保障」を確認すると、「日本は、集団安全保障への参加について、武力の行使や武力による威嚇を伴う場合は、憲法9条が許容する「必要最小限度の範囲」を超えるため許されないとの解釈を取っている。一方、集団安全保障は「国連加盟国の義務」であり、憲法上は制約されないと総理大臣私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」は主張している」ということです。国権の発動はしていませんから、1項と集団安全保障が矛盾している訳ではないのは確かなのかもしれません。
ここまで考えてみると、基本的には現在の加憲案でいいような気もしますね。まぁ着弾してからの反撃も怪しいというような現在の懸念が加憲案で払拭されるならばですが。筆者の解釈は筆者の解釈に過ぎません。
ただひとつだけどうしても気になることがあります。戦力の定義で裁判所に余計な口出しをされないか、国民に分かりやすいかです。これを解釈で処理するのがあんまり(多分)法律論的によろしくないんじゃないかと。ここで現行の加憲案を振り返ってみると・・・
>我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。
・・・ですから、この3項に合致する実力部隊の装備は全部戦力ではないと解釈したらどうでしょうか?結局のところ兵器は応用が効きます。自衛のための装備でも侵略に使えることは元より自明です。ですからひとまず自衛をフルスペックで認めて(平和維持のために最大効率で抑止力を認めて)、侵略のための体制整備もしないし訓練もしないしそうした団体に無条件で参加しないとします。実際のところ、(紛争解決のため)先制攻撃をしなければいいのであれば、1項があればそれで事足りますし、相手に手を出させるための挑発も1項を残しておけば禁止されているということになります。1項がありながら、それをやってしまうというなら、もうそんな国は何をやっても駄目だと言わざるを得ません。筆者は日本不信論の反日派でありませんし、誰それが総理大臣ならやりかねない等と疑っていませんから、そういう有り得ない妄想による因縁は反日派の皆さんに任せておこうと思っています。
集団安全保障との絡みをここでもう一度検討すると、やはり湾岸戦争のイメージが強いと思います。ただ結論から言えば、やはりこの類の戦争に参加するという話は現状絶対アウトだと思います。でも3項案を見れば我が国の平和と独立を守りと書いています。じゃあOKなのかと言えば、集団安全保障は結局理論上バーターで何処まででも行ってしまいそうですから、明快に否定しておいた方が良さそうです。集団的自衛権だけなら、中東まで出て行って戦争で前線に立つのようなことは基本的にないと考えられます(既に考察済みですが、アフガニスタン戦争は自衛の定義から対テロ戦争だから参加できないということになります。気になる方は前回記事をお読みください)。まぁ可能性が狭まるのは残念ですが、筆者はやはり(アジアでも)現状で集団安全保障をしないとしておきます。集団的自衛権を認めるというのは事実上の周辺事態条項ではないでしょうか?思考実験だけならアメリカ本土が攻められる事態も考えられますが、誰が攻めるのかという話です。よって攻められそうにもない国・団体と集団的自衛をするのであれば(要はアメリカが入らない枠組みを問題外とすれば)、実際問題戦争に巻き込まれず抑止力を高められるという話になります(しつこいようですが対テロ戦争は除外していますし、集団安全保障も排除しています)。美味い話に見えるかもしれませんが、日本も(日米同盟もありますし)「攻められそうにもない」強い国であるということを忘れてはなりません。いずれにせよその辺は相手がある話なのであって、想定すべきはアメリカだけということになります。
掃海艇の派遣は石油が止るんですから存立危機事態でしょうが、通商破壊戦を仕掛けられたら(海軍はそれが主要な目的のようです)、戦争するのも自衛のひとつとは言えそうです。ただこの辺は自衛の定義(急迫性、違法性、必要性、相当性、均衡性)の範囲内ということですね。海上封鎖への対抗は自衛の範囲内です。某国の問題に関して言えば、集団的安全保障ではない国連の義務という考え方です。少なくとも瀬取り対策は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求していますし、国権を発動していませんし、武力による威嚇又は武力の行使をしている訳ではありません。まぁ誰も問題にしていませんから、別に一々考察しなくていいのかもしれませんが。南シナ海の問題に関して言えば、アメリカも今のところ領土問題に関わろうという話ではありませんね。
後は大量破壊兵器をどう考えるかですが、大量破壊兵器は国際的に禁止の動きが強烈で、これを戦力と解釈すれば良さそうです。「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」なければなりませんしね。これで随分スッキリしました。結局現行案の解釈次第(現状と全く同じでは意味が小さく分かりにくい)ですが、やはり現行案でいいんじゃないかということになります。以下念のため現行案で改憲されると(政府・自民党はそうは言ってないようですが、筆者の考え方では)どうなるかまとめておきます。
①自衛は全て認められる。攻撃されたら間違いなく反撃できる。ただし自衛に要件(急迫性、違法性、必要性、相当性、均衡性)があって自衛の名の下に何でも出来るということにはならない。
②個別的自衛権だけでなく、集団的自衛権も認められる。ただし自衛の要件はここでも守らなければならない。疑えばキリはないが、現実には9条が盾になっており、事前の説明が覆ると考えられない。
③集団安全保障はしない。集団的自衛だけで良い。日本は自衛に深く関わる核の傘という例外を除き、現状で(日米同盟以外の枠組みへの参加がなければ)事実上バーターで援軍に行かない(日本駐留以外の国連軍に巻き込まれる可能性はない。まぁ敵国ですんで)。
④戦力とは大量破壊兵器である。大量破壊兵器を日本が開発し所持することは無い。
⑤以上の解釈を守る限り違憲の疑いは全く無い。
以上です。軍法だけは落とした感じですが、9条に関係ないんでこれは止むを得ません。後、サイバー戦争とか反撃オンリーで大丈夫かという論点も有り得ますが、自衛だけで論争になる現状でここまでがMAXと考えます。
一晩経って追記。9条解釈を明記しておけば、凄くいい気もします。つまり既に明記されている必要性以外(必要に応じて~)も憲法に書き込んでおくと学者や裁判官の勝手な解釈を防げますし、国民も誤解しません(明記してれば、民間などが勝手に研究してくれるオマケつき)。具体的には例えば「急迫性、違法性を踏まえて」「相当性、均衡性を考慮し」を追加。これで自衛を理由に拡大解釈されてきた説を撃退します(広く国民を説得します)。それでも「疑いを払拭できない」とか言われたら何もできません。クレーマーとはなるべく関わらず。
自衛と書いてますから集団的自衛権云々は書きません。当然自衛の定義を満たしていれば全て認められます。シンプルイズベスト。しつこいようですが、力の強いものに言われたら~とか言ったところで実際戦後何もしなかったでしょ。同じく集団安全保障云々も書きません。「我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つため」が世界平和を守るための戦争参加を否定しているからです。国際社会から見れば何とも情けない話ですが、日本は国連に敵国認定されていますし、久しく自衛のみが仕事でしたから、それでいいんだろうと思います。結局のところG7でアジアの国は日本だけなのであって、アメリカに対抗するモンスターが隣国に現れた現状で世界平和を守る余裕なんて全く無いとも言えます。当面この現状が変わる見込みもありません。前衛に立たなければ、これまで通り治安維持活動による「戦争参加」は有り得ます。正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求しなければなりませんし、国権を発動している訳でもありませんから、参加しないというのが無い話です。戦争は戦争だろうと因縁つけられてきましたが、作戦立案に関わっていませんし、戦争の要件を十分満たしていないというのは確かです。ハッキリ言えば何処からどう見ても全くの治安維持活動です。これは防災で自衛隊派遣するのと同じなのであって、自衛隊が制限されているのは戦争に関わる部分に過ぎません。ただ戦地での治安維持活動は非常に危険を伴うことは確かです。この定義だと治安維持活動の拡大の懸念は出てきます。ただ「軍隊」の本来業務は治安維持活動ではありません。ですから警察に出来ないレベルの治安維持活動は軍隊業務だとして自衛以外は否定しておくことになりそうです。よく考えてみれば海外の国は我が国でもありませんが、緊急事態条項も治安出動を考慮せず防災に絞っているようであり、国内においてもその辺は想定外というか憲法上治安を理由に軍隊を出す国ではないということになります(ナチスの事例で結局治安を口実にしたのが問題です)。じゃあイラクの平和維持活動とは何かと言えば、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し国権の発動ではない」治安維持活動です。レベルとしては警察の機動隊レベルぐらいならOKではないでしょうか。警察がやれるような治安維持活動は軍隊業務ではないということです。じゃあ警察が行けと言われたところで警察は海外で仕事をする組織ではありません。防災にしろ危機管理のプロとして何でも屋をするのは自衛隊の仕事です。自衛隊の装備は機動隊を超えている部分もありますが、戦車や自走砲を持っていって砲撃するのようなことが無ければ誤解は生じないと考えます。装甲車に関して言えば機動隊も持っているようです(特型警備車)。逆に言えば、機動隊がやるような仕事は自衛隊も海外でやれますということにはなります。さすがに自衛隊ほどの組織が機動隊に出来ることも出来ませんとは筆者は言えません。憲法上の根拠は(書き込めば)「相当性、均衡性」になるでしょうか。何かを理由に拡大した業務を行うことはこれに反するということです。海外での治安維持活動を行うために派遣したのに、それが戦争業務の遂行になってはなりません。戦争参加しているに違いないというのは断っておきますが100%の難癖です。その論法を認めれば日本は物資を売り基地を提供したので朝鮮戦争に参加したということになりますし、資金を提供したので湾岸戦争に参加したということになります(感謝されなかった事件とは何だったのでしょうか?)。戦争業務の遂行が戦争参加です。これが普通の定義で他の解釈は有り得ません。繰り返しますが治安維持を口実にした軍隊活動とは治安当局に出来ない仕事をすることです。この例外は海外での治安維持活動ということになります(警察に海外での仕事をする法的根拠が無いのでしょう)。防災(消防が災害対処の実働部隊と言えます)も含め自衛隊は本来業務でない仕事も行える危機管理のプロ組織ですが、本来業務の自衛戦争以外では量的にはともかく質的にプロ以上の仕事をしません。治安を理由に自衛隊がフル活動をすることを想定するなら、緊急事態条項に治安を入れてシッカリ議論しましょうということになります。掃海艇の派遣は自衛隊にしかできない業務ですが、シーレーンの封鎖は我が国の存立危機事態と言え(国及び国民の安全の正に危機です)、「相当性、均衡性を考慮」すれば、機雷除去が自衛隊の任務なのであって、それ以上のこと(首都を叩くのようなこと)はしないと言えるんでしょう。港を叩くのような話がグレーゾーンで何とも言えませんが、海自はヘリ空母を保持しF-35bの導入も決まっており南シナ海でも訓練してきたことは指摘しておかねばなりません。機雷除去の仕事をしながら、機雷をまく船をどうにもしないのはどうでしょうか。
戦力の定義は揉めますんで、現状の3項案に更に加憲して決着を図るべきです。具体案としては「国際社会に禁じられた大量破壊兵器を我が国は所持しない」です。我が国はというのは核(大量破壊兵器)の傘で守られることは排除しないということです。向こうは持っている訳ですから。国際社会に禁じられたの明記が必要なのは、破壊力を基準にしたら裁判所に安全保障政策の実権を与えるのを防ぐためであり、誰も(多くのものが)問題にしていないものを日本だけが問題にするのような戦後レジームの奇観を防ぐためです。実務上は後から禁止されたら不味い新しい兵器の開発は諸外国に任せようということにはなります(皆が持っているレベルを超えず性能が良いという難しい課題があるということにはなります)(よって破壊力の追及は難しいかもしれません)(まぁ防衛装備の機能は破壊力だけではありませんし、他国が開発して受け入れられた装備を買うことも出来ますし、何にせよ(猛追している国がいるようですが)一番強い国が同盟国です)。また実務上は太洋を超えて自衛戦争をするような装備の導入・体制整備もなさそうです(サイバー戦争だけは地球の裏側まで近隣と同様の扱いです)(宇宙戦争は日本の平和的宇宙利用を守る仕事は考えられます。具体的には日本の衛星破壊に対応することは禁じられるべきとは思えません)。安全保障政策上持てる可能性を保持したい人もいらっしゃるかもしれませんが、戦力条項があって現状で持てていません。万難排して何が何でも可能性を確保したところで、日本が今から核実験をしたり生物兵器の開発したり出来るでしょうか?
そういう訳でこうしたことが明記されれば違憲論が教科書に記載されることはなくなり、憲法学者がああだこうだ言ってくることは少なくなっていくんだろうと思います。結果的に国民の理解も広がってくると考えます。



















