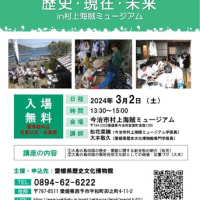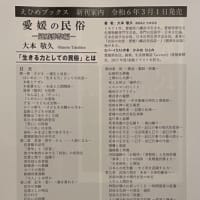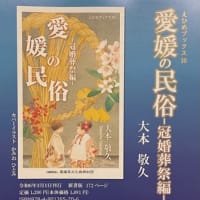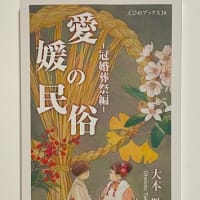「南瓜の方言」
八幡浜では一般に南瓜(かぼちゃ)のことをナンキンというが、この方言は近畿地方を中心に西日本各地に聞くことのできるものである。江戸時代中期の各地の方言をまとめた『物類称呼』によると、「南瓜 ぼうふら 西国にてぼうふら、備前にてさつまゆうがほ、津国にてなんきん、東上総にてとうぐはん、大坂にてなんきんうり、又ぼうふら、江戸にて先年はぼうふらといひ、今はかぼちやと云」とあり、全国的にみると南瓜の方言は様々であることがわかる。ナンキンは大坂で言われていた「なんきんうり(南京瓜)」の省略形であろう。つまり、中国の南京から伝わった瓜という意味である。
そもそも、全国的な呼称であるカボチャも、カンボジア(産の野菜)が訛ったものであり、南瓜の方言には海外の地名が含まれることが多い。『綜合日本民俗語彙』(平凡社)によると、山形県荘内地方では、南瓜をロスンまたはルスンという。宮崎県東臼杵郡ではナンバン、高知県宿毛市沖之島ではチョウセンという。ロスン=ルソン(フィリピン)、ナンバン=南蛮、チョウセン=朝鮮と、いずれも海外の地名で呼ばれている。御荘町の大正初期生まれの方に聞くと、チョウセンという呼称は南宇和郡でも用いられており、カボチャやナンキンは近年になって使い始めた言葉だという。
現在の南瓜の方言分布を示したのが図1である。関東地方で用いられるトーナスは「唐茄子」のことであり、中国の「唐」の名が用いられている。徳川宗賢編『日本の方言地図』(中公新書)によると、九州で使われるボブラは、南瓜のポルトガル語aboboraに由来する言葉で、戦国時代にポルトガル船によって九州に南瓜がもたらされ、定着した名残だと思われる。やはりこの方言は海外との結びつきが強い。
なお、八幡浜にはもう一つの南瓜の方言がある。大正時代初期以前の生まれの人が使用していた言葉だが、「トウガン」と言う。トウガンといえば南瓜とは別の野菜で、瓜の一種である「冬瓜」を思いおこすが、八幡浜や広島県、高知県の一部では南瓜のことを「トウガン」と呼んでいた。これも外国名が付けられているとすれば、漢字で表記すると「唐瓜」になると思われる。この忘れられかけている方言「トウガン」も、日本の南瓜の方言を研究する上で、海外名を残しているものとして、貴重な存在といえるだろう。
2000/11/23 南海日日新聞掲載
八幡浜では一般に南瓜(かぼちゃ)のことをナンキンというが、この方言は近畿地方を中心に西日本各地に聞くことのできるものである。江戸時代中期の各地の方言をまとめた『物類称呼』によると、「南瓜 ぼうふら 西国にてぼうふら、備前にてさつまゆうがほ、津国にてなんきん、東上総にてとうぐはん、大坂にてなんきんうり、又ぼうふら、江戸にて先年はぼうふらといひ、今はかぼちやと云」とあり、全国的にみると南瓜の方言は様々であることがわかる。ナンキンは大坂で言われていた「なんきんうり(南京瓜)」の省略形であろう。つまり、中国の南京から伝わった瓜という意味である。
そもそも、全国的な呼称であるカボチャも、カンボジア(産の野菜)が訛ったものであり、南瓜の方言には海外の地名が含まれることが多い。『綜合日本民俗語彙』(平凡社)によると、山形県荘内地方では、南瓜をロスンまたはルスンという。宮崎県東臼杵郡ではナンバン、高知県宿毛市沖之島ではチョウセンという。ロスン=ルソン(フィリピン)、ナンバン=南蛮、チョウセン=朝鮮と、いずれも海外の地名で呼ばれている。御荘町の大正初期生まれの方に聞くと、チョウセンという呼称は南宇和郡でも用いられており、カボチャやナンキンは近年になって使い始めた言葉だという。
現在の南瓜の方言分布を示したのが図1である。関東地方で用いられるトーナスは「唐茄子」のことであり、中国の「唐」の名が用いられている。徳川宗賢編『日本の方言地図』(中公新書)によると、九州で使われるボブラは、南瓜のポルトガル語aboboraに由来する言葉で、戦国時代にポルトガル船によって九州に南瓜がもたらされ、定着した名残だと思われる。やはりこの方言は海外との結びつきが強い。
なお、八幡浜にはもう一つの南瓜の方言がある。大正時代初期以前の生まれの人が使用していた言葉だが、「トウガン」と言う。トウガンといえば南瓜とは別の野菜で、瓜の一種である「冬瓜」を思いおこすが、八幡浜や広島県、高知県の一部では南瓜のことを「トウガン」と呼んでいた。これも外国名が付けられているとすれば、漢字で表記すると「唐瓜」になると思われる。この忘れられかけている方言「トウガン」も、日本の南瓜の方言を研究する上で、海外名を残しているものとして、貴重な存在といえるだろう。
2000/11/23 南海日日新聞掲載