日々、イラン情勢が伝えられている。
今般行われた大統領選挙は保守派のアフマディネジャド大統領(現職)の圧勝に終わったが、改革派のムサビ支持者が選挙には不正があったとして大規模な抗議デモを行っているという内容だ。
軍隊はこのデモの鎮圧にあたり、死者も出た。
普段、あまり報道されることのないイランという国だが、この機会に色々とイランについて詳しい説明がなされるかと思うと期待はずれだった。
昨日の「報道ステーション」ではイランは1979年に民衆が王制を倒すというイラン革命をやり、亡命していた最高指導者ホメイニ師を向かえ現体制に移行したとまでは説明してたが、革命の結果イランの国情がどうなったかは一切触れないまま。
これじゃあ、革命の意義がわからない。
どころか、民衆が悪い王様を追い出して民主的な国をつくりましためでたしめでたしと視聴者が受け取ってしまう可能性もある。
はっきりいって、イランは日本人の価値観からみればとんでもない人権抑圧国家なのだが、普段、北朝鮮やミャンマーに向けられる人権抑圧国家という非難は今回の一連の報道では鳴りをひそめている感がある。
またそのパターンか、と思われるかもしれないが、イランについて少しばかり書いておく。
ホメイニ師の革命が起こる前、この国は宗教観は日本によく似ていた。
イスラム圏にありながらイランは二十世紀以降、脱イスラムを宣して近代化に努めた。
近代化の過程で民族衣装を脱ぎ捨てたのは日本とイランだといわれている。
地理的な理解からイランをアラブの一国と思っている人も多いが、この国の主要民族はアーリア系のペルシャ人で言語もペルシャ語が公用語だ。
アラブ連盟にも加盟していない。
ペルシャ人は元来、食べ物、酒、踊り(ベリーダンス)、そして麻薬が大好きな享楽的な民族だった。
食べ物で云うと日本にある野菜や果物、米も大根も白菜もスイカもペルシャが原産。
酒はブドウ酒(つまりワイン)が有名でこれはアレキサンダー王を虜にした。
ペルシャの踊りはベリーダンスなどと云われるが、イスラムに追われたササン朝ペルシャの民がシルクロードを経て唐の都・長安に他のペルシャ文化と共に持ち込んで白楽天や李白を魅了させている。
麻薬で云うと、阿片戦争で有名なアヘンはペルシャ語のアピンが原語。
アピンとは高級なマリファナ樹脂からとれるねっとしとした褐色の塊のことだ。
これをペルシャ人は食後に酒と共に楽しんだ。
ところで、英語で「楽園」を意味するパラダイスの語源も実はアケメネス朝ペルシャのダリウス大王(ダレイオス1世)が作らせた庭園で、大王はそこに鹿や猪、虎、ライオンを放しハンティングを楽しんでいる。
そんなわけで、ペルシャは禁欲を絵に描いたようなイスラム教とは一線を画す文化を持っていた。
元々、ペルシャ人は拝火教とも言われるゾロアスター教を信仰していた。
ゾロアスター教の教えは天地創造、復活、救世主、最後の審判などのちの
ユダヤ教やキリスト教に大きな影響を与えている。
そんなペルシャにイスラム教が流入するのは七世紀中頃。
ペルシャ軍をイスラム軍がカーディシーア(636年)、ネハーベント(646年)の二つの戦い破った後のことだが、ゾロアスター教の持つ論理性に馴れたペルシャ人にはイスラムの教えはなかなか馴染まなかった。
そこに生れたのがシーア派でアラブ諸国が信仰する本家スンナ派と違ったコーランの解釈をとり、シーア派はイラン独自の宗教として栄えた。
例えば、スンナ派で厳しく禁じられている偶像崇拝をシーア派では部分的に是認されているし、日本人がよくやる神様に対する願掛けもスンナ派ではタブーだがシーア派ではOK。
これらはゾロアスター教からの影響が強い。
このあたりの宗教の換骨奪胎も日本に伝わったのちの仏教のあり方と似てなくも無い。
食べ物でもイスラム教徒が食べない事で有名な豚肉をはじめ、貝や海老、カニなども普通に食べてきた。
他のイスラム圏では極端に低い女性の地位も比較的高く、ファションも自由に楽しんでいた。
女性とは反対にムッラーと呼ばれるイスラム教の聖職者は他のアラブ諸国と違い社会的地位はそんなに高く、仕事は日本の僧侶や神官のように葬式や結婚式の仕切りや立会い。
そんなイランに革命が起きる。
1979年のことだが、原因はパーレビー皇帝の専制と急速な近代化と説明されている。
民衆が王制を倒し、ホメイニ師とそれを支えるイスラム協会(アンジョマネ・イスラム)がやって来た。
民衆の期待を大きく裏切り、ホメイニ師は恐怖政治を始めた。
旧王制関係者は次々に処刑され、国民にはイスラム原理主義を押し付けた。
まづ、酒とアヘンを禁止し、ウロコのない魚介類の食用も禁じた。
その中にはイラン人の大好物だったチョウザメのキャビアも入っていた。
食べても良い羊なども正しい方法、すなわち「アッラーのなを唱えた者が鋭利な刃物で苦しませず喉を掻き切ったもの」を細かく指定された。
音楽も賭博も未婚の男女の交際も禁止。
つまり、デートも禁止でこんな法日本でやったらスイーツ(笑)さん達が卒倒しそうだ。
冗談はさておき、レストランで男女で入るときは夫婦である証明がないと即逮捕され鞭打ち刑。
不倫が発覚すると石打ちによる死刑に処させる。
女性の地位も一気に下がった。
女性はチャドルで身を包むことが強制され、髪の毛を出したり、体のラインがわかる服を身につけたり、口紅や化粧をすることも禁じられた。
これを犯すと鞭打ち刑。
またコーランには
「女というものは汝らの耕作地。だから(男は)どうでも好きなように自分の畑に手をつけるがよい」(コーラン・牝牛の章223項)
「アッラーはもともと男と女との間には優劣をおつけになったのだし、また(生活に必要な)金は男が出すのだから、この点で男の方が女の上に立つべきもの。だから貞淑な女はひたすら従順に・・・(略)・・・反抗的になりそうな心配のある女はよく諭し、それでも駄目なら寝床に追いやって懲らしめ、それも効かない場合は、打擲を加えてもよい」(同・女の章38項)
などという、日本のフェミニスト女性連中が読んだらこれまた卒倒しそうな文言が至る所にあり、イスラム原理主義のホメイニ師はこれを厳密に適応して女性の人権を著しく抑圧した。
社会的・法的な権利は「女は男の二分の一」とされ、公務員を例にすると給料は男の半分。
刑罰は等量報復と定められているが、これも男同士の場合に限る。
被害者が女性だった場合は半分。
こういう裁判の例がある。
1985年に夫婦喧嘩の末、夫が妻の両目を潰した事件があった。
妻がイスラム新刑法に基づいて夫への報復を要求した。
判決は「夫の片目をえぐりだすべし」。
「女は男の二分の一」原則が適応された形だ。
革命後のイランでは反政府活動、それがビラを撒いただけでも陰惨を極める拷問ののち死刑にされることがままあったが、これも女性の場合は悲惨だった。
ホメイニ師のいうイスラムの教えでは処女は死ぬと天国へ行く。
そこで女性は刑務官から拷問の後に強姦も加えて銃殺刑に処された。
さながら北朝鮮並みの所業だが、そもそも、イスラム聖職者は女性を「ザイフェ」と呼ぶがこれは「より劣ったもの」「精神薄弱者」という意味を持つ。
イスラム原理主義がいかに女性を低くみているかを示す一端だ。
前近代的な刑罰も次々と復活した。
例えば、窃盗は一回目で右手指を切断。(拇指を除く四本を切断)
二回目は右手首、三回目は左足首、四回目は窃盗に限らず如何なる犯罪も死刑となる。
公開処刑も街角いたるところで見られた。
すでに不倫は死刑と書いたが、ホメイニ師は性について特に厳しい。
殺人でさえ、金銭でケリがつくことがあるのに、近親相姦、義母との情交、非イスラム教徒との情交、強姦の四罪は死刑。
法廷で弁護士がつくことも禁じられる。
さらに同性愛も重罪の対象で男同士が性行為を行った場合も死刑。
ホモが駄目だなんて!と日本の腐女子さんや腐男子さん(これは私)の嘆きが聴こえてきそうだ。
ポルノなんかも当然駄目。
日本からの赴任者や旅行者が「週刊ポスト」あたりを持ち込むとヌードグラビアのページは空港のチェックで没収され、普通のグラビアなどもマジックインキで塗りつぶされたという。
「週刊文春」に乗っていた林真理子の水着のイラストが塗りつぶされたなんて話もある。
それがポルノに該当するのかしらんと首を捻らざるを得ないが、漫画の性的表現まで厳しく規制する姿勢は日本の野田聖子や千葉景子を思い起こさせる。
ちなみに、革命後のイランには人権もなかったが犬権もなかった。
ホメイニ師はどういうわけか犬を豚と同列において「生来、不浄だ」と決め付け、テヘラン市には野犬狩部隊が作られた。
部隊が発足した1985年当時、銃殺された犬がトラックの荷台にいっぱいになった光景が見られた。
市民も犬に石をぶつけてウサ晴らしをした。
これも北京五輪の際に、野犬は景観を損ねるとして北京政府が犬を殺しまくったことを思い起こさせる。
そんな、北朝鮮や中国に負けずとも劣らない国家へと変貌を遂げた革命後のイランだが、1989年に最高指導者ホメイニ師が死去した。
国民はここがイスラム原理主義の止めどきだと思った。
それでも、長い圧政に打ちひしがれた国民たちは急激な変化を求めなかった、というより果たせなかった。
以後、緩やかに民主化が進み、1997年宗教政治を批判する改革派のハタミ政権になった時にはテヘランの風景は大きく変わった。
女性は髪の毛一本でも見せれば鞭打ちだったが、前髪を見せるのは当り前になった。
いまも改革派の女性は前髪を見せて街を歩いている。
先日の「学べるニュースショー」で池上彰さんが女性の髪型をみれば保守派か改革派かがわかると云っていたのはそういう事情からだ。
デートも問題なくなった。
レストランに入っても結婚証明書の掲示を要求されなくなった。
もともと、享楽的な民族だ。
イスラム原理主義は肌に合わなかったということだろう。
それから八年後、イスラム原理主義者たちが巻き返しをはかる。
イランでは大統領の上に聖職者で構成される護憲評議会という組織があり、これが実質的に最高の権力を握っている。
この護憲評議会が改革派大統領の立候補を認めず、2005年には保守派のアフマディネジャドが大統領に選ばれた。
アフマディネジャドは狂信的なホメイニ師信奉者で、反米を看板にし「堕落した欧米風」を嫌い、髭をそった部下を叱ったとか、ホメイニ師でも云わなかったエレベーターを男女別にするとかイスラム原理主義的な言動で知られる。
今回の選挙ではそんな超保守派のアフマディネジャドが当選した。
選挙で不正があったのかどうか知らないが、ありえない話しじゃない。
どんな異常な政権でも一度権力を握ってしまえば国民がどうあがこうともなかなか潰れないといういい例だが、もともと急進的な王制に反撥してのイラン革命だった。
駄目な政権に愛想を尽かし、革命を起こしてみたが待っていたのは駄目どころか異常な政権だった。
これ、どこかの国の状況と似てないか。
いや、これから起こりうる状況に。
駄目な自民党政権に愛想を尽かして、政権交代してみたら異常な民主党政権が出現したなんてことにならない保証は無い。
今般行われた大統領選挙は保守派のアフマディネジャド大統領(現職)の圧勝に終わったが、改革派のムサビ支持者が選挙には不正があったとして大規模な抗議デモを行っているという内容だ。
軍隊はこのデモの鎮圧にあたり、死者も出た。
普段、あまり報道されることのないイランという国だが、この機会に色々とイランについて詳しい説明がなされるかと思うと期待はずれだった。
昨日の「報道ステーション」ではイランは1979年に民衆が王制を倒すというイラン革命をやり、亡命していた最高指導者ホメイニ師を向かえ現体制に移行したとまでは説明してたが、革命の結果イランの国情がどうなったかは一切触れないまま。
これじゃあ、革命の意義がわからない。
どころか、民衆が悪い王様を追い出して民主的な国をつくりましためでたしめでたしと視聴者が受け取ってしまう可能性もある。
はっきりいって、イランは日本人の価値観からみればとんでもない人権抑圧国家なのだが、普段、北朝鮮やミャンマーに向けられる人権抑圧国家という非難は今回の一連の報道では鳴りをひそめている感がある。
またそのパターンか、と思われるかもしれないが、イランについて少しばかり書いておく。
ホメイニ師の革命が起こる前、この国は宗教観は日本によく似ていた。
イスラム圏にありながらイランは二十世紀以降、脱イスラムを宣して近代化に努めた。
近代化の過程で民族衣装を脱ぎ捨てたのは日本とイランだといわれている。
地理的な理解からイランをアラブの一国と思っている人も多いが、この国の主要民族はアーリア系のペルシャ人で言語もペルシャ語が公用語だ。
アラブ連盟にも加盟していない。
ペルシャ人は元来、食べ物、酒、踊り(ベリーダンス)、そして麻薬が大好きな享楽的な民族だった。
食べ物で云うと日本にある野菜や果物、米も大根も白菜もスイカもペルシャが原産。
酒はブドウ酒(つまりワイン)が有名でこれはアレキサンダー王を虜にした。
ペルシャの踊りはベリーダンスなどと云われるが、イスラムに追われたササン朝ペルシャの民がシルクロードを経て唐の都・長安に他のペルシャ文化と共に持ち込んで白楽天や李白を魅了させている。
麻薬で云うと、阿片戦争で有名なアヘンはペルシャ語のアピンが原語。
アピンとは高級なマリファナ樹脂からとれるねっとしとした褐色の塊のことだ。
これをペルシャ人は食後に酒と共に楽しんだ。
ところで、英語で「楽園」を意味するパラダイスの語源も実はアケメネス朝ペルシャのダリウス大王(ダレイオス1世)が作らせた庭園で、大王はそこに鹿や猪、虎、ライオンを放しハンティングを楽しんでいる。
そんなわけで、ペルシャは禁欲を絵に描いたようなイスラム教とは一線を画す文化を持っていた。
元々、ペルシャ人は拝火教とも言われるゾロアスター教を信仰していた。
ゾロアスター教の教えは天地創造、復活、救世主、最後の審判などのちの
ユダヤ教やキリスト教に大きな影響を与えている。
そんなペルシャにイスラム教が流入するのは七世紀中頃。
ペルシャ軍をイスラム軍がカーディシーア(636年)、ネハーベント(646年)の二つの戦い破った後のことだが、ゾロアスター教の持つ論理性に馴れたペルシャ人にはイスラムの教えはなかなか馴染まなかった。
そこに生れたのがシーア派でアラブ諸国が信仰する本家スンナ派と違ったコーランの解釈をとり、シーア派はイラン独自の宗教として栄えた。
例えば、スンナ派で厳しく禁じられている偶像崇拝をシーア派では部分的に是認されているし、日本人がよくやる神様に対する願掛けもスンナ派ではタブーだがシーア派ではOK。
これらはゾロアスター教からの影響が強い。
このあたりの宗教の換骨奪胎も日本に伝わったのちの仏教のあり方と似てなくも無い。
食べ物でもイスラム教徒が食べない事で有名な豚肉をはじめ、貝や海老、カニなども普通に食べてきた。
他のイスラム圏では極端に低い女性の地位も比較的高く、ファションも自由に楽しんでいた。
女性とは反対にムッラーと呼ばれるイスラム教の聖職者は他のアラブ諸国と違い社会的地位はそんなに高く、仕事は日本の僧侶や神官のように葬式や結婚式の仕切りや立会い。
そんなイランに革命が起きる。
1979年のことだが、原因はパーレビー皇帝の専制と急速な近代化と説明されている。
民衆が王制を倒し、ホメイニ師とそれを支えるイスラム協会(アンジョマネ・イスラム)がやって来た。
民衆の期待を大きく裏切り、ホメイニ師は恐怖政治を始めた。
旧王制関係者は次々に処刑され、国民にはイスラム原理主義を押し付けた。
まづ、酒とアヘンを禁止し、ウロコのない魚介類の食用も禁じた。
その中にはイラン人の大好物だったチョウザメのキャビアも入っていた。
食べても良い羊なども正しい方法、すなわち「アッラーのなを唱えた者が鋭利な刃物で苦しませず喉を掻き切ったもの」を細かく指定された。
音楽も賭博も未婚の男女の交際も禁止。
つまり、デートも禁止でこんな法日本でやったらスイーツ(笑)さん達が卒倒しそうだ。
冗談はさておき、レストランで男女で入るときは夫婦である証明がないと即逮捕され鞭打ち刑。
不倫が発覚すると石打ちによる死刑に処させる。
女性の地位も一気に下がった。
女性はチャドルで身を包むことが強制され、髪の毛を出したり、体のラインがわかる服を身につけたり、口紅や化粧をすることも禁じられた。
これを犯すと鞭打ち刑。
またコーランには
「女というものは汝らの耕作地。だから(男は)どうでも好きなように自分の畑に手をつけるがよい」(コーラン・牝牛の章223項)
「アッラーはもともと男と女との間には優劣をおつけになったのだし、また(生活に必要な)金は男が出すのだから、この点で男の方が女の上に立つべきもの。だから貞淑な女はひたすら従順に・・・(略)・・・反抗的になりそうな心配のある女はよく諭し、それでも駄目なら寝床に追いやって懲らしめ、それも効かない場合は、打擲を加えてもよい」(同・女の章38項)
などという、日本のフェミニスト女性連中が読んだらこれまた卒倒しそうな文言が至る所にあり、イスラム原理主義のホメイニ師はこれを厳密に適応して女性の人権を著しく抑圧した。
社会的・法的な権利は「女は男の二分の一」とされ、公務員を例にすると給料は男の半分。
刑罰は等量報復と定められているが、これも男同士の場合に限る。
被害者が女性だった場合は半分。
こういう裁判の例がある。
1985年に夫婦喧嘩の末、夫が妻の両目を潰した事件があった。
妻がイスラム新刑法に基づいて夫への報復を要求した。
判決は「夫の片目をえぐりだすべし」。
「女は男の二分の一」原則が適応された形だ。
革命後のイランでは反政府活動、それがビラを撒いただけでも陰惨を極める拷問ののち死刑にされることがままあったが、これも女性の場合は悲惨だった。
ホメイニ師のいうイスラムの教えでは処女は死ぬと天国へ行く。
そこで女性は刑務官から拷問の後に強姦も加えて銃殺刑に処された。
さながら北朝鮮並みの所業だが、そもそも、イスラム聖職者は女性を「ザイフェ」と呼ぶがこれは「より劣ったもの」「精神薄弱者」という意味を持つ。
イスラム原理主義がいかに女性を低くみているかを示す一端だ。
前近代的な刑罰も次々と復活した。
例えば、窃盗は一回目で右手指を切断。(拇指を除く四本を切断)
二回目は右手首、三回目は左足首、四回目は窃盗に限らず如何なる犯罪も死刑となる。
公開処刑も街角いたるところで見られた。
すでに不倫は死刑と書いたが、ホメイニ師は性について特に厳しい。
殺人でさえ、金銭でケリがつくことがあるのに、近親相姦、義母との情交、非イスラム教徒との情交、強姦の四罪は死刑。
法廷で弁護士がつくことも禁じられる。
さらに同性愛も重罪の対象で男同士が性行為を行った場合も死刑。
ホモが駄目だなんて!と日本の腐女子さんや腐男子さん(これは私)の嘆きが聴こえてきそうだ。
ポルノなんかも当然駄目。
日本からの赴任者や旅行者が「週刊ポスト」あたりを持ち込むとヌードグラビアのページは空港のチェックで没収され、普通のグラビアなどもマジックインキで塗りつぶされたという。
「週刊文春」に乗っていた林真理子の水着のイラストが塗りつぶされたなんて話もある。
それがポルノに該当するのかしらんと首を捻らざるを得ないが、漫画の性的表現まで厳しく規制する姿勢は日本の野田聖子や千葉景子を思い起こさせる。
ちなみに、革命後のイランには人権もなかったが犬権もなかった。
ホメイニ師はどういうわけか犬を豚と同列において「生来、不浄だ」と決め付け、テヘラン市には野犬狩部隊が作られた。
部隊が発足した1985年当時、銃殺された犬がトラックの荷台にいっぱいになった光景が見られた。
市民も犬に石をぶつけてウサ晴らしをした。
これも北京五輪の際に、野犬は景観を損ねるとして北京政府が犬を殺しまくったことを思い起こさせる。
そんな、北朝鮮や中国に負けずとも劣らない国家へと変貌を遂げた革命後のイランだが、1989年に最高指導者ホメイニ師が死去した。
国民はここがイスラム原理主義の止めどきだと思った。
それでも、長い圧政に打ちひしがれた国民たちは急激な変化を求めなかった、というより果たせなかった。
以後、緩やかに民主化が進み、1997年宗教政治を批判する改革派のハタミ政権になった時にはテヘランの風景は大きく変わった。
女性は髪の毛一本でも見せれば鞭打ちだったが、前髪を見せるのは当り前になった。
いまも改革派の女性は前髪を見せて街を歩いている。
先日の「学べるニュースショー」で池上彰さんが女性の髪型をみれば保守派か改革派かがわかると云っていたのはそういう事情からだ。
デートも問題なくなった。
レストランに入っても結婚証明書の掲示を要求されなくなった。
もともと、享楽的な民族だ。
イスラム原理主義は肌に合わなかったということだろう。
それから八年後、イスラム原理主義者たちが巻き返しをはかる。
イランでは大統領の上に聖職者で構成される護憲評議会という組織があり、これが実質的に最高の権力を握っている。
この護憲評議会が改革派大統領の立候補を認めず、2005年には保守派のアフマディネジャドが大統領に選ばれた。
アフマディネジャドは狂信的なホメイニ師信奉者で、反米を看板にし「堕落した欧米風」を嫌い、髭をそった部下を叱ったとか、ホメイニ師でも云わなかったエレベーターを男女別にするとかイスラム原理主義的な言動で知られる。
今回の選挙ではそんな超保守派のアフマディネジャドが当選した。
選挙で不正があったのかどうか知らないが、ありえない話しじゃない。
どんな異常な政権でも一度権力を握ってしまえば国民がどうあがこうともなかなか潰れないといういい例だが、もともと急進的な王制に反撥してのイラン革命だった。
駄目な政権に愛想を尽かし、革命を起こしてみたが待っていたのは駄目どころか異常な政権だった。
これ、どこかの国の状況と似てないか。
いや、これから起こりうる状況に。
駄目な自民党政権に愛想を尽かして、政権交代してみたら異常な民主党政権が出現したなんてことにならない保証は無い。











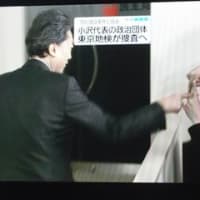
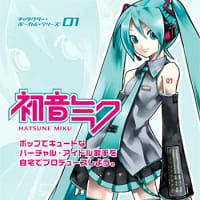
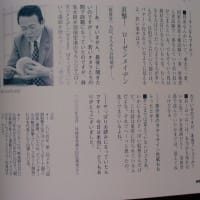
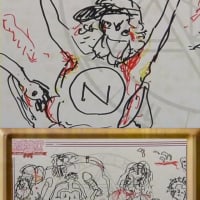


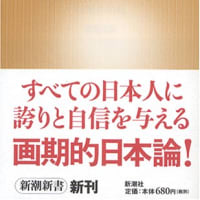


だいたい書かれているとおりですが…。
イランのイスラム信仰におけるシーア派への変容過程を日本に伝わった仏教のそれと「似ていなくもない」というのは些か言い過ぎですね。
全く似ていません。そもそも侵略者イスラムアラブに無理矢理押し付けられて嫌々改宗したイランと、外から伝わり支配階級より先に民衆に信仰が拡がり(蘇我と物部が対立する頃には既に民衆の間に仏教が拡がっていました)自ら進んで受け入れた日本とは新たな宗教との出会いと始まりからして全く違いますから。
アラブ人による散々な嫌がらせや差別から逃れる為にペルシャ人は度々反乱を起こしながら遂には生きる為にイスラム教の前に屈したんですから。