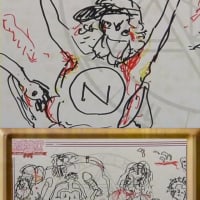「世界を変える100人の日本人」という番組で戦前の外交官、安達峰一郎が紹介されていた。
安達は国際聯盟でも活躍し、アジア系として初めて国際司法裁判所の裁判官、所長となった人物。
安達には、語学習得の為に河原の小石を口に含んで発音の練習をし、英語、フランス語、イタリア語を習得したとか、
弁舌を鍛錬する為に三遊亭圓朝の寄席に通ったという逸話がある。
実際、彼の舌はポーツマス条約締結の時に発揮され、のち多くの場面で調停役として活躍した。
特に有名なのは1924年に聯盟で「ジュネーヴ議定書」が審議されたときで、英仏を相手に一歩も引かず日本の主張を通し、当時、国聯事務次長だった新渡戸稲造に「安達の舌は国宝だ」と評させたほどだ。
海外でも高い人気を誇り、1934年にアムステルダムで死去した際、オランダ政府は国葬を以って彼の功績を顕彰した。
これが外国で日本人が国葬された最初の例になる。
こいう人物を紹介するのはいい。
ただ、気になったのは当時の日本に対する評価だ。
安達は国際司法裁判所において「応訴義務」の規定を創設しようとした。
応訴義務とは国家間の紛争において一方の国が告訴した場合、相手の国は必ず法廷に出頭し、裁判に応じなければならないとする制度だが、これに応じなかったのが日本だったと日本軍の映像と被せていかにも日本は悪い国でしたという風に描く。
満洲事変が勃発した時、安達は当時の総理大臣・斎藤実に日支間の問題解決は国際司法裁判所で決着すべしとの書翰を送っているのだが、ここにも「軍国主義下にありその行動に命の保証はない」というナレーションを挿入する。
戦前の日本は戦争に反対する意見を言うと命の危険があったような軍国主義国家だったというのはあまりにも粗雑な言い方だし、なにより事実に反する。
満洲事変が始った昭和六(1931)年当時の日本は世界恐慌から脱し、高度経済成長を向かえようとしていた。
満洲事変を誰も戦争だなんて思っていない。
海の向こう、遠い大陸で関東軍がドンパチやっている。
それで、景気も良くなったので誰もこれに恐れや不安を抱く人はいなかった。
前年の昭和五年は関東大震災から東京が完全復興し、モダンな帝都が出現していた。
東京行進曲が流行したのもこの年だ。
私鉄は昭和六年に現在あるものがすべてそろい、デパート、映画館、劇場が賑わい大衆文化が花咲いた。
全体はまだまだ不景気だったが、ネオンは輝きデパートに商品はあふれカフェーバー、ダンスホールは満員だったと故・山本夏彦さんも振り返っている。
1930年代は日本の重工業が飛躍的に発展した時期で、国民の生活も日々豊かになっていた。
まさか、この当時の人が日本を軍国主義国家だとは思っていなかったろうし、これから戦争が起こるなんてことも信じていなかった。
支那事変(日中戦争)が始ったときも、それが泥沼の戦争になるなんて思っていない。
昭和十二年十二月に南京が陥落したときもこれで戦争は終わったとホッとしていた。
じじつ、この時点ではまだ支那事変は「天佑」で戦争景気がもたらす消費生活をエンジョイしていた。
歳末商戦を伝える当時の新聞は「軍需景気の反映か、デパートの売上げぶりは正に記録的」と伝えている。
話を戻して。
戦争に反対したからといって命が危険に晒されるなんてこともナチスや今の北朝鮮と違って日本では無かった。
当時の雑誌を開けばいたるところに戦争反対の意見を見ることができるし、昭和十二年までは反ファッショの「人民戦線」論が盛んだった。
一つ例を挙げておくと、昭和十二年六月に近衛文麿内閣が成立したとき、市川房江は『日本評論』という月刊誌に「国際的平和を確立し、戦争を未然に防止する事」を要求しているし、「戦争が人類にとっての最大不幸であることはいふ迄もない」とも書いている。
当時はもちろん「伏字」もあったが、戦争反対の論を展開することはごく普通のことだったのだ。
政治の批判も自由に出来た。
先ほどの斎藤実首相が議会を解散して総選挙に打って出たとき、石橋湛山は政党出身ではない軍人首相が議会を解散しても国民はどの政党の議員に投票してその意思を表明してよいのか、と批判し「およそかような馬鹿らしい総選挙はありはしない」と書いた。
他にも、軍人首相だった林銑十郎が「喰い逃げ解散」(註)をした時、評論家の馬場恒吾は雑誌『改造』誌上で「信を国民に失ってそれで政治ができると思うならば、それはもはや常識のあるなしの問題でなく、精神に異常のあるなしの問題になる」と痛烈に批判している。
言論の自由が保障されているいまの時代でも首相に対して「精神の異常のあるなしの問題」なんて書くのは憚られると思う。
支那事変が泥沼化してきた昭和十五年に石原莞爾が『最終戦争論』を展開したときも「世界の統一が戦争によってなされるということは人類に対する冒涜であり、人類は戦争によらないで絶対平和の世界を建設し得なければならないと思う」との批判がきている。
軍国主義国家ならこういう批判はこない。
もっとも、治安維持法によって多くの人々(主に共産主義者とされた人たち)が逮捕・拘留されたのは事実だし、取り調べの過程で拷問もあった。
それでもナチスドイツや戦後のソ連や中国などと違い、この法によって死刑になった人は日本では一人も居ない。
だから、戦後、多くの共産党員が大手を振って出所してきたのだ。
彼らは戦争にも行かず、食事もきちんと与えられていた。
戦争で悲惨な目にあった人たちよりもある意味で幸福な生活を送っていたともいえる。
日本全体が本当に窮屈になったのは昭和十六年十二月にアメリカと戦争を始めて戦況が悪化してきた昭和十八年頃からだろう。
この頃はさすがに戦争に反対する言論の自由もなくなっていた。
昭和十九年に入ってからは空襲も激しくなり、食料も欠乏し始めた。
「戦前は真っ暗だった」という真っ暗な期間はこの二年間をさすのだろう。
多めに見積もっても三年。
支那事変が始ってから計算すれば八年になるが、それでもやはり長い戦前の期間を一括りにしてをすべて「真っ暗だった」「軍国主義だった」と言うことは歴史を無視した言い回しに違いない。
*******
註:「喰い逃げ解散」とは林銑十郎内閣が予算を成立させた翌日に議会を解散させたことを指す。
衆議院の反省を求める為の解散と説明されたが、予算成立後の解散とあって解散理由が明確でなく、「喰い逃げ解散」と揶揄された。
なお、総選挙後、林内閣は総辞職。在任期間わずか四ヶ月であった。
安達は国際聯盟でも活躍し、アジア系として初めて国際司法裁判所の裁判官、所長となった人物。
安達には、語学習得の為に河原の小石を口に含んで発音の練習をし、英語、フランス語、イタリア語を習得したとか、
弁舌を鍛錬する為に三遊亭圓朝の寄席に通ったという逸話がある。
実際、彼の舌はポーツマス条約締結の時に発揮され、のち多くの場面で調停役として活躍した。
特に有名なのは1924年に聯盟で「ジュネーヴ議定書」が審議されたときで、英仏を相手に一歩も引かず日本の主張を通し、当時、国聯事務次長だった新渡戸稲造に「安達の舌は国宝だ」と評させたほどだ。
海外でも高い人気を誇り、1934年にアムステルダムで死去した際、オランダ政府は国葬を以って彼の功績を顕彰した。
これが外国で日本人が国葬された最初の例になる。
こいう人物を紹介するのはいい。
ただ、気になったのは当時の日本に対する評価だ。
安達は国際司法裁判所において「応訴義務」の規定を創設しようとした。
応訴義務とは国家間の紛争において一方の国が告訴した場合、相手の国は必ず法廷に出頭し、裁判に応じなければならないとする制度だが、これに応じなかったのが日本だったと日本軍の映像と被せていかにも日本は悪い国でしたという風に描く。
満洲事変が勃発した時、安達は当時の総理大臣・斎藤実に日支間の問題解決は国際司法裁判所で決着すべしとの書翰を送っているのだが、ここにも「軍国主義下にありその行動に命の保証はない」というナレーションを挿入する。
戦前の日本は戦争に反対する意見を言うと命の危険があったような軍国主義国家だったというのはあまりにも粗雑な言い方だし、なにより事実に反する。
満洲事変が始った昭和六(1931)年当時の日本は世界恐慌から脱し、高度経済成長を向かえようとしていた。
満洲事変を誰も戦争だなんて思っていない。
海の向こう、遠い大陸で関東軍がドンパチやっている。
それで、景気も良くなったので誰もこれに恐れや不安を抱く人はいなかった。
前年の昭和五年は関東大震災から東京が完全復興し、モダンな帝都が出現していた。
東京行進曲が流行したのもこの年だ。
私鉄は昭和六年に現在あるものがすべてそろい、デパート、映画館、劇場が賑わい大衆文化が花咲いた。
全体はまだまだ不景気だったが、ネオンは輝きデパートに商品はあふれカフェーバー、ダンスホールは満員だったと故・山本夏彦さんも振り返っている。
1930年代は日本の重工業が飛躍的に発展した時期で、国民の生活も日々豊かになっていた。
まさか、この当時の人が日本を軍国主義国家だとは思っていなかったろうし、これから戦争が起こるなんてことも信じていなかった。
支那事変(日中戦争)が始ったときも、それが泥沼の戦争になるなんて思っていない。
昭和十二年十二月に南京が陥落したときもこれで戦争は終わったとホッとしていた。
じじつ、この時点ではまだ支那事変は「天佑」で戦争景気がもたらす消費生活をエンジョイしていた。
歳末商戦を伝える当時の新聞は「軍需景気の反映か、デパートの売上げぶりは正に記録的」と伝えている。
話を戻して。
戦争に反対したからといって命が危険に晒されるなんてこともナチスや今の北朝鮮と違って日本では無かった。
当時の雑誌を開けばいたるところに戦争反対の意見を見ることができるし、昭和十二年までは反ファッショの「人民戦線」論が盛んだった。
一つ例を挙げておくと、昭和十二年六月に近衛文麿内閣が成立したとき、市川房江は『日本評論』という月刊誌に「国際的平和を確立し、戦争を未然に防止する事」を要求しているし、「戦争が人類にとっての最大不幸であることはいふ迄もない」とも書いている。
当時はもちろん「伏字」もあったが、戦争反対の論を展開することはごく普通のことだったのだ。
政治の批判も自由に出来た。
先ほどの斎藤実首相が議会を解散して総選挙に打って出たとき、石橋湛山は政党出身ではない軍人首相が議会を解散しても国民はどの政党の議員に投票してその意思を表明してよいのか、と批判し「およそかような馬鹿らしい総選挙はありはしない」と書いた。
他にも、軍人首相だった林銑十郎が「喰い逃げ解散」(註)をした時、評論家の馬場恒吾は雑誌『改造』誌上で「信を国民に失ってそれで政治ができると思うならば、それはもはや常識のあるなしの問題でなく、精神に異常のあるなしの問題になる」と痛烈に批判している。
言論の自由が保障されているいまの時代でも首相に対して「精神の異常のあるなしの問題」なんて書くのは憚られると思う。
支那事変が泥沼化してきた昭和十五年に石原莞爾が『最終戦争論』を展開したときも「世界の統一が戦争によってなされるということは人類に対する冒涜であり、人類は戦争によらないで絶対平和の世界を建設し得なければならないと思う」との批判がきている。
軍国主義国家ならこういう批判はこない。
もっとも、治安維持法によって多くの人々(主に共産主義者とされた人たち)が逮捕・拘留されたのは事実だし、取り調べの過程で拷問もあった。
それでもナチスドイツや戦後のソ連や中国などと違い、この法によって死刑になった人は日本では一人も居ない。
だから、戦後、多くの共産党員が大手を振って出所してきたのだ。
彼らは戦争にも行かず、食事もきちんと与えられていた。
戦争で悲惨な目にあった人たちよりもある意味で幸福な生活を送っていたともいえる。
日本全体が本当に窮屈になったのは昭和十六年十二月にアメリカと戦争を始めて戦況が悪化してきた昭和十八年頃からだろう。
この頃はさすがに戦争に反対する言論の自由もなくなっていた。
昭和十九年に入ってからは空襲も激しくなり、食料も欠乏し始めた。
「戦前は真っ暗だった」という真っ暗な期間はこの二年間をさすのだろう。
多めに見積もっても三年。
支那事変が始ってから計算すれば八年になるが、それでもやはり長い戦前の期間を一括りにしてをすべて「真っ暗だった」「軍国主義だった」と言うことは歴史を無視した言い回しに違いない。
*******
註:「喰い逃げ解散」とは林銑十郎内閣が予算を成立させた翌日に議会を解散させたことを指す。
衆議院の反省を求める為の解散と説明されたが、予算成立後の解散とあって解散理由が明確でなく、「喰い逃げ解散」と揶揄された。
なお、総選挙後、林内閣は総辞職。在任期間わずか四ヶ月であった。