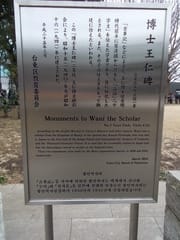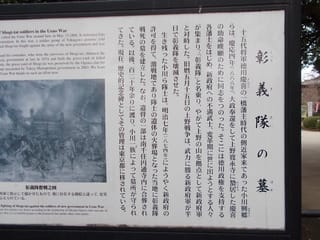千住大橋駅でNさん、Kさん、私(K)のアラ、eighty の散歩となって、駅前の石洞(せきどう)美術館に行きました。




“石洞”というのは、コレクター佐藤千壽さん(1918~2008 )の雅号です。美術館の建物は千住金属工業KKの本社ビルで、館内はスロープで1・2階がつながれています。
今回の展示は 18 世紀のマイセンの磁器が主で、カップ&ソーサーが何品も展示してありました。骨董品が好きな N さん向きでした。
隣接の喫茶室「妙好」で一休みです。(コーヒー等 250 円)


次に行ったのは、南隣りにある橋戸稲荷。伊豆長八の鏝絵が本殿の扉の内側にあることで有名です。









ここは、千住大橋北詰、芭蕉の奥の細道の旅( 元禄二年・1689 )はここから始まります。


旧日光街道にある浄土宗源長寺は開山が慶長 15 年( 1610 )といいますから、この寺の前を芭蕉は通ったことでしょう。




少し先に鎌倉時代創建の寺がありました。新義真言宗の千龍山慈眼寺です。



一箇所に集められた石碑をみると、元禄、天和など、江戸時代初期の年号が刻まれていました。



また、境内には豊川稲荷が祀ってありました。


宿場町北千住は史跡が多くタイムスリップできる街と思いました。